さて、今回のコラムでは、進歩性判断の一要素である「予測できない顕著な効果」について、その言葉の意味するところを考えてみたいと思う。
きっかけは、先日の判例記事「令和5年(行ケ)第10056号」である。この事件で知財高裁は、最高裁(平成30年(行ヒ)第69号)が示した判断に対し、自らの解釈を加えて判断基準を示したが、果たしてその解釈は適当と言えるのかには疑問が残る。
本コラムで考えたい議題は、「予測できない顕著な効果」とは、「予測できない効果 or 顕著な効果」を意味するのか、「予測できない(程の)顕著な効果」を意味するのか、についてである。
両者の意味は全く異なるものである。「予測できない効果 or 顕著な効果」であれば、その効果が顕著なものであることは必須ではなく、予測できない効果であっても「予測できない顕著な効果」に該当することになる。一方で「予測できない(程の)顕著な効果」であれば、その効果の顕著性が予測できない程度のものであるかを考えるため、あくまで判断の対象は効果の程度=顕著性となり、予測できない効果が発生しただけでは「予測できない顕著な効果」には該当しないことになる。(効果の発生そのものが予測できないものであれば、その効果の顕著性は判断の仕様がない。)
令和5年(行ケ)第10056号で知財高裁は以下のように判断を示した。
「本件発明1の奏する効果が予測することのできない顕著なものであるか否かの判断に当たっては、本件優先日当時において、本件発明1の構成が奏するものとして本件優先日当時の当業者が予測することのできないものであったか否か、当該構成から当該当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものであったか否かという観点から検討するのが相当である(最高裁令和元年8月27日第三小法廷判決(平成30年(行ヒ)第69号)裁判集民事262号51頁参照)。
…参加人が主張する本件効果は、甲11発明(認定)に本件周知技術を組み合わせた構成(本件発明1の構成)が奏するものとして本件優先日当時の当業者が予測することのできないものであったと認めることはできず、また、当該構成から当該当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものであったと認めることもできないというべきである。」
このように、上記知財高裁は、主語を「本件効果」とし、本件効果が「予測することのできないものであったか、また、予測できた範囲を超える顕著なものであったか」という判断を行っているため、「予測できない顕著な効果」を「予測できない効果 or 顕著な効果」と解釈したものといえるだろう。
しかしながら、平成30年(行ヒ)第69号で最高裁が示した判断は、下記ように(特に下線部)、上記の知財高裁の判断基準とは完全には一致していない。
「原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく,このような原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」
この最高裁の判断は非常に厄介である。
最高裁は「予測できない顕著なものであるかについて,①優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,②当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討」しなかったことに法令の解釈適用の誤りがあると判断しているが、その直前にある「本件各発明の効果,取り分けその程度が,」との部分が、どのように係るのかが判然としないのである。
この下線部を「本件各発明の効果、及びその程度が」と解すれば、本件発明の効果が①に係り、本件発明の効果の程度が②に係るという解釈ができ、上記の知財高裁がしたような、①は「その効果が予測できないような効果であるか否か」②は「その程度が予測できることのできた範囲を超える顕著な効果であったか否か」という解釈から、「予測できない効果 or 顕著な効果」の解釈を導くことができるだろう。
一方で、この下線部を「本件各発明の効果について、その程度が」と解すれば、①も②も効果の程度に係るため、①は「その程度が予測できないような効果であるか否か」②は「その程度が予測できることのできた範囲を超える顕著な効果であったか否か」という解釈になり、「予測できない(程の)顕著な効果」との解釈を導くことができるだろう。
私は、上記知財高裁の判断基準に疑問を抱く立場であるため、「予測できない顕著な効果」は「予測できないほどの顕著な効果」と解すべきとする立場である。
その理由はいくつかあるが、第一に、最高裁の示した文面が挙げられる。上記最高裁判示の「本件各発明の効果,取り分けその程度が,」との文言を素直に読めば、あくまで主語は「その程度が」であると解するのが自然であるだろう。また、最高裁は①と②を、「または」や「あるいは」で並列的に記載していない。単に句点「、」を設けているだけであり、①と②の主語が異なる(①の主語が「効果」であり②の主語が「効果の程度」である)と解するのは不自然だからである。(主語が異なるならば、それがわかるように書き分けたはずである。)
「本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から」
第二に、発生する効果が「予測のできないもの」であることによって特許性(進歩性)を認めることは、効果の発見そのものに特許性を認めることであり、単なる発見を特許として認めない日本の特許法との平仄が合わないことが挙げられる。また、発明が「予測できない効果」を奏するものであることのみから直ちに「予測できない顕著な効果」が認められ、進歩性が認められるとすれば、出願人や発明者の発明意欲は「新たな創作」ではなく「効果の発見」に向かってしまうことも危惧される。既に知られた公知技術から容易に想到できる発明であっても、当業者が気付けなかった効果を発見するだけで特許が認められるというのでは、産業の発達を却って阻害するだろう。(例えば、高価な分析装置を使ってこれまで発見されていなかった効果の作用機序を見い出すだけで、容易想到な発明を権利化できるため、企業の知財活動がこのような方向に向かいかねない )。
第三に、用途発明を認めたことの意義が失われることが挙げられる。用途発明は、新たな用途を見い出したことに起因して特許を認めるものであり、実質的にその性質は「予測できない効果」の発見にあるといえるだろう。これまで知られていなかった新たな用途に対する効果は、用途が知られていない以上、予測もできないからである。そして、用途発明は、単なる「効果の発見」に対して特許を認めるものではなく、その効果が「異なる用途」に係るものであることを要求するのであるから、「予測できない効果の発生」によって進歩性が認められるとなっては、用途発明を別個に認める意義は失われるだろう。
このように、「予測できない顕著な効果」についての上記最高裁の判断は、予測できない顕著な効果を「予測できない効果 or 顕著な効果」と解するものではなく「予測できないほどの顕著な効果」と解するのが相当であるものと私は考える。(その意味で、上記知財高裁は、なおも、法令の解釈適用を誤っているものと考えている。)
それでは、「予測できない顕著な効果」を「予測できないほどの顕著な効果」と解したとして、上記最高裁の判示、特に上記の①と②をどのように理解すればよいだろうか。
そもそも、最高裁の判示は、①と②が並列関係にあり、それぞれ独立した要件を述べたものと解すべきであろうか。この点からして既に、私の考えは上記知財高裁の考えとは違っている。
「①優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,②当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点」
上記の最高裁の判示のなかで、どのように理解すべきかが難解なのは①であろう。②は素直に読めるだろうが、①はそれだけを読めば「顕著な効果」という言葉とは結び付きにくい。その効果の程度が予測できないものであるならば、「効果の顕著性」はわからないように思えるからである。(「効果の程度が予測できないのに顕著って何?」)
そのため、①を独立した要件と解してしまうと、主語を効果の程度ではなく効果とし、効果そのものの予測性と解する方が理解が容易であるが、要件であるという思い込みから、これに当てはまるように主語を置き換えてしまうのはまずいだろう。また、仮に、①の主語が「効果の程度」であるとしても、「効果の程度が予測できない」場合に、予測できない程度の効果なら全て「顕著な効果」としてよいというのも、理論的にはおかしい。
効果の程度が予測できないならば、その効果がどの程度であっても、顕著なものとみなされるとなってしまうと、効果の程度の予測可能性という発明の本質からさらに離れたところで進歩性の判断が決せられてしまうこととなり、より一層不合理な判断となってしまうからである。(そもそも、効果とは結果であり、実際にやってみなければ効果の程度はわからないのであるから、やる前から完全な予見はできず、その意味では常に不安定な予測可能性しかない。)
また、①と②は、パッと見た限りでは似たようなことを述べているようにも見える。特に①の「予測することができなかった」と②の「予測することができた範囲の効果を超える」という部分である。少なくとも「予測することができた範囲を超える効果」ならば「予測することができなかった効果」であるといえるだろうから、(②が成立するならば①は成立するという論理式は成立する。)
このような記載も、別個独立の要件と解した場合に①の主語を②とは異なるものにしたくなる原因となっているだろう。
つまり、主語が「効果の程度」であるならば、最高裁はなぜ①を記載したのか。②に該当すれば①は満たされるのだから、わざわざ難解な①を持ち出さずとも、②だけでよかったのではないか、とも思えるのである。しかし、これは上記最高裁判決の事例が深く関わっているものと考えられる。
最高裁は、前審の知財高裁がした判断を「本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定」したものと評している。
つまり、前審知財高裁は、本件発明に係る化合物ではなく、他の化合物が奏する効果から「これと同等の効果であれば当業者が予測できる範囲の効果といえるだろう」と考え、本件発明の化合物も同等の効果しか奏していないから、顕著な効果とはいえないものと判断した。
しかし、おそらく最高裁は、「なぜ他の化合物が奏する効果の程度が、これと異なる化合物である本件化合物が奏する効果の程度として予測できるのか」という点に疑念を抱き、知財高裁のした判断が合理的な根拠を欠いていると判断したのではないだろうか。その効果はあくまで他の化合物の効果であって、他の化合物が奏するからといって、本当にそれが本件化合物でも同様に奏すると予測できるのだろうか。このような疑問があったからこそ最高裁は判示において「本件発明の構成が奏するものとしての予測可能性」を強調したのではないだろうか。
それまで用いられてこなかった化合物を用いた場合、その化合物によってどの程度の効果が得られるかは予測しづらいことがある。その化合物が、効果の発生原理に関して、他の化合物と同じ特性や構造を有しているならば、少なくとも当業者は「この化合物においても同様の効果が発生すること」を予測できるし、そこから更に「この化合物を使えば、他の化合粒と同じ程度の効果は得られるだろう」と予測することもできるかもしれない。
一方で、化学の分野においては、効果を発生させる正確な原理がわからず、よって、効果の発生に直結する特性や構造がわからない場合も少なくない。このような場合には、当業者は「他の化合物と同じ程度の効果が発生して欲しい」と期待することはあるかもしれないが、予測はできないと言うべきである。
そして、発生する効果の程度が未知数であるならば、既存の他の化合物と同等の効果が得られることを以て「顕著」と言ってもいいかもしれない。
実態的に捉えれば「まさか、既存の他の化合物と同じ効果が得られるなんて予想もしていなかった!」と当業者が驚く場合も十分にあり得るということである。
つまり、本件発明の構成が奏するであろう効果が予測できたとしても、どの程度の効果が発生するかについては「予測できる場合とできない場合がある」というのが社会の実態であり、この実態を踏まえて、最高裁は②だけでなく①を記載したのではないだろうか。
また、予測できる場合には、その予測を超えるような効果が得られれば顕著な効果といえるであろうが、予測できない場合にまで、その効果の程度が顕著であるというために、常に同じ効果を発生させる既存のものを超えなければならないとする理由もないことを最高裁は述べたかったのではなかろうか。
私には、最高裁の判示が、顕著性のハードルを「他の化合物が奏する効果の程度」に設定したことについて、その予測可能性を十分に考慮しておらず、そのような前審の判断の仕方に誤りがあったと述べているに過ぎないように読め、詰まるところ、「もっと当業者の身になって、実態を踏まえて考えなさい」といっているように思えるのである。
このような視点に立てば、下記再掲の最高裁の判示についても、別の見方ができるだろうし、より素直に読めるのではないか。
「原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく,このような原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」
下線を付したように、最高裁はあくまで「観点から」と述べているのであり、①と②を要件として規定しているわけではない。また、「十分に検討することなく」という言葉も、検討の不十分性を指摘しているのであるから、素直に読めば「①や②の観点を取り入れながら、もっと考えて判断しなさい」と言っているに過ぎず(考慮すべき事項を考慮していない考慮不尽を指摘したに過ぎず)、①と②を別個の要件とする意図は、この判示からは全く読み取れないのである。
この最高裁の事例でいえば、公知技術を踏まえれば、「本件化合物によって、他の化合物が奏する効果と同様の効果が発生すること」については、当業者であれば予測できたのではないかと思える(既存の他の化合物の代替物として本件化合物を適用することの動機付けが当業者にあるならば、代替物として同様の効果が発生することは、単なる期待を超えた、相当程度の化学的見地に基づく予測可能性として認められるのではないか。)。一方で、発明の技術分野を踏まえれば、その効果の程度がどれくらいになるかは予測できない未知なものであっただろう。その上で、既に知られている他の化合物と同程度の効果が得られることは、単に予測できないだけでなく、予測できない顕著なものであったと評価できるのではないだろうか。
私が述べたように最高裁の判示を解釈すると、実体的な判断は、上記知財高裁が示したものよりも一層難しくなるだろう。「その効果が予測できないものであればよい」とする安直な判断とは違い、「効果の程度が予測できない場合」であってときには、「ではその場合には、どの程度の効果を奏すれば顕著と評価してよいか」という判断をしなければならないからである。だからといって、実体的・本質的な判断を避けて安直な判断に逃げるというのでは、何のために裁判所に自由心証が認められているのかの意義が失われるだろう。(安直な判断に逃げていいための自由心証ではない!)
この判断の一手法として、既存の代替物によって生じる効果の程度を基準とすること自体は許されないものではないだろうし、これを基準とすることには合理性も認められるだろう。「顕著性」というからには、何らかの基準は必ずなければならないのであり、その基準は、既存の公知技術に基づく他ないはずだからである。
問題は、既存の代替物による効果の程度を基準とした場合に、これの何%に達すれば顕著といっていいかであろう。100%を超えればよいのか、150%を超えなければならないのか、あるいは100%を下回る80%でもよいのか。この点については、その技術分野における事情が考慮されるべきと考える。
例えば、これまで用いられてこなかった本件化合物を用いたことで、既存品の80%の効果が得られたとする(また、80%は製品としての品質基準は十分に満たすものであったとする)。これに加えて、本件化合物は、安価であり、資源も豊富にあり、毒性も少ないため、このような本件化合物を用いることができれば、安全に大量生産ができ、安価に提供することができるため産業の発達に多大に貢献するものであるとするならば、80%でも「予測できない顕著な効果」を認めてよいかもしれない。(このような有意な物質の中に、既存品の80%という十分な品質をクリアできる物質があったとは、当業者は思いもしなかった!)
「効果の顕著性」という判断要素は、言ってしまえば、産業発達への貢献度というべきであり、想定よりも貢献度が大きいから、このような発明に特許権を付与することも、産業発達に寄与する発明を保護するという特許法の法目的に反しないと考えるのが、スマートな考え方かもしれない。
このように、「予測できない顕著な効果」は、最高裁の判示は、あくまで効果の顕著性の話として「予測できないほどの顕著な効果」と解すべきというのが私の考えである。
その一方で、それでは発生する効果そのものが予測できない所謂「予測できない効果」については無視していいのかというとそういうわけではない。効果そのものが「予測できない効果」であることは進歩性の判断においてどのように扱われるべきか。最後にこの点について補足しておく。
既に述べた通り、その効果が、「発生することの予測できない効果であった」というだけで進歩性を認めることには反対である。しかしながら、予測できない効果が生じたことが、産業の発達に貢献し得ることも疑いようのない事実であろう。
審査基準には、次のような記載がある。
「引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。
(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合」
「引用発明と比較して」とされている部分は、必ずしも引用発明との比較によらなくてよいとした最高裁の判断とは異なっており、宜しくない部分ではあるが、注目したいのは(i)の「異質な効果を有し、予測することができたものではない」との記載である。
このように、単に「予測できない効果」であるかを判断するだけでなく、その効果が「異質なものである」という観点を取り入れるのは賛成である。「異質なもの」とは、本願発明の構成に対応する既知の構成(上記最高裁の事例で言えば、本件化合物に対応する他の化合物)が奏する効果と比較して異質といえるだけでは不十分であり、当該構成が奏する効果でなくとも対象発明(上記最高裁の事例で言えば、眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤)が客観的・一般的に有するとされている効果とは異質の効果であるべきである。
なぜならば、たとえ当該構成が奏するものであることが認識できずとも、本願発明がその対象発明に係る発明を創作するものである以上、その対象発明が有する一般的な効果については、当該構成も何らかの効果を及ぼし得ることは期待できるからである。当業者が期待できるような効果であれば、それは異質とはいえず、当該構成が奏する効果として予測できなかったというだけで進歩性を認めるべきではない。(単なる「効果の発見」を助長してしまうからである。)
つまり、上記のような「異質性」に限られるものでもないかもしれないが、「予測できない効果」については、当該効果が「その構成によって生じることの予測困難性」だけでなく「対象発明が奏するものとしての新規性」を評価すべきではないかと考える。
このような考え方によると、上位最高裁の事案では、本件化合物による効果が既に他の化合物によって奏する効果と同様のものである以上、仮に「本願発明の構成によって生じることが予測困難」であったとしても、発生した効果そのものは「対象発明である眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤が従来から奏している効果」に過ぎないため、これだけで進歩性を認めることはできない、という評価になる。

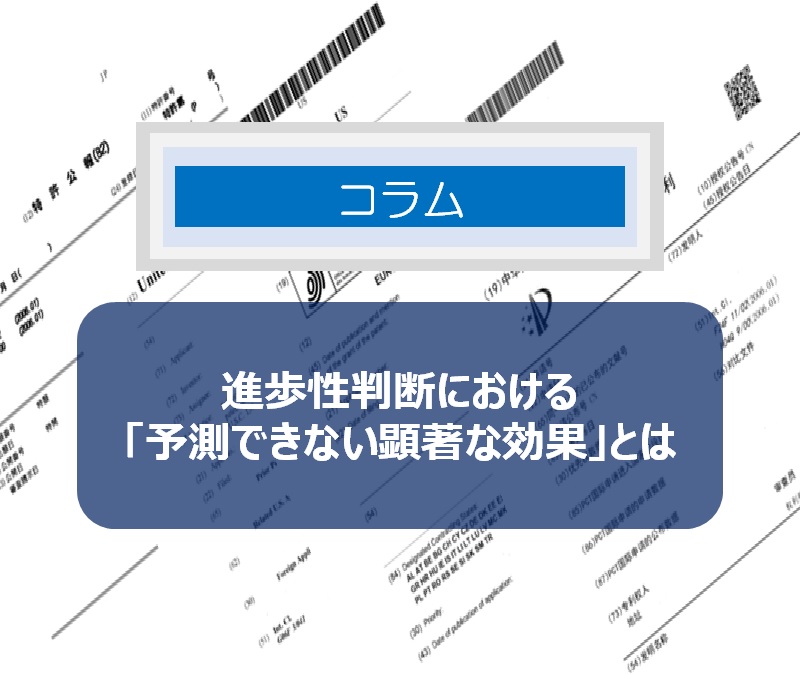


コメント