企業が特許を取得するのは、その特許が“ビジネス(事業)のため”になるからである。また、“ビジネスのため”になる特許といえるには、その特許権が市場に対するプレゼンスを有していなければならない。市場に対する存在価値のない特許権は、競合他社に見向きもされず、他社参入に対する何らの歯止めにもならないからである。
企業が特許を取得する目的は、実際に権利を行使するか否かはともかく、その特許権によって市場における企業のプレゼンスを向上させ、長期にわたってビジネス上の優位な立場を維持することにある。これ以外の目的は、ただの誤魔化しに過ぎない。
1件の特許を取得する費用は決して安くない。
最初の出願費用だけでなく、その後の審査に関する費用や、特許が認められた後に払う年金費用などを含めれば、安くても100万円は予算をみておくべきだろう。
100万円以上の費用をかけて取得する特許権なのだから、100万円以上の利益創出に貢献しないことには元が取れない。例えば、ある商品Aを販売したときに、特許権があってもなくても、その販売額に変わりがないならば、特許は出願するだけ無駄であり、出願しなければ得られていたはずの100万円以上の利益を奪ったという視点からみれば、特許出願は損失とも捉えられる。
特許に精通していない企業経営者であれば、特許を出願しておきながら、特許権があってもなくても販売額に変わりないなどということがあるのか?と疑問に思うかもしれない。特許権を持っているからには、その特許権は何らかの形で売上の上昇に貢献するはずではないかと。
しかし、あなたが取得できた特許権が、商品Aに搭載される技術をカバーする権利でなかった場合、また、商品Aに搭載される技術をカバーする権利であったとしてもその技術が競合他社が模倣したがるような技術でなかった場合など、取得した特許権が利益創出に貢献しないものとなってしまうことは決して珍しくない。
当たり前の話だが、特許を出願するからには、そこに投じる費用が回収され、投じた費用以上の利益創出に貢献することを目指さなければならず、飾りで持っておく特許ほど企業の利益を無駄にするものはない。
そんなことは言われなくても理解していると思うかもしれないが、実際にこれを実践できている企業は決して多くはないだろう。日本に出願されている特許の多くが、利益創出に貢献することなく、只々コストとなって終わっていくだけのものではないだろうか。
その原因が「特許」に対する理解不足にある。
細かいことを話せば、話が長くなり、かえって理解し難くなることが予想されるため、ここであえて細かな話に踏み込むことはしないが、簡単な理解として、「特許は出願すれば「望んだ権利」が取れるわけではなく、後戻りで発明を出し直すことはできない(最初に出願した内容で、取れる権利の範囲は決まってしまう)」ということを覚えておくとよいだろう。
あなたの発明が素晴らしいからといって、あなたが取得する特許権が素晴らしい権利になるとは限らない。一方で、あなたが取得する特許権が、あなたが考えていた発明の価値よりも遥かに高い価値のものとなることもある。
このように、あなたが手にするアウトプット(得られる権利の質)は、どの特許事務所を選んでも等しく与えられるものではなく、特許事務所によってばらつきがある。それはビジネスでも同じことで、より優れたサービスを提供することが差別化になり、売上になるからである。
従って、あなた(企業)が我が子同然にビジネスを大事にし、成功へと辿り着くための努力を惜しまないというならば、最も重要なのは特許出願をどこに依頼するかにあり、初動の「特許事務所選び」にこそ労力を割くべきである。
あなたのビジネス成長に大いなる武器を与えてくれる可能性が高い特許事務所を選ばなければならない。
しかしながら、実際にどのようにして特許事務所を選べばよいのか。特許事務所の良し悪しを判断する材料は、極めて少なく、具体的でない。どの特許事務所のHPをみても、理念のような「想い」や、得意とする技術分野、国内外のサービスの充実度などは語られるものの、「ではあなたは実際にどのようなアウトプットを出せるのですか?」という問いに答えてくれるような記載はほとんど見ることができないだろう。特許事務所は、具体的な実務能力については、ブラックボックス化しているのが定常となっているのである。
このコンテンツを閲覧するには会員ログインをしてください。 ログインはこちら. 新規会員登録はこちら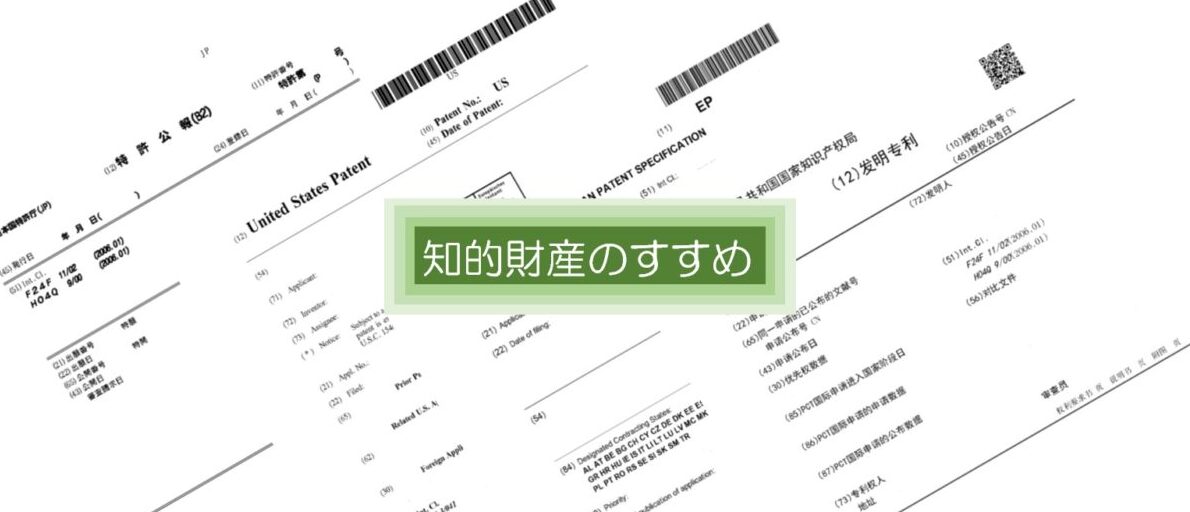
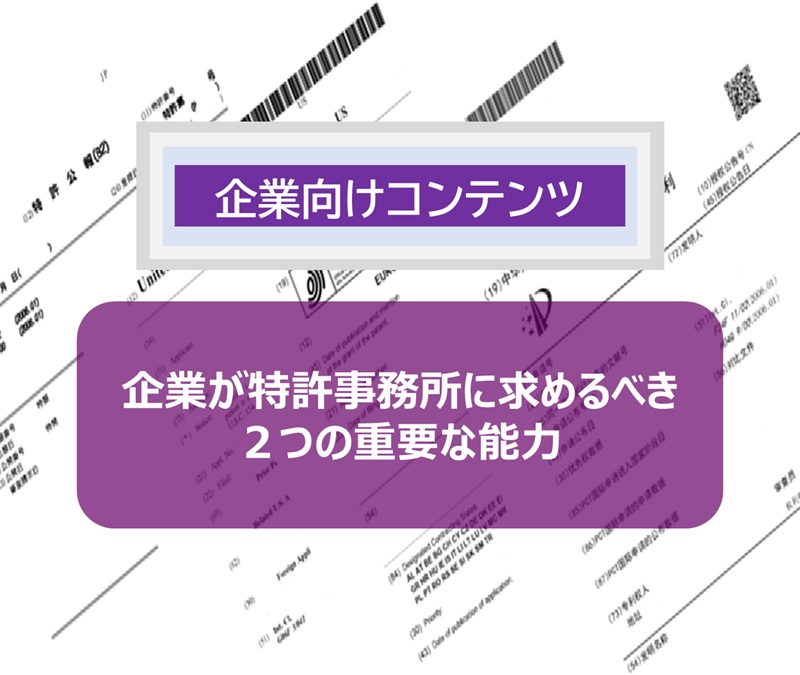
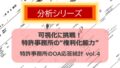
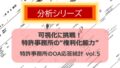
コメント