進歩性判断における請求認容判決の「拘束力」と請求棄却判決の「既判力」
2024/3/25判決言渡 判決文リンク
#特許 #進歩性 #既判力 #判決の拘束力
1.実務への活かし
・無効化 #判決の拘束力
無効審判段階において、進歩性判断で争いとなる「本願発明の認」「引用発明の認定」「一致点及び相違点の認定」「論理付け」「発明の効果(予測できない顕著な効果)」の全ての項目について、その公知事実(特定の引用文献等)から考えられる全ての論点を余すところなく挙げておくべきである。
∵本件の知財高裁は、進歩性判断における「論理付け(主引用発明に副引用発明を適用する動機)」が争点となり取消判決が確定した第一次(前訴)判決の「判決の拘束力」に基づき、再審理となった無効審判で「第一次判決で審理判断されなかった事項(「相違点の認定」における実質的相違点性)を主張すること」が許されないと判断した。
具体的に知財高裁は、「相違点の認定」における実質的相違点性が第一次判決において判断されなかったものと認めた上で、「(判決の)拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、甲1引用発明に基づく進歩性欠如を否定した第一次判決の法律判断の前提となった本件発明1等と甲1引用発明との間の相違点に係る事実認定についても、第一次判決の拘束力は及ぶというべきである。」と判断した。
2.概要
本件は、第一次判決によって確定した「請求認容(審決取消)判決」の拘束力と、請求棄却(審決認容)判決」の既判力について、知財高裁が判断を示した事例である。(なお、第一次判決は、当サイトでも紹介した「令和3年(行ケ)第10136/10138号」である。)
第一次判決では、その前審において、訂正された請求項1、2、4-7のうち請求項1、2、5乃至7については無効と判断され、請求項4については有効と判断された審決に対して、特許庁が無効と判断した部分(請求項1、2、5乃至7)については取り消し(請求認容)、有効と判断した部分(請求項4)については審決を維持した(請求棄却)。
この第一次判決が確定し、審理が再び特許庁に戻ったため、特許庁は、請求項1、2、4-7について有効と判断し、無効審判の請求人であるアンド社が審決の取り消しを求めたのが本件である。
本件でアンド社は、進歩性判断の誤りを取消理由とする訴訟を提起した。また、アンド社のした主張は、甲1(特開2009-195938号)に記載された発明(甲1引用発明)を主引用発明とする進歩性欠如の無効理由についてであり、この無効理由自体は第一次判決と同様であった。
<判決の拘束力について>
アンド社は、請求項1に係る発明(本件発明1)については、相違点2に係る構成の一部である「溶融した前記半田片が…前記ノズルの内壁と前記端子の先端に規制されるため必ず真球になれないまま…停止」するとの部分(以下「本件構成」という。)については、発明特定事項とは言い難く、意味を持たない事項に過ぎないため、相違点とならないと主張した。
第一次判決におけるアンド社の主張は、甲1引用発明との相違点である相違点2については、甲15や甲10の記載から当業者が容易になし得たことという主張であった。
つまり、第一次判決では、「主引用発明に相違点2に係る構成を適用することは当業者が容易になし得たことである」という進歩性欠如の論理構成であったのに対し、本件では「そもそも相違点2における本件構成は、相違点として認定すべきではない」という進歩性欠如の論理構成へと、主張内容が変更されたのである。
本件におけるアンド社の主張(判決より抜粋。下線は付記)
「溶融した半田片が「必ず真球になれない」か否かは、実際に半田付け装置が使用されるまで確定されないことになり、その時点まで、当該装置が本件発明1の技術的範囲に属するか否かが決まらないことになるところ、本件発明1の発明特定事項に関し、そのような結果を招くような解釈をするのは相当でない。したがって、本件構成は、本件発明1が想定する実施品の利用態様に係る事項(用法を特定する事項)であるとしか解されず、発明に係る物の構造や特性を限定し得るような発明特定事項とはいい難いものである。
…本件構成は、本件発明1を特定する上で意味を持たない事項(単に本件発明1の用法を特定する事項)にすぎず、したがって、相違点2に係る本件発明1の構成のうち本件構成に係る部分は、本件発明1と甲1発明の相違点ではないと解するのが相当である。」
第一次判決におけるアンド社の主張(第一次判決より抜粋)
「発明の進歩性に関する判断は、先行技術に基づいて当業者が当該発明の構成に容易に想到し得たことの論理付けができれば足りるところ、甲15には、フラックス含有量が1wt%の半田が記載されているほか、甲10には、日本工業規格として記号F1の半田が定められ、フラックスを1wt%含有する半田は、記号F1の半田に該当するから、このような半田を採用して相違点2に係る本件発明1の構成を得ることは、当業者が容易になし得たことである。」
この点について、本件の知財高裁は、行政事件訴訟法33条1項の判決の拘束力、及び、これに係る最高裁判例に基づいて、アンド社の主張は許されないと判断した。
行政事件訴訟法33条1項
「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」
判決の拘束力に関する最高裁判例(昭和63年(行ツ)第10号)
「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は、特許法181条2項の規定に従い、当該審判事件について更に審理を行って審決をすることとなるが、審決取消訴訟は、行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理又は審決には、同法33条1項の規定により、当該取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は、取消判決の当該認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につき、これを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは、当該主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。
このように、再度の審決取消訴訟においては、審判官が当該取消判決の主文のよって来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上、その拘束力に従ってされた再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは、確定した取消判決の判断自体を違法として非難することにほかならず、再度の審決の違法(取消)事由たり得ない。
以上を特許発明の進歩性判断が問題となる特許無効審判事件の審決の取消訴訟について具体的に考察すると、特許無効審判の対象とされた特許発明が、特許出願前に当業者において特定の引用例に記載された発明に基づき容易に発明をすることができたとはいえないとの理由により、当該特許発明に係る特許を無効とした審決の認定判断が誤りであるとして当該審決を取り消す旨の判決がされ、これが確定したときは、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は、同一の引用例に記載された発明に基づく進歩性の判断に当たり、当該判決と異なる認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審決に係る審決取消訴訟において、関係当事者が、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断が誤りである(当該特許発明は特許出願前に当業者において同一の引用例に記載された発明に基づき容易に発明をすることができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、また、裁判所が、これを採用して取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることは許されないと解するのが相当である」
特に、本件で知財高裁は、判決の拘束力の範囲である「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」について、次のように述べ、「相違点に係る事実認定についても判決の拘束力は及ぶ」ものと判断した。
知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)
「確かに、乙22によると、第一次判決においては、原告が本件訴訟において取消事由1…として指摘する事項(相違点2…に係る本件発明1等の構成のうち本件構成に係る部分の実質的相違点性)についての判断がされなかったものと認められる。しかしながら、本件発明1等に係る甲1引用発明に基づく進歩性の判断は、本件発明1等及び甲1引用発明の各認定並びにこれを前提とする一致点及び相違点の認定を踏まえて行われる法律判断である。前記のとおり、拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、甲1引用発明に基づく進歩性欠如を否定した第一次判決の法律判断の前提となった本件発明1等と甲1引用発明との間の相違点に係る事実認定についても、第一次判決の拘束力は及ぶというべきである。」
<判決の既判力について>
アンド社は、請求項4に係る発明(本件発明4)については、相違点5について、「甲11から13までにより認められる後記(2)の周知技術を適用し、甲1発明の「半田鏝の先端部の貫通孔の内径」を局所的に拡大すれば、相違点5に係る本件発明4の構成が得られる。」と主張した。この主張は、第一次判決においてなされた主張とおよそ同じものであった。
第一次判決におけるアンド社の主張(第一次判決より抜粋)
「甲1発明においても、「ノズル後端部」に相当する部分は、「当接位置規制手段」に相当する部分の後端部であると解釈すべきである。そして、甲11ないし13によると、半田ごての先端部の貫通孔においてピンが挿入される部分の内径を局所的に大きくすることは、周知技術であると認められるところ、「ノズル後端部」に相当する部分を「当接位置規制手段」に相当する部分の後端部であると解釈した場合、上記周知技術を適用して甲1発明の半田ごての先端部の内径を局所的に大きくしても、「当接位置規制手段」に相当する部分の後端部の内径は、十分小さいままであるから、「半田片の端子側の端部を端子の先端に必ず当接させ」るとする本件発明4の構成は維持されているといえる。したがって、甲1発明に上記周知技術を適用することには何らの阻害要因もないから、当業者は、甲1発明に上記周知技術を適用して、相違点5に係る本件発明4の構成に容易に想到し得たものである。」
行政事件訴訟法33条1項の「判決の拘束力」は条文の通り「取消判決」について及ぶものであるが、本件発明4については、第一次判決の前審である無効審判において有効(請求不成立)と判断され、第一次判決もこれを支持したため、請求棄却となった部分である。そのため、請求棄却判決については、民事訴訟法114条の「既判力」が及ぶに留まり、「判決の拘束力」が及ぶと解することはできない。
民事訴訟法114条1項
「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」
しかしながら、本件の知財高裁は、最高裁大法廷判決(昭和42年(行ツ)第28号)を踏まえて、次のように判断し、判決の拘束力を拡張した。
知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)
「行政処分の取消訴訟については、請求棄却判決が確定すると、処分に違法性がないことについて既判力(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法114条)が生じるから、審決取消訴訟についても、請求棄却判決が確定すると、審決に違法性がないことについて既判力が生じる。
しかるところ、最高裁昭和51年3月10日大法廷判決(昭和42年(行ツ)第28号)民集30巻2号79頁の趣旨を踏まえると、特許発明の進歩性判断が問題となる特許無効審判事件の審決の取消訴訟における請求棄却判決の既判力は、審決に違法性一般がないことではなく、特許無効審判事件において審理された特定の引用例に記載された発明(公知技術)に基づく進歩性の有無について判断した審決に違法性がないことに関して生じるものと解するのが相当である。」
その上で、知財高裁は「甲1引用発明に基づき、本件発明4が進歩性を欠くとはいえないとした第一次審決に違法性がないことは、既判力をもって確定されている」とし、「本件訴訟において、甲1引用発明に基づき、本件発明4が進歩性を欠く旨主張し、進歩性欠如を否定した本件審決の判断部分が違法である旨主張することは、実質的にみれば、第一次審決の違法性に関し既判力が生じている部分(同じ引用発明に基づき進歩性がないとはいえないとの判断)について、これと異なる判断を求めるものとして、許されないというべきである」と述べて、アンド社の主張は許されないものと判断した。
3.雑感
3-1.判決についての感想
全体的な結果について:結論納得度100% 判断納得度70%
本判決は、結論としては至極まともなものであり、本件訴訟において知財高裁のした結論が導かれるべきであろうことは、おそらく疑いがないだろう。特に、第一次判決において請求が棄却された「請求項4に係る発明の進歩性」については、その主張内容もおよそ同じものであり、第一次判決が確定した後の本件訴訟(後訴)においては、まさに紛争の蒸し返しになっているため、許されるべきでないことは明らかである。
一方で、どのような法律構成によってこの結論を導くかという問題があり、本件の知財高裁が、既判力の及ぶ範囲(客観的範囲)として、その内容を主文から拡張させたところに本判決の非常に興味深いところがある。判決を素直に読めば、本件の知財高裁は、既判力の客観的範囲として争点効を認めたものとする解釈も可能なように思えるが、これまで最高裁が争点効を認めてこなかったことからすると、本件は民訴法学者にとっても興味をそそる裁判例ではないだろうか。
既判力の判断について
当サイトは法学者向けではなく、知財実務家向けであるため、既判力について簡単に説明しておく。民訴法114条1項は、既判力を「主文に包含するものに限る」と規定しており、既判力の及ぶ客観的範囲については争いがある。
既判力とは、前訴確定判決が与える後訴に対する拘束力である。同一の当事者が前訴と後訴で同じ訴訟物を争った場合、後訴の裁判所は、既判力の及ぶ範囲において、前訴と矛盾抵触する判断をすることができない。
そもそも、なぜ既判力が認められるのか、という話に立ち返ると、一般には、当事者に手続き保障が図られていることを前提に紛争の蒸し返しを防ぐことが挙げられる。当事者に十分な攻撃防御の機会が与えられており、その結果として出された確定判決に対して、紛争の蒸し返しとなる当事者の行為を許してしまえば、裁判による紛争解決の実効性が失われてしまうからである。このことが、既判力を認める根拠となる。
それでは判決のどこまでに既判力を及ぼせばよいか。上記の根拠に基づくなら、紛争の蒸し返しとなり、紛争解決の実効性が失われてしまう事態を防げればよいということになる。
例えば、判決文のおける裁判所の事実認定及び法律判断の全てに既判力を認めるとどうなるか。
知財関連の例を挙げると、冒認出願に基づく特許無効を争った前訴において裁判所が「被告は故意に発明を冒認した」と判断し、冒認出願を認めたとする。その後、前訴原告が前訴被告に対し冒認出願の不法行為に基づく損害賠償を請求する後訴が提起された場合、全てに既判力が認められるとなると、前訴の冒認出願では要件となっていない「故意(故意により発明を冒認し、原告の特許を受ける権利を侵害したこと)」にも既判力が及ぶことになるため、後訴において、損賠請求の要件である「故意」を争うことはできなくなる。
しかし、訴訟の実態を考えてみるとどうだろう。前訴で冒認出願を争った当事者において、故意の有無は大きな争点ではない。故意であろうが過失であろうが無過失であろうが、他人の発明を勝手に出願して権利化すれば、冒認出願は成立する。
そのため、前訴における当事者間の争点意識は「故意」には向いていないだろうし、この点についての十分な訴訟活動が行えたとも言い切れないだろう。それにもかかわらず既判力が及んでしまうとなっては、既判力の根拠である「当事者の手続き保障が図られたこと」が前提とならず、不十分な手続き保障の上で司法が強引に紛争を終結させてしまうことになりかねない。
このように、既判力が前訴判決文に記載された一切の事実認定及び法律判断に及ぶことに問題があることについては争いがない。それでは、既判力の及ぶ範囲は主文のみとすればよいか。この点については、裁判による紛争解決の実効性が図れるか、紛争の蒸し返しとならないかの観点で争いがある。
既判力を主文から拡張する考え方の一つとして争点効がある。争点効は、既判力の及ぶ範囲を、主文のみに限らず、主要な争点についての裁判所の判断にまで拡張する考えである。争点効は、「主要な争点についての裁判所の判断」が判決文の内容のどこまでをいうのかが不明瞭であり、価値判断となってしまうために新たな争点を生じさせる懸念がある。既に述べたように、最高裁判所は、根拠条文の無い“争点効”の考えを悉く否定している。
その上で、本件の知財高裁は「審決取消訴訟についても、請求棄却判決が確定すると、審決に違法性がないことについて既判力が生じる」としながらも、続けて、「最高裁昭和51年3月10日大法廷判決(昭和42年(行ツ)第28号)民集30巻2号79頁の趣旨を踏まえると、特許発明の進歩性判断が問題となる特許無効審判事件の審決の取消訴訟における請求棄却判決の既判力は、審決に違法性一般がないことではなく」と述べ、さらに「特許無効審判事件において審理された特定の引用例に記載された発明(公知技術)に基づく進歩性の有無について判断した審決に違法性がないことに関して生じるもの」と判断したのである。
拒絶審決や特許無効/有効の審決といった行為は行政処分であり、審決取消訴訟は、行政処分の取消訴訟である。そして、行政処分の取消訴訟における審理の対象は、処分の違法性一般であり、我々は、特許庁のした処分が適法か違法かを争っているわけである。そのため、訴状においては「審決を取り消す」ことが請求され、判決主文においても「審決を取り消す」ことあるいは「請求を棄却する」ことが判断される。
そうすると、少なくとも既判力が及ぶ「主文」については、知財高裁が述べるように「請求棄却判決が確定すると、審決に違法性がないことについて既判力が生じる」に過ぎない。特定の引用例に記載された発明(公知技術)に基づく進歩性の有無について判断は、判決理由中の判断であり、審決に違法性がないことを導くための請求原因に対する判断のはずであるが、知財高裁は、既判力の及ぶ範囲をここまで拡張したのである。
従って、本件の判決を、争点効の考えに通ずるところがあると読むことは十分に可能であろう。
上述の通り、最高裁が争点効を否定する理由には、その根拠条文がないことが推測として挙げられる。主文に“包含するもの”の解釈として、主文以外の部分にまで既判力が及ぶという法律解釈を最高裁は採っていない。
本件の知財高裁は、おそらくこの点に配慮して、判決文に「最高裁昭和51年3月10日大法廷判決(昭和42年(行ツ)第28号)民集30巻2号79頁の趣旨を踏まえると」と記載したのであろう。つまり、最高裁の大法廷判決を挙げて、既判力を主文から拡張した部分にまで認める法的根拠を補充しようとしたように思える。
一方で、本件知財高裁は「大法廷判決の趣旨を踏まえると」と述べるのみであり、具体的に大法廷判決のどのような記載を踏まえたのかについては明言していない。これは意図的なものであろう。法的根拠の具体的な明言は避け、曖昧にしておきたいという心理が働いたように思える。
本件知財高裁は、上記大法廷判決のどのような記載を踏まえたのか。私なりの推測をピックアップしておく。
第一に、以下の部分が挙げられる。
「法は、特許出願に関する行政処分、すなわち特許又は拒絶査定の処分が誤つてされた場合におけるその是正手続については、一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判及び抗告審判(査定については抗告審判のみ)の手続の経由を要求するとともに、取消の訴は、原処分である特許又は拒絶査定の処分に対してではなく、抗告審判の審決に対してのみこれを認め、右訴訟においては、専ら右審決の適法違法のみを争わせ、特許又は拒絶査定の適否は、抗告審判の審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめていることが知られるのである。
…法は、特許無効の審判についていえば、そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされることを要求し、審判手続においては、右の特定された無効原因をめぐつて攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかであり…。そしてまた、法が、抗告審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判及び抗告審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならないと解されるのである。
右に述べたような、法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。」
この部分は、特許の無効審判が、通常の行政処分とは異なる性質を有していることを述べている。無効審判においては、そもそも審判請求の時点において、特許が無効となるべき無効理由を特定すること、言い換えれば、審判対象を特定することが要求されており、その意味で、特許査定という行政処分の違法性一般を広く争わせる構造を採用していない。そして、これを受けた取消訴訟においても、審理の対象は「無効審判において現実に争われ、審理判断された無効原因のみ」とされているのである。
これは、既判力の根拠となる「当事者への手続保障」に関わるところであろう。審判請求時に「進歩性」を無効理由として特許の無効を争った場合、その後の取消訴訟において実施可能要件やサポート要件などの他の無効理由を争うことはできない。これは、無効審判において、第1審に相当する制度の充実を図り、当事者による攻撃防御の機会が事実上与えられていることとの関係から、取消訴訟における後出しの無効理由の主張を制限する趣旨と取ることもできよう。
既判力を認める根拠が、当事者への手続保障にあるとすれば、既判力の及ぶ範囲も当事者への手続保障が図られたといえる範囲のみに及ぶものとすべきである。取消訴訟において主張することが禁止されている無効理由にまで、裁判所のした審決の適法/違法性の判断の既判力が及ぶことになっては、主張が禁止されていることとのバランスが取れず、既判力を正当化する根拠が失われることになる。
しかし、ここで考えなければならないのは、無効審判請求時に特定の無効理由を挙げることが要求されているとはいえ、その無効理由を選択するのは請求人であるという点である。請求人はいずれの無効理由も選択できる状況の中で、自ら特定の無効理由を選択し、無効審判を請求するのであるから、その時点において、自らの意思で「その余の無効理由を放棄した」と考えることもできるため、既判力を拡張して請求人の利益を図る必要があるのかという議論が生じよう。
そこで、大法廷判決が述べた次の点も、重要な要素といえるだろう。
「公知事実は、広範多岐にわたつて存在し、問題の発明との関連において対比されるべき公知事実をもれなく探知することは極めて困難であるのみならず、このような関連性を有する公知事実が存する場合においても、そこに示されている技術内容は種々様々であるから、新規性の有無も、これらの公知事実ごとに、各別に問題の発明と対比して検討し、逐一判断を施さなければならないのである。法が前述のような独得の構造を有する審査、無効審判及び抗告審判の制度と手続を定めたのは、発明の新規性の判断のもつ右のような困難と特殊性の考慮に基づくものと考えられる。…そうであるとすれば、無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。」
大法廷判決は、広範多岐に存在する公知事実を根拠とする無効理由については、その全てを一回的に解決することの現実的困難性を考慮し、審判請求における審判対象を特定の無効理由とし、取消訴訟においても審理の対象を審判で争われた無効理由に制限するという、独特の法律構造を特許法が採ったものと理解している。そしてこのことは「発明の新規性の有無が証拠として引用された特定の公知事実に示される具体的な技術内容との対比において個別的に判断されざるをえないことの反映」として、特許法において一事不再理の効果の及ぶ範囲を同一の事実及び証拠によつて限定すべきものとしていることの趣旨として理解できるとも大法廷判決は述べている。
このように、大法廷判決は、少なくとも、広範多岐に存在する公知事実を根拠とする無効理由(新規性、進歩性、拡大先願、同一発明)については、あらゆる公知事実に基づく「新規性」や「進歩性」の判断を一回的に判断できないことから、ある公知事実に基づく無効の主張と他の公知事実に基づく無効の主張を別個の理由と解したのである。
これらの大法廷判決の判断をまとめると、特許法に規定された独特の法律構造(審判請求において無効理由を特定し、知財高裁においても審判で争われた無効理由に審理対象を制限する構造)は、広範多岐に存在する公知事実に基づく無効理由の一回的解決の現実的困難性を考慮したものであり、この法律構造においては、当事者の攻撃防御の機会は「ある公知事実に基づく無効理由」に、審判開始の当初から制限されているのである。
本件知財高裁はこのような大法廷判決の趣旨を踏まえ、少なくとも進歩性の無効理由に対しては、「特許発明の進歩性判断が問題となる特許無効審判事件の審決の取消訴訟における請求棄却判決の既判力は、審決に違法性一般がないことではなく、特許無効審判事件において審理された特定の引用例に記載された発明(公知技術)に基づく進歩性の有無について判断した審決に違法性がないことに関して生じるものと解するのが相当である。」と判断したものと理解することができるだろう。
また、本件知財高裁が「大法廷判決の趣旨を踏まえる」と述べるのみであったのは、これらの記載が全て傍論であったからではないかと考えられる。大法廷判決が示した法規範は「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」というものである。
大法廷判決を、法律判断の拠り所としながらも、その拠り所が傍論部分であることから、本判決において、大法廷判決の具体的な内容を示すことを避けたと考えるのが自然なように思える。
さて、ここまで話した上で、アンド社による再度の主張を認めるべきではないとの結論は至極真っ当なものであると思うが、本件の知財高裁がした「既判力」の判断には、解決できていない大きな問題点(欠陥)が残されている(判断納得度が結論納得度よりも低かったのはこの点にある)。おそらく、知財に明るくない民訴法学者でも、この問題点の存在に気付くことはできるかもしれないが、なぜこの問題点が残されているのかに気付くことは難しいだろう。
この点については、話すとまた長くなってしまうため、「既判力の判断について」はこの程度にしておき、「判決の拘束力の判断について」に移ろうと思う。(当サイトの会員の方は、会員専用ページから質問してもらえれば概要をお伝えしたいと思う。)
判決の拘束力について
判決の拘束力については、結論及び判断のいずれにおいても、違和感なく読めたのではなかったかと思う。(但し、こちらも掘り下げていけば、議論すべき課題は残されている。)
本件の判決から覚えておくべきことは「判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、たとえ第一次判決が判断していない事項についての判断誤りを指摘するものであっても、第一次判決の進歩性判断の中で認定判断を経ているといえる事実認定についても、第一次判決の拘束力が及ぶ」ということであろう。
着目すべきは、アンド社の主張した「本件構成が実質的な相違点といえるか否かという点(実質的相違点性)」に関し、本件知財高裁は「第一次判決において判断がされなかったものと認められる」と述べている点である。
第一次判決において判断されなかった「相違点」の判断部分であっても、つまり、十分に当事者が主張を交わし判断がされなかった部分であるにしても、進歩性の判断は、「一致点及び相違点の認定を踏まえて行われる」ものである以上、新たな争点を持ち出して既に認定された「相違点」を争うことは、判決の拘束力によって許されないというのが、本件知財高裁の判断であろう。
本件知財高裁の考えに従えば、「予測できない顕著な効果」はさておき、少なくとも進歩性判断においては「本願発明の認定」「引用発明の認定」「一致点及び相違点」及び「論理付け」の各ステップを必ず経ることになるため、これらのステップにおいて十分に争われていなかった論点があったとしても、これらの各ステップにおける判断の全てが「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」である以上、判決の拘束力により争えないということになろう。
個人的には、本件知財高裁は中々踏み込んだ判断をしたように思える。また、この判断には、アンド社にとっては酷と思える部分もある。
第一次判決を詳細に見てみると、第一次判決では、その前審の無効審判において、本件発明1の進歩性はないと判断されていた(アンド社の主張は通っていた)。そこでは主に「フラックスの含有量が1.0wt%の半田片を用いることが容易になし得たか」が争点となっていた。
本件発明1の発明特定事項に「1.0wt%の半田片」という記載があるわけではなく、引用発明に1.0wt%の半田片を用いることができれば、結果的に「溶融した半田は真球になれない」ため、相違点2の構成となるという論理であった。
前審において「フラックスの含有量が1.0wt%の半田片を用いること」の動機付けが認められ、進歩性がないとされた審決に対して、パラッド社は取消訴訟を提起し、フラックスの含有量が1.0wt%の半田片が市場に存在していなかったことを理由として、その動機付けがないことを争った結果、パラッド社の主張が通り、出願時に市場に存在していなかった1.0wt%の半田片を適用する動機はないと裁判所は判断した。これが第一次判決である。
前審の無効審判で請求が認められていたアンド社は、審決の判断を維持すればよい立場である。取消訴訟では既に争点が「フラックスの含有量が1.0wt%の半田片を用いることの動機付け」に集中している中、このような立場にあるアンド社に、本件構成の実質的相違点性を新たに追加主張することを果たして期待できたか。
第一次判決においてアンド社が取消訴訟を提訴した者であれば、アンド社は審決の取消しを求めるために進歩性判断を覆すあらゆる主張をする立場にあるのだから、第一次判決の時点において実質的相違点性の主張もすべきであったと言われても納得がいく。
しかし、バラッド社の主張が妥当でないことを述べればよい立場のアンド社に対し、第一次判決においておよそ主張することが期待できなかったと考えられる本件構成の実質的相違点性が、第一次判決の拘束力によって封じられてしまうことは酷なように思える。
このような実態を考慮したときに、「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」の解釈を、全く挙がってもいなかった争点事項にまで及ぼすことが果たして適当といえるかは考える余地が残されているように思えるし、少なくとも第一次判決において裁判所が審理判断していなかった事項を持ち出すことは、裁判所のした判断を違法とするものとはいえない、という理屈を持ち出すことはできるだろう。
その一方で、本件のアンド社の主張が認められるとなれば、無効審判請求人による主張の後出しを助長することになるだろう。前訴において争われなかった判断事項に判決の拘束力が及ばないとなると、審判請求時やその取消訴訟時において「敢えて争わないでおく」ことを請求人は選択できてしまう。
敢えて争わない自体のメリットはあまりなさそうではあるが(結局前訴で主張できないなら、1つの判断事項について主張できる回数が1回ということに変わりはない。)、著しい訴訟の長期化を招くことは明白であろう。従って、このような訴訟行為の増長は、訴訟経済や紛争の一回的解決という裁判所が果たすべき重要な役割に悪影響を与えるものであり、これを防止することが強く要請されると考えるならば、やはり結論は妥当ということになる。
そうすると、アンド社としては、無効審判の請求時点において、実質的相違点性の主張をすべきであったという帰結になる。
それだけでなく、進歩性で議論となる項目「本願発明の認」「引用発明の認定」「一致点及び相違点の認定」「論理付け」「発明の効果(予測できない顕著な効果)」の全てについて、その公知事実(特定の引用文献等)から考えられる全ての論点を余すところなく挙げておくべきということになる。
言い換えれば、どのような論点を挙げられるかという実務能力が試されるのであり、この点では、私が「特許実務のすすめ」の形で各項目についての使えそうな論点を整理している取り組みは正解であったと評価できるかもしれない。

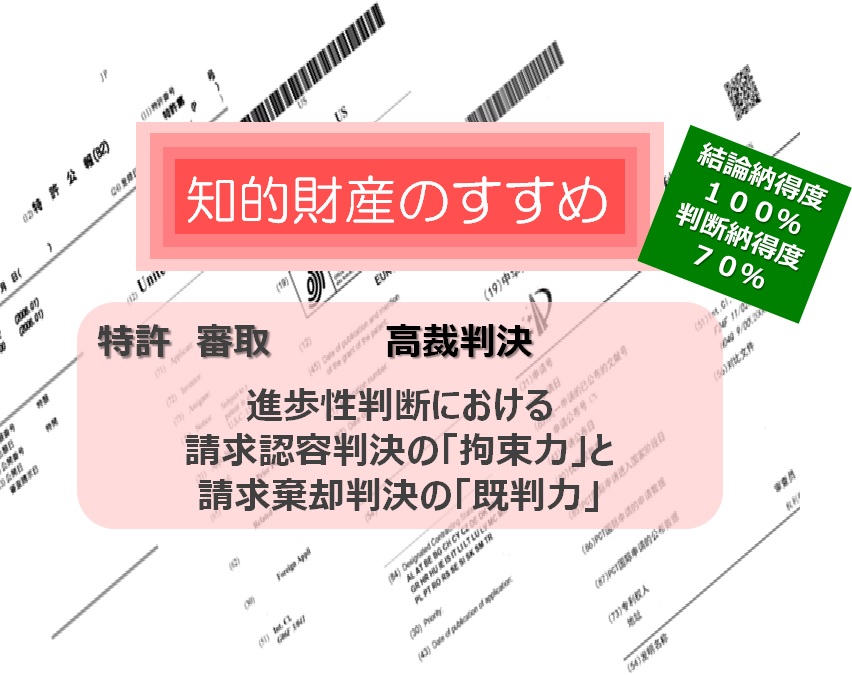


コメント