題材について
題材の選定条件:審査請求がされ、拒絶理由通知が出されたが、これに応答することなく拒絶査定が出された案件
例1:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
例2:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 意見書/補正書 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
題材:特願2020-211128
出願人:TOYO TIRE株式会社
代理人:特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
発明の名称:押出物の製造方法およびタイヤの製造方法
審査記録
2023年10月13日 審査請求
2024年 6月18日 拒絶理由通知(1回目)
同年 8月 6日 意見書及び補正書の提出
同年11月 5日 拒絶理由通知(2回目)
2025年 3月25日 拒絶査定
検討対象:2回目の拒絶理由通知
拒絶理由:29条1項3号および2項(新規性および進歩性)
簡単な概要
1回目の拒絶理由通知に対する補正後の請求項1は以下の通りである。
【請求項1】
カーボンブラックを含有するゴムコンパウンドにマイクロ波で熱入れする工程と、
熱入れされた前記ゴムコンパウンドを押出機で押出す工程とを含み、
前記ゴムコンパウンドに熱入れする前記工程で前記ゴムコンパウンドを60℃~90℃ の範囲内まで温める、
押出物の製造方法(ただし、前記ゴムコンパウンドに熱入れする前記工程で前記ゴムコ ンパウンドを90℃まで温める場合を除く。)。
また、1回目の拒絶理由通知で主引例として挙げられた引用文献1は特開平6-304923号公報であり、2回目の拒絶理由通知では新たに特開2010-189511号公報が引用されているため、この補正によって1回目の拒絶理由については一応の解消がみられたということができる。
なお、新たに引用された引用文献1(特開2010-189511号公報)は、出願人が東洋ゴム工業株式会社で、TOYO TIRE株式会社の社名変更前の会社名であるから、10年以上前の自社の過去出願が引用文献1に挙げられたといえる。(本願の出願日は2020年12月21日で、引用文献1の出願日は2009年2月17日)
また、引用文献1の審査経過をみると、審査請求後、1回目の拒絶理由通知を受け取ってから対応することなく拒絶査定となっている。こちらも権利化を断念した案件と考えられる。
10年以上前の出願内容を会社の従業員が把握していることは難しいし、知財担当がいたとしても当時の担当は別の者である可能性も十分にある。このような類似の出願を事前に把握できなかったのは残念ではあるが致し方ないかもしれない。
なお、引用文献1の出願における代理人も「ユニアス国際特許事務所」であるため、当事務所はTOYO TIRE株式会社と10年以上の付き合いがあると推測できる。それなり以上の信頼関係が構築されているのだろう。
1回目の拒絶理由通知では、29条2項の進歩性のみが拒絶理由に挙がっていたが、2回目の拒絶理由通知では、自社の過去出願が新たな引用文献1として引用された上で、29条1項3号及び2項、つまり進歩性だけでなく新規性の拒絶理由も挙げられた。
2回目の拒絶理由は「新規性」も含まれており、しかもそれが自社の過去出願である、というのはそれなりのインパクトがあるかもしれない。加えて、本願発明が開示されていると判断された引用文献1は10年以上前の出願であり、この出願に対しても出願人は権利化を諦めているのである。
これだけの状況を見ると、本願についても権利化を諦めるのが妥当のように見えるかもしれない。
しかし、このような外形的な状況だけで権利化が難しいと結論を出すのは尚早であるし、第一印象として「権利化が難しいのでは?」という先入観を持ってしまうのもよくない。
果たして、本願は、拒絶理由を解消することが困難であり、審査官の判断に承服するしかないのか。この点を検討していく。
検討の公開まで
「拒絶理由対応のすすめ」は、実際に検討された上で、記事の詳細を読む方が、スキルアップに効果的かもしれません。まずはご自身で検討してみてから記事を読みたいという方がいることも想定し、具体的な検討の詳細は、記事のアップから期間をあけて、7月31日に公開する予定です。
また、以下の「応答方針の検討」をご覧になる前に、「拒絶理由対応の本質」を読まれることをお薦めします。こちらを読んで頂いた上で以下の記事を読まれる方が、理解が深まると思います。
以下の「応答方針の検討」には、応答方針に至るまでの思考過程と、意見書案文を載せています。
応答方針の検討(結論:補正無しで応答できる) 公開予定7/31~8/31
応答方針の詳細については、2025年7月31日に公開予定(会員のみ閲覧可)
このコンテンツを閲覧するには会員ログインをしてください。 ログインはこちら. 新規会員登録はこちら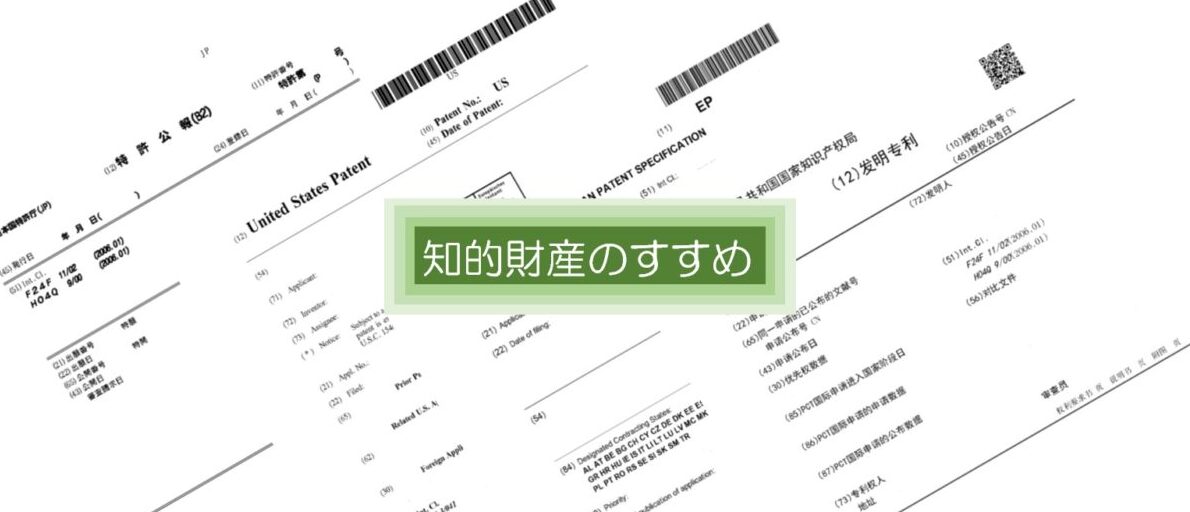
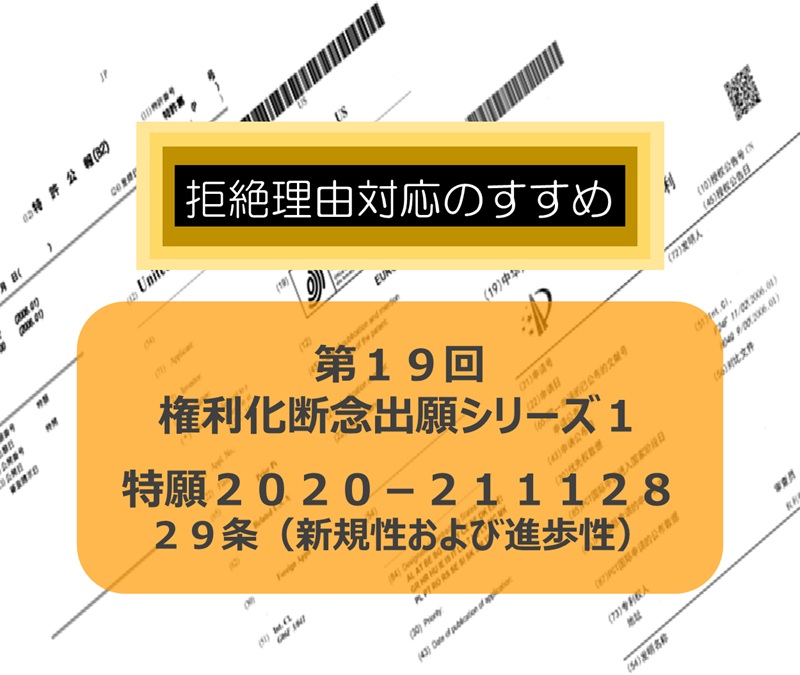
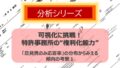

コメント