題材について
題材の選定条件:審査請求がされ、拒絶理由通知が出されたが、これに応答することなく拒絶査定が出された案件
例1:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
例2:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 意見書/補正書 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
題材:特願2020-201288
出願人:ミツボシプロダクトぷラニング株式会社 株式会社パートナーズ
代理人:弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
発明の名称:妊活情報提供システム
審査記録
2023年11月30日 審査請求
2024年 7月 2日 拒絶理由通知(1回目)
同年 8月28日 意見書及び手続補正書の提出
同年11月19日 拒絶理由通知(2回目)
2025年 4月15日 拒絶査定
検討対象:2回目の拒絶理由通知
拒絶理由:29条2項(進歩性)
簡単な概要
本件は、妊活をサポートする情報を提供するシステムに関する発明である。1回目の拒絶理由通知に対し、請求項の補正を行い意見書で特許性を主張したが、2回目の拒絶理由通知が出され、そのまま応答せずに拒絶査定が来たという案件である。
本願の請求項1は以下の通りである。
【請求項1】
妊娠に関する積極的な活動を行うことを望むユーザに健康状態の改善につながる有用な情報を提供するための妊活情報提供システムであって、
妊娠に関する検査の受診についての情報を提供する検査情報提供部と、
前記ユーザの妊娠に関する検査結果を基準値に基づいて判定する検査結果判定部と、
前記検査結果判定部の判定結果に基づいて前記ユーザが補充すべき栄養に関する不足栄養情報を特定する不足栄養特定部と、
前記不足栄養情報に基づいて前記ユーザが入手可能となる製品情報を提供する推奨製品選定部とを備えたことを特徴とする妊活情報提供システム。
1回目の拒絶理由通知では、29条2項(進歩性)の拒絶理由が挙げられた。主引例として挙げられたのは引用文献1で、特開2016-139310号公報である。また、請求項1に対し、引用文献2の特開2015-194807号公報及び引用文献3の特開2011-204194号公報が挙げられている。
本願の補正後の請求項1は以下の通りである。
【請求項1】(下線部が補正)
妊娠に関する積極的な活動を行うことを望むユーザに健康状態の改善につながる有用な情報を提供するための妊活情報提供システムであって、
妊娠に関する検査の受診についての情報を提供する検査情報提供部と、
前記ユーザの妊娠に関する検査結果を基準値に基づいて判定する検査結果判定部と、
前記検査結果判定部の判定結果に基づいて前記ユーザが補充すべき栄養に関する不足栄養情報を特定する不足栄養特定部と、
前記不足栄養情報に基づいて前記ユーザが入手可能となる製品情報を提供する推奨製品選定部とを備え、
前記製品情報はサプリメントに関する情報であって、前記推奨製品選定部では前記不足栄養情報に適した、少なくとも成分配合を含む推奨条件を満たすサプリメントを選定して、前記ユーザに前記推奨条件とともに製品情報を提供することを特徴とする妊活情報提供システム。
2回目の拒絶理由通知では、主引例と引用文献2はそのままで、引用文献3に代えて、引用文献4の特許第6684424号公報が新たな副引用発明の文献として引用された。出願人は、この2回目の拒絶理由通知に対して応答せず、その後に拒絶査定が来ており、最終処分が”拒絶”となっている。よって、本願の権利化は断念されたものといえるだろう。
本願は、図面を入れても全ページ数が12ページと少なく、コンパクトな内容となっている。私個人としては、読んでいて発明の厚みが感じられない、ビジネスモデルに近い内容のような印象を受けた。
例えば、引用文献1に挙げられている特開2016-139310は、全ページ数が61ページであり、段落数も【0350】の重厚なものとなっている。また、引用文献1は、特許査定となっており、特許第6608142号は2025年10月時点においても有効な特許となっている。また、この特許の請求項1は以下の通りである。
【引用文献1に係る特許の請求項1】
ユーザの検査結果データを含むヘルス情報と、前記ユーザの利用する医療機関または検査機関を含むユーザ属性情報と、を登録して管理し、医療機関または検査機関、検査方法、及び医学的な基準情報の数値範囲、を含む医療検査情報を管理するデータ管理部と、
前記ユーザ属性情報、及び前記医療検査情報を用いて、前記ユーザの前記検査結果データの検査項目の時系列の数値と、前記検査項目及び前記ユーザの利用する医療機関または検査機関に対応した、前記医療機関もしくは検査機関の前記検査方法に関連付けられた前記医学的な基準情報の数値範囲と、を比較した結果に基づいて、前記ユーザのヘルス状態を判定した結果を前記ユーザに対して出力する出力部と、
を有し、
前記医療検査情報は、前記医療機関もしくは検査機関、または、前記検査方法に応じて異なる前記医学的な基準情報の数値範囲の設定を含む、
サーバ装置。
下線が補正段階で追加された内容だと思うが、下線部を見ればわかるように、情報処理の具体的な内容に落とし込むことができ、特許を取るために内容を充実させたことが功を奏したことがわかる。出願時にきっちり「発明の深化」をさせておくと特許は取得しやすくなるが、引用文献1と比較すると、この部分の差が本願の結果に繋がってしまったのかもしれない。
なお、引用文献1に係る特許は、本願の出願人が本願発明に係るシステムを提供しようとする場合には気を付けておかなければならない特許になっているだろう。(きちんと回避しないといけない。)
本願における「検査情報提供部と検査結果判定部」が関係するからである。例えば、ユーザに対して、検査結果を判定した結果は出力せずに製品情報だけを提供するといった対応や、上記請求項に記載された必須パラメータのうちの一つは使用しないといった対応が求められる。このような対応は、出願人が理想とするビジネスモデルを一歩後退させるものになるかもしれない。
当然ながら、ページ数が全てではなく、少ないページ数でも発明の本質部分が十分に深化されている明細書は存在するだろう。一方で、発明が厚くなれば記載することが増えるというのも事実であり、ページ数は全く無関係ということでもない。(無駄な記載だらけでやたらページ数が多い出願もあるが)
それでも、本願に対する私の印象は、手持ちのカードが少ないといった印象であり、補正によって発明を限定できる要素もあまり多くないように思えた。私ならばこの状態では出願しなかったであろうし、もう少し発明内容を深化させてから出願するようにアプローチしただろう。
どこに出願のボーダーを持ってくるかは事務所や担当者それぞれの考えに影響されることであるし、ページ数が増えれば弁理士の作業も増えるため基本的には出願料金も上がるため出願人側の意向もある。
何が正解とは言えないが、どうせお金をかけて出願するならば、多少の費用は惜しまず特許出願に投資をすべきであると思うし、中途半端に投資して良い権利を得られないくらいなら、投資しない方がいいというのが私の考えである。
さて少し話は脱線したが、本願は拒絶理由の解消が困難であったのか。補正後の請求項1に係る発明の進歩性は認められず、手詰まりとなってしまったのか。明細書を読む限り、厳しい戦いになることは予想されるが、この点をじっくりと検討していきたい。
検討の公開まで
「拒絶理由対応のすすめ」は、実際に検討された上で、記事の詳細を読む方が、スキルアップに効果的かもしれません。まずはご自身で検討してみてから記事を読みたいという方がいることも想定し、具体的な検討の詳細は、記事のアップから期間をあけて、10月5日に公開する予定です。
また、以下の「応答方針の検討」をご覧になる前に、「拒絶理由対応の本質」を読まれることをお薦めします。こちらを読んで頂いた上で以下の記事を読まれる方が、理解が深まると思います。
以下の「応答方針の検討」には、応答方針に至るまでの思考過程と、応答案の概要を載せています。
応答方針の検討(結論:補正して応答) 公開予定10/5~10/31
本件は「請求項を補正し、意見書で反論する」ことで、拒絶理由の解消を試みることができたであろう。また、望ましくは、1回目の拒絶理由通知の対応において、この補正内容での拒絶理由の解消を目指すべきであったとも考えられる。
このコンテンツを閲覧するには会員ログインをしてください。 ログインはこちら. 新規会員登録はこちら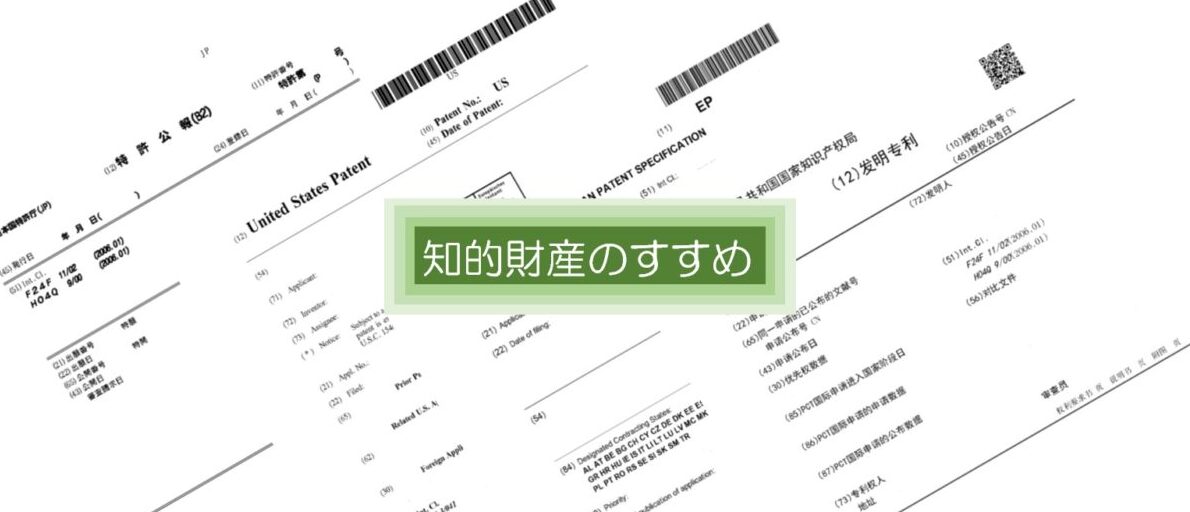
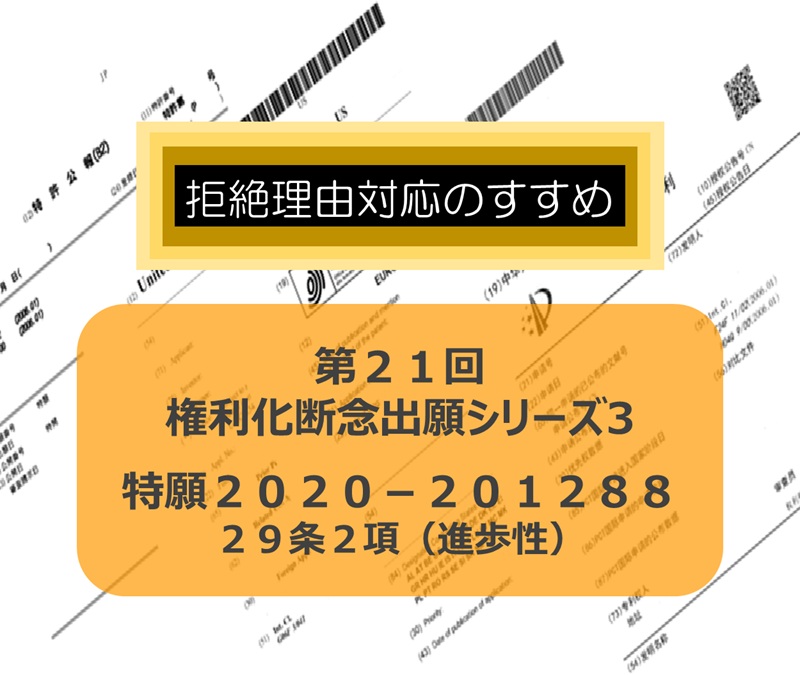


コメント