今回のコラムでは、タイトルの通り「意見書の記載量」について話したいと思う。
おそらく多くの実務家が「意見書の記載はなるべく少ない方がいい」という考えを持っていると思うが、私はこれを間違った実務だと考えている。私にとってこの考えは、理論的な根拠に乏しい迷信に成り下がっているのである。
きっと多くの実務家は「意見書の記載が多くなると、禁反言の法理によって後々発明が限定解釈されるリスクが上がるため、意見書の記載はなるべく少なくした方がいい」と考えているのではないだろうか。
しかし、立ち止まって冷静に考えてみればわかるが、禁反言のリスクと意見書の記載量は比例するものではない。意見書の記載が増えるほど、禁反言の法理が緩く適用されるといったルールは存在していないからである。
本質的に理解をするならば、問題なのは意見書の記載量ではなく、「発明の限定解釈に利用されてしまうような記載の有無」である。
例えば、どんなに長々しくても引用発明との相違点を述べるだけで本願発明の効果については何ら述べていない意見書と、どんなにコンパクトでも本願発明の効果を主張する意見書では、どちらが後の発明の限定解釈に利用されるリスクが高いだろうか。
実際、コンパクトに余計なことを書いている意見書は存在する。文章の多い少ないによって禁反言の適用に差異は見られず、何を記載すべきでないかを知らなければ長かろうと短かろうと余計な記載がされるリスクはあるし、何を記載すべきでないかを知っている者であれば、どんなに長い文章を作成しようともリスクは回避できるのである。
このような本質論は、多くの実務家も理解しているはずである。
それでも多くの実務家にとって「意見書の記載は少ない方がいい」という実務が定着しているのはなぜか。
一つには、上述した通り、どのような内容を記載すればリスクになり、どのような内容であればリスクにならないかについての深い理解や検討が足りていないからであろう。実際、禁反言の法理はそう易々と適用されるものではない。それに、令和5年(ネ)第10040号大合議判決のような判断がされてしまうと、分水嶺もわからなくなってしまうだろう。
しかし、「どのような記載がリスクになるかわからないから記載は少ない方がいい」という考えは、一見すると理屈が通っているようにみえるが、これだけでは論理的な正しさを導くことはできない。この論理を正しいものに導くには、もう一つ「意見書の記載を少なくすることによるデメリットはない(あるいは上記のリスクよりはデメリットが小さい)」という考えがなければならない。
つまり、「意見書の記載は少ない方がいい」と考えている実務家は、その考えを正当化する理屈として、「どんな記載が後々不利に働くかがわからないし、記載量を少なくすることによるデメリットは小さいから、意見書の記載は少ない方がいい」と考えているものと推測できる。(このように考えることなく、先輩や教育者からの受け売りで信じ込んでいるだけの実務家もいるだろうが)
私も多くの実務家と同様に「意見書の記載は少ないに越したことはない」という考えを持っていた頃があった。意見書はなるべくコンパクトに、最小限の記載だけを審査官に端的に伝える方がよいという考えである。
しかし私はある時点で、意見書の記載をなるべく少なくすることの大きなデメリットに気付いた。そして実際に、この考えを捨ててからの方が、OA応答の質は大きく向上した。それは、私の異常な意見書のみ応答率の高さの一因になっているかもしれない。
ここで間違えないで欲しいのは「意見書の記載は多い方がいい」と考えているわけではないということである。要は、なるべく少ない記載にしようという思考で意見書を作成していないというだけで、必要十分な記載が結果的に少ない記載量に収まることはある。
そこで今回は、意見書の記載が少ないことによるデメリットについて話していきたいと思う。残念ながら、この先の「デメリット」については、当サイトの会員(拒絶理由対応のすすめを閲覧できる有料会員)限定になる。
会員に限定する理由は明白で、会員の皆様の中にもし「意見書の記載は少ない方がいい」という考えを持っている方がいるとすれば、おそらくOA応答の実務力向上の妨げとなってしまうと思われるからである。
私のする話を理解した上で、会員の方が自ら「意見書の記載は少ない方がいい」という結論に辿り着いたとすれば、私はそこに異論を唱えるつもりはない。しかしそれは、私の考えを咀嚼した上であって欲しい。
また、私は間違いだと思っているが、だからといって多くの実務家が正しいと信じている考えを変えたいわけではない。「意見書の記載は少ない方がいい」という実務を正しいと信じている実務家の方は引き続き自身の信じる実務を継続すればよい。あるいは、ここまでの記事を読んで「果たして本当に意見書の記載は少ない方がいいのか?」と気になった人は、自ら考察すればよいだろう。本当に気になって知りたい人だけ、会員になることを検討してもらえれば、この記事は十分に役割を果たしたといえる。
少なくとも、こうして一石を投じたことが、読者の実務を見直すきっかけになれば幸いである。
このコンテンツを閲覧するには会員ログインをしてください。 ログインはこちら. 新規会員登録はこちら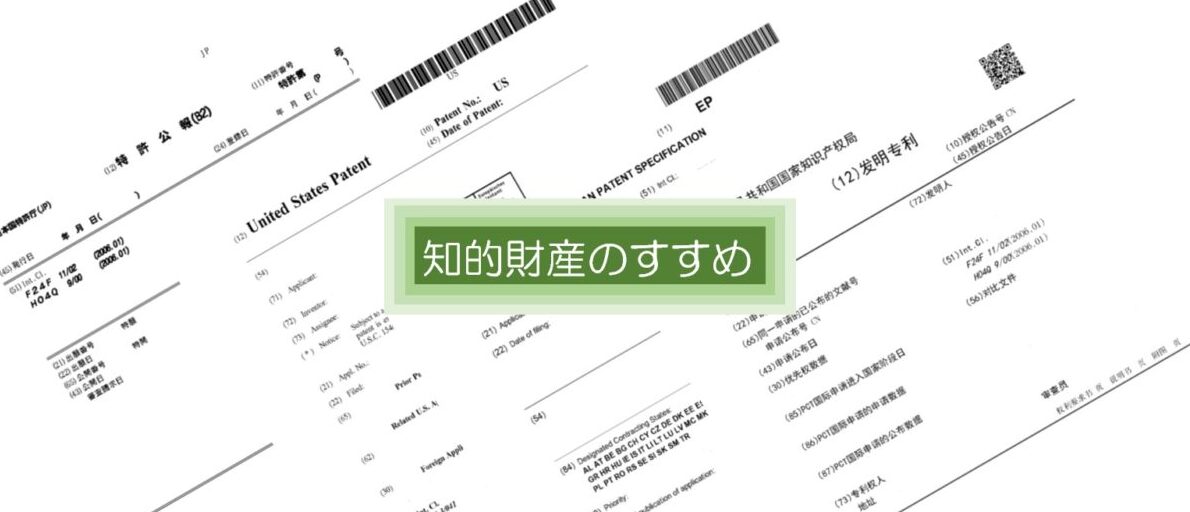
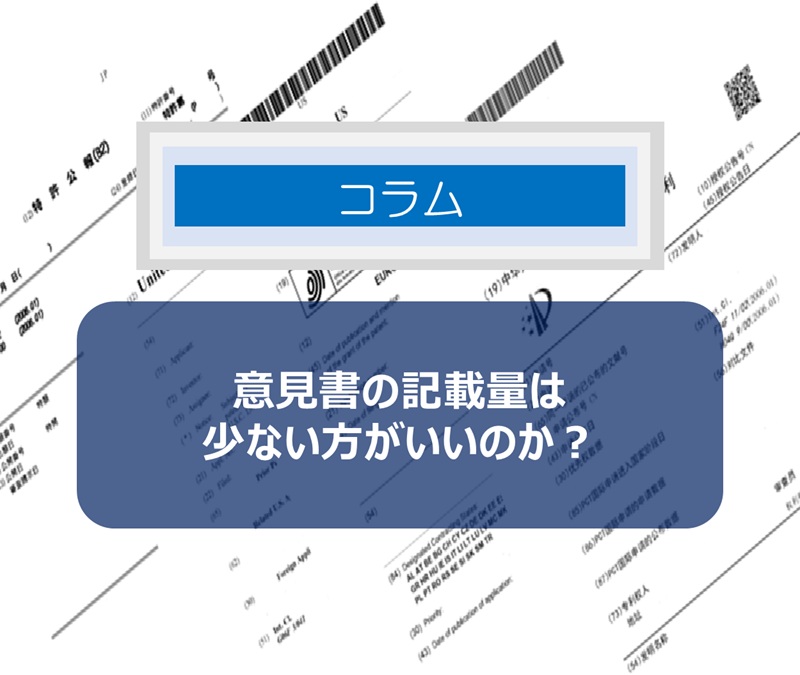

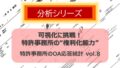
コメント