禁反言の法理
令和4年1月12日(2022/1/12)判決言渡 判決文リンク
#意匠 #手続一般 #禁反言
1.実務への活かし
・~権利化まで #意見書 #禁反言
登録査定を得るまでの審査・審判・訴訟において、審査官等とのやり取りの中で既にした主張と矛盾する主張をしてもよい(原則、禁反言の法理には触れない)。
但し、本判決によれば、それで権利が取得できても、その後の当事者との間では禁反言の法理が働く可能性はあり得るので、その点は考慮しなければならない。(なお、私はこの点については同意していない)
意見書に記載してしまった不利益な内容は、その後の審査で意見書を提出する機会があれば、撤回の意思を記載しておけば、禁反言の法理に触れない可能性もあるので、権利化において不要な主張は積極的に撤回しておくことを薦める。(それが認められるかはわからないがやっておいて損はないと思う)
∵審査は職権により判断されるべきであり(出願人の主張をそのまま採用するのではなく、客観的に判断すべきであり)、出願人が従前の主張と異なる主張をしたとしても、行政庁である特許庁においては、禁反言の法理によって保護されるべき利益(=不当に害される利益)がない。
2.概要
原告ポータル インストルメンツ,インク(以下、原告ポータルという。)が、意匠登録出願(以下、本件出願という。)の拒絶査定に対して不服審判請求をし、特許庁が拒絶審決をしたため、これの取消を請求した事案である。
本件出願に係る意匠(以下、本願意匠という。)は、その物品を「インジェクターカートリッジ」とするものであり、引用された意匠はその物品を「注射器用シリンジ」とするものであったため、これらの物品の同一類似の判断が争いとなった。
特許庁は、審決において、これらの物品を表記は異なるが「同一」であると判断した。本訴において、原告ポータルは、これらの物品は同一ではないと主張したが、特許庁は、本訴における原告ポータルの主張は禁反言に抵触するものであり許されないと主張した。
その理由は、原告ポータルが、拒絶理由通知に応答して提出した意見書において「本願意匠の物品は「インジェクターカートリッジ」であるところ,引用意匠の意匠に係る物品が「注射器用シリンジ」であり,物品が共通する。」と述べ,審判請求書においても,「本願意匠の意匠に係る物品は,注射器などに用いられ,薬液を満たすための「インジェクターカートリッジ」に係るものであり」,「本願意匠と引用意匠(略)は,意匠に係る物品が共通しており,」と述べており,出願段階から本件審決に至るまで,本願意匠の意匠に係る物品について,「注射器などに用いられ,薬液を満たす」ものであると述べていたことにある。
知財高裁は、特許庁の主張を容れず、本件で、原告ポータルが、本訴において、審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されないということはできないと判断した。それは、本件が、拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟であり、被告は行政庁であること、並びに、拒絶理由の存否については、審査官の職権審理事項(職権で判断すべき事項)であることから、原告ポータルの主張によって被告の利益が不当に害されるという関係も生じないといえるためであった。
原告ポータルの主張(判決から抜粋)
「本件のような拒絶査定不服審判は職権のもと審理され(意匠法52条の準用する特許法150条1項,151条,153条1項等),自白の拘束力もない上,本件の審判は査定系審判であって,当事者系の無効審判でもない。本訴の審理対象は,「…本件審決における被告の判断の是非」にほかならない。
禁反言の法理は,権利の行使又は法的地位の主張が,先行行為と直接矛盾するか,先行行為により惹起させた信頼に反することから,その行使を認めることが信義則に反する場合に適用されるが,本件はこれらの場合に当たらない。被告は,当事者の主張にかかわらず職権で物品の同一性を判断すべき立場にあり,仮に被告が原告の従前の主張を信頼していたとしても,その信頼は保護に値しない。」
特許庁の主張(判決から抜粋)
「…ところが,原告は,本訴に至って上記と異なる主張をしており,これは,いわゆる「禁反言」に抵触し,許されない。
仮に本願意匠が登録されたとしても,原告が権利行使をすることは禁反言の法理又は信義則に違反することになり得るので,意匠権は不安定なものということになり,法が審査主義を採用して安定した権利を設定しようとした趣旨にもとる。」
知財高裁の判断(判決から抜粋)
「意匠登録出願についての拒絶理由の存否は,審査官が職権により判断すべきものであって(旧法17条),出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くものではない上,権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟である本件において,被告は行政庁として対応しているものであって,本願意匠の意匠に係る物品につき,査定及び審判の各段階における原告の主張が本訴における主張と異なるものであったことにより被告の利益が不当に害されるとの関係もないことからすると,本件意見書や本件審判請求書における上記の原告の主張をもって,禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。
また,被告以外の第三者との関係において,禁反言の法理が適用されることにより,原告が本願意匠に係る意匠権を行使する場面に制限を受けるおそれがあるとしても,特定の当事者間における権利行使の制限の当否と権利の付与の適否とは,およそ場面が異なるのであるから,直ちに本願意匠について,意匠権登録による保護を与えるべきではないなどということはできない。」
3.判決内容の考察
3-1.判決についての感想
全体的な結果について:納得度80%
言われてみれば『それはそうか』と思う判断だが、改めて、この考えを(自分なりに)整理しておくことは実務においても非常に有益であると思われる。特に「実務への活かし」でも書いたように、先に述べた意見や主張を撤回することが禁反言の回避に有効となる可能性も否定できないため、これまでの「意見書」実務では考えもしなかった「撤回」という手法が、有用な権利の形成に重要な意味を持つかもしれない。
禁反言の法理について
私は、弁理士になりたての頃は「包袋禁反言」と「禁反言の法理」の違いもわかっていなかったし、「包袋禁反言」や「禁反言の法理」というのが、知財法の中で生まれた考えだと思っていた。
実際には、「禁反言の法理」は、民法や商法などの私法一般に適用される法理であり、「包袋禁反言」は、知財法向けに発展した「禁反言の法理」の一形態といった位置付けのようである。
そこでまず、大枠にある「禁反言の法理」について、
禁反言の法理とは、「一方の自己の言動(または表示)により他方がその事実を信用し、その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他方に対し、それと矛盾した事実を主張することを禁ぜられる」という法である。
この文からすると、他方当事者が特許庁の審査官、審判長、あるいは特許庁長官などのいわゆる行政庁である場合に、それだけで禁反言の法理が適用されないとは言えない。両当事者に特に制限がされているわけではないためである。
一方で、この法理は、他方当事者が、信用を前提とした行動によって不利益を被らないように保護する趣旨であると読むことはできる。それは、「不利益」という明言はないものの、この法理が「両当事者間」におけるものであり、両当事者を超えて、社会一般の秩序や法的安定までをも考慮しているとは読めないからである。あくまで当事者間の話であるから、仮に、一方当事者に矛盾した主張があったとしても、それが他方当事者の利益になる場合や、他方当事者に何らの不利益を及ぼさない場合にまで、この法理を持ち出す必要性はない。
そこで、本件では、一方当事者である原告ポータルが、審査及び審判段階で行っていた従前の主張と矛盾する主張をしたことにより、特許庁がこの従前の主張を信用し、これを前提として拒絶査定や拒絶審決をしたこととの関係で、不利益を被ったかという点を判断することになると思われる。
原告ポータルの主張と、知財高裁の判断との比較
ざっと判決を読むと、本件で裁判所は原告の主張を採用したように感じるが、注意深く判決を読むとそうとも言い切れない。
そこで、対比をしてみると、本件で、原告ポータルは、禁反言の法理が及ばないことの理由として、(あ)職権審理(準特150条~153条等)、(い)自白の拘束力が及ばないこと、(う)当事者系ではなく査定系の審判であること、を挙げている。
他方で、知財高裁は、「拒絶理由の存否は審査官が職権により判断すべきもの」と述べ、一見すると職権審理を挙げているようにも見えるが、「(旧法17条)」としており、準特150条~153条等を挙げていない。意匠法の旧法17条(現16条)は、「特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。」として、審査主義を規定する条文である。また、知財高裁は、自白の拘束力が及ばないことは挙げているが、査定系審判であることは挙げていない。代わりに、知財高裁は、本件が「権利行使の当否ではなく権利設定の適否を問題としている」点を挙げている。
このように、知財高裁の判断の根拠は、(ア)審査主義(旧意匠法17条)、(イ)自白の拘束力が及ばないこと、(ウ)権利行使ではなく権利設定の適否の問題であること、を挙げており、自白の拘束力以外の点は、原告の主張を採用しているわけではないことがわかる。
原告(あ)と裁判所(ア)の違いについて
私も最初この判決を流し読みしていたときは、「審査/審判は「職権審理」だから当事者の主張を鵜吞みにして信用することなく、公正な判断をしなければならない」のであり、当事者が主張を変えたところで禁反言の法理には触れないというようなことを裁判所は言いたいのだと思った。」
しかし、よく考えてみると「職権審理(職権で審理すべき事項)だからそこには禁反言の法理は及ばない」という理屈も、どこか腑に落ちないところがあるように感じた。つまり、「職権で審理すべき事項なのだから、出願人がころころ主張を変えてもそれに惑わされずに判断しなさい」というのは、完璧ではない審査官や審判官に対し酷であり、やや乱暴な言い方のように思った。
そのため、職権審理を直接の根拠とするのではなく、もっと本質的なところから論じるべきではないかと考えていたときに、私も「審査主義」が頭に浮かんだ。
意匠権や特許権などの知的財産権は、対世的な効力を有する公権である。また、これらは行政庁から付与される権利であり、その効力は国内全域に及ぶ。そのため、このような権利を認めるには、そのための要件について公正な判断が求められるのである。そして、旧法17条は、この判断を審査官が行うことを規定しているのである。
審査が職権審理であることも、自白の拘束力が及ばないことも、このような権利の性質から要請されるものであり、審査官が出願人の主張を鵜呑みにして傾聴することが許されないのも、当事者の言い分をそのまま聞いて権利を認めてしまうと、公正に判断されたと言えないような権利が対世効を持ち、これによって第三者に不利益を与えてしまう危険が発生するためである。
審査官や審判官が出願人の主張を容れるのは、単に出願人の言う意見そのものに説得力があるからではなく、その主張が客観的にみて合理的であるからでなくてはならない。尤もらしいことを言ったところで、それが客観的にみて適切といえないならば採用してはならないのである。
このように、職権審理というのはあくまで審査の手法(やり方)の一つに過ぎず、これを直接の根拠とすると、審査のやり方という「形式」によって禁反言の法理の適用が拒まれることになり、実質的な説得力に欠けると考えたために、知財高裁は、原告ポータルが主張の根拠として挙げた「準特150条~153条等」ではなく「旧法17条」を挙げたのではないかと推測する。
原告(う)と裁判所(ウ)の違いについて
禁反言の法理の適用があるか否かの判断において、当事者系審判であるか査定系審判であるかは根拠とはならないように思う。
例えば、逐条解説(第21版)には、特許法151条の解説で、「特許法における審判が職権主義によって貫かれている以上、当事者主義と関連する規定は準用されない。」と述べており、査定系か当事者系かを区別していない。(特許法の条文のつくりとして、158条から166条に各審判の特則が規定されており、150条~153条は全ての審判を対象にした規定である。)
また、査定系の審判に類する異議申立てと当事者系の無効審判との関係で、異議申立人は「禁反言の法理に反する」という意見ができず、無効審判の請求人はこれができるというのも均衡が取れておらず、その根拠を査定系か当事者系かという違いに持ってくるのは説得力に欠ける。
そして、査定系であろうが当事者系であろうが、係争物は知的財産権という対世的な権利であり、その判断は、当事者系であろうと当事者間にのみ及ぶものではないという点では共通している。(それゆえに、無効審判であっても職権審理が認められているのである。)
この点については、知財高裁は、査定系か当事者系かという分け方ではなく「権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟である本件において」と述べており、侵害訴訟や損害賠償請求訴訟などの純然たる当事者訴訟と区別するようにしている。この分け方からすると、知財高裁は、当事者系と査定系ではなく、当事者主義と職権主義とで区別すべきと判断しているように読める。
なお、私は、このような区別も不十分であると思っている。なぜならば、権利設定の適否と言ってしまうと、異議申立てや無効審判の場で、禁反言の法理の適用が除外されるように読めるからである。個人的には、一度設定登録がされた後か否かで区別すればよいと思う(詳細は後述)。
査定処分の不利益の所在
公正な判断のため職権で審査をする審査官が登録査定あるいは拒絶査定をした場合に、その利益あるいは不利益は誰に及ぶのか。
確かに、審査官は、当事者の矛盾する主張によって審査がかく乱されるという不利益を受けるが、職権で公正に判断する建前になっている以上、理論上は査定の判断にその影響は及んでいないはずである。つまり、このような審査のかく乱という不利益は、権利設定の判断に与える直接的な不利益ではなく、間接的な不利益であると考えられる。
知財高裁は、判決で「被告は行政庁として対応しているものであって,…被告の利益が不当に害されるとの関係もない」と述べている。設定登録をしたところで、その権利の直接の利害関係人は第三者であって、行政庁である特許庁には不利益はないのだからと、一刀両断しているようにも思える。
なお、ここで重要なのは、知財高裁のこの判断は、禁反言の法理の定義における「一方の自己の言動により他方がその事実を信用し、その事実を前提として行動した」という点についての判断ではなく、別の議論をしているということである。もう少し分かり易く言うと、知財高裁は「審査官は職権で判断するのだから、出願人の主張を信用し、それを前提に査定処分をするということはないはずだ」と考えて結論を導いているわけではなく、「行政庁である特許庁には利害関係がないはずだ」と考えて結論を導いているように感じる。
つまり、ここでも知財高裁は、原告ポータルの「被告は,当事者の主張にかかわらず職権で物品の同一性を判断すべき立場にあり,仮に被告が原告の従前の主張を信頼していたとしても,その信頼は保護に値しない。」との主張は採用していないように読めるのである。
実際に、審査官が審査をする上で、全く出願人の主張を気にしないということはないだろうし、そうだとすると意見書を提出する意味はない(意見書を提出する機会を与えている法の趣旨にも反する)。審査官は、出願人の主張が合理的と思えば、その主張を採用して審査判断するのであり、客観的に判断する立場にあるとはいっても、技術の専門家でもない審査官が、その出願に係る技術分野に属する当事者としての出願人の主張を信用するというのは、当然に起こることだろう。
そのため、例えば、当該技術分野に係る深い技術知識を有していない審査官に対し、そのことを奇貨として、出願人が自己に有利な主張をし、職権で調査をしてもその真偽がよくわからなかった審査官が出願人の主張を信じて査定をし、後に出願人がこれと矛盾する主張をしたとして、それでも常に審査官の信用(信頼)は保護に値しないといってもいいのか。禁反言の法理が信義則とも通ずることからすれば、出願人側の行為の内容によっては、審査官の信用が常に保護に値しないとはいいきれないように思う。
前置きが長くなったが、「不利益」の所在、つまり、矛盾する主張により利益を害される他方当事者を考えてみたい。既に述べたように、特許庁は、原則として、査定処分による直接の利害関係人にはならないのであり、出願人は一方当事者なのであるから、残る選択肢として、他方当事者は、第三者ということになるだろう。
また、ここでは、査定処分が、登録査定なのか拒絶査定なのかで分けて考えることが望ましいように思う。
査定処分が登録査定の場合、その後の矛盾する主張によって利益を害されるのは第三者である。登録査定がされた時点で審査は完結するためである(第三者による異議申立てや、利害関係人による無効審判請求などはあり得るが、それらは第三者側からの求めがあってなされるものである)。そして、第三者は、登録査定となったことで、そこに現れる権利内容を信用し、その後の行為を行うといえる。
一方で、査定処分が拒絶査定の場合はどうだろう。拒絶査定は、出願人にとっての不利益処分であり、矛盾した主張によってこれが覆されて登録査定となることは、第三者にとっては不利益であるといえるだろう。しかし、ここで忘れてはいけないのは、拒絶査定に対して不服審判がされ、さらに審決に対する取消訴訟が提起されている間、審査は完了していないということである。
もう一度「禁反言の法理」に戻ると、この法理によって保護される他方当事者は「その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他方」当事者である。そうすると、審査が続いている間は権利関係が確定していないのであるから、この段階で一方当事者の主張を信用して行動した第三者を保護する必要性はあるのかが疑問となる。
例えば、本件を例にとって照らすと、審査の途中で本願意匠の「インジェクターカートリッジ」が引用意匠の「注射器用シリンジ」と同一であると言っているから、自分たちの物品はこれに類似しない意匠であり権利侵害とならないと思ったと言われても、職権主義の下、出願人の主張が常に通るわけでもない以上、そのような軽率な信用に基づいて第三者が行動するというのは不注意でしかなく、保護に値するとは思えない。
そうすると、査定処分が拒絶査定であり、出願人がこれを不服として争っている場合においては、第三者は、利益を害される他方当事者とはいえないように思う。従って、原則として、拒絶査定に対する審判や取消訴訟の中で、出願人から矛盾する主張がされたとしても、禁反言の法理によって保護されるべき対象はいないと考えるのが妥当なように思う。
なお、「原則として」と書いたのは、既に述べたように、審査官の信用は常に保護に値しないということはないと私は考えているからである。
確かに知財高裁は、「被告は行政庁として対応しているものであって,…被告の利益が不当に害されるとの関係もない」と述べており、素直に読めば、行政庁に禁反言の法理が適用される余地はないと言っているようにも思えるが、そうだとしたら私はこの意見には反対である。
その審査が対象としている一つの具体的な出願に係る権利設定の適否が問題であれば、つまり、具体的な一つの権利が対象となるのであれば、その当事者に行政庁が入ることはないであろう。
しかしながら、先にも述べたように、出願人が、審査官の不知を奇禍として詭弁的に主張をころころと変えている場合には、いかに職権審理であろうとも、審査官の職務である「公平な審査」の遂行を妨害するものであり、このような妨害は、審査官だけでなく、広く第三者にも影響を与えかねないのであるから、出願人の行為の程度によっては、審査官の「公平に審査を実施することを妨害されない権利」あるいは第三者の「公平な審査の下で知的財産権が設定されることへの期待権」とでもいう権利が、保護に値する権利になることはあり得るのではないかと思う。
知財高裁が、判決で「本件意見書や本件審判請求書における上記の原告の主張をもって,禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。」と述べ、あくまで、本件が事例判決であり、この事情からは許されないとまではいえないといった言い回しをしているのも、事案によっては許されないケースがあるかもしれないことへの予防線のように思える。
但し、原則として職権で審査がされるのであるから、このような権利が、保護に値する権利と言えるには、詐欺的な、あるいは、欺罔的な行為がされ、それによって信用が毀損され、利益が害されたといえるような、極めて悪質なケースに限られるのでないかというのが、私の自論である。
つまり、ある程度誠実に、あるいは、理性的に対応しているのであれば、審査の過程の中で、既に述べた主張と矛盾する主張を後からしたとしても、禁反言の法理に触れるということはないと考えられ、実務の際に、禁反言に怯えて矛盾する主張を控えるといったことはせず、素直に思ったことを主張するのがいいように思う。
権利行使において禁反言の法理に触れるか
知財高裁は判決の中で「また,被告以外の第三者との関係において,禁反言の法理が適用されることにより,原告が本願意匠に係る意匠権を行使する場面に制限を受けるおそれがあるとしても,特定の当事者間における権利行使の制限の当否と権利の付与の適否とは,およそ場面が異なるのであるから,直ちに本願意匠について,意匠権登録による保護を与えるべきではないなどということはできない。」と述べているが、これは、
特許庁側の「仮に本願意匠が登録されたとしても,原告が権利行使をすることは禁反言の法理又は信義則に違反することになり得るので,意匠権は不安定なものということになり,法が審査主義を採用して安定した権利を設定しようとした趣旨にもとる。」という主張に応じたものだろう。
これだけを読むと、特許庁も知財高裁も「原告が権利行使をすることは禁反言の法理又は信義則に違反することになり得る(その可能性はある)」と考えているように思う。
しかし私は、本件出願が登録査定となった場合に、権利行使の際に第三者との関係で禁反言の法理が適用されるとは考えていない。なぜならば、本件取消訴訟までの経緯を読めば、原告ポータルの従前の主張は採用されず、後の主張が採用されたということを第三者は容易に理解できるからである。
何度も戻るが、禁反言の法理は、単に一方当事者だけの問題で、一方当事者が矛盾する主張をすることを禁ずるものではなく(そのような行為そのものを戒めるものではなく)、一方当事者と他方当事者との間の問題のはずである(利害関係の中での問題のはずである)。
そうすると、当然ながら(私は当然だと思っているが)、一方当事者の主張を信用して行為に及んだ他方当事者の当該行為が、まずもって適法あるいは適切な行為であることが要件とされるはずである。他方当事者の行為が不適切なものであったり違法なものであれば、その行為を保護する必要性もなくなるからである。
このように考えると、第三者において、後の主張が採用されて登録査定となったことが容易に理解できるにもかかわらず、これと矛盾する従前の主張を信用し、これを前提とした行為に及び、その上で他方当事者が禁反言の法理を主張するというのは、それこそ信義則に反し許されないのではないかと思う。
審査における出願人の主張に対する禁反言の法理の射程
これまで述べてきたことを整理して、権利者と第三者(異議申立人や利害関係人)との間で、禁反言の法理が適用される射程を考える。
特許や、意匠、商標などの審査においてした出願人の主張のうち、どのような主張に対して禁反言の法理が及ぶかであるが、結論から言うと、登録査定の判断の基礎として採用された出願人の主張に限られる、というのが私の考えである。
この考えの根拠には、やはり、禁反言の法理が、まずもって「主張を信用し、これを前提とした他方当事者の行動」が適切であることを前提としていると思うからである。
審査が確定するまでの間の主張は、権利が定まっていない不安定な状態のものであるから、このような主張を信用して行動すること自体が不適切である。また、審査や審判、取消訴訟を経た結果、拒絶査定が確定したのであれば、第三者の行為を制限する権利そのものが発生していないのであるから、第三者において不利益は生じない。
登録査定となり権利が設定されることで初めて、当該権利によって第三者の行為がどのように制限されるのかが決まるのであり、第三者を制限する権利がどのような内容であるかについても、登録査定の判断の基礎となった出願人の主張を踏まえて検討されるものであるから、第三者がここでの出願人の主張を信用し、これを前提に行動することも適切と言えるのである。
このように解するとすれば、侵害訴訟に限らず、異議申立てや無効審判の場でも、禁反言の法理は適用され得るものと考えられる。判断が難しいのは訂正審判であるが、従前の主張と矛盾する主張を権利範囲に含ませるような訂正は、目的要件を満たさないか、実質的な拡張あるいは変更にあたるといえるため、別の理由から封じられるだろう。(潜在的に利害関係人となり得る第三者を他方当事者と見立てるアプローチもあるかもしれないが、具体的な当事者がいない中で禁反言の法理を持ち出すことにはやや抵抗がある。)
実務における「撤回」の意義
上述の「禁反言の法理の射程」の話の中で私は、「登録査定の判断の基礎として採用された出願人の主張」と述べた。つまり、私の考えでは、禁反言の法理が及ぶのは、登録査定までに出願人がした主張全般ではなく、その中でも登録査定の判断の基礎とされた主張に限られる。
その理由も、上述した内容と同じで、第三者(他方当事者)はあくまで設定された権利に基づいて自らの行動が制限され、権利侵害を避けるように行動するのであるから、信頼の対象となるのはあくまで、その権利の内容がどのようなものであるかに関する権利者(一方当事者)の主張のはずであり、登録査定の判断に関係ない主張についてまで、この射程に含める必要はないからである。
しかし、そうはいっても「登録査定の判断の基礎として採用された出願人の主張」というのがどこまでを指すかは、何の手当もしていなければ、当然争いになるだろう。また、その主張が判断の基礎とされているかどうかが、公開されている審査経過の書類から一見して明らかでないような内容については、判断の基礎とされたものとみなされるべきであろう(他方当事者がその主張を信用してしまうのも致し方ないのであれば、やはり保護されるべきであるから、反証を許す推定ではなく、みなすべきである。)
そうすると、何らの手当もしていない状態であれば、例えば、意見書で「A」と主張するつもりが間違って(誤記で)「not A」と主張しており、また、not Aという主張では、明らかにその後の主張内容と矛盾し、Aと解釈しないと整合が取れないといったような、当業者の技術常識で考えれば明らかにその主張に誤りがあり、かつ、本来の主張を容易に推認できるものでない限りは、審査における出願人の主張は登録査定の判断の基礎とされたものとされるのが妥当なように思う。
そこで、私が有効な手段と考えるのが従前の主張の「撤回」である。つまり、登録査定の前までに機会があるのならば、意見書において、従前の主張のうち不要となった部分を「撤回」しておくことである。(登録査定後に上申書などでいくら「撤回」をしても、審査のやり直しができない以上、それは信義則により認められない可能性が高いと思う。登録査定後であれば、訴えの利益が認められるなら確認訴訟という手はあるかもしれない。)
仮に「撤回」を行った場合、特許庁との関係では原則として禁反言の法理は及ばないから、撤回をしたことについて特許庁側が「禁反言の法理により撤回は認めない」ということはできないし、出願人が撤回しているにもかかわらず、特許庁がこれを無視して従前の主張を採用し登録査定をするということもないだろう。(たとえ従前の主張を採用して登録査定になったとしても、それは、出願人が従前に主張していたからという理由ではなく、職権審理の下、客観的にみて従前の主張内容が合理的であり採用できるものであったからというだけで、その後の当事者訴訟において、この点(特許庁が採用した内容が適切であったか)の適否を争うことはできるだろう。)
また、第三者との関係でも、意見書で主張を撤回していることが明記されていれば、従前の主張が登録査定の判断の基礎とされていないこと、あるいは、出願人が判断の基礎とされるべきでないという意思を明確に表示したことは明らかになるので、それにもかかわらず撤回された主張を信用した場合には、その信用を前提とした第三者の行為を禁反言の法理で保護する必要性もなくなるように思う。
従って、例えば、一回目の拒絶理由対応では意見書でAという主張をしたが、これでは登録査定とならず再度拒絶理由通知がきたという場合に、今度はBという主張で反論しようと考えるのであれば、その際には、従前のAの主張を維持することが登録査定の判断に影響するかどうかを考え(つまり、A+Bという主張が有効なのか、Bという主張だけで十分なのかを考え)、Aの主張を維持しておく必要性がないと判断したときには、意見書でBの主張をすると共に、従前のAの主張は撤回する旨を記載しておくのが良いかもしれない。(なお、あくまで自論ですので、その効力は保証しません)

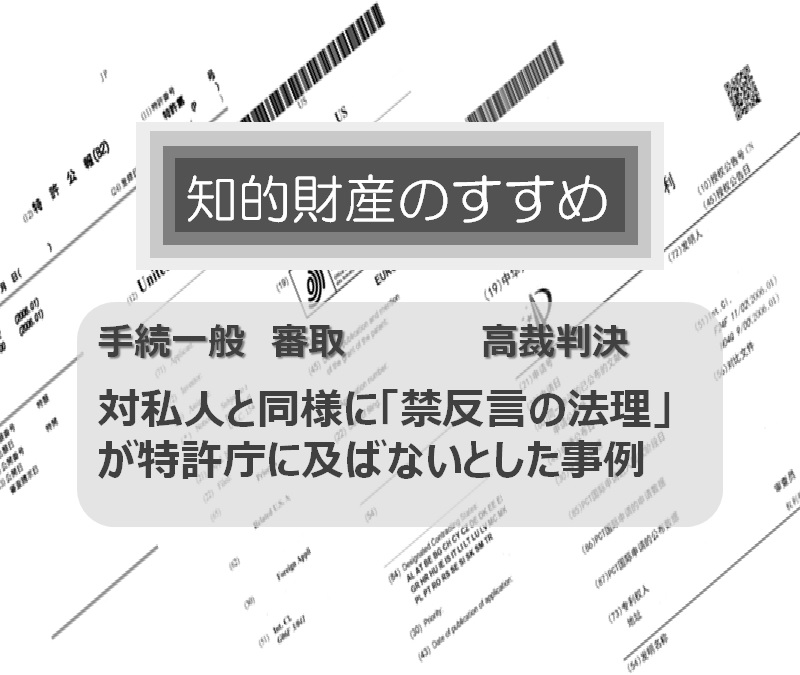

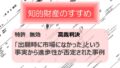
コメント