訂正:形式上の包含関係があっても訂正が認められなかった事例
補正:審査官の「補正の示唆」に従った請求項が無効にされた事例
令和4年10月17日(2022/10/17)判決言渡
#特許 #新規事項の追加 #訂正要件
1.実務への活かし
その1
・権利化後~ #請求項の訂正
請求項の訂正は、表面的な文言上から、訂正後の請求項が訂正前の請求項に包含される関係にあると見える場合であっても認められないことがあるので、訂正の適否を判断する際には、表面的な文言上の関係だけで訂正要件(目的要件や拡張・変更)を満たすか否かを検討するだけでは不十分であり、実質的にみてその訂正が要件を満たしているといえそうかを検討するべきである。
∵本件では、文言上は、8つの選択肢から4つの選択肢に限定する訂正がなされた、特許権者はこれを「択一的記載の要素の削除」にあたると主張したが、知財高裁は、本件特許に係る発明の性質を踏まえ、端的に両者は異なる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には立たないと判断し、訂正を認めなかった。
その2
・~権利化まで #請求項の作成
複数の実施形態の記載を根拠として上位概念の請求項を作成する際や、そのような請求項を補正する際には、作成/補正された請求項の構成要素の中に、ある実施形態に係る記載と別の実施形態に係る記載を混合した構成要素が含まれていないかを確認すべきである。
そして、このような複数の実施形態の記載を混合した構成要素が確認できた場合には、特に、新規事項、サポート要件、実施可能要件に適合しているかに気を付けなければならない。明細書において、複数の実施形態の記載を複合した発明が開示されているか否かをきちんと確認すべきである。
また、拒絶理由対応では、審査官から拒絶理由を解消する一案として補正の示唆が与えられていた場合であっても、安易に審査官の示唆を受け入れてはいけない。審査官による補正の示唆が間違っている場合には、無効理由を有する特許権が設定されてしまうリスクがあるので、示唆された補正案が適切といえるかを自らの頭で考えて検討すべきである。
∵本件では理由通知において審査官から示唆された補正案を採用して特許査定を受けたが、結果的に、これが新規事項追加の無効理由となった。
2.概要
本件は、特許が無効とされた特許無効審判の審決取消しを求める訴訟である。
ソニックステクノロジー株式会社(以下、「ソニックス社」という。)は、グリッドマーク株式会社(以下、「グリッドマーク社」という。)が保有する特許第4392521号(発明の名称「ドットパターン」。以下、「本件特許」という。)の特許無効審判を請求し、特許権者のグリッドマーク社は訂正請求を行ったが、特許庁は、この訂正を認めず、特許を無効にした。
無効審判に係る無効理由は、訂正前の請求項1に係る発明が明細書等に記載されていない発明であり、新規事項の追加にあたるとする理由である。また、無効審判においてグリッドマーク社が行った訂正請求は、この新規事項の追加を回避することを目的としてされたものと推察される。
本件特許に係る技術は、例えば印刷物などに人が目視では気にならないような情報を埋め込み、これをコンピュータで読み取って情報を抽出する、いわゆる情報埋め込みに関するものであり、本件特許においてドットパターンと称される発明は、この情報の埋め込みの仕方に関する発明である。
グリッドマーク社は、請求項1において、このドットパターンによる情報の定義を記載した
「前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、」
との部分の訂正を請求し
「前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°の2倍である90°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、」
とする訂正を求めたが、特許庁はこれを、目的要件違反(特許法134条の2第1項各号違反)、及び、特許請求の範囲の変更(同条第9項で準用する特許法126条第6項違反)にあたるとして認めず、訂正請求前の請求項が、新規事項の追加にあたると判断して、特許無効の審決を下した。
グリッドマーク社は、本件訴訟において、45°ずつずらした方向のいずれかの方向が、8つの方向(45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°、及び360°)の中から選択されるいずれかの方向であったのに対し、訂正後は、4つの方向(90°、180°、270°、及び360°)の中から選択されるいずれかの方向となったため、「特許請求の範囲の減縮に該当するとされる「択一的記載の要素の削除」である」と主張し、「数値による限定は、数値によって限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、8方向から4方向への限定は、下位概念化である」と主張して、本件訂正が、減縮を目的とし、実質的な変更にもあたらないと主張した。
これに対し、知財高裁は、グリッドマーク社の主張を容れず、特許庁の審決を支持した。
知財高裁の判断(判決から抜粋。下線は付記)
「本件訂正前の上記構成は、任意の45°間隔による8方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件訂正後の上記構成は、縦横の4方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異なる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には立たない。したがって、訂正事項1は、特許法134条の2第1項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
…原告は、…択一的要素の削除であって、「特許請求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第3の1⑴アにて主張するように、本件発明1の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成は、1つの単一な構成としてデータ内容を定義しているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずらされていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情報の定義に利用されているというものではない。
…そうすると、それぞれの5 各方向を取り出してそれぞれに独立した意味があるというものではなく、8方向全部が一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、8方向を4方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることのできる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについて選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきである。 …原告は、…数値による限定は、数値によって限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、8方向から4方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記において説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるから、その主張を採用することはできない。」
3.本件のより詳細な説明、及び、判決内容の考察
3-1.本件特許について
上述したように、本件特許は、発明の名称を「ドットパターン」とするものである。また、本件特許の明細書はかなりのボリュームがあり、図面が113、段落は300もある。しかし、本件特許明細書に記載されている内容のほとんどは、ドットパターンを利用する種々の利用形態(利用シーン)の説明であり、本件発明である「ドットパターン」について具体的に説明されている記載はそれほど多くはない。本件発明に係る「ドットパターン」の使用例は、例えば、絵本であったり、玩具であったり、カメラや携帯電話を用いたりと、多岐にわたって示されている。(なお、本件の理解のためだけであれば、これらの使用例の記載は読む必要がないだろう。)
また、本件特許のファミリー出願は非常に多く、分割は第15世代まである(原出願及び分割出願の総数は23もある)。また、本件特許を含め、いくつかの特許には専用実施権の設定もされており、その意味で、客観的にみて本件特許は特許権者にとって重要な特許ということができるだろう。
ちなみに本件特許は第4世代であり、本件特許の他にも関連する判決が同日に3件出されている(令和3年(行ケ)第10145号~10147号)。残りの3件は、特許第4817157号(第5世代、専用実施権設定あり)、特許第4899199号(第6世代)、特許5259005号(第9世代)であるが、これら3件も論点は本件に類するものである(令和3年(行ケ)第10145号は、本件で争点となった構成が請求項に含まれていて、争点はほぼ同じである。)。
さて本件特許の内容の説明に戻る。本件特許では、全部で113ある図面のうち、図2、図5~図8、図22、図103~図106にしか、ドットパターンの具体的な態様を示す図はない。また、図2、及び、図5~8は、共通する定義のドットパターンであるとみえ、図103~図106は、共通する定義のドットパターンであるとみることができる。そのため、判決文では、前者を図5ドットパターン、後者を図105ドットパターンと呼んでいる。
なお、図2、図5~図8、図22、図103~図106のうち、図2及び図22については、明細書に、この図に記されたドットパターンについての具体的な説明がされていないことから、これがどのような定義のドットパターンであるかは検討されていない(従って、正確には、図5ドットパターンの対象は、図5~図8である。)。参考までに、この部分に係る判断を以下に抜粋する。
参考(判決文の「裁判所の判断」から抜粋)
「【図2】については,発明の詳細な説明にはドットパターンを示す一例であるとだけ記載され,ドットパターンの内容に関する説明はなく、図中の説明を見ても、当該説明がデータ内容を定義する情報ドットに関するものなのか不明であり、仮に、これを情報ドットに関する説明であるとしても結局そのデータ定義方法は不明であり、このドットパターンは図5ドットパターン又は図105ドットパターンのいずれに関するものとも認められない。」
このように、たとえ出願人(発明者)が、同じ定義のドットパターンと認識しており、そうであると善解することができたとしても、特許の明細書は出願人の認識よりも客観的な理解の方が重要であり、開示内容は厳格に判断される。およそ当業者において一義的に導くことができないといえる合理的な解釈の余地を残す場合に、発明者の内心に留まる認識(図2も図5~図8も同じ定義のドットパターンを説明している)を、その明細書の開示として扱うことについては厳しく判断され得るということには留意しておくべきである。
言い換えれば、作成した明細書を確認するときは、「自身の認識」が正確に明細書に現れているか、「自分はこういうつもりで書いている」というのが思い込みに留まっていないかを注意深く確認すべきである。
「そんなの当たり前!」と思うかもしれないが、明細書作成の経験が豊富な人ほど、これを実践することの難しさはわかっているだろう。
さて本題に戻ると、本件を読み解く上で、これら2種類のドットパターン(図5ドットパターン及び図105ドットパターン)の具体的な態様を知っておくことは欠かせない。以下に、図5ドットパターンと図105ドットパターンの図の例を示す。

これだけ見て、それぞれの定義がわかる人はすごいと思うが、私も含めほとんどの方はそうではないと思うので、もう少し直感的に捉え易くなるように、図に編集をしてみる。
まずは図5ドットパターンである。

上記編集した図5ドットパターンにおいて赤丸で記したところは、ドットパターンが等間隔に(縦横3マス置きに)並んでいることがわかるだろう。なお、元々黒のドットがあった点については透過させた赤丸を記しており、黒のドットがなかった点については透過させずに赤丸を記している。
このようにしてみると、透過させていない赤丸から矢印が伸び、矢印の先に黒のドットがあることがさらに見て取れると思う。このように、図5ドットパターンは、等間隔に並ぶはずのドットに対し、実際のドットがその位置からどの方向にずれているかによって情報を抽出する。図5では、ドットが、等間隔だとしたらあるべき点から左にずれたらx=0、右にずれたらx=1、下にずれたらy=0、上にずれたらy=1、という情報を抽出する例が示されている。(図中、x0、x1、y0、y1と記されている)
つまり、あるべき点から左右のどちらかにずれた点と、上下のどちらかにずれた点の2点を埋め込むことで、それぞれx方向に関する0-1の並びと、y方向に関する0-1の並びができる。図5では、透過させていない赤丸が全部で9点あり、0-1が9つ並んだ二進数を表現できることになる(図の下側に「上記は、x座標100110001、や座標は110101011」と記載されている。)従って、これらの0-1のパターンを変えることで、x座標y座標のそれぞれで29-1の情報を定義できるということである。
なお、実際に情報を抽出するときには、あるべき位置に点があるラインを基準線として特定し、そこから水平方向、垂直方向に情報を抽出する。
次に、図105ドットパターンである。

図105ドットパターンでは、赤と青で交互に示した各ブロックが、1つの情報を表している。なお、各ブロックの4隅にはドットが記されているのがわかるだろう。裏を返せば、この4隅のドットからブロックを特定できることになる。(一部、KDと符号が付されてずれているドットがあるが、これはデータ範囲を特定するためのキーとして利用される。本件発明にはそこまで関わらないので、ここでは特に詳細な説明はしない。)
また、各ブロックの中心に黄色の点を記したが、このように、図105ドットパターンでは、各ブロックの中心付近にドットが付されている。そして、ドットがこのブロックの中心(黄色の点)からどの方向にずれた位置に付されているかによって、情報が特定される。下図の図103のように、45°刻みでずらすことで、1つのブロックにおいて000~111(2進数)までの8通りの情報を表すことができる。

図5ドットパターンと図105ドットパターンはいずれも、基準となる位置からどの方向にずれたところにドットがあるかによって特定の情報を抽出するという点では共通するといえる。
一方で、図5ドットパターンは、等間隔に配置されていたとしたらそこにあるはずの「ドット」が基準となる一方で、図105ドットパターンは、4つのドットによるブロックの「中心点」が基準となる点で、両者は異なる。
また、図5ドットパターンは、ずれる方向が上下と左右の4通り(90°刻み)であったのに対し、図105ドットパターンは、45°刻みの8通りである点で、両者は異なる。
判決文の分析にも重要であるため、図5ドットパターンに係る明細書の記載の一部、及び、図105ドットパターンに係る明細書の記載の一部を、以下に抜粋する。
図5ドットパターンの説明に関する明細書の記載(本件特許より抜粋)
【0025】 このドットパターンの認識では、先ず連続する等間隔のドット605により構成されたラインを抽出し、その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のラインを抽出する。
【0026】 次に、抽出したラインの1つを水平ラインとする。この水平ラインを基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは、水平ラインを構成するドットからスタートし、次の点もしくは3つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。
【0027】 最後に、情報領域を抽出してその情報を数値化し、この数値情報を再生する。
図105ドットパターンの説明に関する明細書の記載(本件特許より抜粋)
【0185】 ドットパターン部601は、図105に示すように、格子状に配置されたドットで構成されている。なお縦横方向の格子線はドットの配置位置を説明するためのものであり実際の印刷物上には存在しない。
【0186】 ここで、4×4個の格子領域を1つのデータブロックまたは格子ブロックと呼び、この格子ブロックの四隅( 格子線の交点( 格子点) 上) には格子ドットLDが配置されている。格子ドットLD同士の間隔は0.35mm~1.0mm、好ましくは0.5mm程度であることが最適である。また、ドットの直径は前記格子ドット間隔の8~10%程度であることが望ましい。
【0191】 データは、図103に示すように、ドット605を格子ブロック内の中心点からどの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。同図では、中心から等距離で45度ずつそれぞれずらした点を8個定義することによって単一の格子ブロックで8通り、すなわち3ビットのデータを表現できるようになっている。なお、さらに中心点から距離を変更した点をさらに8個定義すれば16通り、すなわち4ビットのデータを表現できる。
上記説明を踏まえた上で、訂正前の請求項1と、訂正請求がされた請求項1とをそれぞれ記す。なお、請求項1のうち、本件に関する重要な2つの記載部分を、それぞれ赤字(以下、構成部分1という。)、及び、青字(以下、構成部分2という。)で記す。
【訂正請求前の請求項1】
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置された
ことを特徴とするドットパターン。
【請求された訂正に係る請求項1】
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°の2倍である90°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置された ことを特徴とするドットパターン。
3-2.無効審判について
無効審判において上記の訂正は認められなかったが、そもそもの無効理由について説明しておく。(※訂正が認められないこと自体は無効理由でない(訂正前の請求項で審理判断されるにすぎない))
既に説明したように、図5ドットパターンは、あるべき位置にあるはずの「ドット」を基準にしている一方で、図105ドットパターンは、四角の「4隅にあるドットの中心位置」を基準にしている。
すると、上記の訂正請求前の請求項1における構成部分1(赤字部分)は、「格子点を中心に」と規定されているため、これは図5ドットパターンに対応する記載と解するのが素直である。
一方で、図5ドットパターンは、基準点から上下左右の90°にずらす態様が示されている一方で、図105ドットパターンには、基準点から45°ずつの8通りにずれた態様が示されている。
すると、上記の訂正請求前の請求項1における構成部分2(青字部分)は、「格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に」と規定されているため、これは図105ドットパターンに対応する記載と解するのが素直である。
このように素直に読めば、訂正請求前の請求項1は、図5ドットパターンと図105ドットパターンを混合した構成要件を規定しているが、本件特許の明細書において、図5ドットパターンと図105ドットパターンを混合して情報ドットが規定できることについては記載がされておらず、また、これら2つのドットパターンは、情報の定義の仕方が大きく異なっている。
従って、訂正請求前の請求項1は、明細書等に記載されておらず特許法第36条第6項第1号のサポート要件に違反し、また、構成部分2は、審査経過において補正によって追記された事項であることから、特許法第17条の2第3項の補正要件に違反(新規事項追加)するものであり、無効とされることになる。
そこで、これを回避するために、グリッドマーク社は上記の訂正を試みたと推察できる。つまり、グリッドマーク社のした訂正「45°の2倍である90°ずつずらした前記縦横方向」は、図5ドットパターンが上下左右の90°ずつでずれていることから、図5ドットパターンに当てはめようとした訂正と解することができる。 このような訂正が認められれば、図5ドットパターンを示していると解される構成部分1(赤字)に合わせることができ、サポート要件違反や補正要件違反を解消できると考えたのだろう。
3-3.判決についての感想
全体的な結果について:納得度95%
本件の結論については特に異論はない。特許権者により請求された訂正は、外観上、減縮と言う余地は残されているかもしれないが、実質的にみて、設定登録時の請求項の記載を、その記載に係る実施形態(図105ドットパターン)とは異なる実施形態(図5ドットパターン)へと変更する訂正は、実施形態同士の混同が明細書から読み取れない以上、特許法126条第6項の実質的変更にあたるといえるだろう。
本件で私が気になったのは、なぜ知財高裁が “目的要件違反”を根拠にして訂正を認めないとしたのかである。以下では、この点について、目的要件の判断をどのようにすべきかの考察も含めて検討していきたい。
知財高裁の判断についての考察
本件の訂正要件違反の判断
私が本件でまず最初に疑問に思ったのは、「なぜ目的要件違反(特許法126条第1項各号)を、特に同項第一号の「特許請求の範囲の減縮」にあたらないことを判断し、訂正要件違反という結論を導いたのか」という点である。なぜならば、今回の訂正は特許法126条第6項(拡張・変更の禁止)に違反しているという方がスマートに思えたからである。
なお、前審の無効審判では、グリッドマーク社のした訂正は、特許法126条第1項第一号違反であり、かつ、特許法126条第6項違反であると判断している。一方で、本件訴訟では、特許法126条第6項の拡張・変更の禁止については特に触れていない。
知財高裁は、次のように訂正要件違反についての判断を述べた。(下線は付記)
「本件訂正前の上記構成は、任意の45°間隔による8方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件訂正後の上記構成は、縦横の4方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異なる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には立たない。したがって、訂正事項1は、特許法134条の2第1項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
…原告は、前記第3の1⑴ア のとおり、①訂正事項1は、8方向のうちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを4方向にする制限を直列的に付加するものである、②「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことのできる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
…そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味があるというものではなく、8方向全部が一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、8方向を4方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることのできる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについて選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきである。
以上によれば、訂正事項1を発明特定事項の直列的付加又は択一的要素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはできない。」
上述のように、知財高裁は、グリッドマーク社が「特許請求の範囲の減縮」と主張して行った訂正について、訂正前後の構成を「端的に、両者は異なる構成」であるといい、また、「端的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべき」と言っている。これはつまり、訂正によって発明が異なる内容になったと言っているのであるから、直接的には、126条第6項の「実質上の特許請求の範囲の変更」の話である。
言い換えれば、上述の知財高裁の判断は、「実質上の特許請求の範囲の変更にあたるから、特許請求の範囲の減縮ではない」という論理を展開しているように読める。しかしこれは、判断アプローチとして適切ではないように思える。
目的要件の規定と拡張・変更の禁止の規定は、それぞれに独立した規定であり、異なる要件を判断しているはずである。それにも関わらず、目的要件の判断の根拠に、拡張・変更の禁止に関する判断結果を利用するというのは、それぞれに条文が設けられている立法構造を無視しているようにも思える。
知財高裁は、目的要件の判断について、このような判断ロジックではなく、本来的な目的要件にマッチした判断ロジックを立てるべきではなかっただろうか。あるいは、それが難しいようであれば、目的要件の判断をするまでもなく、準用126条6項に違反するため訂正を認めないとすべきではなかっただろうか。
特許法134条の2第1項と特許法126条第6項の規定
ここでさらに踏み込んでみて、134条の2第1項と126条6項のそれぞれの規定を見てみることにする。下記は、両条文である(なお、議論に不要なところは省略している)。
特許法第134条の2第1項
特許無効審判の被請求人は、…により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一.特許請求の範囲の減縮
…
特許法第126条第6項
第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
ここで注目したいのは、第6項の「拡張・変更の禁止」については、条文上に「実質上」という言葉が明記されている一方で、第1項の「目的要件」の規定には、このような記載はないということである。
そこで、本件との関係で、次の論点が浮かび上がる。
「特許請求の範囲の訂正が目的要件を充足するかの判断において、訂正された特許請求の範囲が、実質的な意味で第1項各号の目的に該当するか否かによって判断すべきか、形式的に各号の目的に該当すれば実質的な判断までしなくてもよいか」
つまり、目的要件の判断に際して「実質上」の観点が要求されていないのであれば、「実質上」の観点から判断された126条6項の結果を目的要件の判断に持ち込むことは、特許請求の範囲を実質的にみて、減縮等に該当するかを判断したことになるため、条文の要件に合致しておらず、その判断には誤りがあるということにもなり得る。もっといえば、知財高裁は、法律の解釈を誤って判断したといわれるかもしれない。(結論に影響しないため、上告受理の申立て理由にはならないとは思うが)
上記論点についての私は、後者の「形式的に判断すれば足りる」とする方が適切ではないかと考えている。つまり、明細書等からその発明の本質的な意味や意義を考慮し、その上で、実質的な意味で該当するかを判断するということまでしなくても、より客観的・一般的な見方で、形式上、該当するかどうかを判断すれば足りるのではないかと思う。
私がそう思う理由は、一つには、条文上「実質」と記載されていないことがあり、もう一つには、他の条項との切り分けが不明瞭になるということがある。
特許法の条文を検索してみると、意外にも(意外なのは私だけかもしれないが)、特許法の中で、「実質」という言葉は、126条6項にしか登場していない。特許法には、補正、訂正、記載要件(36条)、権利(70条)など、多くの箇所で「特許請求の範囲」に関する規定がなされているが、その上で、法は、126条第6項にしか「実質」という言葉を置いていないのである。126条第6項に「実質上」と記し他の条項にこれが記されていないことについては、立法者にこれらの判断を切り分ける意図があったのではないだろうか。
また、目的要件を実質上の観点で判断するとなると、126条6項との切り分け、特に、「特許請求の範囲の減縮」を判断することと「特許請求の範囲の拡張」を判断することの切り分けの意味が薄れる。実質的に捉えるのであれば、誤記の訂正でもない限り、訂正の前後で特許請求の範囲が全く変化しないことはないだろうから、そうすると、訂正によって特許請求の範囲は、およそ減縮するか拡張するかのどちらかに該当することになる。そうなると、「特許請求の範囲の減縮」に当たるか否かを判断することは、「特許請求の範囲の拡張」に当たるか否かを判断していることとおよそ同義であり、これらが別個の規定として存在している理由が薄れてしまう。
このように考えてみると、126条第1項や134条の2第1項の規定が「次に掲げる事項を目的とするものに限る」としていることにも意義があるように思える。 つまり、実質的に減縮にあたるとかそういった判断ではなく、あくまで目的要件はその名の通り、このような「目的」の下でされた訂正か否かを客観的に判断すれば足りると考えるのが相当ではないだろうか。
特許請求の範囲の記載によって表れる発明に実質的な拡張や変更があったか否かは、126条第6項で考えればよく、目的要件においては、実質上、特許請求の範囲の減縮に該当していないかどうかを判断するのではなく、その訂正の内容を客観的に捉えた上で、当業者の一般的な視点から、その訂正の目的は何であるかを判断すべきだったのではないだろうか。
私の考える判断手法
特許請求の範囲の減縮とは、訂正前の特許請求の範囲をより限定的にするものであるはずだから、減縮を目的としているかどうかの判断は、客観的に特許請求の範囲に記載された発明を捉えた上で、「訂正後の特許請求の範囲」に記載された発明を実施した場合に、「訂正前の特許請求の範囲」に記載された発明を実施したといえるかどうかで判断すればよいのではないかと考える。
このように判断すると、
訂正前の特許請求の範囲では、
「前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、」
という記載によって、データ内容が定義されていたが、
訂正後の特許請求の範囲では、
「前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°の2倍である90°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、」
という記載によって、データ内容が定義されたことになる。
そこで、訂正後の特許請求の範囲の記載でデータ内容を定義した場合に、訂正前の特許請求の範囲の記載に該当するといえるかどうかである。訂正前は、45°ずつずれた計8つのパターンを用いてデータ内容を定義することを規定しているのであるから、8つのパターンを用いずにデータ内容が定義されていたとしても、訂正前の特許請求の範囲に記載された発明を実施しているとはいえないだろう。
なぜなら、訂正後の4つのパターンを用いただけで訂正前の発明を実施していることになれば、訂正前の発明は計8つのパターンを全て用いなくてもよいということになり、このことはつまり訂正前の発明においてパターンは最低でも1つあればよいということになる。しかし、このように発明が解釈されていたとすれば新規性や進歩性の判断に影響するであろうし(実際にこのような解釈に基づいて審査はされていないだろう。)、この解釈が含まれるなら、おそらく容易に新規性がないことを証明する先行文献が見つかるであろうから、特許権者においてもこのような解釈を主張するメリットはない(自ら首を絞めることになりかねない。)。
このように、8つのパターンを用いずにデータ内容が定義した場合に、訂正前の特許請求の範囲を充足しないのであれば、4つのパターンを用いてデータ内容を定義することしか規定していない訂正後の特許請求の範囲を実施したとしても、訂正前の特許請求の範囲を実施したことにはならない。従って、本件の訂正は「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではないという結論に至る。
このような判断の方が、客観性も高く、また、論理がシンプルなのでわかりやすいだろう。また、本件において、この訂正に関し原告が縷々主張している内容も、この判断の下では当を得ないものとして一蹴することができる。(参考までに、一番最後にこの訂正に関する原告の主張を載せておく(長文なので後ろに回した。))
無効審判における傍論と知財高裁の判断
無効審判では、上記の訂正に係る判断の中で、「(逆に、4個しか定義できない構成を8個定義できる構成に変更する場合であれば、そのための構成を付加し、上位概念から下位概念に限定したといえる余地もある。)」と述べられた。
本件訴訟では、グリッドマーク社が、審決のこの部分を挙げた上で自らの主張を展開している。このような経緯もあってか、知財高裁は、その判断の中で「単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左右するものではない」として、特許庁の判断の是非には触れないという対応を採った。
しかしながら、私は、この無効審判における傍論は当を得ていると思っている。
その理由の一つには、上述の私の考える判断手法に従えば、減縮に当たると判断できることがあげられるが、それはあくまで小さな理由である。(自らの判断手法を肯定したいがために担いでいるというわけではない) より大きな理由は、実は本件の判断そのものにも関わるが、これを認めないと、特許権者の適切な保護が図れないと思うからである。
本件訴訟だけでなく無効審判でも同様に述べているが、本件では、8つのパターン(8方向)で情報を定義することと、4つのパターン(4方向)で情報を定義することは、異なる情報定義体系であり、異なる構成であると言っている。しかし、これは、本件においてグリッドマーク社が、8パターンを4パターンにしようとする訂正を請求し、特許庁及び知財高裁がこれを認めないために考えられた理由のようにも思える。
そして、この判断の致命的ともいえる問題は、仮に「異なる構成である」とするこの判断ロジックが正しいとしたら、本件発明の実施を回避する方法は極めて容易となってしまうということである。
選択できるパターン数が変われば構成が変わるというのであれば、8パターンではなく9パターンにすればいい。特許庁や知財高裁は、パターン数が異なるものは構成が異なると言ってしまっているため、適当にパターンを足せばそれで権利侵害は回避できてしまうのである。(なお、パターン数を減らした場合に充足しないことは既に述べた通りであり、この権利回避は妥当であると思う。)
しかし、これではあまりに特許権者の保護に欠けるのではなかろうか。本件の判断に従えば、22.5°ずつの16か所でドットパターンを定義すれば、たとえ45°ずつにドットパターンを用いていたとしても権利侵害とならないことになるが、公開代償として権利を与えるという特許制度の趣旨からして、これでは代償のバランスが取れていないというべきである。
第三者が22.5°ずつでデータ定義をした場合、45°ずつの8か所にドットを設けるという本件発明の技術思想をそのまま利用した上で、さらに細かくドットを置けるように、他の箇所にも情報を定義するためのドットを設けるようにしたに過ぎないと考えるのが妥当だろう。つまり、第三者は、本件発明に表れている技術思想はそっくりそのまま頂いているのであり、それにも関わらずこのような第三者が本件発明を利用していない(実施していない)となっては特許権者が浮かばれない。
従って、私は、特許庁及び知財高裁が、4パターンと8パターンを「異なる構成」と判断したことは、誤りではなかったかと考えている。(そもそも特許庁は、異なる構成であると言いながら、上述の傍論を述べているのであり、自らの論理に矛盾が生じているようにも思える。)
そして、計4パターンで定義された発明と、当該4パターンを用いつつ計8パターンで定義された発明とは、後者の発明が前者の発明を利用する関係にあるというべきであり、よって、訂正の目的要件を判断するのであれば、後者は前者の減縮と判断できるのではないかと思う。
(但、そもそもの利用用途やデータの定義形態が異なるといったような、実質的に利用しているとはいえない特段の事情があれば、この利用関係が成立しない余地はあるだろう。)
その他
本件特許の審査経過(出願人と審査官の対応)
本件は、特許査定となるまでの審査経過にも興味深い点があるので考察してみたい。
まず、J-PlatPatから取得した本件特許の審査経過を以下に示す。

このように、本件出願は、2回の拒絶理由通知を受けており、いずれも拒絶理由は36条のみである。
一回目の拒絶理由通知では、請求項1に対し、サポート要件及び明確性要件(36条6項一号二号)が指摘された。なお、一回目の拒絶理由通知では、新規性・進歩性の審査を行っていない。二回目は最後の拒絶理由通知であり、請求項1に対し、明確性要件(36条6項二号)が指摘されている。出願人による一回目の拒絶理由対応によって、サポート要件違反は解消し、また、新規性・進歩性の拒絶理由は発見されなかったことになる。また、ここでは補正の示唆(補正案)が提示されている。以下、請求項1の内容と、拒絶理由通知の内容を、時系列に記す。
出願時の請求項1
【請求項1】
媒体面上に形成され、且つ情報としての情報ドットが配置されたドットパターンであって、
該ドットパターンは、情報を表現する部分として、複数の、縦横方向に所定間隔ごとに設けられた格子線の交点である格子点を中心とした、情報ドットを配置する領域を含み、
該領域のそれぞれには、少なくとも1つの情報ドットが配置され、
該ドットパターンは、水平方向に、所定間隔ごとに引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように、垂直方向に、所定間隔ごとに引いた第二方向ライン上とにおいて、前記格子線との交点を基準点として配置された複数の基準ドットを含み、
該基準ドットの少なくとも1つは、該ドットパターンを識別するフラグとして配置されたことを特徴とするドットパターン。
一回目の拒絶理由通知(請求項1に係る内容)
「請求項1に記載の「格子線との交点を基準点として配置された複数の基準ドット」とは具体的にどのようなものであるのか不明であるとともに、詳細な説明及び図面のいずれの記載に対応するものであるのか不明りょうである(上記文言に該当する記載は見当たらない)。」
一回目の補正
【請求項1】
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットをいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方 向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方 向ライン上とにおいて、前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。
最後の拒絶理由通知(請求項1に係る内容。なお、補正の示唆では請求項1の全文+補正内容が記されていたが、ここでは適宜省略して記す。)
「請求項1における「いずれかの方向に」の記載は不明りょうである(本願発明では、【0191】及び図面第103図にも示されているように、情報ドットによる情報定義のための方向は限定されているが、上記記載は全ての方向を含むため、発明の構成を的確に表していない。上記【0191】及び図面第103図の記載に沿うように補正されたい)。
<補正等の示唆>
請求項1に関し、以下のような補正が一案として適当と解されるので、参考とし検討されたい。
「媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、…格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによって…ことを特徴とするドットパターン。」
なお、上記の補正等の示唆は法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等をどのように補正するかは出願人が決定すべきものである。」
二回目の補正
【請求項1】
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。
このように、本件特許の請求項1は、出願時における請求項1が広く上位概念的に記載されていたのに対し、一回目の補正のよって、大きく補正がされ、また、二回目の補正は、およそ拒絶理由通知で示された補正の示唆に従った内容であるものと見て取ることができる。
出願時の請求項1は、請求項の記載が特定の実施形態を表しているとは言いづらい内容であり、明細書のどこにも記載されていない「基準ドット」という用語を用いている。おそらく、この基準ドットによって、情報ドットが設けられている領域(明細書では情報領域と言っている。)を特定できることを言いたかったのではないかと推測するが、「害ドットパターンを識別するフラグとして」というのが、基準ドットが一体どのドットを特定しようとしているのかを不明にする要因となっているように思える。(例えばここが「前記情報ドットが配置される領域である情報領域を識別するフラグとして」となっていたら結果は変わっていたかもしれない。)
異なる実施形態の構成が混同していると言えるのは、一回目の補正後の請求項1であろう。そのことは、一回目の補正を説明する意見書の記載内容からうかがえる。以下、一回目の拒絶理由通知に対する意見書の記載の一部である。(下線はこちらで付記)
意見書の抜粋
「まず、「格子線との交点を基準点として配置された複数の基準ドット」が不明確であったことから、「基準ドット」を「格子ドット」とする補正を行いました。この補正は、明細書の段落0186の記載を根拠としております。また、「格子ドット」が「情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように」配置されることについては、図5,6,7,8を根拠としております。すなわち、各図面において、破線で示された複数の情報ドットが配置されている部分で情報を表現し、その周りを囲むように「格子ドット」が配置されていることは、これらの図面を参照することで当然に読み取れます。この格子ドットは、ドットパターンから数値情報を求める際に必要となります。すなわち、ドットパターンの撮影画像を処理する際、ライン(第一方向ライン、第二方向ライン)を抽出するために用いられます。さらに、この抽出されたラインをから情報領域が定まり、最終的に数値情報が得られることになります。このことは図4(b)に記載があります。
…また、拒絶理由にはなっていませんでしたが、「情報ドット」の意義を明確にするために、「情報としての情報ドット」を「データ内容が定義できる情報ドット」とする補正を行いました。この補正は、明細書の段落0191の記載を根拠としております。」
この意見書で説明する補正部分は、本件訴訟で争った記載部分とは異なっているが(なお、この補正部分に関しても無効審判では争っており、審理がされている。)、既に出願人は、図5ドットパターンと図105ドットパターンの実施形態を混合して、請求項1に係る発明を説明していると言っていいだろう。
しかしながら、まだ、この時点の請求項1では、図5ドットパターンと図105ドットパターンの実施形態において、一方の実施形態にしか記載がないといえるような記載が、確定的に存在しているとはいえないように思える。一回目の補正における
縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットをいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
との記載は、「格子点を中心に」との記載が、図5ドットパターン寄りの記載ではあるが、格子点を基軸にとか、基軸点をポイントにといった意味合いであれば、4つの格子点の中心を基準としている図105ドットパターンについても、解釈できる余地はあったように思える。
ただし、出願人としては、やはり、意見書で丁寧に説明をしておくべきだったと思う。上位概念化の結果、明細書にない用語を用いたり、一方の実施形態は直接的に表現できているものの他方の実施形態についてはやや曖昧な表現になってしまうというのであれば、請求項に係る記載が各実施形態のどの部分を根拠としており、それが請求項にどのように表れているかを説明しておく。それだけで、本件の結果は全く違ったものになり得たのであり、また、このような対応は、結果論ではなく(本件の争いがあるまでは予測が難しかったことではなく)、注意深く、丁寧に対応を心掛けていれば、十分に予見できたし、対処もできた事項である。その意味で、グリッドマーク社にとっては、非常に勿体ない案件になっただろうと思う。
その上で、さらに不運だったのが、最後の拒絶理由通知のおける補正の示唆であろう。この示唆に応じる形で、二回目の補正によって請求項は、
縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
とされ、「前記格子点の中心から」というのと「45°ずつずらした」という記載が付加されることになった。しかしながら、「格子点を中心に、情報ドットをどの方向にずらすか」という記載と「格子点の中心から、情報ドットをどの方向にずらすか」という記載は、本件にとっては致命的ともいえる解釈の限定を及ぼした可能性がある。
格子点を中心に、であれば、(やや苦しい主張ではあるが)情報ドットを設ける位置を決定するために格子点を中心にして考える、という見方ができる余地はあっただろうし、上述したようにこの点を意見書できちんと説明しておけば、特許権者有利に判断される可能性の方が高かったようにも思う。
これが、格子点の中心から、となってしまうと、正に情報ドットを配置するための起点が「格子点の中心」となることが、一義的に明確になってしまったと言える。そして、「格子点の中心」を起点として情報ドットを配置するのは図5ドットパターンにしか開示されていない一方で、45°ずつずらした方向のいずれかでデータ内容を定義するのは図105ドットパターンにしか開示されていない。
言い換えれば、審査官によって示唆された補正をそのまま出願人が採用して二回目の補正を行ったことが、本件の無効理由をおよそ確定的なものとした原因になっているかもしれないのである。
このように、審査官による補正の示唆は、拒絶理由を解消する唯一の案でないことは当然であるが(審査官もそのことは拒絶理由で述べているが)、そもそも拒絶理由を解消する一案ですらない可能性もあることは、肝に銘じておくべきである。
そして、補正の示唆に安易に飛びつくことはせず、出願人側は、自ら考えて、本当に拒絶理由が解消されているかを判断し、権利化を図らなければならない。
本件は、第4世代の出願であり、専用実施権が設定されたことからしても、出願時において重要な案件であるという認識はあったのではないだろうか。
そうだとすると、審査経過における本件の対応は、やや配慮に欠けるものであったかもしれない。十分な注意を払い、丁寧な対応を心掛けさえすれば、本件のような結果を事前に回避できることは十分に可能だったはずである。
国家賠償という選択の可能性
最後に、本件については、行政庁である特許庁審査官の審査について、特許庁に国家賠償を求めるという途もあり得るのではないか、という点について触れておきたい。
国家賠償法第1条第1項は次のように規定している。
国家賠償法第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人である出願人/特許権者に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
このように、公務員たる特許庁審査官が、その職務である審査を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、公共団体である特許庁が、これを賠償する責に任ずることになる。
ここで重要なのは、「故意又は過失」と「違法性」と「他人への損害」である。但し、「違法性」については、およそ「故意又は過失」の要件に含まれるので、故意又は過失があり、これによって他人に損害が発生したといえる場合には、違法性の要件も充足するというのが通例である。(判例は、国家賠償法上の「違法」を、公務員の職務上の注意義務違反と捉えているため、故意は当然のこと、過失(注意義務違反)があった場合にも、違法性は認められるとしている(最判平成5年3月11日、最判平成11年1月21日)。)
そこで、「故意又は過失」の要件だが、さすがに、審査官が故意に出願人を陥れようとして、無効理由があると知りながら補正の示唆をするとは考え難いので、「過失」があったといえるかが、一番の論点になるだろう。
前提として、特許の審査は、非常に難しいものであり、必ずしも正しい審査結果を導くことが審査官に要求されているとは言えない。そのために、異議申立てや無効審判などの制度が設けられており、従って、「結果的に無効になった」という理由から、審査官に国家賠償法上の「過失」があったと認められることはさすがにないだろう。
例えば、刑事裁判にかけられて無罪になったからといって、警察官の行った逮捕に、国家賠償法上の「過失」があったと直ちに導くことはできない。(これについては判例がある。)
それでは、審査官による「補正の示唆」はどうであろうか。仮に、「補正の示唆」に従った結果、特許権が設定登録され、その後、無効になったとして、このような場合に、審査官の審査に「過失」があったと直ちに導くことも、適切ではないと思われる。
なぜならば、拒絶理由への対応の第一義的な責任はあくまで出願人にあるのであり、法律上、補正の示唆に従わないと特許査定にならないというのであればまだしも、補正の示唆を受け入れて対応するか、これを受け入れず他の対応をするのかについて、出願人には意思決定の自由があり、このように出願人が自らの意思に基づいて最終的に行った結果に対する責任を無視して、審査官にその責任を転嫁させるというのも不当だと考えられるからである。
加えて、もしこれで「過失」が認められるとすれば、審査官が「補正の示唆」を行うことはなくなるだろうし、「補正の示唆」が、審査官の経験に基づく有益な情報として活用されているという実態からしても(特に、特許実務に精通していない出願人自らが対応する場合には有益な情報である。)、このような結果を招来しかねない判断は、全体の利益を損なうものともいえる。
しかしながら、審査官が審査において全くの責任を負わない(どのような対応を採っても審査に関しては免責される)というのは、公益的に見ても、あり得ない考えだと私は思う。何らの責任も負わないのであれば、審査官は自らの審査に責任を持って対処する必要はなくなり、審査の質も担保されず、行政の腐敗が進みかねない。
同様に、「補正の示唆」があくまで一案であり、それに対する結果について、当然には責任を負わないとしても、審査官のした補正の示唆が、ただの一案であるというだけで免責されるというのも不当な考えだと思う。
なぜならば、たとえ補正の示唆が法律的効果を生じさせないものであるとしても、審査官による補正の示唆は、およそ高い確率で拒絶理由を解消するものであるとの期待を出願人に抱かせ、出願人の意思決定に一定程度以上の影響を与えることも、実態であるといえるからである。
そうすると、(個人的な考えだが)「補正の示唆」に対して審査官の「過失」が認められるには、その示唆の内容が、①特許が無効とされた原因に深く関わるものであり、②示唆された補正がなされなかった場合の請求項であっても特許が無効とされていたとはいえず、③その示唆が、審査官が通常有するべき注意を払ってなされたとは到底いえないような事情(通常の審査官が通常有すべき注意を払っていれば、当該示唆が拒絶理由を解消しないか、あるいは、新たな拒絶理由を生じさせることを容易に認識できたといえる場合等)が認められる場合には、審査官による「補正の示唆」によって、出願人が損害を被ったときの審査官(特許庁)の過失責任を認めてもよいのではないだろうか。
そして、本件についてみると、出願人が一回目の意見書において、図5ドットパターンの実施形態と、図105ドットパターンの実施形態のいずれも補正の根拠にあげていることから、出願人の意図として、出願時の請求項1に係る発明が両実施形態を含み得る発明であり、そのような発明について特許権を認めることを要求していることは容易に認識できたはずであり、既に上述したように、一回目の補正の段階では、本件に係る無効理由と同じ無効理由を有していたとまではいえず(訂正によって回避できる余地も広がっていたはずであり)、そして、格子点の中心から45°ずつずらした方向のいずれかを適宜選択して情報ドットを定義しているような実施形態がないことや、このような図5ドットパターンと図105ドットパターンの複合的な形態ともいえる内容をサポートするような記載が明細書等にないことも、通常の審査官が通常有するような注意を払っていれば、容易に認識できたことであるといえるのではないか。
従って、上記の考え(判断基準)に従えば、本件については国家賠償を認めてもよいのではないか、というのが私の個人的な考えです。(実際に、国家賠償訴訟を提起しないと結果はわかりませんし、結果を保証するものではありませんが。)
それでは、仮に、「過失」が認められたとした場合、何が「損害」に当たるのだろうか。
一つには、本件の審判及び訴訟費用が挙げられるだろう(但し、代理人費用まで含まれるかは不明)。
また、これまで支払ってきた特許料についても認められる余地はあるかもしれない。(無効である特許が登録されて、それによって特許庁に料金を支払うことになったのであるから、詐害行為とまでは言わないものの、本来であれば特許査定にならず、払う必要のなかった特許料を払っているという主張は通るかもしれない。)
なお、本件は、専用実施権の設定がされており、何らかの対価を得ている可能性が高そうだが、得られた対価とこれらの損害との間の覆滅は認められないだろうと思う。これを認めてしまうと、通常実施権がある場合などの判断が複雑になるし、通常/専用実施権があるかないかという特許庁(審査官)の行為が何ら関与しない事情によって、審査官の行為による損害額に差が生じるという事態になる。専用実施権の設定はあくまで、特許権が設定登録されたという法律関係に基づいて発生するこれとは別の法律関係(専用実施権契約等)であり、直接的には別の法律関係から得られた利益であるため、特許査定から直接的に生じる特許権の設定登録料や維持年金とでは、性質を異にするものと言えそうだからである。
また、本件は、同じような論点で、他にも3件の無効審判が請求され、全て同じような結果になっているが、これらについての審判及び訴訟費用や特許料が、本件の損害として認められる可能性は低いと思う。分割出願によって別で出願するときには、他のファミリー出願で特許査定が認められた部分を踏襲することは出願人の自由であるし、そこまで過失責任の幅を広げてしまうのは、出願人側の責任をあまりに軽視することになり、衡平でないように思えるからである。
そうすると、国家賠償を請求したとしても、無効になった特許が復活するわけではなく、損害として認められる金額もそこまで高くはなさそうなので、国家賠償を請求することの実益はあまりなさそうである、(個人的には、裁判所がどのような判断をするのかに興味津々なので、トライしてみて欲しいとは思うが…)
参考(訂正に係るグリッドマーク社の主張)(判決から抜粋)
「(ア)訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の減縮に該当しないとされる「直列的に記載された発明特定事項の削除」ではなく、特許請求の範囲の減縮に該当するとされる「択一的記載の要素の削除」である。
(イ)本件審決の「(逆に、4個しか定義できない構成を8個定義できる構成に変更する場合であれば、そのための構成を付加し、上位概念から下位概念に限定したといえる余地もある。)」との説示(6頁)によれば、本件審決は、本件訂正とは逆の、4個から8個に定義できる構成への変更を、特許請求の範囲の減縮に該当する例とされる「発明を特定するための事項の直列的付加」と解していると理解される。このように、定義できる構成の変更を直列的事項と理解しているということは、本件審決は、45°ずつずらすことで8個定義できる本件発明の構成を、①90°ずつ縦横方向にずらすことで4個しか定義できない構成と②この①の方向を除く斜め4方向にずらすことで4個しか定義できない構成とが直列的に記載された構成とし、本件発明1の構成から本件訂正発明1の構成への訂正を、直列的な発明特定事項となっている上記①及び②の記載から上記②を削除するものと理解し、それゆえ、特許請求の範囲の減縮には該当しないとしたものと考えられる。
しかしながら、本件発明1に「前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」とあるとおり、データ内容を定義する構成は一つの単一な構成であり、上記①及び②のような二つの構成に分離できることも、あるいは、二つの構成が結合したものとも本件明細書には記載されていない。すなわち、本件発明1の構成は、8通りの方向のいずれかに1個のドットを配置することにより8通りの情報(3ビット)が形成されるのであって、縦横4方向のいずれかにドットを配置することにより、4通りの情報を、斜め4方向のいずれかにドットを配置することにより4通りの情報をそれぞれ定義し、これらの組み合わせによって合計16通りの情報を形成するものではない。
(ウ)訂正事項1は、データ内容を定義する単一の構成において、「いずれかの方向」とする選択肢について、「45°ずつずらした方向のうち」に対して「45°の2倍である90°ずつずらした前記縦横方向のうち」とする制限を直列的に追加し、方向の範囲を8方向から4方向に制限するものといえ、限定的に特許請求の範囲を減縮するものである。
あるいは、訂正事項1は、ずらす方向の数であり、それぞれの方向が択一的記載の要素である「45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向」で定義される各方向を、「いずれかの方向」として8方向選択できたものを「いずれかの方向」として4方向にしか選択できなくするものである。すなわち、本件発明の「45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義」について、これを縦横方向に限定してみると、選択肢として少なくとも、①縦横方向の4方向でデータ内容を定義する選択肢、②縦横4方向のうちの3方向でデータ内容を定義する選択肢、③縦横4方向のうちの2方向でデータ内容を定義する選択肢、及び④縦横4方向のうちの1方向でデータ内容を定義する選択肢を含むものである。そうすると、本件訂正発明の「前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°の2倍である90°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に」は、上記①ないし④を一般化したものといえる。このようにみてみると、「45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向」というのは、45°ずつずらした8方向、7方向、6方向、5方向、4方向、3方向、2方向及び1方向のいずれかを選択してデータ内容を定義するものであり、これを4方向以下の方向にすることは、択一的記載の要素の削除である。
(エ)数値による限定は、数値によって限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、8方向から4方向への限定は、下位概念化である。 (オ)訂正事項1は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、かつ、訂正により新たな作用効果を奏するものではないから、特許請求の範囲の実質的な変更にもならない。」

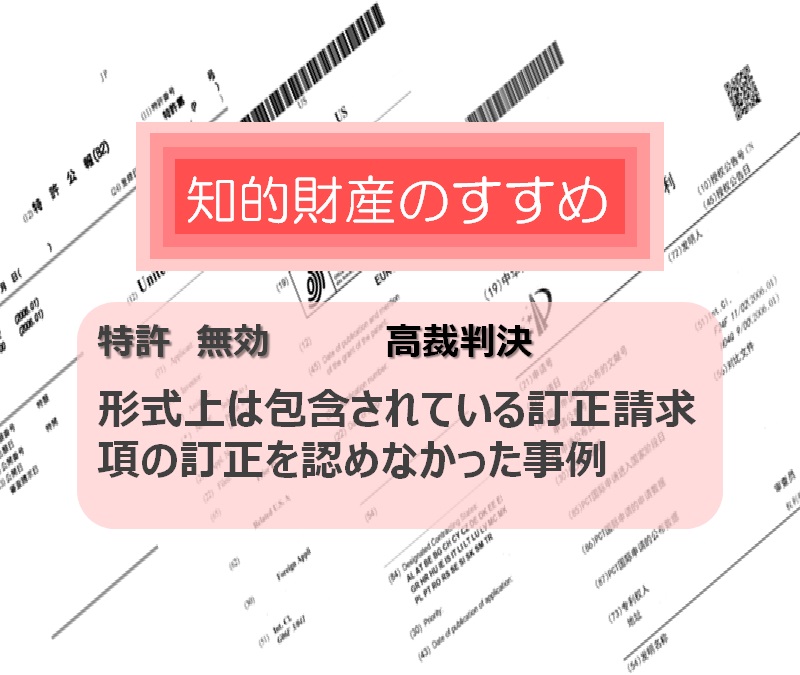

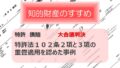
コメント