損害額:特許法102条2項と同条3項の重畳適用を認めた事例
令和4年10月20日(2022/10/20)判決言渡
#特許 #民法709条 #特許法102条2項
1.実務への活かし
~権利行使~ #民法709条(不法行為に基づく損害賠償) #特102条(損害額)
特許法102条第2項(侵害により得た利益)において、覆滅された部分に、同条第3項(実施料相当額)を適用して、損害額を主張することができる。
但し、「特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由」と、「それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由」のうち、前者に基づく推定覆滅部分には、同条3項は原則適用されるが、後者に基づく推定覆滅部分のすべてに同条3項の適用が認められるわけではない。
権利行使者は、後者の覆滅事由については、当該事由に係る事情の事実関係の下で、特許権者が実施許諾をすることができたことを主張しなければならない。
また、特許法102条第2項の適用において、特許権者側が、特許発明の実施品や、特許発明と同様の作用効果を奏する製品を販売していることは必須ではない。
※なお、102条2項と3項の重畳適用という法律構成はともかく、102条2項の規定に基づく損害額の認定においても。実施許諾の機会喪失による利益を認めたことについては同意見である。一方で、覆滅事由ごとにこの利益の有無を検討するときの判断手法や考え方については、いくつか賛成できない点がある。(結果、損害額についても反対の意見がある。この点の詳細は後述。)
2.概要
本件は知財高裁の大合議判決である。
特許権者である控訴人株式会社フジ医療器(以下、フジ医療器という。)が、被控訴人ファミリーイナダ株式会社(以下、イナダ社という。)に対し、特許権侵害に基づく15億円の損害賠償を請求し、同請求に対して知財高裁が3億9154万9273円(及び遅延損害金)の損害を認めた事案である。
なお、原審では、3件の特許権(本件特許A~C)に基づき損害賠償を請求していたが、これに対し、大阪地裁はいずれの特許権についても、「被告製品は特許権の技術的範囲に属しない」として、請求を棄却していた。
本件訴訟(控訴審)でフジ医療器は、3件のうち、本件特許A及びCに係る請求棄却部分(敗訴部分)について控訴し、請求額15億円のうちの4億円弱が認められた。実質的な逆転勝訴といっていいだろう。
本件では、①特許法102条第2項適用の条件である「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」の存在に、特許権者の製品が特許発明の実施品であるか同様の作用効果を奏する製品であることを要するか、という点と、②特許法102条第2項の推定規定に基づいて損害額を主張した場合に、覆滅部分に102条第3項を重畳適用できるか否かという点が争われた。
知財高裁は、①について、特許権者の製品が特許発明の実施品であるか同様の作用効果を奏する製品であることを要しないと判断し、②について重畳適用を認めた。また、覆滅部分の重畳適用の具体的な判断手法について、フジ医療器及びイナダ社のいずれの主張も容れなかった。
知財高裁の示した判断手法は、まず覆滅事由を大きく2つの類型「特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由(以下、第1類型の覆滅事由)」と、「それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由(以下、第2類型の覆滅事由)」に分け、第1類型の覆滅事由については、原則として重畳適用を認められる一方で(特段の事情のない限り、実施許諾をすることができると認める。)、第2類型の覆滅事由については、これに係る事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべき、と判断した。
そして、本件では、具体的な覆滅事由として「特許発明が製品の部分のみに実施されていること(つまり、直接的に完成品に係る発明ではないこと)」及び「市場の非同一性(ある時期において、侵害者が侵害品を輸出していた国に特許権者が製品を輸出していなかったこと)」が認められており、これらはいずれも第2類型の覆滅事由であると判断した上で、前者については重畳適用を認めなかった(1つの製品における寄与の程度であるため、製品の寄与していない部分に実施許諾できたとは認められない)一方で、後者については重畳適用を認めた(自ら輸出はできないが、実施許諾はできる)。
以下に、知財高裁の判断を挙げる。
知財高裁の判断(判決より抜粋。下線、太字はこちらで付記)
「特許法102条3項は、特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができると規定し、同条5項本文(令和元年改正特許法による改正前の同条4項本文)は、同条3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げないと規定している。そして、特許権は、特許権者の実施許諾を得ずに、第三者が業として特許発明を実施することを禁止し、その実施を排除し得る効力を有すること(特許法68条参照)に鑑みると、特許法102条3項は、特許権者が、侵害者に対し、自ら特許発明を実施しているか否か又はその実施の能力にかかわりなく、特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額の最低限度としてその賠償を請求できることを規定したものであり、同項の損害額は、実施許諾の機会(ライセンスの機会。以下同じ。)の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益に相当するものと解される。
一方で、特許法102条2項の侵害者の侵害行為による「利益」の額(限界利益額)は、侵害品の価格に販売等の数量を乗じた売上高から経費を控除して算定されることに照らすと、同項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するものと解される。
特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。
そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。
そして、特許法102条2項による推定の覆滅事由には、同条1項と同様に、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解されるところ、上記の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、上記の販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。」
3.判決内容の考察
3-1.判決についての感想
全体的な結果について:納得度65%
本件で、知財高裁の大合議判決が、102条2項に基づく損害額の認定の中で、特許権者が受けた損害に、特許権者の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の両方を観念し得ると判断し、両利益を含めて損害額を算出したことについては賛成である。
しかしながら、具体的な判断については、判決文を読んでもどこかしっくりとこないところがあった。このもやもや感をクリアにするのは、相当に骨の折れる作業であり、何度も議論の壁にぶち当たっては、この論点をどのように考えるべきかを考察した。結果的に、1ヶ月以上この判例と向き合った。そしてようやく、個人的にすっきりする論理構成がまとまった。
私の論理構成は、次の3点、①法律構成としてこれを102条2項と同条3項の重畳適用と解したこと、②実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の具体的な判断手法、及び、③特許発明が被告製品1の部分のみに実施されていることに係る覆滅事由に対し、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益を認めなかったこと、について大合議判決と異なる意見を持っている。簡単に言えば、大合議判決に対する反対意見である。
その結果、認定される損害額にも違いが生じている(この論理構成では、大合議判決よりも認定額が大きい)
以下では、1ヶ月以上の苦悩の道のりを、そして、私なりに導いた論理構成を述べていくことにする。
3-2.102条2項の推定覆滅部分に対する102条3項の適用について
知財高裁大合議判決の論旨(3つの論点)
本判決には、大きく3つの論点があるといえる。
まず1つ目は、102条2項の請求適格に関し、特許権者が特許発明の技術的範囲に属する製品を実施している必要があるか否かについてである。
この点について知財高裁は「特許権者の製品が、特許発明の実施品であることや、特許発明と同様の作用効果を奏することを必ずしも必要とするものではないと解すべきである」と判断した。
また、イナダ社が102条2項の請求において「侵害主張をする相手方の特許権を侵害しない製品を販売していることを必要とすると解すべきである」と主張したのに対し、知財高裁は「控訴人(フジ医療器)製品が被控訴人の別件特許の侵害品であることが特許権侵害訴訟の判決により確定しているものではないのみならず、上記の競合品が事後的に他人の侵害品であると判断されたとしても、現に、当該競合品が市場において侵害品と同じ時期に流通していた事実が認められる以上は、侵害者の侵害品に向けられていた需要が当該競合品に向かうという関係性が認められるから、特許権者に、侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在することを否定することはできない」と判断した。
2つ目は、推定覆滅部分についての102条3項に基づく損害額の請求可否についてである。
この点について知財高裁は、令和元年改正の特許法102条1項の改正部分に関する逐条解説と共通する記載を用いて判断を行っている。逐条解説及び本判決の該当部分の記載を以下に示す。なお、対比しやすいように下線を記している。
逐条解説第21版
「…旧一項は、主に売上減少による逸失利益のみ規定しており、これ以外の逸失利益については特段の規定を措置していなかったところ、知的財産の権利者自らが実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得ることができると認められるのであれば、売上減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損害賠償額算定の特例を定めることが損失の塡補という観点からは望ましい。」
本判決
「特許法102条3項は、…を規定したものであり、同項の損害額は、実施許諾の機会(ライセンスの機会。以下同じ。)の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益に相当するものと解される。
一方で、…特許法102条2項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するものと解される。
特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。
そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。」
3つ目は、推定覆滅部分に102条3項を重畳適用する際の、「特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき」をどのように判断するかである。
この点について、知財高裁は、令和元年改正102条1項の規定の枠組みと同様の考え方を基準としている。以下に、102条1項の規定と、本判決の該当部分を示す。なお、こちらも対比しやすいように下線を記している。
特許法102条1項
特許権者又は…次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権…を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者…の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者…が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権…に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
本判決
「特許法102条2項による推定の覆滅事由には、同条1項と同様に、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解されるところ、上記の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、上記の販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。」
以下では、これらの3点について考察していきたいと思うが、その前にまず、特許法102条の規定と、この規定の対象となる民法709条の不法行為に基づく損害賠償の規定(特許法102条は民法709条の特別規定である。)の本質的な考えを整理しておくことが、考察を進める上で不可欠である。
特許法102条及び民法709条の規定
民法709条の規定
民法709条は不法行為による損害賠償請求の規定である。そして、この規定は懲罰賠償ではなく填補賠償を定めた規定と考えられている。そのため、不法行為に基づく損害賠償は、不法行為を行ったことへの懲罰的な制裁として侵害者に賠償を命じるのではない。
不法な行為を行った行為者の悪性を裁くのではなく、あくまで、侵害された被害者側に相当な賠償をすることが本質である。よって、不法行為がなかったとしたら被侵害者が得られたであろう利益(逸失利益とか、得べかりし利益などといわれる。)を填補するだけの賠償が命じられることになる。
不法行為による損害賠償において、その損害の算定は、差額説の考えを基礎とするのが判例・通説である。差額説とは、不法行為がなければ被侵害者が置かれているであろう財産状態と、不法行為があったために被害者が置かれている財産状態との差額が損害であるという考えである。
ここで付言しておくと、特許権侵害訴訟では、民法709条の他に民法703条の不当利得返還請求がされることもあるが、不当利得返還請求は、その本質において、不法行為による損害賠償請求と異なる規定である。
不当利得返還請求は、受益者の保持している利益が法的に正当化されない場合に、本来的にその利益を保持することのできる者へと返還させる制度である。民法709条が、侵害者による侵害行為を中心にし損害の填補を図ろうとする制度であるのに対し、民法703条は、受益者の利得を中心にしその利得の所在をあるべき者に返還させることで事態の正常化を図ろうとする制度である。
特許法102条の規定
特許法102条は、民法709条の特別規定であり、損害の額に関する規定である。特別規定とはいっても、損害額の算定についての特則であり、よって、特許法102条の規定を考える上でも、上述の損害賠償の考え方(填補賠償や差額説)はベースになるというべきである。
特許法102条2項により推定される損害額は、その条文の内容だけ見れば、民法709条よりも703条の不当利得返還請求の規定に似ているが、特許法102条2項の規定が不当利得ではなく不法行為であるという点については、逐条解説に興味深い内容が述べられている。
逐条解説
「二項は侵害者が侵害の行為により受けた利益の額をその請求をする者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される旨を規定したものである。…侵害により自己が受けた損害の額の立証をすることの困難に比べれば相手方の受けた利益の額の立証の方が幾分でも容易である(常にそうであるとはいえないが)ことを考え権利者を保護するために規定が設けられたものである。昭和三四年の工業所有権制度改正審議会の答申においては、民法七〇九条の不法行為の規定と同趣旨の規定のほかに「故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害の行為によって受けた利益の返還を請求することができる。」旨の規定をおくこととしていたが、利益が損害の額を超える場合にまでそのすべてを返還せしめるのは侵害者に苛酷であり、民法の原則から著しく逸脱することになるというような理由から、これを改めて利益の額は損害の額と推定するという二項のような規定にしたものである。…
〈利益の返還〉審議会の答申は「特許権者は故意又は過失によって自己の特許権を侵害した者に対しその侵害の行為によって得た利得の返還を請求することができる」旨の規定を設けるべきことを述べている。これは、民法七〇三条及び七〇四条の規定による利得の返還に関する規定が権利者の損失の額を限度として返還することになっていることと著しく異なる。…その代案ともいうべきものが本条二項の規定であるが、本条二項は審議会の結論の代案としてはかなり性質の異なるものとなっている。すなわち、審議会の結論は不当利得の返還として問題を捉えているのに対し、本条は不法行為による損害の賠償として問題を捉えているのである。」
このように、102条2項は、当初の審議会の案が、利益が損害の額を超えていたとしても利益の全額を返還させるものであったのに対し、これでは民法の原則から逸脱するため推定規定とし、権利者の損害の額を超えない範囲での利益の返還を認めようとした。
ここに、特許法102条2項の規定の特殊性が伺える。
填補賠償を考えるとき、差額説の考えに従うなら、賠償額が侵害者の得た利益を超えるか否かは問題にならない。例えば、高級な腕時計の偽物を格安で販売していた場合、侵害者の利益がわずかであり、被侵害者の損害額がこれを上回っているとしても、そのことによって損害額の調整は図られない。もっとわかりやすく言えば、侵害者の儲けがゼロであっても賠償責任は生じるのである。
しかしながら、102条2項は、侵害者の利益が最大限となり、そこから事情に応じて減算していく方向で損害額を認定する規定なのである。(なお、特許法102条2項は推定規定としているだけで、文言だけを見れば、増額する方向で推定を覆すことも許されそうではあるが、逐条解説が「利益が損害の額を超える場合にまでそのすべてを返還せしめるのは侵害者に苛酷であり、民法の原則から著しく逸脱する」と述べていることからすると、推定の覆滅は減額の方向に制限されるというのが立法者の意図だろう。)
つまり、特許法102条2項の規定は、特許権の侵害行為によって相手が利益を得ていたのであれば、侵害行為がなかったとしたら、その利益は全て特許権者が得ることができた可能性があるといえるため、これを損害額と推定し、侵害者の得た利益が実際にはどの程度特許権者に向かったといえるかを、推定の覆滅事由として検討する規定と考えられる。
2項に比べれば、特許法102条1項の規定は填補賠償の考えに素直な規定である。特許発明の譲渡行為が実施行為である以上、これを適法に行えるのは特許権者及び正当な権限者のみと考えることができる。よって、特許権者が代替品を有しているのであれば、侵害者の譲渡数量を特許権者の可能な範囲で特許権者の行為とし(侵害がなければ実施できた行為とし)、これに基づいて損害額を算定することは、正当な考え方といえる。
また、逐条解説が1項に関し、
「(1項制定)前においても、特許権を侵害する製品が販売された結果、特許製品の販売数量が減少したことに伴う損害(逸失利益)の賠償は、民法七〇九条に基づき請求することが可能であった。しかし、こうした請求に対する従来の判決においては、市場構造が極めて単純で、「侵害製品の販売数量全てを権利者が販売し得た」ことの立証ができた場合にしか逸失利益の賠償が認められておらず、それ以外の場合には、妥当な損害の塡補がなされているとはいえない状況であった」
と述べているように、102条1項は、民法709条の規定のみでは特定の侵害態様しか解決されないという、特許権侵害に対し硬直的であった民法709条の柔軟な運用を可能とさせる規定といえる。
さらに、平成30年(ネ)第10003号(令和2年2月28日判決)の大合議判決では、「特許法102条1項は,…侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより,より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。」と述べており、差額説の考えを極力維持したまま、立証責任の転換を図ることが、1項の制度趣旨と解されている。
特許法102条1項の規定が「立証責任の転換」を図ることを趣旨とする規定であるのに対し、2項の規定は(立証責任の転換も図られているが)「立証の軽減」を図ることを趣旨とする規定である。
この点については、逐条解説で
「侵害により自己が受けた損害の額の立証をすることの困難に比べれば相手方の受けた利益の額の立証の方が幾分でも容易であることを考え権利者を保護するために規定が設けられたものである」
と述べられており、
また、知的財産高等裁判所平成25年2月1日特別部判決、知的財産高等裁判所令和元年6月7日特別部判決で
「この規定の趣旨は、特許権者による損害額の立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定し、これにより立証の困難性の軽減を図ったものである」
と述べられている。
このように、填補賠償の考えを離れ、相手の得た利益を損害額と推定する規定の趣旨は、権利者による立証の軽減にあり、相手の得た利益が上限とされるのも、ある意味で、1項の規定にはない立証負担の軽減という利益を享受することとのトレードオフと捉えることもできる。
論点1について
まず、102条2項の請求適格について、請求権者である特許権者(あるいは専用実施権者)において、特許発明の実施品、あるいは、同様の作用効果を奏する製品の実施が必要とされないことについては、特に異論はない。
上述のように、不法行為に基づく損害賠償請求は、侵害者による侵害行為がなかった場合に、権利者がどれだけの利益を得たかであるのだから、侵害行為によって譲渡された数量分の需要が、侵害品以外の類似品に向くことは当然の帰結といえよう(但し、需要の一部が類似品に向かない、つまり、侵害品でなければ買わなかったという場合もありえるので、その場合は、類似品に向かわない分が覆滅されるべきである)。
そうすると、侵害分の需要が向くであろう類似品、あるいは、この類似品に含まれる部品を製造する者であれば、少なくとも102条2項の請求適格は認められると考えるのが妥当であろう。
それよりも、論点1では、イナダ社の主張に対する知財高裁の見解が興味深い。
侵害分の需要が向く対象となり得る特許権者の製品(以下、競合品という。)が、侵害者の保有する特許権(以下、侵害者保有特許という。)を侵害していた場合に、102条2項の請求が認められるかである。
これに対し、知財高裁はまず、特許権者の競合品が侵害者保有特許を侵害していることが判決で確定していないのであれば、102条2項の請求は認められるとしている。これは当然といえば当然である。
加えて、知財高裁はさらに進んで、事後的に侵害品であると判断された場合であっても、102条2項の請求は認められるとしている。これも当然といえば当然であろう。特許法104条の4が、事後的に特許の無効が確定した場合にこれを理由とする再審の主張を制限している以上、権利が最初から存在しなかったものとみなされた場合ですら紛争の蒸し返しが許されていないのであるから、相対的にみて、後から競合品が侵害品であるとわかった場合に請求が否定されることもないとするのが自然である。
それでは、裏を返せば、本件の判決をするまでに特許権者の製品が侵害者保有特許の侵害品であることが確定していれば、裁判所はこれを考慮するということだろうか。この点について知財高裁は明言を避けている。
私の個人的な見解は、判決前に別件訴訟で侵害が確定していた場合であっても、102条2項の請求適格は否定されないと考える。なぜならば、ここでの請求適格という要件の本質は、侵害者の利益が、特許権者に移る可能性があるかどうかであり、その関係性の有無を見ているに過ぎないからである。
つまり、特許権者が競合品を実施していることは、あくまで、請求の適格性を判断するための一つの指標に過ぎず、この指標に限らずとも、特許権者と侵害者の間に一方が利益を失えば他方が利益を得るであろう因果関係が認められればよいはずである。そうすると、特許権者の競合品が侵害品であることから直接的に因果関係が否定されない以上は、請求適格の議論において持ち出される議題ではないと考える。また、この議論を請求適格において持ち出すことは、審理を複雑化し、訴訟の著しい遅延を招く恐れもあるだろうから適切とも言えないであろう。(例えば、競合品の販売期間と特許の設定登録日との関係から、競合品が相手の特許を侵害している期間(重複部分)とそうでない期間があった場合に、重複部分の期間だけ請求の適格性が否定され、重複していない期間に適格性が認められるというのは、既に本案の審理に入っており(利益と損害の因果関係)、本案前の議論といえないのではないか。)
加えて、102条2項に関して言えば、この規定で推定される損害額は、同条1項とは違い、特許権者の実施品を考慮することなく算出される。特許法102条2項の規定そのものの違法(違憲)を争うのであればともかく、この規定が適法であることを前提にするならば、特許権者が、相手の権利を侵害する競合品を実施しているという事実は、損害額の算定においても何ら関係しない事項である。
一方で、102条1項の規定の「特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」が、侵害者保有特許の侵害品であることは許されないとするべきであろう。この場合に特許権者の侵害品に基づいて損害賠償を認めることは、自らの不法行為によって相手の不法行為に取って代わろうとする、謂わば、相手の不正を自分の不正に塗り変える行為であり、司法による救済としては不適切と言わざるをえない。
但し、これは請求適格の議論ではなく、あくまで、102条1項の規定における「特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」に相手の特許の侵害品を当てはめることの正当性を争うに過ぎず、請求適格が否定されるというわけではない。
論点2について
102条2項と3項の重畳適用を認めてよいか。
知財高裁が述べた「特許権者が受けた損害は、売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される」との判断は、逐条解説で102条1項について述べられている内容と同様だが、この内容自体は、102条1項だから観念できて、2項だと観念できないという話ではない。
そもそもが、特許法102条の規定とは関係なく、一般論として、特許権の行使に、自らの実施と他社への許諾があり、これらは並行して実行され得るという事実を述べているに過ぎないのだから、特許権侵害に対する民法709条の逸失利益を考える上で、この一般的な事実を考慮することは、むしろ差額説の考えに合っているだろう。
その上で、102条2項の規定において、この考え方を当てはめてよいかという点を考えなければならない。
例えば、102条3項の規定は、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益についてのみを最低保証額として定める規定であるから、この規定に対してさらに売上げの減少による逸失利益の考えを組み込もうとすることは妥当ではない。
102条2項は、侵害者の得た利益を損害額と推定し、この利益のうちのどれだけが、侵害行為がないとした場合に特許権者に向くかで、具体的な損害額を認定する規定であるならば、特許権者に向く利益として、売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の両方を観念することはできると解することができるだろう。
売上げ減少による逸失利益は、これをそのまま特許権者が売り上げて得た利益として捉えることができ、そうすると、侵害者の得た利益からこの逸失利益を除いた額は、侵害者が侵害行為によって得た利益として残っているのであるから、侵害を前提とした利益に対し、特許権者には、なお実施許諾をする権利を有しているといえる。
このようにして考えると、102条2項と3項の重畳適用を認めてもよいように思えるが、ここで一点、問題が生じる。
それは、平成30年(ネ)第10063号(令和元年6月7日判決)の知財高裁大合議判決が
「特許法102条2項の上記趣旨からすると,同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは,原則として,侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって,このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。もっとも,上記規定は推定規定であるから,侵害者の側で,侵害者が得た利益の一部又は全部について,特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には,その限度で上記推定は覆滅される」
と述べたことである。
この大合議判決は、102条2項の推定の覆滅部分については「特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠ける」部分であると述べているのである。いくら実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益が観念できるからといって、特許権者の損害との相当因果関係がないとされた覆滅部分に対し、なお実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益を考えることは論理的に適切ではないだろう。
この問題をどうするかについては、2つの考え方があると思う。
一つ目の考え方は、平成30年(ネ)第10063号の判決でいう「特許権者が受けた損害との相当因果関係」とは、あくまで、「売上げの減少による逸失利益」としての損害との相当因果関係であって、102条2項の規定は、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益を、損害額の認定の対象とはしていないという考え方である。
この考え方であれば、102条2項では売上げの減少による逸失利益だけが検討されるのであるから、覆滅部分に対し、102条3項による実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益を適用することもできるだろう。また、102条2項及び3項の重畳適用という知財高裁が導いた法律構成にも合致する。
しかしながら、このような法律構成には疑問が残るだろう。売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の両方を観念することができるといっているにも関わらず、なぜこの両方の観念をまとめて考慮せず、102条2項において前者の利益しか考慮しないのかを合理的に説明できないからである。
この点に関し、本判決で知財高裁は「特許法102条2項の侵害者の侵害行為による「利益」の額(限界利益額)は、侵害品の価格に販売等の数量を乗じた売上高から経費を控除して算定されることに照らすと、同項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するものと解される」と述べているが、これにはやや無理があるように思える。
なぜならば、特許権侵害との関係では、その実施行為である譲渡数量についてはそれを特許権者が行い得たといえるが、「侵害品の価格」については、もはや特許権者との関係で、相当因果関係があるとは言い難いからである。もう少し簡単に言うと、侵害品の価格は侵害者の経営判断で決まるものであるため、侵害者が侵害品を販売していた価格と同額で特許権者が競合品を販売したと想定するには根拠に乏しく、さすがに無理があるということである。
つまり、102条2項の規定は、侵害者の利益を、特許権者の売上げの減少による逸失利益に相当することができると考えた規定ではなく、逐条解説の記載からしても、立証の軽減を図るために、侵害者の得た利益を損害額の全体と推定した上で、実際の損害を超える部分については覆滅するという規定のはずである。
また、仮に、知財高裁の言うように102条2項の規定が「売上げの減少による逸失利益」にあたるとしたら、当然、侵害者の得た利益も、売り上げ減少の逸失利益として推定されることになる。そうすると、推定された売り上げ減少の逸失利益の中に、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益も存在し得るということになり、本来であれば、売り上げ減少の逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とは並列的に観念されるにも関わらず、説明のつかない従属関係が生じてしまう。
そして、仮に推定の覆滅事由が存在しなかったとした場合、売り上げ減少による逸失利益=侵害者の得た利益とは別に、なお、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益を検討しなければならなくなる。覆滅事由があくまで「売り上げ減少の逸失利益」に対するものであるならば、覆滅事由が存在しなかったことから、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益が存在しないことを導くことは論理的に困難と言わざるを得ないからである。一方で侵害者の得た利益を損害額と推定しておきながら、これとは別にさらに賠償額を認定することは、102条2項の法の趣旨に反するのではないだろうか。
知財高裁の判断は、立法者の立法趣旨からは離れた独自の見解であり、適当ではないのではないかという疑問が残る。
そこで、二つ目の考え方として、侵害者の得た利益から売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の両方を除いた部分が、推定覆滅部分であるという考え方があげられる。
この考え方であれば、102条2項と3項の重畳適用という法律構成にはならない。あくまで102条2項に基づく損害額の認定において、売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の両方を考慮することになる。
知財高裁の法律構成とは異なるが、個人的には、二つ目の考え方の方が論理的には適切なように思う。推定覆滅部分を検討するに際し、まずは、売上げの減少による逸失利益がどれだけあったかを検討し、今度は残りの利益に基づいて、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益がどれだけになるかを検討し、残った部分が覆滅部分になる。
最終的な覆滅部分は、第1段階として、推定された損害額の全体から、売上げの減少による逸失利益の覆滅として認められる割合を控除し、さらに、控除された部分のうち実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益を損害額と認定するという、この2段階の検討を経て決定されるべきではないだろうか。
特許法102条2項の規定に基づいて損害倍書を請求する場合に、損害額の算出において売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の両方を観念することについては賛成ではあるが、知財高裁の行った法律構成及び102条2項の規定に対する解釈については、合理性が足りず、やや便法に走ったきらいがあるように感じる。
論点3について
本判決で、知財高裁は、102条2項の覆滅部分に102条3項を重畳適用を「当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき」に認めるものと解した。
言い換えれば、特許権者が実施許諾をすることができないと認められる部分については、重畳適用は認めるべきではないと解したことになる。この考え自体は適切であろう。なぜならば、既に述べたように、民法709条の損害賠償は、差額説の考えで損害を認定するのであるから、覆滅部分=侵害行為によって侵害者が得た利益であろうとも、特許権者が実施許諾をすることができない部分については、特許権者が利益を得ることはできないといえるからである。この部分は、たとえ、結果的に侵害者が侵害行為のもとで得た利益として残ったとしても仕方ない。最初に述べたように、民法709条は懲罰賠償を定めた規定ではないのである。
それでは、特許法102条2項の規定に基づく場合にも、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益を観念でき、特許権者が実施許諾をすることができ部分について重畳適用が認められるとしても、知財高裁が判断したように、特許法102条1項と同様の枠組みでこれを考えることは妥当であろうか。
知財高裁は、覆滅事由には「侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解される」とした。
確かに、覆滅事由をそのように分類することは可能であるが、論点2でも述べたように、そのような考え方ができるということと、その考え方を当てはめていいかどうかは、別問題である。
既に述べたように、特許法102条1項は、填補賠償の考えに素直な規定であり、侵害者の行った特許権の実施行為=譲渡行為に目を向けている。つまり、商品を販売したときの利益は、単位利益×販売数量で計算されるところ、侵害行為=譲渡数量だけが侵害者側の事情であり、単位利益は特許権者側の事情(侵害行為がなければ特許権者が販売できた物の利益)で算出される。
そのため、侵害行為がなかった場合に、侵害者による譲渡数量が実際にそっくりそのまま特許権者へと向かい得たであろうかを考慮するため、譲渡数量に関する事情として、特許権者の実施の能力、特許権者が販売できない事情を考慮している。102条1項との関係では、損害額を算出する上で、譲渡数量に目を向けてこれらの事情を考慮することは合理的といえるだろう。
一方で、特許法102条2項は、侵害者の得た利益をベースに損害額が算出される。侵害者の得た利益とは、侵害品の価格に侵害者の侵害行為による譲渡数を乗じた売上高から経費を控除した額であり、全てが侵害者の事情をベースに算出される。
このような102条2項の規定において、譲渡数量に関する事情によって、覆滅事由を分類することが妥当といえるか。個人的な見解は否、つまり、このような分類を当てはめるのは妥当ではないと思う。
102条2項の規定は、立証の軽減という趣旨から、侵害者による譲渡数量×特許権者の競合品の単位利益という細分化を避け、侵害者の得た利益をベースにしている。本来の差額説の考えからは、「侵害品の単価(単位利益)」というのは侵害と損害の間において因果関係のない要素であるが、立証の軽減という趣旨と、利益という視点でみれば利益がそのまま特許権者に移る可能性はあり得る(=相当因果関係を認め得る)という考えから、利益そのものを対象にし、利益と損害との相当因果関係を損害額算出の考えの基礎にしているはずである。
それにも関わらずこれを細分化し、譲渡数量に目を向けた事情で覆滅事由を分類することは、特許法102条2項の規定の本質に反することが懸念されるし、このように細分化してしまうと、「譲渡数量」だけに目が向けることの合理的な説明がつかない。「譲渡数量」に目を向けるならば、「侵害品の単価」にも目を向けないとおかしいはずである。
侵害品の単価は、それ自体で特許権侵害を構成する要素ではなく、また、特許権者の行為によって単価が決められるわけでもない。民法709条の損害賠償を考えるなら、102条1項の「特許権者の競合品の単価」と違い、「侵害品の単価」は直接的な因果関係を有さない。従って、推定された利益を「譲渡数量」×「侵害品の単価」に細分化し、ここから損害額を算定しようとするならば、「侵害品の単価=特許権者の競合品の単価」と直ちに考えることはできず、「侵害品の単価」についても、これをそのまま競合品の単価としていいかに目を向けて覆滅事由を考慮しなければ適切とは言えないだろう。
しかしながら、侵害者の得た利益を、「譲渡数量」と「侵害品の単価」に分けて、それぞれについての覆滅事由を検討することは、議論を著しく複雑にしてしまう。
たとえば別の大合議判決で裁判所が既に示している推定覆滅の事情、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),②市場における競合品の存在,③侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),④侵害品の性能(機能,デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情をみてみる。
市場の非同一性や競合品の存在が、「侵害品の単価」に影響を与える覆滅事由となるのか否かはよくわからない。一方で、ブランド力の高ければ、それは譲渡数量に影響するだけでなく、商品価格にも影響を与えるのが市場原理であろう。また、宣伝広告を多くすれば商品価格は高くなると考えることもできるだろう。宣伝にお金をかけると、この支出を回収できるように売価も設定される。侵害品が、特許発明の他に購買動機に繋がるような性能やデザインを有していれば、当然「侵害品の価格」には、これらの価値も上乗せされているだろう。
このように、利益を譲渡数量×単価に細分化してしまうと、それぞれに分けて覆滅の程度を判断することが困難な覆滅事由がある。譲渡数量にも価格にも影響を与えており、これらの相関を切り離して論ずることができない以上は、やはり「利益」という対象に対して覆滅を検討すべきであろう。
従って、知財高裁が、102条2項の推定の覆滅事由を同条1項と同様にして解そうとしたことは、102条2項の規定の趣旨からすると不適切ではないかと考える。
それでは、102条2項において、侵害者の利益から売り上げ減少による逸失利益を除いた利益に対し、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益をどのように考えるべきであろうか。
非常に難しい問題だが、まずこの問題を本質的に捉えるなら、覆滅された利益は直接特許権者が売上げることのできない利益であるから、このような利益のうちどれだけが侵害品が特許発明であることと相当因果関係を有する利益であり、どれだけが侵害品が特許発明であることと相当因果関係を有さない利益であるかによって、峻別されるべきであろう。
そうすると、「利益」を基準に考えるならば、一案として「覆滅された利益のうち、特許発明の実施と何ら関係を有さずに侵害者が得られた利益を除いた利益が、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の対象となる」と解するのが良いのではないかと考える。
そして、覆滅された利益をどのように峻別するかについては、売上げ減少の逸失利益に対する覆滅事由がさらに、利益と特許発明の実施との間に相当因果関係を有さない侵害者に固有の事情に基づくものか否かで実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益の対象となるかを判断するという基準が考えられる。(ここで留意していただきたいのは、利益と損害の相当因果関係ではなく、利益と行為(特許発明の実施)との相当因果関係であるという違いである。)
この基準に従えば、例えば本件のように、特許権者が販売していなかった国へ侵害品を譲渡したという市場の非同一性に基づく利益の覆滅は、侵害者に固有の事情ではなく、特許権者側に販路がなかったという特許権者固有の事情に基づくものであるため、なお特許発明の実施との間に相当因果関係を有しているだろう。
競合品の存在に基づく利益の覆滅も、あくまで特許権者と他の競合との関係による覆滅であり、特許権者と侵害者の間の関係には触れていないのであるから、特許発明の実施との間の相当因果関係は維持されているといえる。
一方で、ブランド力や宣伝広告に基づく利益の覆滅は、特許発明の力ではなく、侵害者に固有の力(侵害者のブランド力や、侵害者が対価を払って行った宣伝広告活動)によって得られた利益であるから、特許発明の実施との間に相当因果関係を有さないといえる。
また、侵害品の性能に基づく利益の覆滅は、特許発明を実施したからではなくそれ以外の機能やデザインを有していたことが侵害品の購買動機となったといえることによる覆滅であるから、裏を返せば、特許権者が特許発明の実施品を販売しても売れなかったと考えることができ、特許発明の実施との間に相当因果関係を有さないといえる。
このように、上記の基準を採用したとしても、覆滅事由が利益と特許発明の実施との間に相当因果関係を有さない侵害者に固有の事情に基づくものか否かを判断することはできそうである。
それでは、仮にこの基準に基づいたとき、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること、はどのように判断すべきであるか。
これは、一見すると、侵害品の性能に基づく覆滅の検討のようにも見えるが、侵害品の性能は、特許発明とは別の性能を対象にしているのに対し、純粋に「特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること」だけを考えるというのは、侵害品が他にどんな特徴的な性能を有しているかは関係なく、侵害品における特許発明の寄与の程度(特許発明によって購買動機が生まれたといえる程度)をみているため、正確には異なる議論である。
従って、侵害品の性能と切り離してこの覆滅事由を議論する場合、侵害品の特徴的な性能は無視し、侵害品と同類の製品であって、この製品が通常有する機能を基準にし、これに対して特許発明が需要者の購買動機に影響するか否かを検討すべきであると考える。
また、この検討には、需要者が誰であるかを考えることが重要であり、また、他の競合品が存在していたか否かによっても左右されるものではないかと考えられる。
需要者にとっての購買動機であるから、侵害品が譲渡される対象が一般消費者であるか、完成品を製造するメーカーであるかによって購入動機に違いは生じるだろう。例えば、特許発明が、侵害品が譲渡される需要者うちの些細な一部の部品の発明であり、この発明の効果が、生産効率が上がるとか、安全性が上がるといったメーカー側の利益である場合、一般消費者の購買動機にはならないが、メーカーの購買動機にはなるといえる。一方で、一般消費者に触れる機能の改善であれば、一般消費者及びメーカー両方の購買動機になるだろう。
また、市場に他の競合品が存在している場合、通常の機能を有する同類製品と比較するのであるから、特許発明が一般消費者に触れる機能に係るものであれば、侵害者の利益が競合品が存在している上で得たものである以上、特許発明が購買動機となっているといえ利益の覆滅は認められないだろう。
一方で、他に競合品が存在していないのであれば、一般消費者は、特許発明に係る機能が欲しいから侵害品を購入したのか、通常の機能を有していればいいけど他に選択肢がないから侵害品を購入したのかを検討すべきであろう。この場合には、特許発明に係る機能に基づく購買動機と通常有している他の機能に基づく購買動機の比率、及び、特許発明に係る機能における特許発明の貢献度から、覆滅の程度を検討するのが適当ではないかと考える。
なお、この検討において「他の競合品の存在」を考慮することと、これとは別に「他の競合品の存在」に基づく覆滅が考慮されることが、二重の評価にならないかという点についてフォローをしておくと、仮に、本件等において、他の競合品の存在が、覆滅の具体的な程度を決定する考慮要素とされた場合には二重の評価となるであろうが、具体的な覆滅の程度ではなく、その前提問題として考慮される場合には、「他の競合品の存在」に基づく覆滅を検討しているわけではないため、許されると解するのが相当と考える。
本件で、他の競合品が存在しており、特許発明の「施療者が起立及び着座を快適に行うことができる」という効果は、需要者たる一般消費者の購買動機となる機能/性能であるといえるため、実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益という観点からは、利益と特許発明の実施との間に相当因果関係を有しているといえ、認めるべきではなかっただろうか。
その他
知財高裁の判断の懸念1
本判決で、知財高裁は「特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること」による覆滅を102条2項の場合と3項の場合とで、それぞれ以下のように述べた。
102条2項の覆滅(売り上げ減少による逸失利益の覆滅)
「以上を総合すると、本件各発明Cの技術的意義は高いとはいえず、被告製品1の購買動機の形成に対する本件各発明Cの寄与は限定的であるというべきであるから、被控訴人が被告製品1の輸出により得た限界利益額(前記イ)には、本件各発明Cが寄与していない部分を含むものと認められる。したがって、本件各発明Cが被告製品1の部分のみに実施されていることは、本件推定の覆滅事由に該当するものと認められる。」
102条3項の覆滅(実施許諾の機会喪失による得べかりし利益の覆滅)
「一方で、本件各発明Cが侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品1に対し本件各発明Cが寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Cが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものと認められない。」
このように「特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること」を「被告製品の限界利益額」の覆滅に当てはめているのは、102条1項に基づく損害額について争った平成31年(ネ)第10003号(令和2年2月26日判決)の大合議判決が、「特許発明が特許権者の製品の一部分のみに実施されていること」を特許法102条1項所定の「単位数量当たりの利益の額」の問題として扱ったことに対応している。
しかしながら、改正後の102条1項はその一号で、売り上げ減少の逸失利益を
(特許権者の競合品の限界利益-限界利益額の覆滅)×(実施能力範囲での譲渡数量―販売できない事情の数量)
として算出した上で、さらに二号で、実施許諾の機会喪失による得べかりし利益を
(侵害者の侵害品の限界利益)×(実施能力を超える数量+販売できない事情の数量-実施許諾したといえない事情の数量)×実施料率
として算出するように規定されている。
平成31年(ネ)第10003号(令和2年2月26日判決)は特許法102条1項の令和2年改正前の規定を基にしているが、平成31年(ネ)第10003号の大合議判決は、二号の利益(実施許諾の機会喪失による得べかりし利益)の算出において、一号で考慮された限界利益額の覆滅事由を組み入れていない。一方で、本判決はこれを「実施許諾したといえない事情の数量」として捉えた。
特許法102条1項において、売り上げ減少の逸失利益は、「特許権者の競合品の単価」で算出され、実施許諾の機会喪失による得べかりし利益は、「侵害品の単価」で算出される。このように、そもそもの利益の考え方が異なっているのであるから、「特許権者の競合品の単価」に対して覆滅された部分を、そのまま「侵害品の単価」に踏襲することは適当ではないだろう。(例えば、3,000円の競合品の単価の5割が覆滅されたとして、侵害品の単価が1,000円だったとしたら、5割の覆滅分である1,500円を踏襲してしまうと、-500円になってしまうが、実際には、1,000円の単価に対する覆滅はこれとは別個に考えるべきであり、競合品と同様に5割になるとも限らないが、少なくとも、1,000に対する割合で覆滅されるのであるから、1,500円を基準にして算出された利益をそのまま踏襲するというのは合理性に欠けるように思う。)
知財高裁の判断の懸念2
知財高裁が102条2項の推定の覆滅事由を「特許法102条2項による推定の覆滅事由には、同条1項と同様に、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由」に分類して捉えたことに対しては、部品メーカーが完成品メーカーに対して損害賠償を請求した場合に懸念がある。
なぜなら、一般的に部品メーカーには完成品を実施する能力はないため、このような分類をしてしまうと、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由が常に利益の100%となってしまう。
そうすると、部品メーカーは、102条2項の適用を請求しても、推定される利益の100%が覆滅され、実質的に、特許法102条3項のみでしか損害賠償を請求できないという事態になってしまう。
しかしながら、部品メーカーは、侵害者の侵害行為がなかった場合には、例えば、侵害者以外の者が、適法に部品メーカーから部品を購入して完成品を譲渡できたと考えられる以上、侵害と利益の間の相当因果関係は認められるべきであろう。また、侵害者が特許権者から部品を購入していれば侵害品ではなくなるし、このときの部品の売上げは、侵害者から実施料を得るよりも(特許法102条3項の損害額よりも)多くなるかもしれない。
このような懸念からしても、特許法102条2項の規定はやはり、利益という単位を細分化せず、覆滅事由となる事情の利益への影響度合いを総合的に考量するのが、実質的な救済を図る上で重要ではないだろうか。

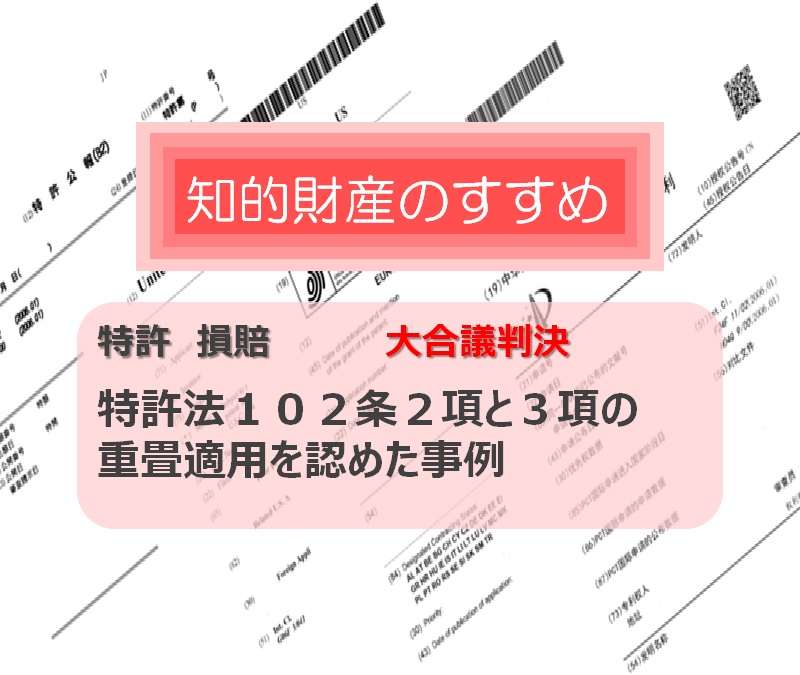
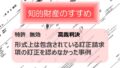
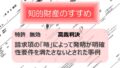
コメント