手続違背:審決で元の主引例に並記して新たな主引例を加えたことが手続違背とされた事例
令和4年11月16日(2022/11/16)判決言渡
#特許 #手続き保障
1.実務への活かし
・~権利化まで #意見書 #審判請求書 #手続き保障
手続き保障(防御の機会の保障)は、無駄な費用をかけずに権利化を進める上で(意見書の提出機会をなるべく確保し、審判や審取まで持ち込まずに審理を確定させる上で)、クライアントの利益にとって非常に重要である。
出願人は、審査または審判において、新たな引用文献に基づき主引用発明が認定されておきながら、拒絶理由が通知されず、意見を述べる機会も与えられずに査定または審決を受けることのないように、意見書または審判請求書において、特許庁に対し、事前に釘を刺しておくべきである。(参考までに、個人的に推奨する定型文を下記に載せている。)
∵本件では、特許庁が、拒絶理由を通知せずに拒絶審決をしたことについて、手続違背があったことが知財高裁により認められた。しかし、事前に釘を刺しておくことで、拒絶理由を通知してもらえたのであれば、訴訟費用をかけずに、同じ結果を得ることができたのである。
<定型挿入文の参考例>
「審査官殿/審判長殿におきましては、拒絶理由及び独立特許要件のいずれの判断であっても、これまで述べられてきました拒絶理由の論理構成とは異なる論理構成で判断を示す場合(例えば、新たな引用文献に基づいて主引用発明を認定し判断を示す場合等)には、たとえ既に挙げられている拒絶理由(あるいは独立特許要件違反)の判断と並記するものであったとしても、出願人に実質的な防御の機会が保障されるよう意見を提出する機会を与えなければならず、これに反しますと手続違背となる点について、ご留意頂きたく存じます。(令和3年(行ケ)第10164号参考)」
2.概要
本件は、進歩性欠如(及び、これに基づく独立特許要件違反)による拒絶審決の取消し、及び、審決の手続違背に基づく拒絶審決の取消しを求める訴訟である。
つまり、前者は、実体的な審理判断の是非に関して審決の取消しを求めており、後者は、手続的な側面から不当な審理の取消しを求めている(所謂、手続き保障というやつである)。
出願人であるユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社(以下、UPT社という。)は、発明の名称を「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置」とする特許出願(特願2018-554604号、以下、本願という。)をした。
特許庁は本願を審査し、2回の拒絶理由通知を経て、特許法29条2項の拒絶理由に基づく拒絶査定をした。なお、1回目の拒絶理由通知から拒絶査定までの間、請求項1は補正されていない。
拒絶査定では、請求項1について、引用文献1(国際公開第2016/159316号)を主引例とし、さらに引用文献2(特開2016-142644号)を用いて、進歩性を否定した。
UPT社は特許庁の拒絶査定に対し不服審判を請求した。ここでUPT社は、審判請求と同時に手続補正を行い、請求項1を補正した。補正後の請求項1は、以下の通りである(下線部が補正)。
【請求項1】
銅に対する銀の添加量が0.2wt%~15wt%であり、0.1[mm]~0.3[mm]の変位量の場合に荷重が4[gf]以下である、銅と銀のみからなる二元銅銀合金体からなるコンタクトピン。
その後、合議体は、拒絶理由通知を発することなく、審理終結通知書を送付し、拒絶審決をした。審決では、上記の補正を限定的減縮(特17条の2第5項第2号)と判断した上で、独立特許要件(特29条2項を満たすか否か)の判断を行った。
その結果、この補正は独立特許要件(29条2項の進歩性)を満たさないとして却下され、そして、補正前の請求項についても29条2項を満たさないとして、拒絶審決がなされた。
このとき、審判長は、補正が却下された請求項(補正前の請求項)に対する特29条2項の判断については、拒絶査定において挙げられていた引用文献1及び引用文献2を用いている。
一方で、独立特許要件における特29条2項の判断については、これらの引用文献に加え、これまでの審査で挙げられていなかった引用文献5乃至引用文献8を用いており、さらに、引用文献1に開示される引用発明1を主引用発明とした判断だけでなく、引用文献5に開示される引用発明5を主引用発明とした判断も行った。
本件訴訟では、上記の審決に対し、①引用発明1との相違点の看過、②進歩性判断の誤り(阻害要因)、③手続違背、④引用発明5の認定誤り、が争われ、裁判所は、②の阻害要因(下記、取消事由2)と③の手続違背(下記、取消事由4)について、UPT社の主張を認めた。
知財高裁の判断(判決から抜粋。下線等は付記)
「4 取消事由2(相違点1の判断の誤り)について
(1) 引用発明1を含む甲8に記載された発明は、特に、「被膜を有しないSn耐食性に優れた合金材料、この合金材料からなるコンタクトプローブおよび接続端子を提供することを目的とする」ものである(甲8の段落[0006])ところ、銀の添加については「Sn耐食性」の向上については触れられていない(同[0018])一方で、ニッケルの添加は「Sn耐食性の向上・硬度上昇に効果がある」ことが明記されている(同[0019])。
そして、実施例においても、硬度等とともに「Sn耐食性」が独立の項目として評価され(同[0036])、甲8に係る発明の実施例には全てニッケルが添加され、いずれも「Sn耐食性」において「○」と評価されている(…)。
この点、比較例7のみにおいては、ニッケルの添加がされていないが、「Sn耐食性」において「×」と評価され、かつ、「Snはんだ等低硬度材向けのコンタクトプローブ用途として好ましくないといえる」と明記されている(同[0046]及び[表1])。
以上の点に照らすと、引用発明1においては、ニッケルの添加が課題解決のための必須の構成とされているというべきであり、引用発明1の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることには、阻害要因があるというべきである。
…
6 取消事由4(手続の違背)について
(1) 前記4の認定判断によると、引用発明1を主引用例とする本願補正発明の進歩性についての本件審決の判断には誤りがあるというべきであるところ、…本件審決は、引用発明5を追加の主引用例として、本願補正発明が進歩性を欠く旨を判断したとみるのが相当である。
…
したがって、前記4のとおり、引用発明1を主引用例とする本願補正発明の進歩性についての本件審決の判断に誤りがある以上、引用発明5を主引用例として本願補正発明が進歩性を欠くものであるとの本件審決の上記判断に関する取消事由4について検討する必要があることになる。
(2) 特許法50条本文や同法17条の2第1項1号又は3号による出願人の防御の機会の保障の趣旨は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも及ぶものと解される(同法159条2項)。
また、同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)において、…補正独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ、同法50条ただし書(同法159条2項により読み替えて準用される場合を含む。)において、上記により補正の却下の決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、平成5年法律第26号による特許法の改正によるものであるところ、同改正の際には、審判請求時にされた補正の判断に当たって審査段階における先行技術調査の結果を利用することが想定されていたものとみられるとともに、同改正の趣旨は、再度拒絶理由が通知されて審理が繰り返し行われることを回避する点にあったものと解される。
以上の点に加え、新たな引用文献に基づいて独立特許要件違反が判断される場合、当該引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正については当該引用文献を示されて初めて検討が可能になる場合が少なくないとみられること等も考慮すると、特許法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、拒絶理由通知をしないことが手続違背の違法と認められる場合もあり得るというべきである。
…
しかるに、前記2(1)及び(2)のほか、本願発明と引用発明1の対比によると、本願補正発明と引用発明5との相違点である相違点3は、本願補正発明と引用発明1の相違点2及び本願発明と引用発明1の相違点4と実質的に全く同一のものであると認められる…一方、本願補正発明と引用発明1との相違点1は、本願補正発明と引用発明5の相違点としては認められないものである。それゆえ、拒絶理由通知をもって甲16(引用文献5)を示されていた場合には、原告においては、審査段階や審判段階において、引用発明5の認定並びに本願補正発明と引用発明5の一致点及び相違点について争ったり、相違点2及び相違点3をより重視した反論をしたり、あるいは相違点3に係る本願発明の構成に関して補正することを検討するなどしていた可能性もあるものとみられ、原告の方針には重大な影響が生じていたものというべきである。 (4) 前記(2)を前提として、前記(3)の諸事情を踏まえた場合、相違点3と同一の相違点2については審査段階で原告に反論の機会が与えられていたこと等を考慮しても、なお、引用発明5を主引用例として本願補正発明の進歩性を判断することは、原告の手続保障の観点から許されないというべきである。」
3.本件のより詳細な説明、及び、判決内容の考察
3-1.判決についての感想
全体的な結果について:納得度70%
本件の手続違背についての結論に異論はない。ただ、審決において特許庁が下した判断も、行政庁として明らかに誤っていたとは言い切れないところがある。
また一方で、結論に異論はないが、知財高裁の示した判断の仕方については懸念がある。以下では、この点について述べておく。
なお、「実務への活かし」にも書いたが、「手続き保障」の問題は事前に対処しておかなければ意味がない。つまり、審査段階における審査官宛に、あるいは、審判段階における審判長宛に、「きちんと手続き保障をしてくださいね!」と釘を刺しておかないと、査定や審決が来てから「手続き保障」について争っている時点で、必要なかったはずの費用が発生していることになる。好ましくは、意見書や審判請求書の最後の方に、釘を刺すための定型文を記載しておくのがいいだろう。(この投稿の最後の方に、参考までに定型文を載せてある。)
3-2.本件特許について
本件特許は、「コンタクトピン」に係る発明である。コンタクトピンとは、検査装置などで、検査対象に接するために用いられるもので、コンタクトピンに接触させて検査対象の特性を検査するといった方法で使用される。(下図をイメージ)

本件特許明細書において先行技術文献に挙げられたコンタクトピンは、銅合金材料を金めっきして製造されているが、導電率、強度の点で、必ずしも最適材料であるとはいえないため、本件特許はこれとは異なる材料および加工方法によってコンタクトピンを製造することを「課題」としている。
そして具体的に、本件特許の発明は、「銅及び銀を含む銅銀合金」を材料に用いることが特徴となっている。以下に改めて、請求項1(審判請求時に補正した請求項1)を記す。
【請求項1】
銅に対する銀の添加量が0.2wt%~15wt%であり、0.1[mm]~0.3[mm]の変位量の場合に荷重が4[gf]以下である、銅と銀のみからなる二元銅銀合金体からなるコンタクトピン。
3-3.手続違背について
問題の所在
特許法第159条第2項は、「第50条の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する」とされ、特許法第50条は、拒絶理由を通知し、出願人に意見書の提出機会を保障するが、第53条第1項による補正の却下がされた場合はこの限りでないと定める。
特許法第49条には拒絶理由が列挙されているが、これらの拒絶理由の中に、独立特許要件違反はない。独立特許要件はあくまで、特許法第17条の2の手続補正についての定めであり、同条第5項第2号の限定的減縮補正をした場合に、その補正の適法性(あるいは有効性)を判断するための規定である。
そうすると、独立特許要件は、直接的には「拒絶の理由」に該当しないため、独立特許要件の判断の中で、新たな主引例を用いることが、特許法第159条第2項の「異なる拒絶の理由」に該当することを直接的に導くことはできない。
なお、これが補正を却下するか否かの独立特許要件の判断ではなく、進歩性の判断だとしたら、新たな主引例を用いることは「異なる拒絶の理由」に該当するといえるだろう(この点は、これまでの判例実務からすると、既に定着している考えだと思われる)。
つまり、補正を却下すべきか否かの判断において新たな主引例を用い、その結果補正が却下され、補正前の請求項に対しては新たな主引例を用いずに従前の引用文献のみで拒絶理由を維持し、これにより拒絶審決の判断を下すという、今回の特許庁の処分は、条文をそのまま読めば直ちに法令違反になるとはいえないわけである。
しかしながら、そうはいっても、独立特許要件は、限定的減縮を目的とする補正後の請求項が独立して特許を受けることができるものであることを要求しており、特許を受けることができるか否かというのは、言い換えれば「拒絶の理由があるか否か」を判断していることと実質的に等しいわけである。
そうすると、独立特許要件の中で判断される「拒絶の理由があるか否か」において、新たな主引例を用いることは、従前とは「異なる拒絶の理由」を持ち出して、拒絶の理由があるか否かを判断しているに等しいと言うこともできるだろう。
ここに、本件の問題の所在がある。
手続き保障
上記の問題について、知財高裁は、これらの特許法の規定の趣旨に翻った。
特許法が、第53条において補正却下の規定を置き、第50条ただし書において、補正却下の場合に拒絶理由通知を要しないとしたのは、「審理が繰り返し行われることの回避」にある。
たとえば、最初の拒絶理由通知を受けて請求項を補正し、拒絶理由で挙げた引例に開示されていない事項が追加された場合、当該事項が開示される新たな副引例を発見して拒絶理由が維持されるときは、最後の拒絶理由を通知しなければならない。
このように審査官によって挙げられた引例に開示されていないことを補正で盛り込むだけで拒絶理由は引き続き通知されるわけだが、これが最後の拒絶理由通知を受けて行った補正に対しても同様に、あるいは、審判請求と同時に行った補正に対しても同様に適用されるとなると、現時点で挙げられている引用文献に開示されていない事項を小出しにしていくことで、延々と審査が繰り返されることになる。
特に、限定的減縮を目的とする補正では、新たな構成要件が追加されるわけではなく、あくまで、それまでの請求項に記載されていた発明特定事項の限定に制限されるのであり、その中でこのような審査のループが起こってしまっては、公正・迅速な審査の弊害となることは明らかであろう。
だが、このような考えに基づくなら、ここでいう「審理の繰り返し」は、従前の拒絶理由における論理構成が維持されていることが前提というべきである。つまり、第53条及び第50条ただし書は、出願人に(小出しではなく)一回的な拒絶理由の解消を要求しているわけだが、出願人へのこのような要求(負担)が正当化されるのは、あくまで「審理の繰り返し」が、公正・迅速な審査との関係で過度な手続き保障になっているからであり、従前の論理構成と異なる論理を用いるのであれば、本来的に出願に保障されるべき機会まで奪うことになりかねない。
出願人への防御の機会の保障は極めて重要な法益であり、公正・迅速な審査も大事ではあるが、それは防御の機会の保障がされていることを前提に追求すべき法益であることに異論はないだろう。簡単に言えば、手続き保障は、公正・迅速な審査の実現に優先する法益なのである。
この点は、知財高裁が「特許法50条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、拒絶理由通知をしないことが手続違背の違法と認められる場合もあり得るというべきである」と述べていることからも明らかである。
手続き保障がされているか否かの具体的判断
本件を分析する上で重要なのは、知財高裁が「出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるか否か」という判断基準を示したことである。
知財高裁は、単純に新たな主引例を用いたというだけで出願人への防御の機会が実質的に保障されていないと認めたわけではない。
知財高裁は「実質的に」と述べたことに対応して、従前の引用文献と本件特許との間にあった「相違点」と、新たに引用した文献と本件特許との間にある「相違点」を比較し、また、これまでの審査及び審判の経過の中で出願人が行った対応(違憲の内容)も踏まえて、出願人の意見の機会が奪われていないかを判断している。
具体的に、補正後の請求項1と従前の主引例との間の相違点は、以下の2点である
(相違点1)
「銅と銀のみからなる二元銅銀合金体である」点
(相違点2)
「0.1[mm]~0.3[mm]の変位量の場合に荷重が4[gf]以下である」点
また、補正後の請求項1と新たな主引例との間の相違点は、以下の点である。
(相違点3)
「0.1[mm]~0.3[mm]の変位量の場合に荷重が4[gf]以下である」点
このように、相違点3(新たな主引例との相違点)は、相違点2(従前の主引例との相違点)と同じである。これだけを見れば、既にこれまでの審査の中で、出願人は相違点2について意見を述べる機会があったのだから、実質的な防御の機会は保障されていたとも思える。
しかしながら、UPT社は、従前の主引例が相違点1に相当する技術の採用に阻害要因を有していると考えられたため、審判請求時の補正で、相違点1の部分を追加し、そこに議論を集中させたのであり、この点について知財高裁は「拒絶理由通知をもって甲16(引用文献5)が示されていた場合には、相違点3をより重視した反論をしたり、あるいは相違点3に係る本願発明の構成に関して補正することを検討するなどしていた可能性もあるものとみられ、原告の方針には重大な影響が生じていたものというべきである」と判断した。
端的に言えば、実質的な意味で、これまでの経過の中で相違点2(=相違点3)についての防御の機会は十分に保障されていなかったと判断したのである。
実務上の懸念
知財高裁が行った「実質的な」観点からの判断は合理的であったと思う。しかしながら、「実質的に保障されているか否か」の判断は、上述したように、具体的かつその事案ごとに審査経過を詳細に分析する必要があり、容易には判断し難いところがある。
それ故に、このような判断基準では、防御の機会を適切に保障すべき特許庁の側においても、その是非をすんなり判断することができず、本件のような事例に対し、実効的な抑止とならないのではないかが懸念される。
行政は、基本的には法令を遵守し、裁判所のように柔軟に法律を解釈して対応することには消極的である。行政は司法ではないから、そのこと自体は当然と言えば当然だろう。本件も、独立特許要件の判断において「異なる拒絶の理由」で判断してはならないという条文はなく、特許庁からすれば、特許法の条文通りに対応しただけである。
このような行政の立場からすれば「結局、裁判所の判断を仰がないと実質的な防御の機会が保証されたか否かは判断できないのであり、そうなると拒絶審決を出す他ない」という対応に傾いてしまうかもしれないことが懸念される。
しかし、審決取消訴訟を起こさない限り「手続違背」が認められないというのであれば、それこそ実質的な意味で手続き保障(防御の機会の保障)が成されているとは言えないだろう。出願人側としては、訴訟などせずに、審査/審判の段階で、適切な防御の機会の保障を受けたいわけで、手続き保障は行政に対する警鐘なのであるから、知財高裁が、本件のような裁判所ライクな判断基準を示したことは、これで手続き保障という問題の実効的な解決を図れるのかという点において、やや問題があったようにも思う。
そもそも審理の論点に変わりがないのであれば新たな主引例を持ち出す必要はなく、裏を返せば、新たな主引例を持ち出すという行為自体が、従前の論理構成を維持したままでは結論を維持できず、異なる論理構成によって同じ結論を維持しようとする行為なのであるから、「実質的な」判断などしなくても、一般的には、新たな論点が発生する蓋然性が高いといえるだろう。
また、少なくとも、意見の機会を与えられつつ新たな主引例が示されていたならば、従前の引例に対する意見とは別の意見(反論)や補正を検討していた可能性は十分に考えられる。
そうすると、新たな主引例を用いるのであれば、それが拒絶理由の判断であろうと、独立特許要件の判断であろうと、一律に出願人側に防御の機会を保障すべき(拒絶理由を通知すべき)というのが、真の意味での手続き保障といえ、知財高裁はそのように判断すべきではなかっただろうか。
実務において
何度も言うように、手続き保障(防御の機会の保障)は、裁判で争っている時点で無駄な費用が発生しており、そこまで来てしまっている時点で実質的には負けなのである。なぜなら、手続き保障は、審理の判断結果に誤りがあるのではなく、あくまで審理の進め方に間違いがあったことを示すに過ぎないからである。
本件をみても、知財高裁は、審決を取り消した後に審理が再開されることを踏まえ「相違点2(=新たな主引例との相違点3)について、以下のように判断を述べている。
相違点2についての知財高裁の判断(判決より抜粋、下線は付記)
「5 取消事由3(相違点2の判断の誤り)について
(1) 前記4の認定判断によると、取消事由3について判断するまでもなく、…本件審決の判断には誤りがあるというべきであるが、特許庁において更なる審理判断がされることを考慮して、取消事由3についても判断する。
(2) 本願明細書の段落[0055]の記載等に照らすと、相違点2に係る本願補正発明の構成は、ある変位量に対してコンタクトピンとして要請される荷重となることのみを特定するものといえるところ、コンタクトピンにおいて、どの程度の荷重をかけたときに、どの程度変位するようにするかは、試験装置のサイズや試験対象の特性等から生じる制約に応じて適宜設定されるべき事項にすぎないというべきである。このことは、甲9(引用文献2)の段落【0064】の記載や甲18(引用文献7)の段落【0080】の記載からも裏付けられているといえる。この点、本件審決における甲9及び18に基づく技術常識Bの認定及び甲19に基づく技術常識Cの認定について、誤りがあるとも認められない。
したがって、相違点2に係る本願補正発明の構成は、当業者において容易に想到し得たものである。」
このように、補正後の請求項が、新たな主引例に基づき進歩性を具備しないという結論自体に誤りがないことについては、知財高裁のお墨付きがされてしまっているのである。そして本件は、2023年1月10日に拒絶理由通知がされ、この新たな主引例に基づき進歩性が否定されている。知財高裁のお墨付きがある以上、最早、相違点2についての容易想到性を争うという選択肢は残されていないだろう。
従って、手続違背については、訴訟でこれを争えばいいという考えではなく、「手続違背とならないようにしてください」ということを伝え、特許庁に予め釘を刺しておくことで、訴訟まで持ち込まずに適切な機会の保障を受けるにはどうすべきかを考えるべきである。そのためには、以下のような文章を、拒絶理由通知に対する意見書や拒絶査定不服審判の請求書の末尾に記述しておくのが良いだろう。
<定型挿入文の参考例>
「審査官殿/審判長殿におきましては、拒絶理由及び独立特許要件のいずれの判断であっても、これまで述べられてきました拒絶理由の論理構成とは異なる論理構成で判断を示す場合(例えば、新たな引用文献に基づいて主引用発明を認定し判断を示す場合等)には、たとえ既に挙げられている拒絶理由(あるいは独立特許要件違反)の判断と並記するものであったとしても、出願人に実質的な防御の機会が保障されるよう意見を提出する機会を与えなければならず、これに反しますと手続違背となる点について、ご留意頂きたく存じます。(令和3年(行ケ)第10164号参考)」
このように述べておけば、審査官/審判長の側も、安易に査定や審決を出せなくなり、一定の抑止効果が得られるはずである(あくまで参考なので、絶対の保証ではないが、何も書かないよりは良いはずである)。
なお、本件は、進歩性および独立特許要件において新たな主引例が用いられた事例であったが、「防御の機会の保障」という本質に立ち返れば、必ずしも本件の事例に限らなくてよく、重要なのは「審査官によってそれまで述べられていた拒絶理由の論理構成」とは本質的に異なっており、その異なる論理構成が出願人において予期できるもの、あるいは、反論しておくべきものであったと言えるかどうかであると思う。上記の参考文は、そのことも踏まえた文章にしている。
仮に、審査官/審判長が意見の機会を与えずに査定/審決を強行し、それが審判/審取訴訟の場で誤りと認定された場合には、審査官/審判長の行った審査/審判には、単に手続違背の違法があったというだけに留まらず、そのような手続違背を行ったことについての「故意又は過失」が認められる可能性が高くなる。
そうすると、審査官/審判長は、国家賠償法1条の賠償責任を負う(実際は審査官/審判官個人ではなく行政庁たる特許庁が負う)可能性も十分にあることになり、そのようなリスクを負ってまで、査定/審決を強行する理由はなくなるだろう。
審査/審理を早く終わらせたいという思いを別にすれば、意見の機会を与えたところで特許庁としての実害はないのであり、予め釘を刺しておくことには、このような観点からの抑止力も期待できるはずである。

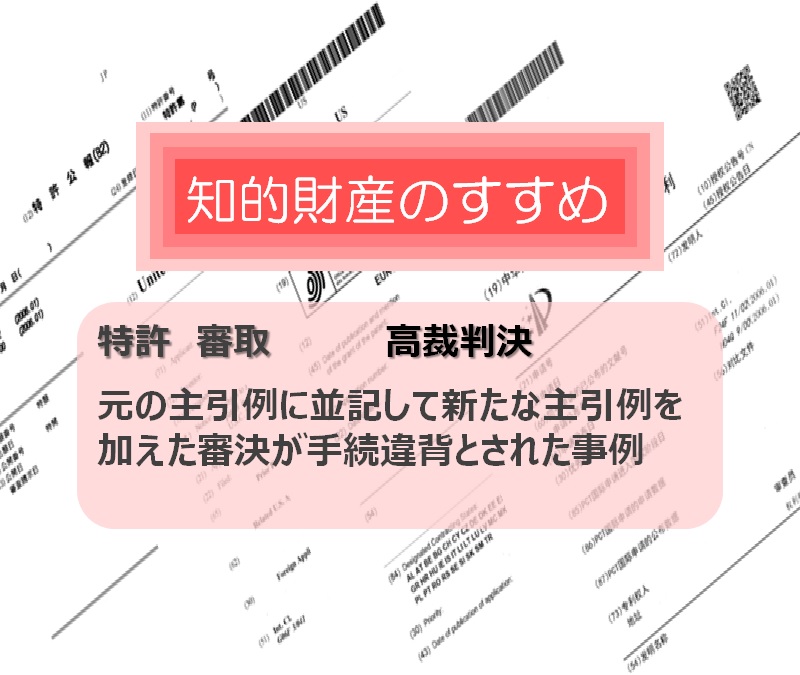
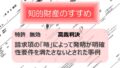
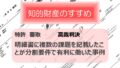
コメント