2025年は、判例記事の有料会員様向けに「充足論」シリーズを配信する。
そこでまず、なぜ充足論かという点について話したい。
充足論をテーマにする理由は大きく三つ挙げられる。
一つ目は「権利活用を見据えたとき充足論対策は非常に重要であること」
二つ目は「充足論対策に長けている実務家は非常に少ないこと」
三つ目は「充足論対策の分析には無効論対策よりも困難な面があること」
これらについて説明していく。
1.権利活用を見据えたとき充足論対策は非常に重要であること
ほとんどの特許出願が、権利化に至った(特許査定を得た)としても権利活用の武器には用いられない。事業の核となる特許、強力な競争優位を生み出すような特許はそう簡単には生まれない。そのことは、年間10万件単位の特許出願がされているのに対し、特許権侵害訴訟の件数が100件に満たないことからもわかる。
しかし、特許権の効力は、発明実施の専有(独占排他)にあり、飾りとして特許権を持つことは本来的には意味がない。特許表示やステークホルダーへのアピールなど、何とか意味を持たせようとする活動はあるが、これらは特許権の本懐とはいえないだろう。
理想的には、「特許権の存在によって誰も事業に参入することができず、参入しようとすれば特許権によってその行為は差し止められてしまう」という状況を創り上げる特許権でありたい。それ以外の特許の活用方法は、それができないがゆえの二次的活用に過ぎないのである。
険しい道のりであり、1%に満たない確率を掴み取るものではあるが、それでも我々が目指すべきは、理想的な特許の活用であるだろう。
そしてその機会がきたとき(特許権を権利行使するとき)には、ほぼ100%の確率で「充足論」と「無効論」が立ちふさがる。当然、特許の有効性を維持すること(無効論の争いに勝つこと)も求められるが、無効審判請求事件ではなく特許権侵害訴訟事件において特に注意しなければならないのが充足論なのである。このことは、次の統計データからわかる。
裁判所ホームページの裁判例検索で調べたところ、2024年1月1日から同年12月31日までに判決があった特許権侵害訴訟は地裁高裁含め56件あり、特許権者の勝訴(請求認容)判決はそのうち14件であった。
勝率でいうと25%ということになるが、75%にあたる42件は特許権者の敗訴(請求棄却)ということになる。それでは、この42件の敗訴のうち何件が「充足論」で負けたのか(非充足と判断されたのか)。その数は実に35件にのぼる。割合でいうと85%弱、5件中4件以上が充足論によって負けているのである。
当然、裁判は判決以外の方法によっても終わる。取り下げや和解で終わった事件については判決が下されないため、この集計には上がってこない。このような事件は、被告側がほとんど対抗できないと白旗をあげるケースもあれば、時間や労力を惜しんで和解に舵を切るケースなど、様々な事情から決定されるものである。
しかし、取り下げや和解で終わる場合、少なくとも被告に対し「骨の折れる特許だ」という第一印象は与えていることが多いだろう。一方で、裁判所の判決までもつれるような事件は、被告側もそれなりの確度で「非侵害を争える」と考えているのである。
そしてこの統計が示すのは、被告側は「充足論で十分に争える」と考えるときに裁判所の判断を求める(判決まで踏み切る)傾向にあり、2024年度の集計では全体の60%強で被告側の主張が認められているということになろう。
35件/42件中という数字が物語っているように、充足論対策が、特許権行使の勝率を上げる重要な要素であり、その対策が十分に発展していない領域といえるだろう。
2.充足論対策に長けている実務家は少ないこと
これは私を含めての話でもあるが、特許事務所、企業知財、および弁理士のいずれにおいても、充足論対策に長けた実務家は非常に少ないだろう。その理由の一つに、「特許権侵害訴訟の経験を持つ弁理士の少なさ及び特許権侵害訴訟が弁護士主体で進められること」があげられる。特に充足論の議論に弁理士が入る機会は少なく、ほとんどのケースにおいて準備書面は弁護士によって作成される。
無効論であれば、特許査定までの審査を進めてきたことや、審査実務の経験の差から、弁理士からの積極的なサポートを求められることも多いだろう。しかし、通常の審査実務において、充足論を経験することはない。権利解釈(特許法70条)の場面で、明細書等の記載内容の説明を求められることはあるかもしれないが、充足論は「裁判所にそれらしい主張を通せた方が勝つ」という謂わば弁護士の腕の見せ所なのである。よほどのレベルでなければ、充足論の議論において、弁理士が弁護士と対等に話を交わすことは難しいだろう。
このように、訴訟経験を持つ弁理士が少ないだけでなく、たとえ訴訟経験があったからといってそこで十分な役割を果たせる弁理士がどれだけいるのか(充足論においてはほとんど傍観者になっているのではないか)という点からも、きちんと充足論の経験を踏んだ実務家は極めて少数といえるだろう。
そして別の理由の一つに「実務家の主な実務において、充足論対策が不要であること」があげられる。実務家の主な仕事は、特許出願と権利化である。(侵害鑑定もあるがその数は非常に少ない。)
したがって、実務家の多くは、自身の仕事に直結する無効論対策(特許の有効性を担保するための対策)には積極的に目を向けることができても、充足論対策については消極的になりやすい。訴訟は弁護士の仕事と、弁理士実務と訴訟実務を切り離して考えている者もいるだろう。
しかしながら、実務家がこのような思考になるのは、極めて自然なことである。彼らの報酬の多くは、特許出願と権利化の仕事によってもたらされるものであり、侵害訴訟への参加によって得られる報酬など0%に等しいのであるから、自らの報酬に直結する実務の研鑽に取り組むのが当たり前であり、正解なのである。
一方で、特許権者にとっては、充足論対策は極めて重要である。それこそ、実務家が無効論対策に向くからこそ、充足論対策は特許事務所に頼るべきではなく、特許事務所任せのスタンスを取るべきではない。
折角巡ってきた権利行使の機会を、充足論の対策不足によってふいにしてはならない。企業及び企業知財こそ、無効論対策は事務所に任せつつ、充足論対策に力を入れるべきであろう。そして、クライアントの利益を追求する実務家も、少ない機会かもしれないが、そこで最大限の価値提供ができるよう、充足論対策を充実させておくに越したことはない。
3.充足論対策の分析には無効論対策よりも困難な面があること
充足論対策の検討は、無効論対策の検討と比べると難しい面がある。それは、突き詰めれば、無効論が説明責任を果たすことにある一方で、充足論は立証責任を果たすことにあるという点、よって当業者の実態(内情)に大きく左右されるという点にある。
多少雑な言い方をすれば、説明責任は机上の理論だけでも十分に考えることができるが、立証責任はそうはいかない。寧ろ、机上の理論だけでは失敗することの方が多く、より現実的な状況を理解しなければならない点に充足論対策の難しさがある。
一つ例を挙げてみよう。
最近話題にもなった令和6年(ネ)第10026号(令和7年3月4日判決)で、「分子量700以上」の解釈を小数第1位の数字を四捨五入した数値「699.5以上」とすべきかが争われた事例である。本件では、地裁判決、高裁判決ともに、「699.5以上」とは解釈せず、よって、被告製品の分子量「699.91848」は、技術的範囲に属するとはいえず、侵害不成立(非充足)とされた。
この事案から対策を考えるとき、最も単純には「明細書に記載される数値が小数第1位の数字を四捨五入した数値を含むものとして記載されることを、明細書に記載しておく」という案が考えられるかもしれない。しかしこれは、机上の対策であって、実質的に意味のある対策にはなっていない。なぜならば、実態を考えてみれば、出願時に、出願人及び発明者は、分子量「699.91848」という他社品の存在を知らず、分子量699.5から700未満の間で争点が生じるなどと予測できてはいないからである。
仮に、分子量「699.91848」が争点になることを知っていたとするならば、100人中100人が、明細書に上述の記載をしておくか、そもそも、請求項に直接記載することを選択するだろう。だが、それを知らない状況において、出願人や発明者が、なぜ700以上という数値の解釈に699.5以上を含めなければならないのか、どちらを選択すべきかの判断材料を出願時に持ち合わせていないのである。
確かに、699.5以上を含むように記載しておけば、権利範囲は広がるだろう。しかし、それならば端から「分子量700以上」とは記載せずに「分子量699.5以上」と記載すればよいことになる(四捨五入を含むという説明にすれば、699.5以上と記載することにより699.45以上も含まれ、さらに権利範囲は広がるだろう。そして、仮に被告製品の分子量が「699.49」であれば、「分子量700以上」ではなく「分子量699.5以上」と記載しておけばよかったね、ということになる。)。
このように、「四捨五入をした数値を含む」という記載を盛り込めばよいという対策は、「四捨五入」が争点になったから出てくる発想であり、実効的な解決(対策)にはならない。詰まるところ、四捨五入という表現になってはいるが、わかりやすく言えば、700という数字を選択するか、699.5という数字を選択するかという話にしかなっておらず、好きな数字を選んでくださいというだけの話なのである。(分子量「699.91848」という問題に直面していない出願人及び発明者にとって好きな方を選ぶという話でしかない。)
加えて、四捨五入を含むことは、権利範囲を広げるというメリットしか生じないわけではなく、分子量699.91848が公知発明として見つかった場合には寧ろデメリットになる。
分子量700以上とだけ記載していれば「本願発明に分子量699.91848は含まれない」という主張をする余地が残され、本件知財高裁が判断すれば、この主張は通ることになる。出願時に四捨五入を含むと記載したばかりに、新規性や進歩性の解消が一層困難になるリスクもあり、事務所弁理士や企業の知財担当が薦めたせいでこのような事態になってしまった場合、発明者から「余計なお世話のせいで権利を取り損ねた」と非難を浴びるかもしれない。
このように、700を選ぶか699.5を選ぶかは、どちらを選んでもメリットとデメリットの両方があり、発明者は、どちらを選ぶべきかについて判断できる十分な材料を持ち合わせていない。そうすると、このような机上の対策は、本質的には対策となっておらず、実態を踏まえた実効的な解決手段を提供するものではないのである。
「充足論」シリーズに取り組むことの価値
以上説明してきた通り、充足論対策は、その重要性が高いにもかかわらず、その難しさと費用対効果の関係から、企業及び事務所において、十分な対策が検討されているとは言い難い現状にあるのではないか。
そして、今回「充足論」シリーズに取り組むわけは、ここで説明した課題を実際に抱えている企業や、こういった企業の力になりたいと考えつつも力不足を感じている実務家の方の助けとなればよいと共に、私自身も未熟な充足論対策を追求していきたいという強い思いがあったからに他ならない。
この「充足論」シリーズは、まさに実効的な対策であったと言ってもらえるように、事例分析のアプローチの仕方をより充実させ、通常の判例記事よりも実態的な観点からの考察と検討を入念に重ねていくつもりである。その価値を信じて下さる会員の方に、決して損はさせない、料金以上の価値を持ち帰っていただければ幸いである。
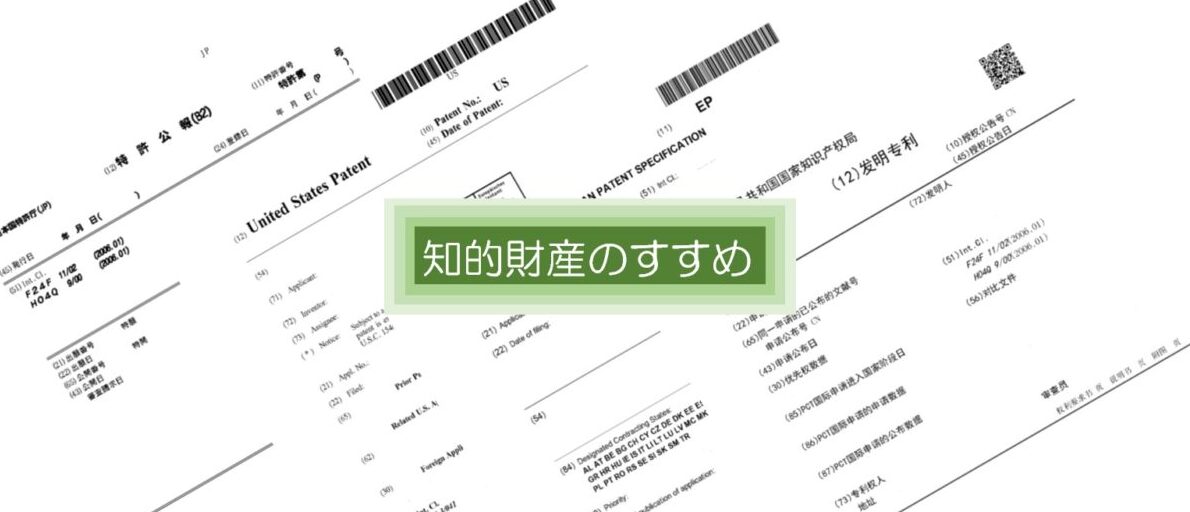
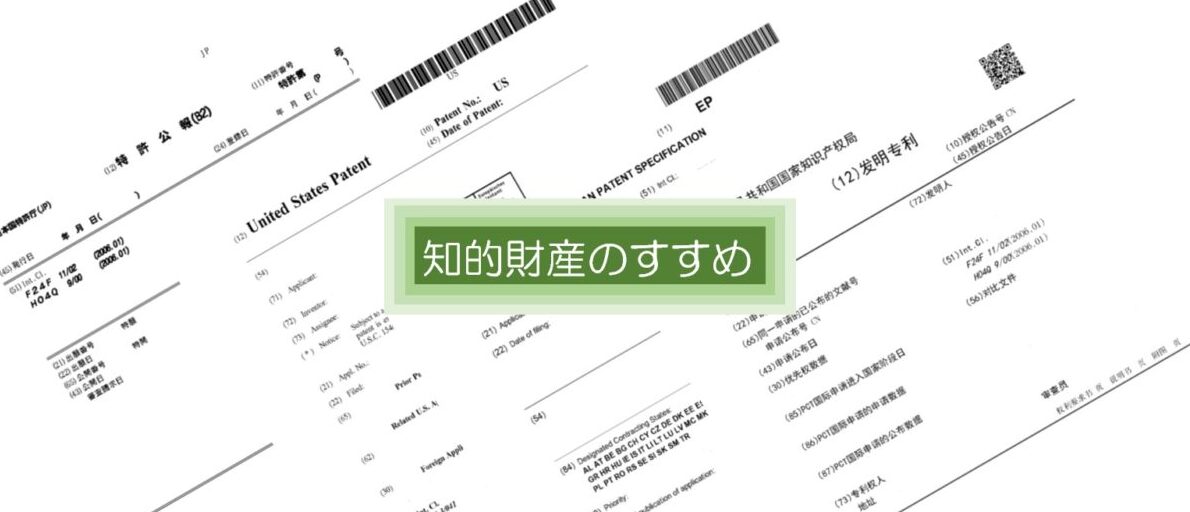
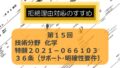

コメント