進歩性:国内の開発事情から引用発明が限定的に解釈された事例
2025/6/24判決言渡 判決文リンク
#特許 #進歩性
1.概要
特許権者であるYら(Y1及びY2)が有する特許第6498843号(発明の名称「溶解炉」。以下、「本件特許」という。)に対し、株式会社ダイキエンジニアリング(以下、「請求人ダイキ」という。)が特許無効審判を請求し、特許庁は、請求項1、2及び6については無効と判断したが、請求項3~5については請求不成立(有効)と判断したため、請求不成立部分の審決の取消しを求めた事案である。
本件特許の請求項1~5は以下の通りである。
【請求項1】
材料投入路(17)とともに蓋(16)を備える予熱部(5)と、
前記予熱部(5)の下方の溶解部(6)と、
バーナー(9)を上部に備える傾斜炉床(15)と、
前記溶解部(6)で前記バーナー(9)によって溶解された後に前記傾斜炉床(15)上を流れる溶融材料(1a)を受け入れて溶融材料(1a)の温度を上昇させる加熱部(7)と、
火炎を放射する温度調整バーナー(12)を備え、溶融材料を貯留する温度調整部(3)と、
傾斜又は湾曲した底部を特徴とし、前記加熱部(7)から溶融材料(1a)を前記温度調整部(3)に流し込む接続路(2)と、
前記接続路(2)を形成する隔壁(10)であって、前記加熱部(7)内の溶融材料(1a)の液面及び前記温度調整部(3)内の溶融材料(1b)の液面よりも低く位置する下縁部(13)を有する隔壁(10)と、
溶融材料の出湯口(4)と、を備え、
前記温度調整部(3)は、閉システムであり、
前記温度調整バーナー(12)は、前記温度調整部(3)内の酸素濃度を1%~5%又は1%未満となるよう制御される、溶解炉。
【請求項2】
溶融材料(1a)、(1b)、(1c)の液面レベルを制御又は検出して酸化物(21a)が前記温度調整部(3)内に流れ出ることを防止するセンサー(8)を更に備え、
前記センサー(8)は、前記出湯口(4)に近接して配置される、請求項1に記載の溶解炉。
【請求項3】
前記温度調整バーナー(12)は、フラットフレームバーナーである、請求項1又は2に記載の溶解炉。
【請求項4】
前記温度調整部(3)は、炉壁の一部又は天井蓋(11)に設置された熱交換器(20)を更に備える、請求項1~3のいずれかに記載の溶解炉。
【請求項5】
前記温度調整部(3)は、扉を有しない閉システムである、請求項1~4のいずれかに記載の溶解炉。
本件の主な争点は「進歩性(29条2項)」であり、甲第3号証を主引用例とする進歩性欠如の有無が争われた。甲第3号証は、平成9年5月現在の株式会社大紀アルミニウム工業所作成のカタログであり、タワー型非鉄金属溶解保持炉「TERRA PAC MELT」についてのカタログである。
特許庁の審決は、請求項3に係る発明(本件発明3)について、甲3発明から本件発明3に至る動機がないと判断し、さらに阻害要因があると判断した。また、請求項4に係る発明(本件発明4)については、甲3発明から本件発明4に至る動機がないと判断した。また、請求項5に係る発明(本件発明5)について、甲3発明から本件発明5に至る動機がないと判断し、さらに阻害要因があると判断した。
本件訴訟において、本件発明3の進歩性判断に関し、請求人ダイキは、動機付けがあることを、次のように主張した。
請求人ダイキの主張(判決より抜粋。下線は付記)
「(2) 動機付けがあること
ア …日本では、本件優先日までの間にフラットフレームバーナーが広く知られていた。…当業者にとってフラットフレームバーナーを炉に採用することの強い動機付けになる。
イ そして、本件米国会社のフラットフレームバーナーには、①均一な温度分布が得られる、②急速な加熱が出来る、③炉体が非常にコンパクトになる、④耐久力が抜群である、⑤特殊な炉にも可能である、⑥ノズル先混合燃焼方式である、⑦あらゆる炉に適応する、という利点がある。…さらに、低NOxで、蓄熱体を内部に有さないことから構造は複雑ではなく、かつ、炉体表面温度もリジェネレーティブバーナーほど高温にならない、耐久性も抜群であり費用も安いといった利点もあった。また、本件優先日前に、フラットフレームバーナーの用途として、アルミ溶解の保持バーナーがあることも知られていた。
ウ これに対し、リジェネレーティブバーナーには、①…バーナーの構造が非常に複雑になる、②…局所的に加熱される、③…溶湯面に生じた酸化膜が破壊されることがあり、…鋳物の特性を著しく阻害する等といった、溶湯品質に関わる問題が生じる場合がある、④かようなリジェネレーティブバーナーの特性から、火炎とアルミ溶湯面の距離・配置に配慮する必要があった、⑤リジェネレーティブバーナーは価格・ランニングコストも高額であった等の問題があった。
エ 以上のように、フラットフレームバーナーは、アルミ溶解炉の業界において、当業者が常に追求してきた省エネ及びアルミ酸化物抑制といった命題(課題・目的)を達成するために、リジェネレーティブバーナーと比較してより良いバーナーであった。リジェネレーティブバーナーは、甲3発明がなされた当初は省エネ効果が高いとして注目され採用されたものの、18年以上を経過した平成27年(2015年)10月13日(本件優先日)時点までの間に、運用していく中で上記①ないし⑤の欠点があることがより一層明らかとなった一方で、フラットフレームバーナーは、アルミ溶湯の保持バーナーとして用いることで上述の利点を有することが当業者に認知され、広く使われるようになった。かような経緯に照らせば、本件優先日時点において、甲3発明のリジェネレーティブバーナーをフラットフレームバーナーに変える動機付けが醸成されていたことは明らかである。」
一方で、特許権者Yらは、動機付けがないことについて、次のように主張した。
特許権者Yらの主張(判決より抜粋。下線、太字は付記)
「(2) 動機付けがないこと
ア フラットフレームバーナーは、甲3発明(平成9年5月)より前の昭和50年(1975年)9月ないし平成3年(1991年)10月には製造販売されており、その頃から既に日本国内で十分に広く展開されていた。…よって、甲3発明は、フラットフレームバーナーも選択肢にあったにもかかわらず、リジェネレーティブバーナーを保持バーナーとして採用したものであって、フラットフレームバーナーが紹介されていなかったために技術的課題のあるリジェネレーティブバーナーを採用せざるを得なかったとの原告の主張は、その前提を欠く。
イ そして、甲3発明は、高い省エネルギー率(CO₂の低減)やNOxの低減を可能にするリジェネレーティブバーナーを採用することで、「1高効率」「3 好環境」という優れた効果を発揮している。リジェネレーティブバーナーのような長炎を噴射するロングフレームバーナーは、…アルミ溶湯を内部から効率よく加熱でき、アルミ溶湯を素早く昇温できる。
一方で、フラットフレームバーナーは、…炉床の昇温に長い時間がかかり、多大なエネルギーを必要とする。
このように、保持バーナーにフラットフレームバーナーを用いるよりもロングフレームバーナーを用いる方が、高い省エネルギー効果を実現できることは、当業者において常識である。
ウ リジェネレーティブバーナーに関しては、…平成5年(1993年)に当時の通商産業省…のプロジェクトに採択されて…積極的に研究開発が進められてきた。また、…従来方式の工業炉に比べて30%以上の省エネルギーの効果と、50%以上のNOx低減を可能とする「高性能工業炉」の開発に成功し、実用化が急速に進み、導入炉基数も少なくとも平成23年(2011年)には国内で約1300基に達するほどの増加傾向にあり、令和2年(2020年)に至っては、リジェネレーティブバーナーは「日本の誇る『低炭素技術』」と評価されるまでになった。実際の製品を見ても、リジェネレーティブバーナーは一貫してその省エネルギー率及びNOx低減効果を謳っており、当業者が長年にわたりこの効果を重視し、実用に供されてきていることが分かる。また、上記プロジェクトの推進によりリジェネレーティブバーナーを採用した工業炉が「エネルギー需要構造改革投資促進税制」の優遇措置対象設備の対象となり、補助金の対象にもなっていたため、当業者は積極的にタワー型非鉄金属溶解保持炉にリジェネレーティブバーナーを採用していた。甲3発明についても、「エネルギー需要構造改革投資促進税制」の優遇措置対象設備となっている。
エ 他方で、ロングフレームバーナーを保持バーナーに採用するタワー型非鉄金属溶解保持炉では、…アルミ酸化ロスの増加や、…酸化物除去のために清掃作業が必要であるといった問題が生じていた。
…本件優先日時点においては、上記のロングフレームバーナーの高い省エネルギー効果が重視され、保持バーナーにリジェネレーティブバーナー又はリジェネレーティブバーナー以外のロングフレームバーナーを採用することが当業者にとっては技術常識であり、フラットフレームバーナーを採用するということは当業者においてはほとんど考えられていなかった。実際、…甲3発明においても、リジェネレーティブバーナーを採用した上で、「4 保全性」の効果があるものとされており(甲3の1)、当業者は、甲3発明のタワー型非鉄金属溶解保持炉は、フラットフレームバーナーを採用せずとも、非鉄金属の酸化物の堆積を相当程度抑えることができるものとして認識していたといえる。」
本件知財高裁は、本件発明3の進歩性について、次のように判断した。
知財高裁の判断(判決文より抜粋。下線、太字は付記)
「(2)ア …まず、甲3発明の「保持バーナー」について検討するに、…甲3発明は、高い省エネルギー率(CO₂の低減)やNOxの低減を可能にするリジェネレーティブバーナーを採用し(甲23、24)、その自己完結型排熱回収機能により、…高効率(…)、好環境(…)を実現したものであり、加えて、高品質(…)で、保全性(…)にも優れたものであることが示されている。
イ そして、リジェネレーティブバーナーに関しては、…平成5年(1993年)に当時の通商産業省…のプロジェクトに採択されて…積極的に研究開発が進められてきた(甲23、乙5の1~3)。こうしたプロジェクトは、…従来方式の工業炉に比べて30%以上の省エネルギーの効果と、50%以上のNOx低減を可能とする「高性能工業炉」の開発に成功し、実用化が急速に進み(乙5の3)、導入炉基数は年々増加し、少なくとも平成23年(2011年)には国内で約1300基に達するほどの増加傾向にあった…。
実際の製品を見ても、リジェネレーティブバーナーは一貫してその省エネルギー率及びNOx低減効果を謳っており(乙6の1乃至5)、当業者が長年にわたりこの効果を重視し、実用に供されてきていることが理解される。
このように、リジェネレーティブバーナーの上記の効果が重要視され、また、…リジェネレーティブバーナーを採用した工業炉が…補助金の対象にもなっていたため(…)、リジェネレーティブバーナーが多く採用されるようになっていたといえる。
ウ そうすると、甲3発明において、リジェネレーティブバーナーは必須の構成であるといえるから、溶解バーナーと保持バーナーともに、リジェネレーティブバーナーを採用したものであると認めるのが相当である。
(3) 次に、フラットフレームバーナーについてみると、甲3発明がなされていた平成9年5月より前の昭和50年(1975年)頃には、既に低融点の非鉄金属の溶解用途等として、日本国内で大阪瓦斯株式会社から販売されていたから(乙1の1)、フラットフレームバーナーは、アルミ溶解用途等において本件優先日前に周知のものであったと認められる。
この点、原告は、本件優先日当時、…動機付けがあった根拠として、フラットフレームバーナーは、…性能の優れたフラットフレームバーナーを遅くとも平成21年(2009年)3月の時点において日本国内で広く展開したため、その後普及したと主張するが、甲3発明の前後に日本国内で販売されていた上記のフラットフレームバーナーを比較しても、…用途(アルミ溶解)及び性能に大きな差はないことが認められる(…)。そうすると、甲3発明は、平成9年5月の時点で、アルミ溶解を用途とするバーナーとしてフラットフレームバーナーが周知であり、それを選択することが可能であったにもかかわらず、あえてリジェネレーティブバーナーを採用したものといえる。
…
(5) 以上によると、甲3発明のタワー型非鉄金属溶解保持炉は、その発売当時、フラットフレームバーナーがアルミ溶解等の用途において周知のものであったにもかかわらず、エネルギー効率等の観点であえて保持バーナーにリジェネレーティブバーナーを採用したと認めることができる。そうすると、甲3発明に接した当業者において、そのような保持バーナーに代えて、あえてフラットフレームバーナーを採用する動機付けが存在していたとは認められない。
よって、本件発明3は、当業者が甲3発明に基づいて容易に想到し得たものではないから、取消事由1は理由がない。」
また、本件発明4及び5については、請求人ダイキも特許権者Yらも、甲3発明にフラットフレームバーナーを適用する動機付けがあるか否かを根拠にして動機の有無を主張している。つまり、甲3発明に容易に想到する動機があれば甲4発明及び甲5発明にも当然に動機があり、甲3発明に容易に想到する動機があければ甲4発明及び甲5発明にも当然に動機がないといった主張となっている。
2.雑感(判決についての感想)
全体的な結果について:結論納得度80% 判断納得度20%
本件は、裁判所の心証が大きく影響した事案ではないかと思う。請求人ダイキも特許権者Yらも、裁判所の判断の決め手となるような決定的な証拠を持っていたわけではなく、間接的な状況証拠の応酬になっていたように見える。
その意味で、結論の納得度は80%と高めになっている。決め手に欠ける証拠資料の中で知財高裁は、自由心証の下に、まさに自由に結論を下した。この証拠の中で判断せざるを得ないならば、知財高裁のした結論は特におかしなものではない。
一方で、判断の納得度は20%と低い。それは、本件で知財高裁が示した論理そのものは十分に納得のいく説得力を与えてくれるものではなかったからである。今回の知財高裁の判断ロジックには大きな問題点があるが、まずは、本件での証拠の応酬について簡単に振り返ってみる。
本件では、主引用発明である甲3発明がリジェネレーティブバーナーであり、フラットフレームバーナー自体は周知であったところ、リジェネレーティブバーナーをフラットフレームバーナーに置き換えることが当業者に容易であったか(置換の動機があったか)が争われた。
まず、この点についての当事者間の応酬は非常に面白い。
請求人ダイキの論理は「フラットフレームバーナーには利点(均一な温度分布)がある。一方で、リジェネレーティブバーナーには問題点(局所的に加熱と酸化膜の破壊)がある。よって置換の動機がある。」といった骨格になっており、
対照的に特許権者Yらの論理は「リジェネレーティブバーナーには利点(効率的な加熱)がある。一方で、フラットフレームバーナーには問題点(昇温に長時間、多大なエネルギー消費)がある。よって置換の動機は無い。」といった骨格になっている。
どちらも、一方をけなし、他方を褒めるという論筋で、その一方と他方が互いに異なっている。
結果(自由心証の判断)を分けたのは、この骨格に対する肉付けといえる。
請求人ダイキは、「甲3発明当時には、リジェネレーティブバーナーの欠点(問題)は周知になっておらず、甲3発明当時から本件優先日時点までの間に明らかになったことで、本件優先日時点においては動機があった」というシナリオであった。
特許権者Yらは、「甲3発明当時には、フラットフレームバーナーは周知であり、甲3発明は、リジェネレーティブバーナーとフラットフレームバーナーの選択ができる中で、その利点からリジェネレーティブバーナーを採用した」というシナリオであった。
そして、裁判所が採用したのは特許権者Yらの主張「甲3発明当時にはフラットフレームバーナーは周知である」であったが、判決文における「裁判所の判断」では、特許権者Yらの主張内容のほとんどが採用されている。
そこにはやはり、特許権者Yらのストーリーの方が説得力(証明力)があるという裁判所の心証が働いたといえるだろう。
特許権者Yらが挙げた証拠は、リジェネレーティブバーナーの産業発達の歴史を織り交ぜたものとなっており、通商産業省が絡むプロジェクトなど、本件発明の技術分野における日本の産業の歴史的経緯から、甲3発明においてリジェネレーティブバーナーは、その利点から選択的に選ばれたものであるというストーリーを語るものであった。
一方で、請求人ダイキは、ある特定の会社(「本件米国会社」に当たる米国フィブスノースアメリカン社)から販売されたフラットフレームバーナーによって、フラットフレームバーナーが周知となったというストーリーであった。
フラットフレームバーナー自体は既に存在しているにもかかわらず、日本国内で広く知られるようになったのは、特定の会社から販売されたフラットフレームバーナーによるものであるというのは、シナリオとしてやや強引な印象を受ける。実際にそれが事実だとしても、このシナリオを裁判所に認めてもらうには、相当高い証明力(のある証拠)が要求されるように感じられる。
たが逆に、このような具体的な会社の製品があがってくるというのは、実際に当業者においてはこのような歴史の一事情があったのかもしれないとも思える。全くの創作で、特定の米国の会社の特定の製品が挙がってくることにも違和感があり、実際に米国フィブスノースアメリカン社の販売したフラットフレームバーナーは、日本の市場に大きな影響力を与えたのではないだろうかという疑問が残る。
仮にこのような事情が日本の溶融炉の業界における事実だとしたら、本件訴訟は、事実を事実として認定してもらうことの難しさを教示してくれる事例だったかもしれない。
請求人ダイキの主張するストーリーよりも特許権者Yらの主張する“国家的プロジェクト”のストーリーの方が客観的事実としてその事実の存在を立証しやすく(認めやすく)、自由心証で論理を組み立てる裁判所にとって、こちらの事実の方が与しやすい。
本件知財高裁は。請求人ダイキの主張に対し、「原告は、本件優先日当時、甲3発明の保持バーナーをリジェネレーティブバーナーからフラットフレームバーナーに変更する動機付けがあった根拠として、フラットフレームバーナーは、本件米国会社が、本件優先日である平成27年10月までに、「あらゆる炉に対応する」ものとして、性能の優れたフラットフレームバーナーを遅くとも平成21年(2009年)3月の時点において日本国内で広く展開したため、その後普及したと主張するが、甲3発明の前後に日本国内で販売されていた上記のフラットフレームバーナーを比較しても、これらは型番が違うものの、用途(アルミ溶解)及び性能に大きな差はないことが認められる。」と述べている。
知財高裁の心理は「大きな性能差がない」という事情から、請求人ダイキの主張を退けており、つまりは「前後で大きな性能差がないのだから、請求人ダイキの主張する製品が日本国内に普及するきっかけとなるには根拠に欠ける」といったものであろう。
しかし、一般的な産業の流れからすると、時代の流れの中で急に大きな性能差を生む製品が出ることは非常に稀である。市場に普及する要因は、性能だけでなく、その時代の流れの中で、受け入れられる事情がやってくることもある(例えば、環境面からの規制など)。
性能差の比較を持ち出す裁判所の論理は、市場原理からすれば十分な説得力を持つものとは言い難い面があるが、おそらく提出された証拠からはそれ以上の要因を取り出せなかったのだろう。
仮に、請求人ダイキが、実際にこの本件米国会社のフラットフレームバーナーの発売後において、日本市場でフラットフレームバーナーを採用した溶融炉の販売台数が伸びていったとか、甲3発明販売当時と優先日当時と現在におけるフラットフレームバーナーの普及率が上がっているとか、自社だけでなく他社の製品ラインナップにおいても優先日当時にはフラットフレームバーナーが増えているといった証拠資料を提出できれば、裁判所の心証や判断も変わっていたかもしれない。
判決文を読む限りでは、この主張に係る争点は性能や技術的なメリット/デメリットに終始しており、証明したい事実が「甲3発明販売から本件優先日の間のどこかでフラットフレームバーナーが日本国内に普及し、当業者における採用の動機が強まった」ということに対する効果的な立証活動にはなっていなかったかもしれない。
なぜならば、その技術にメリットやデメリットがあるというのは、いつの時点においてもどの製品についても言えることだからである。そして、市場に存在している以上、その製品は、メリット/デメリットが享受された上で顧客に受け入れられているのであり、常に何らかのデメリットは存在しているという定常的な性質の事柄に基づいて、ある特定の期間に動機が強まったという突発的な事実を証明しようとするのは、あまり筋の良い方向ではなかったかもしれない。
その意味では、自己に有利な事実を認定してもらうために、何をどのように使って証明するか。証拠の採用やシナリオ形成などの訴訟戦略の違いが結果を分けたと捉えることもできよう。
「どんな事実を証明したいのか」
「その証明に効果的な事実は何か」
実務家においては、その事実の性質を捉え、この点をしっかりと意識しながら、証拠の収集を行っていきたいところである。
さて次に、本件知財高裁の論理構成の問題点について触れてみよう。
この問題点は、知財高裁の結論部分「以上によると、甲3発明のタワー型非鉄金属溶解保持炉は、その発売当時、フラットフレームバーナーがアルミ溶解等の用途において周知のものであったにもかかわらず、エネルギー効率等の観点であえて保持バーナーにリジェネレーティブバーナーを採用したと認めることができる。そうすると、甲3発明に接した当業者において、そのような保持バーナーに代えて、あえてフラットフレームバーナーを採用する動機付けが存在していたとは認められない。」との記載から窺い知ることができる。
この記載によれば、本件知財高裁は、甲3発明の発売当時である平成9年5月当時において、甲3発明が「フラットフレームバーナーがアルミ溶解等の用途において周知のものであったにもかかわらず、エネルギー効率等の観点であえて保持バーナーにリジェネレーティブバーナーを採用した」ものであると判断したことになる。
しかしこれは、厳密には、甲3発明の発売当時=平成9年5月時点の当業者において認識される甲3発明であり、このような事実を認定したことから直ちに、本件特許の優先日当時の当業者によって認識される発明とまで判断することができるのか。この点は甚だ疑わしい。
論理的にみれば、甲3発明の販売当時の当業者の認識から直ちに本件優先部当時の当業者の認識が特定されるためには、「甲3発明の販売当時の当業者による甲3発明の捉え方と、本件優先日当時の当業者による甲3発明の捉え方が同じである」という中間条件の成立が必要となる。
例えば、これら両時点での当業者の技術常識が同等のものであれば、同レベルの技術常識に基づいて発明を理解する以上、発明の捉え方も同じになるといえるだろう。
しかしながら、甲3発明当時は平成9年5月であり、本件優先部は平成27年10月である。甲3発明当時にはそのように認識されたとしても、そこから18年以上が経過した当業者が甲3発明を見たときに、甲3発明当時の当業者と同じ認識で(=同等の技術常識を備えたレベルで)甲3発明を捉えることは当然といえるのか。常識的な感覚からすると、18年経っても技術の捉え方が変わらないというのは納得しがたいところである。
特許法29条2項の進歩性は「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた」かによって判断される。この規定の通り、進歩性の判断は「特許出願前(=本件出願当時)の当業者」に基づいてなされるものである。
例えば、引用文献1には構成要件A1が記載されており、引用文献1の出願時においてはA1の他に採り得る選択肢がなかったとする。この場合、引用文献1に開示される発明において構成要件A1は必須の構成であったといえるだろう。
しかし、それから10年後、もはや構成要件Aの選択肢としてはA1の他にもA2やA3の代替技術が見い出され、当業者において周知になっていたとする。
このとき、引用文献1の出願時における当業者と、引用文献1の出願から10年後の当業者が、引用文献1に記載される発明を同じように「構成要件A1が必須である」と認識するだろうか?
10年後の当業者においては、10年前はA1しか選択肢がないから必須であったに過ぎず、既にA1の他にA2やA3が周知になっているのであるから、引用文献1に記載される発明が「A1を必須とする発明ではない」と認識することも十分にあり得るように私には思えるのである。
加えて、本件の認定事実は、「甲3発明は、平成9年5月の時点で、アルミ溶解を用途とするバーナーとしてフラットフレームバーナーが周知であり、それを選択することが可能であったにもかかわらず、あえてリジェネレーティブバーナーを採用した」という、甲3発明の主観面の事情である。
例えば、甲3発明はその構造上の理由から、リジェネレーティブバーナーしか採用できない等の客観的な事情であれば、甲3発明そのものの構造は何年経っても変化しないため、どの時点の当業者にとっても必須の構成となると言い得るかもしれない。(但、その構造が、甲3発明当時は必須のものであったが、その後の技術革新によって必須ではなくなったということも当然に考えられることである。)
しかし、本件知財高裁の認定した事実は、概要「甲3発売当時から両方のバーナーが周知であり、それぞれにメリット/デメリットはあったが、国家的プロジェクトによって、積極的にリジェネレーティブバーナーの採用が促進、増加していく時代の流れにあった」といったものである。
このような事情は変動的であり、いわば「トレンド」のようなものであって、いつの時代においても同様に受け入れられるものではない。トレンドとひとまとめにしたところで、18年の月日が流れれば、甲3発明当時の勢いと、本件優先日当時の勢いにも違いは生じるものだろう。
そうであるにもかかわらず、甲3発明の販売当時の当業者(発明者)における主観的な事情が、そこから18年以上も経過した本件優先日当時の当業者になお承継されることの説得的な説明を本件知財高裁は行えていないのではないか、というのが私の率直な感想である。
また、甲3発明は、日本で販売された製品であり、リジェネレーティブバーナーの積極的な研究開発が進められてきたという事情もあくまで日本の事情である。しかし、本件優先日当時の特許法29条の規定に基づけば、既に世界公知となっている本件優先日時点の当業者が、なぜ「日本で販売された製品から発明を認定するときに、日本に事情に基づいて発明を認定しなければならないのか」という点も、非常に説得性に欠ける。
本件知財高裁が、日本で販売された製品を日本の事情に基づいて限定的に解釈したのは、やはり本件知財高裁の頭の中に「甲3発明の販売当時の当業者(=販売者)」の視点から発明を捉えようとする部分があったからではないかと推察される(というよりは、そのように推測するしかない)。
確かに、甲3発明を販売するその当事者たる当業者の視点であれば、販売先は日本であるし、日本の事情を考えて甲3発明を製造したのであるから、その者の捉える発明が上述した日本の事情を加味したものとなってもおかしくはないだろう。
しかしながら、そもそも引用発明である甲3発明を「甲3発明を販売するその当事者たる当業者の視点」で捉えること自体が、特許法29条2項の条文に則った判断とはいえないのではないだろうか。
世界公知である以上、当業者という架空的な存在は、日本の事情に拘泥して発明を捉える必要はなく、世界の事情を知ることができ、当業者の技術常識もそこから形成されるものである。そのような当業者が「これは日本で販売された製品だから、当時の日本の開発事情に基づいてこの製品に搭載されている技術(=発明)を認識しよう」などと考えるはずもない。
そして最後に、本件知財高裁の判断ロジックには、全体としての大きな問題が存在する。取消事由1についての裁判所の判断を一通り読んでもらえばわかるが(せいぜい2~3ページなので時間があれば読んでみてもらいたい。)、今回の知財高裁の判断ロジックは、甲3発明に係る販売製品に限らず、平成5年から令和2年の間に販売された「リジェネレーティブバーナーを採用する全ての溶融炉」に対しておよそ当てはまってしまうような論理構成なのである。
もう少し具体的に説明すると、リジェネレーティブバーナーには、NOx低減と省エネルギーという他のバーナーにはない特徴があり、これは周知な事実であった。そして、甲3発明の製品カタログは「好環境」と「高効率」を謳っていた。
これに基づいて、甲3発明においてリジェネレーティブバーナーが必須の構成であると判断されたわけだが、甲3発明に限らずとも、リジェネレーティブバーナーを採用する溶融炉であれば、製品アピールとして、他のバーナーにない利点「好環境」と「高効率」を謳うことは、当然のことではないだろうか。私からすれば、これをアピールしない者の方が、経営者としてどうかしていると思ってしまう。
そうすると、使う言葉は違えど「好環境」や「高効率」と同じような内容の製品アピールは、この利点がなくならない限りリジェネレーティブバーナーを採用する溶融炉であれば当然にカタログ記載されるであろうから、およそどのような溶融度であっても「リジェネレーティブバーナーを採用する溶融炉」から認定される発明においてリジェネレーティブバーナーは必須の構成ということになる。
しかし、このような結論は、製品などの公然実施品から発明を認定する公然実施発明においては、およそその実施品に表れる形態に限定されるという不当な判断を導いてしまう。特許出願においては、リジェネレーティブバーナーを構成要素とする溶融炉を実施形態とした発明であるからといって、リジェネレーティブバーナーが常に必須の構成であるとは認定されないのであり、公然実施発明と文献公知発明の間で、このような不合理な差が生じてしまうのはおかしいだろう。
以上の問題点を考えると、本件知財高裁のした容易想到性の判断ロジックは、十分な合理性が担保されたものとはいえず、本件知財高裁が正しい結論を導いたといえるかは非常に疑わしい。
少し誤解がないように述べておくと、私が今回、結論納得度を80%としているのは「結論の正しさ」に対するものではない。限られた材料の中でされた判断としては及第点と思えたから80%にした。訴訟法を理解している者であれば、私のこのような発言にも違和感はないだろう。
今回、このような不十分な論理構成で進歩性の判断がされてしまった原因は、詰まる所は当事者の立証活動にあるのだろう。知財高裁は、当事者から出された証拠に基づいて判断するため、当事者からの十分な主張立証がされていなければ、裁判所に第一次的な責任はない。無効審判は、対世効の側面から職権主義的な領域はあるが、当事者系審判である以上、原則としては当事者主義が働く領域であるからである。
私が指摘した上記の問題点は、裁判所がこの問題点と向き合えるだけの十分な主張および争点整理がなされなかった結果に過ぎないともいえるのである。
当事者(特に請求人ダイキ)において、「甲3発明当時の当業者の認識と、優先日当時の当業者の認識を混同することなく適切に切り分け、29条2項の条文に則して優先日当時の当業者の認識を認定すべきである」といった主張や「優先日当時の進歩性は世界公知を基準としており、当業者が発明を認識する上で、日本で販売された製品だからといって、日本の事情に基づいてこれを限定的に解釈するのは誤りである」といった主張をすべきであったと思うが、そのためには当事者がまずこの論点そのものに気付かなければならない。
一方で、当事者だけの責任かというと、裁判所には訴訟指揮権があり、当事者に実効的な手続き保障を与えるためにも、適切な訴訟進行が求められている。当事者が、日本での販売製品に対し、国家プロジェクトのような日本特有の事情から限定解釈を主張しているのであるから、裁判所としては、その違和感に気付くべきであるし、本件の当事者が本来争うべき本質的な争点に辿り着けるように、世界公知の規定となっている特許法29条の規定を指摘し、釈明権を行使するなどの対応が求められていたと考えることもできよう。
以降では、実務に関係する論点にスポットを当てて、より詳細な分析をしていくことにする。
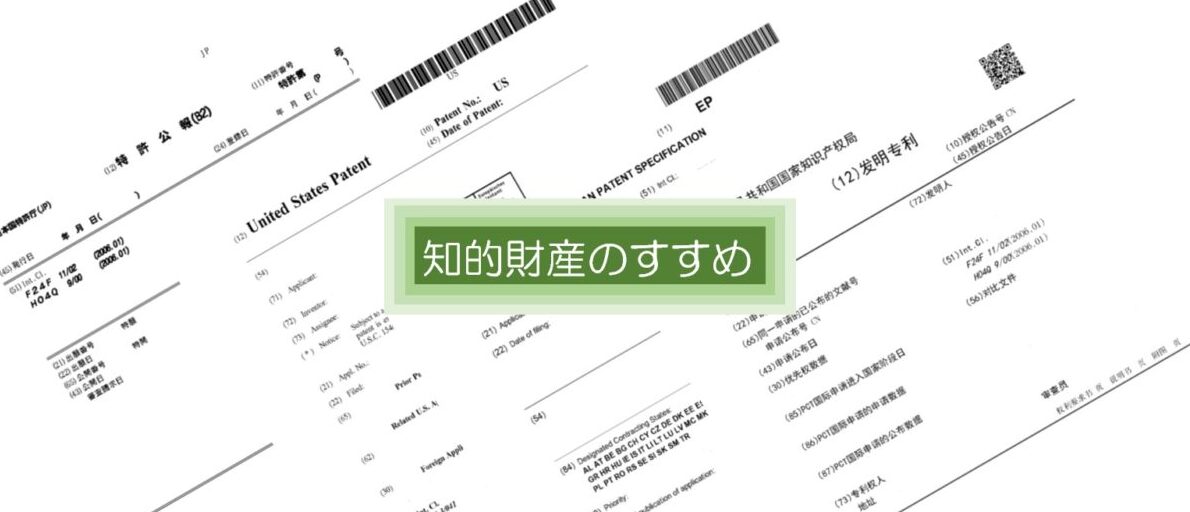
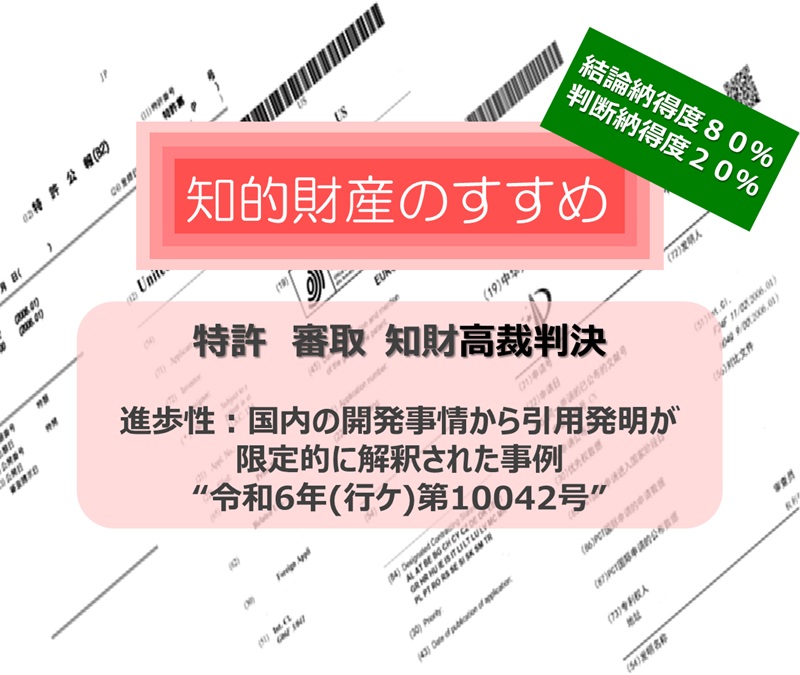


コメント