進歩性:異なる技術分野の引例から容易想到と判断された事例(副引例が上位)
2024/7/17判決言渡 判決文リンク
#特許 #進歩性
1.実務への活かし(雑感まででいえること)
・無効化 #進歩性 #論理付け
進歩性における容易想到性の判断に関し、「主引用発明に、主引用発明の技術分野よりも上位の技術分野に属する副引用発明を適用する」動機の有無(論理付け)を判断するときは、「関連する技術分野」を①主引用発明が属する技術分野に設定する他に、②副引用発明が属する上位の技術分野に設定し、両方のアプローチで検討するのがよい。
また、②のアプローチをするときは、動機を導く「課題」の設定に際し、「周知、自明の課題」であり、かつ、「重要な要素についての課題」を設定するとよい。
∵本件で知財高裁は、電動式衝撃締め付け工具に属する主引用発明と電動モータに属する副引用発明は「電動モータ」という関連する技術分野に属しており(②の技術分野の設定)、主引用発明の属する技術分野「電動式衝撃締め付け工具」においては高トルク化という「重要な要素における周知、自明の課題」があり、その課題を容易に解決する周知技術として「アウタロータ型モータへの置換」があった、という論理を展開して容易想到であったと判断している。
2.概要
本件は、ヨコタ工業株式会社(以下、「特ヨコタ」という。)が保有する特許第4362657号(以下、「本件特許」という。)に対し、アトラスコプコ株式会社等(以下、「アトラス社」という。)が無効審判(無効2021-800019号)を請求したが、本件特許の訂正を認めた上で請求不成立(特許有効)と審決されたため、審決の取消しを求めた事案であり、裁判所によって審決の判断が取り消された事案である。
審決取消の争点は、進歩性であり、本件知財高裁は、「相違点の認定」と「論理付け(動機付け)」の判断において、審決と異なる判断をした。なお、アトラス社は、甲1を主引例とする進歩性欠如、甲2を主引例とする進歩性欠如、甲3を主引例とする進歩性欠如をそれぞれ主張していたが、本件知財高裁は、甲2を主引例とする進歩性欠如について、審決の判断を取り消している。
訂正後の請求項1(以下、「本件発明1」という。)は以下の通りである。
【請求項1】(下線は訂正部分)
電動モータの出力部の回転を、作動油によりトルクを発生する油圧パルス発生部である衝撃発生部に伝達し、前記衝撃発生部において発生する衝撃力によりメインシャフトに強力なトルクを発生させる電動式衝撃締め付け工具において、電動モータは、磁極部を持つステータと、前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設された磁石と、前記磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備えるアウタロータ型電動モータであることを特徴とする電動式衝撃締め付け工具。
本件発明1と甲2に記載された発明(甲2発明)の相違点について、審決は次のように認定したが、アトラス社は、審決の認定した相違点を2つの相違点に分離した。
審決で認定された相違点
「その相違点は、本件訂正発明1の電動モータが「磁極部を持つステータと、前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設された磁石と、前記磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備えるアウタロータ型電動モータ」であるのに対して、甲2発明の電動モータ15は「ステータと、前記ステータの内周側にロータとを備えるインナロータ型電動モータ」である点」
アトラス社の主張する相違点
「(相違点Ⅰ)本件訂正発明1では、電動モータが「磁極部を持つステータと、」「磁極を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備えるアウタロータ型」であるのに対し、甲2発明は「ステータと、前記ステータの内周側にロータとを備えるインナロータ型電動モータ」であって、アウタロータ型ではない点
(相違点Ⅱ)本件訂正発明1では、磁石が「前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設され」ているのに対し、甲2発明では、磁石を保持する態様が明示されていない点」
アトラス社の主張する相違点に対し、特ヨコタは次のように主張した。
特ヨコタの主張(判決より抜粋。下線は付記)
「ア 原告らは、本件訂正発明1と甲2発明の相違点を2つに分けているが、適切ではない。相違点の認定に当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であるところ、本件特許の請求項1の「B 電動モータは、B1 磁極部を持つステータと、B2 前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設された磁石と、B3前記磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備える、B4 アウタロータ型電動モータであることを特徴とする」との部分は、ひとまとまりの技術思想を示す発明特定事項であるから、B2の部分のみを独立の相違点Ⅱとして抽出するのは失当である。」
この点について、本件知財高裁は以下のように判断し、2つの相違点に分離することを認めた。これにより、容易想到性の判断は、「インナモータ型からアウタロータ型への置換」と「磁石の具体的な保持態様」の個々の相違点についてなされることとなった。
知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)
「電動モータに使用される磁石がどのように保持されているかという問題は、電動モータの型式如何にかかわらず独立して検討対象となり得るものである。したがって、本件訂正発明1と甲2発明との相違点を認定するに当たり、電動モータに関し、ステータと磁石を保持するロータとの位置関係による型式(インナモータ型とアウタロータ型)の相違点Ⅰと、電動モータの型式に関わらない事項である磁石を保持する具体的な態様に関する相違点Ⅱを区別して認定することは可能というべきである。」
次に、容易想到性の判断について、審決は以下のように判断していた。
審決での容易想到性の判断(判決より抜粋。下線は付記)
「当該相違点について検討すると、甲2発明は、電動式衝撃締め付け工具に関するものではあるが、電動モータがインナロータ型であり、これをアウタロータ型とする記載も示唆もない。他方、甲1発明は、アウタロータ型モータ自体の発明であって、パワーハンドツールへの応用が記載されているものの、その下位概念である電動式衝撃締め付け工具への適用までは示唆されていない。したがって、甲2発明及び甲1発明のいずれにも、電動式衝撃締め付け工具の電動モータについて、インナーロータ型をアウタロータ型に置き換える、すなわちステータとロータの内外関係を逆にすることについての記載も示唆もなく、置き換えの動機はないから、甲2発明に甲1発明を適用して、本件訂正発明1に想到することが容易とはいえない。」
一方で、知財高裁は、相違点Ⅰについて、甲2及び甲1に共通する上位の技術分野からアプローチし、以下のように判断した。
知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)
「相違点Ⅰの容易想到性について
ア 甲1文献の記載事項
(ア) 甲1文献は、2002年(平成14年)頃に刊行された文献であり、同文献の644頁から649頁までに次の記載がある。…
(イ) 甲1文献の記載及び弁論の全趣旨によれば、甲1文献には、本件審決が認定したとおり「…」という発明(甲1発明)が記載されているものと認められる。
イ その他の文献の記載事項
(ア) 甲24文献(原告ら作成”Industrial Power Tools”)は、2004年(平成16年)に刊行された原告らの工業用工具のカタログであり、同文献には…との記載がある。
そして、以下の各文献からも、手持ち式の電動締め付け工具(インパクト・レンチ等)では、仕様においてトルクが重要な要素であり、トルクを高めることが重要であることが技術常識となっていたことが認められる。
すなわち、甲66文献(電設資材、2003年(平成15年)4月号。服部憲靖「最近の電動工具の動向」)には…との記載がある。また、甲67文献(応用機械工学、1993年(平成5年)11月。)には、…が記載されている。そして、甲68文献(電設資材、1994年(平成6年)4月号。小西順一「コードレスが主流!電気工事用電動工具の種類と特長」)には…が記載されている。
(イ) 甲18文献(シャープ技報、第82号・2002年(平成14年)4月「モータの最新技術動向」池防泰裕)は、家電製品の分野ではブラシレスDCモータとしてインナロータ型とアウタロータ型が採用されており、インナロータ型の課題は、アウタロータ型と比較し、同一外形ではロータの大径化が困難であり、その結果、大トルクを要するときに高い駆動電流を必要とする点であることを指摘する。また、甲19文献(平成16年度電気関係学会東北支部連合大会「アウターロータ型ブラシレスDCモータの駆動方式の検討とその応用(第1報)」櫻井隆憲外4名)及び甲20文献(Research Reports of Sendai National College of Technology、No.35〔2005〕「アウターロータ型ブラシレスDCモータの駆動方式による特性比較」櫻井隆憲外3名)は、アウタロータ型モータは、インナロータ型モータよりも高トルク化が容易であることを指摘する。
ウ 以上を踏まえ、相違点Ⅰについて検討すると、甲2発明は「電動式衝撃締め付け工具」(電動手工具の一種)に係るものであり、甲1発明は「パワーハンドツール」(電動手工具)に応用される「電動モータ」に係るものであるから、両者の技術分野は関連する。また、本件優先日(平成17年9月7日)当時、甲2発明が属する「電動式衝撃締め付け工具」の技術分野においては、その性能においてトルクが重要な要素であり、トルクを高めることが周知、自明の課題であったと認められる(甲2発明の段落【0013】、甲24)。さらに、本件優先日当時、甲1発明のようなアウタロータ型モータは、インナロータ型モータよりも高トルク化が容易であることは周知であったと認められる(甲18から20まで)。
したがって、甲2発明には、トルクを高めるという周知の課題を解決するため、甲1発明を適用する動機付けがあるから、甲2発明に、甲1発明のアウタロータ型電動モータを適用し、相違点Ⅰの構成とすることは当業者にとって容易想到であったというべきである。
…被告は、高トルク化を図るには種々の手段があり得るから、甲2発明に触れた当業者は、インナロータ型を維持しつつ高トルク化を検討するのが自然なのに、モータの種類を根本的に変更し、未完成品である甲1発明を適用することに想到するのは不合理な論理付けであるなどと主張する。しかしながら、高トルク化の代替候補があることによって、甲1発明のアウタロータ型の技術を適用することができないものと解することは困難である。」
また、相違点Ⅱについては、以下のように、文献の記載を列挙した上で、周知技術であると簡潔に判断した。
知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)
「⑷ 相違点Ⅱの容易想到性について
ア 各文献の記載事項
(ア) 甲70文献は、平成13年3月23日公開された発明の名称を「モーターの磁石の固定構造及び固定方法」とする特許出願の公開公報(特開2001-78377)である。甲70文献に記載された技術は、永久磁石の接着方法、特にモーターなどの永久磁石を使用する機器、部品などにおける永久磁石の接着方法に関するものであり…モーターのヨークと磁石の固定構造を示す概念図(甲70文献の図1)には、磁石3がヨーク2に相互に隙間を空けて貼設されていることが記載されている。
(イ) 甲71文献は、平成14年3月15日公開された発明の名称を「モーター及びそのローター」とする特許出願の公開公報(特開2002-78257)である。甲71文献に記載された技術は、ローターに永久磁石を用いたモーターに関するものであり…永久磁石1は、例えば接着剤を用いてローターヨーク2に接着され、3は隣り合う永久磁石1間の隙間であり、例えば、ローターヨーク2の回転軸の軸方向に隣り合う永久磁石1の間に、隙間3が設けられること(甲71文献の段落【0019】)、永久磁石1とローターヨーク2とを接着する2液室温硬化型接着剤5には、アクリル系又はエポキシ系の接着剤があること(甲71文献の段落【0024】)が記載されている。
(ウ) 甲8文献は、平成15年9月19日公開された発明の名称を「ロータおよびその製造方法」とする特許出願の公開公報(特開2003-264963)である。甲8文献に記載された技術は、ロータ軸に接着剤を用いて焼結磁石を固定したロータおよびその製造方法に関するものであり(甲8文献の段落【0001】)、…が記載されている。
(エ) 甲9文献(日本接着学会誌Vol.39、No.9〔2003/9/1〕「構造接着技術の応用展開と最適化技術の構築」原賀康介)には、モーターの磁石接着について、…が記載されている。
(オ) 甲5文献は、平成17年6月2日公開された発明の名称を「回転電機のロータ」とする特許出願の公開公報(特開2005-143248)である。甲5文献に記載された技術は、発電機やモータ等の回転電機に使用されるロー5 タに関するものであり(甲5文献の段落【0001】)、…上記実施形態は、回転電機として働くモータのアウターロータ、インナーロータに適用しても良いこと(甲5文献の段落【0072】)が記載されている。
(カ) すなわち、甲5文献においては、磁石を保持する態様として、アウタロータ型電動モータでは、ステータの外周側(ロータの内周側)に複数の磁石が相互に隙間を空けて配置されることが記載されている。また、甲8、9文献においては(甲70、71文献にも同様の記載があることから、当時の技術常識と認められる。)、接着剤固定法では、通常、エポキシ系やアクリル系などの接着剤で固定する方法により貼設されることが、それぞれ記載されている。
イ 以上を踏まえ、相違点Ⅱについて検討すると、アウタロータ型電動モータにおいて、磁石を保持するために、複数の磁石をステータの外周側(ロータの内周側)に沿って配置し、接着剤固定法等により「貼設」することは、周知技術であると認められる(甲5、8、9)。 したがって、上記周知技術を適用して、相違点Ⅱの構成とすることは当業者にとって容易想到であったというべきである。」
3.雑感
3-1.判決についての感想
全体的な結果について:納得度95%
本件は、相違点Ⅰの容易想到性の判断において、主引用発明と副引用発明の「技術分野の関連性」を、主引用発明の直接の技術分野(電動式衝撃締め付け工具)ではなく、これを含む上位の技術分野「電動手工具」に置き、容易想到と判断した点に特徴がある。
また、これはすでに紹介した記事「令和4年(行ケ)第10037号」の空調服の発明においてなされた容易想到性の判断と共通している。この事件では、本件発明及び主引用発明が空調服であったのに対し、副引用発明が介護用パンツであったものの、関連する技術分野を両社に共通する「被服」として容易想到性を判断し、進歩性を否定した。
(なお、本件は知財高裁第2部 清水裁判長、空調服は知財高裁第2部 本多裁判長)
当然ながら、関連する技術分野を主引用発明の直接の技術分野に設定して容易想到性を判断する方が、関連する技術分野を「上位の共通する技術分野」に設定して判断するよりも、適用の動機は考え易くなる。技術分野の上位化は発明の抽象化であり、どこかで抽象化された技術を具体化し直さなければならないからである。
もっとわかりやすく、自身を当業者だと思って直感的に捉えてみるとよい。
当業者であれば通常、ある既存の製品に技術を加えようとする際に、真っ先に異なる技術分野の技術の適用を検討しようとは思わないだろう。第一に検討されるのは、同じ技術分野の技術である。異なる技術分野の技術は、その既存製品に合わせた技術とは限らず、これを取り入れるには検討すべき事項が増える。
その検討の手間が、容易想到を遠ざけるのであるから、上位の技術分野からアプローチするには、このような「通常とは異なるプロセス」を経てもなお、容易想到といえるだけの説得的な理由が必要となる。
前審の審決はこれを避け、直接の技術分野からアプローチした。そして、「甲2発明は、電動式衝撃締め付け工具に関するものではあり、他方、甲1発明は、パワーハンドツールへの応用が記載されているものの、その下位概念である電動式衝撃締め付け工具への適用までは示唆されていない。」という論理付けによって、進歩性を肯定した。
副引用発明である甲1発明は、上位の技術分野に属する技術を開示するものである。上位の技術分野に係る技術である以上、この技術は上位の技術分野に包含される多くの下位の技術分野への適用可能性を与えている、とまではいえるはずである。(※厳密には、多くの技術分野への適用可能性≠特定の技術分野への適用の示唆、であることに注意)
しかし、下位の技術分野が多岐にわたると、上位の技術分野の技術だからといって、直ちにそれら全てに「容易に」適用できるといえるとは限らなくなるだろう。その意味では、「上位の技術分野に包含される下位の技術分野の範囲」は容易想到性を考える上での一つの重要なファクターとなるはずである。
副引用発明である甲1発明は「モータ」そのものの発明であった。モータは、我々が日常生活で目にする種々の製品に搭載されている。電気製品の中で、モータが搭載されていないような製品は少ないように思える。
モータが適用される技術範囲は非常に広く、その用途に応じて、サイズや構造が違っているであろうことは、素人目にも直感的に理解できるのではないだろうか。
前審の審決は、副引用発明を適用する動機を認めるのに「下位概念である電動式衝撃締め付け工具への適用の示唆」までを求めたが、これは、かなりハードルの高い要求だろう。
なぜならば、「下位概念である電動式衝撃締め付け工具への適用の示唆がある」ということは、実質的に、下位概念における発明の開示を要求しており、上位概念の副引用発明によって動機を導くことそのものを否定しているに等しいからである。
仮に、甲1において下位概念である電動式衝撃締め付け工具への適用の示唆があるならば、それはもはや、副引用発明として、「モータ」ではなく「電動式衝撃締め付け工具のモータ」の発明が開示されているに等しいのであって、副引用発明を「モータ」の発明と認定する必要はないのである。
しかし、前審の審決がこのような厳しいハードルを要求したのも、まさにモータという技術分野の大きさが影響していたのかもしれない。あまりにその適用範囲が広範であるがゆえに、モータそのものの発明から、「電動式衝撃締め付け工具」への適用を当業者がすんなりと認識できるかに疑念を抱き、電動式衝撃締め付け工具への適用の示唆が必要と考えたのではないかと推測する。
前審の審決が、このような「選択肢の多さ(技術分野の広さ)」を重視したであろうと思える点は、相違点Ⅱに係る審決の判断「しかしながら、電動モータに発生トルクの大きなものが必要とされるという数多くの解決手段が存在する一般的な要請のみをもって、これらの解決手段からインナロータ型モータをアウタロータ型モータに置き換えるという具体的手段の選択に至ることが容易とまではいえず」からも読み取れるように思える。
進歩性に関し「選択発明」という考えもある以上、容易想到性の判断において「選択肢の多さ」を考慮要素に取り入れることは間違っていない。選択肢が多くなると、当業者の創作過程において「適切な選択肢といえるかを見極める」プロセスが必要になり、容易想到を遠ざける事情となり得るからである。
しかしながら、容易想到性の判断思考において、「選択肢の多さ」の壁を打ち破る考え方(論理アプローチ)が、「関連する技術分野の上位化」にあるのかもしれない。このことは、本件だけでなく上述の令和4年(行ケ)第10037号の事例にも共通するものといえ、進歩性欠如(特許の無効)を主張する側にとって、どのような主張戦略を採るべきかの重要な判断材料を与えてくれるのではないだろうか。
本件知財高裁は「相違点Ⅰについて検討すると、甲2発明は…「電動モータ」に係るものであるから、両者の技術分野は関連する。また、…甲2発明が属する「電動式衝撃締め付け工具」の技術分野においては、その性能においてトルクが重要な要素であり、トルクを高めることが周知、自明の課題であったと認められる。さらに、…アウタロータ型モータは、インナロータ型モータよりも高トルク化が容易であることは周知であったと認められる。したがって、甲2発明には、トルクを高めるという周知の課題を解決するため、甲1発明を適用する動機付けがある」という論理付けを行った。
知財高裁は、主引用発明と副引用発明は「電動モータ」という関連する技術分野に属しており、主引用発明の属する技術分野「電動式衝撃締め付け工具」においては高トルク化という「重要な要素における周知、自明の課題」があり、その課題を容易に解決する周知技術として「アウタロータ型モータへの置換」があった、という論理を展開している。
電動モータという広い技術範囲に対しては、単なる「周知、自明の課題」ではなく「重要な要素における周知、自明の課題」を持ってくることで相殺を図っているものと、論理的には捉えることができるだろう。
我々が容易想到性を主張するときも、単に「周知、自明の課題がある」と主張するのではなく、「重要な要素における課題である」という点も加えて主張する方が、裁判所や特許庁の心証を動かす主張ができるように思える
さて、技術分野を上位化した進歩性欠如の主張をより有効なものとするには、本件知財高裁のした判断ロジックをさらに分析する必要があるが、ここから先は詳細な考察で述べることとする。
最後に、その他の争点である「相違点の認定」と「相違点Ⅱについての容易想到性」について簡単に述べておく。
相違点の認定に関し、本件では、アトラス社の主張する相違点Ⅰ及びⅡが採用されたわけだが、この点について、前審の審決と大きく判断が異なったかというとそうではない。これは、前審審決における判断をみるとわかる。
前審審決における容易想到性の判断(審決より抜粋)
「(2)相違点の検討
ア …甲2発明は、電動式衝撃締め付け工具に関するものではあるが、電動モータがインナロータ型であり、電動モータ自体をアウタロータ型とする記載も示唆もないものであるところ、甲1発明は、アウタロータ型モータ自体の発明であって、パワーハンドツールへの応用が記載されるものの、パワーハンドツールの下位概念である電動式衝撃締め付け工具への適用までは示唆されていないものである。
したがって、甲2発明及び甲1発明のいずれにも、電動式衝撃締め付け工具の電動モータについて、インナロータ型モータをアウタロータ型に置き換える、すなわちステータとロータの内外関係を逆にすることについての記載も示唆もなく、そのような置き換えの動機はないから、甲2発明に甲1発明を適用して、本件特許発明1に想到することが当業者にとって容易であるとはいえない。
イ また、甲5、8~9に、上記相違点における磁石を貼設することについて開示されており、磁石を貼設することが周知技術であるとしても、上記アのとおり、そもそも甲2発明に甲1発明を適用する動機はないのであるから、本件特許発明1が容易に想到できたものであるとはいえない。」
確かに審決は、相違点そのものの認定においては、相違点ⅠとⅡを分けなかったが、容易想到性の判断においては、上述のように、実質的に相違点ⅠとⅡを分けて判断しているといえる。また、相違点Ⅱについては、そもそも相違点Ⅰの適用が容易想到ではないという理由から特に踏み込んでいない。
次に、相違点Ⅱの容易想到性であるが、こちらも、周知技術を認定するための文献は多数挙げているものの、論理付けそのものの判断は「~は、周知技術であると認められる。したがって、上記周知技術を適用して、相違点Ⅱの構成とすることは当業者にとって容易想到であった」としており、非常に簡潔である。
ただし、ここで間違えてはいけないのは、周知技術=適用は容易想到ではないという点である。本件の相違点Ⅱに対する判断では省略されているが、厳密には、周知技術であっても、その周知技術を適用する動機の有無は判断される。周知技術の適用を阻害するような消極的事情が認められれば、周知技術の適用も容易想到ではないとされる点には注意が必要である。
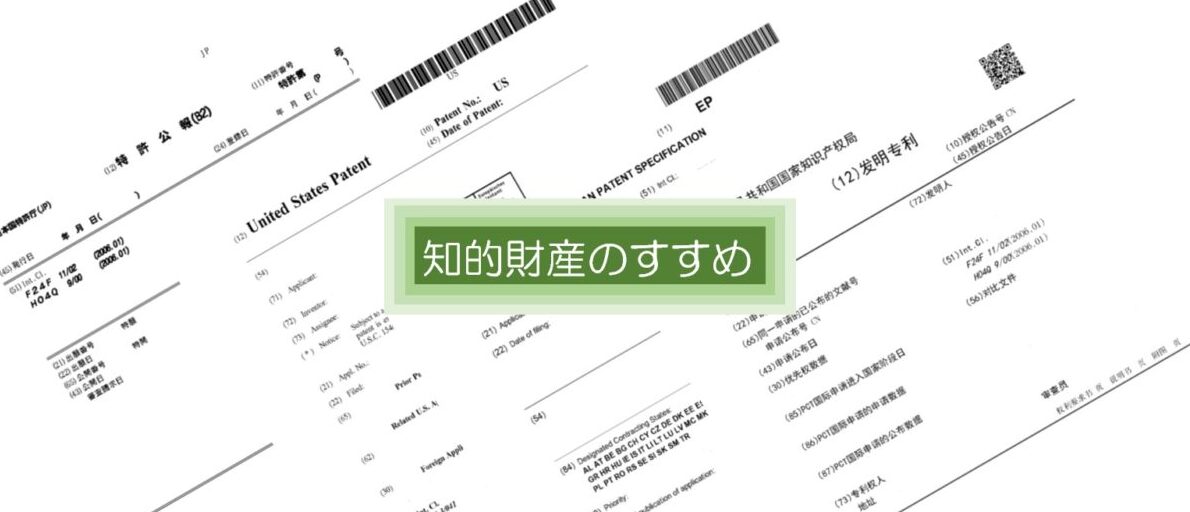
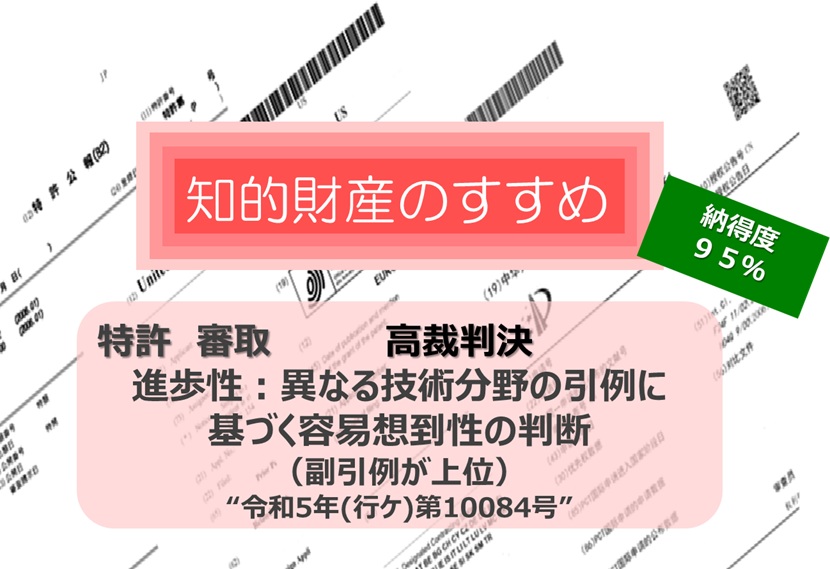
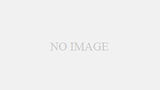
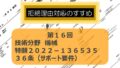
コメント