補正の目的要件
令和4年4月28日(2022/4/28)判決言渡 判決文リンク
#特許 #第17条の2第5項
1.実務への活かし
・~権利化まで #補正手続き #第17条の2第5項各号
最後の拒絶理由の対応時や不服審判請求時の補正が目的要件を充足するか、判断が微妙だと感じるときは、事前に審査官に連絡or面接して確認すべきである。また、事前のOKが貰えない場合は、強行突破を試みないで分割出願で対応すべきである。
∵特許法第17条の2第5項各号の目的要件については審査官の裁量が比較的大きく、また、無効理由ではないので審査が通りさえすればいい。だからある意味で、審査官の了承を得られるか否かの勝負であり、補正手続前に審査官に連絡してそこを交渉するのが最もリスクを下げる対処法と考えられる。
強行突破が功を奏すればいいが、ダメだったときは訴訟で争うしかなく、桁違いの訴訟費用を負担するリスクに比べれば、素直に分割出願しておく方が、安全面でも費用面でも合理的である。(審査官の了承が得られなかった場合は、クライアントにそのように説明して、分割を薦めるとよい)
2.概要
原告ショットスコープテクノロジーズリミテッド(以下、ショット社という。)が、特願2016-563421号(以下、本願という。)に対する拒絶審決を不服として審決取消訴訟を提起した事案である。
知財高裁は、ショット社の請求を棄却した。
本件での主な争点は、拒絶査定不服審判と同時に行った増項補正(以下、本件補正という。)が限定的減縮の目的要件(特許法17条の2第5項2号)を満たすか否かである。ショット社は、拒絶査定時のいずれの請求項にも対応しない新たな従属請求項(補正後の請求項8)を加える増項補正を不服審判と同時に行った。また、この追加された従属請求項(以下、追加従属項という。)は、拒絶査定において「拒絶理由を発見しない」請求項1に従属するクレームであった。
ショット社は、追加従属項は請求項1の内的付加にあたり、特許法17条の2第5項の制度趣旨から許容されるべきであるなどの主張を行った。つまり、「既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を認める」という制度趣旨からすると、たとえ追加従属項が補正前の請求項1と一対一で対応する請求項ではないとしてもこれに準ずるような対応関係に立つものであり、特許法17条の2第5項2号が許容する増項補正であるなどと主張した。
知財高裁は、追加従属項が、補正前のどの請求項と対応関係にあるかについて、補正前の請求項1ではなく請求項10と対応関係にあるとして、ショット社の主張する対応関係を認めず、補正前の請求項10との関係では、追加従属項はこれの一部の構成を削除したものであるから「特許請求の範囲の減縮」とは認められないと判断した。
ショット社の主張(判決から抜粋)
「本件拒絶理由通知では、本件補正前の請求項1について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理由の指摘はなく、本件補正前の請求項1に特許性が認められていることからすると、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1に対する従前の審査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項1についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を生じさせないことも明らかである。
そうすると、厳密には、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項1は、既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法17条の2第5項の制度趣旨に反するものではなく、同項2号が許容する増項補正に相当するから、本件補正前の請求項1との関係で「特許請求の範囲の減縮」(同号)を目的とするものに該当する。」
知財高裁の示した判断手法(判決から抜粋)
「補正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものと解される。」
3.本件のより詳細な説明、及び、判決内容の考察
3-1.本願に係る審査経過について
本件は、上述のように、前後の補正の変更内容さえわかれば、発明の内容自体はわからなくても分析できる。また、より詳細な分析を行うには、発明内容の理解よりも、全体的な審査経過について知っておく方がよいと思われるため、これを紹介する。なお、発明の名称は「ゴルフスイングモニタリングシステム」であり、いわゆるシミュレーションゴルフや、ゴルフのスイング分析を行うために、センサを腕などの身体に取り付けてて動作を検知し、分析するような内容のようである。
本願は、ドイツの会社であるショット社がPCT出願をし、PCT出願が日本に移行されたものである。審査請求の後、拒絶理由通知がされ、手続補正書を提出した後に、今度は拒絶査定を受けている。
拒絶理由通知を受けた時の請求項は、請求項1~10が「システム」、請求項11~12が「携帯装置」、請求項13~14が「タグ」、請求項15が「方法」の全15項であり、全請求項について、29条1項または2項の拒絶理由が通知された。なお、請求項15の方法クレームは、請求項1~14のいずれかに係る物を利用することが特定された請求項である。
拒絶理由通知の応じて提出された手続補正書では、請求項1~16が「システム」、請求項17~18が「携帯装置」、請求項19~20が「タグ」、請求項21が「方法」の全21項となり、システムについての請求項が6項追加された。
これに対し、拒絶査定では、請求項17~21について、29条1項または2項の拒絶理由が解消していないとしたが、請求項1~16については先の述べた拒絶理由は解消したが、新たに拒絶理由を発見したと述べている。この新たな拒絶理由は、主に、請求項の不明確な点を挙げるものであり、少なくとも29条の拒絶理由は解消したものと判断されている。
そこで、ショット社は、上述の追加従属項を足すと共に、請求項17~18の「携帯装置」及び請求項19~20の「タグ」を、「システム」に変え、これらを請求項1の従属項とした(なお、審判では請求項17~20の補正も認められていないが、本件訴訟ではこれについて判断するまでもなく、追加従属項が適法でないことだけ判断されているので、ここでもこの点については触れないでおく。)。また、追加従属項については、審判請求書において次のように説明された。
審判請求書の一部を抜粋
「最後に、請求項8を新たに追加しました。請求項8に記載の内容は、ストラップとストラップセンサと複数のアンテナ整合回路またはシステムおよび/または調整可能な整合回路またはシステムとを備えた構成により、請求項1に記載の発明を限定的に減縮することを目的とするものです。当該事項は、補正後の請求項11(補正前の請求項10)の前半部に記述された内容であり、直前明細書の段落0133および0134の記載に基づいています。よって、新規事項を追加するものではないと思料いたします。」
拒絶査定不服審判は、前置審査に移管され、前置報告書が出された。前置報告書では、審査官から「平成17(行ケ)第10192号の知財高裁における判示からすれば、本件補正のように請求項を増加させる補正は、特許法第17条の2第5項第2号の定める「特許請求の範囲の減縮」に該当しないものである。また、当該態様の補正が、特許法第17条の2第5項第1号に規定する請求項の削除、同項第3号に規定する誤記の訂正、同項第4号に規定する明りょうでない記載の釈明の何れの目的にも該当しないことは明らかである。したがって、この補正は、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。」といった報告がされた。
そして、審査前置解除が通知され、その後、審理終結通知書が出され、審決において、追加従属項が特許法17条の2第5項各号のいずれの目的にも該当しないため、この規定に違反するものであるとして補正が却下され、拒絶審決がなされた。
なお、審査前置移管から審決までの期間は比較的短いと思われる。
2020/10/13 審査前置移管
2020/11/2 前置報告書 (移管から約3週間)
2020/11/6 審査前置解除
2021/3/23 審理終結通知 (前置解除から約4か月半)
2021/4/27 審決
参考のため、補正前の請求項1~10と補正後の請求項1~11の関係を簡素的にまとめた表を下に記す。詳細を知りたい人は、実際の公開公報や経過書類、あるいは、判決文を読んで欲しい。この表は、細かな説明内容はさておき、「~を備え」という記載から構成を抽出し、どの構成に関する記載かを特定するという簡単な方法で模式化した。追加従属項である補正後の請求項8を赤で記している。

3-2.判決についての感想
全体的な結果について:納得度80%
個人的には、判決の結果については特に異論はないが、判断の内容についてはいくつか疑問が残る。また、本件は、審査及び審判の進め方次第でこのような結果を回避できたのではないかと思うので、その意味では非常に残念な結果である。この点を考察するために、特許法17条の2第5項の規定に今一度向き合ってみようと思う。
判決における知財高裁の判断内容について
ショット社の主張は主に、①追加従属項は、請求項1に内的付加をしたものである、②追加従属項によって審査遅延などの事態は生じない、③追加従属項は、請求項1と一対一で対応するか、これに準ずる対応関係に立つ、という3つの主張である。
これに対し、知財高裁は、まず、補正前後の請求項の対応関係を明らかにしてから、その対応関係にある請求項との関係で、いわゆる限定的減縮となっているかを判断すべきとした。上記の主張に対し、③を先に行ってから①の判断を行うという流れである。
そして、知財高裁は、③についての判断で、追加従属項は補正前の請求項1ではなく請求項10と対応関係に立つと判断した。
3-1で示した表をみれば、補正前の請求項1~10が、補正後の請求項1~7、9~11に対応していることはわかるだろう。また、追加従属項である補正後の請求項8が補正前の請求項1と対応関係にあるか、補正前の請求項10と対応関係にあるかについては、過半数が知財高裁と同様の判断を下すと思う。私もその判断に異論があるわけではない。私が気になったのは、なぜ「仮に請求項1と対応関係にあるとしても限定的減縮ではない」と述べておかなかったのかという点である。
補正後の請求項8は、補正前の請求項1に対し、「システムがさらにストラップセンサを備える」ことを付加している。これは外的付加と判断できるのではないか。「システムが~するように構成されており」という長文の中に、「ストラップセンサを備え」という文言があるのだが、ショット社はこれを内的付加に相当すると主張している。つまり、「システム」をさらに限定するものであるというスタンスなのだろう。
しかし、本件における「システム」は、構成要件の一つではなく、発明の名称である。例えば、「~装置がA、B、及びCを備える」と書けば、A、B、及び、Cをそれぞれ構成要件と捉えるのが通常だろう。同じように「システムがAを備える」と書けば、Aは構成要件となるはずである。そして、「~装置がさらにDを備える」という補正が新たに構成Dを付加する外的付加であり限定的減縮にあたらないなら、「システムがさらにBを備える」というのも同様に判断されるべきではないだろうか。加えて、発明の対象たる「システム」を減縮することが内的付加となってしまうなら、外的付加にあたる補正はおよそ無いといえ、実質的に補正が制限されなくなってしまうように思う。
確かに、追加従属項が補正前の請求項10と対応関係にあるというのが本件の多数意見であるとは思うが、対応関係をどう特定するかに関し、決まった方法が確立されているわけでもない。そうすると、対応関係が請求項1であるか請求項10であるかという点については争いようがあるということになる。
判決をより盤石にするには、対応関係は請求項10であると判断した上で、仮にショット社の主張する請求項1であったとしても、追加従属項は、請求項1には存在していなかった「ストラップセンサ」を構成に追加するものであり外的付加にあたるから限定的減縮にあたらないとして、上記③だけでなく①についてもショット社の主張を認めないと述べておくのがベターだったのではないかと思う。
また、対応関係の特定においても、補正前の請求項1は、追加従属項のシステムが備える「ストラップセンサ」を備えておらず、一方で、補正前の請求項10はこれを備えているという点を理由の一つに挙げることができたのではないだろうか。
加えて、知財高裁は、ショット社の主張②についても応じているが、この判断は失当ではないだろうか。知財高裁は、ショット社が請求項1に特許性が認められていることを根拠に審査遅延等の事態は生じさせず、特許法17条の2第5項の制度趣旨に反しないと述べたのに対し、次のように論じている。
知財高裁の判断(判決から抜粋)
「本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件においては、本件補正前の請求項10の発明特定事項から上記構成を削除した請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかがわれず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1に対する従前の審査内容に沿って特許性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。」
しかし、サポート要件等の記載要件の審査が新たに必要になるのは、補正が限定的減縮であった場合も同じである。これを言ってしまうと、構成の一部を削除しようが、構成を限定しようが条件は同じなので、なぜ限定的減縮が認められて構成の一部削除が認められないのかをうまく説明することができない。一般的には、限定的減縮の方が補正の幅は広く、記載要件を気にしなければ無制限に可能であるのに対し、構成の一部削除は、その一部を削除することで記載要件が成立しなくなるかといった点を考えればいいだけなので、審査の負荷だけで言えば限定的減縮をする方が大きいといえるだろう。
知財高裁は「従前の審査内容に沿って特許性を具備するものと直ちにいえるものではな」いから原告の主張は前提を欠くと述べているが、ショット社は「本件補正前の請求項1に対する従前の審査内容に沿って特許性を具備するものといえる」と主張しているにすぎず、直ちに特許性が認められるはずとは言っていない。あくまでショット社は、「本件補正前の請求項1についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を生じさせないこと」が明らかという主張をしているのであり、これに対して、記載要件の審査が新たに必要となるからショット社の主張は前提を欠くと言ってしまうと、限定的減縮であっても、記載要件の審査が必要であり直ちに特許性を具備するとは言えないのだから、知財高裁の述べる理由が、限定的減縮を認めないことの根拠になるとも言えないはずである。
既に、追加従属項が限定的減縮にあたらないことについてはその他の理由から既に決着がついているのだから、知財高裁がショット社の主張②に応えてこのような理由を述べる必要はなかったと思うし、余計な論点を生むような理由ならば述べない方がよかったのではないかと思う。
どのように対応すべきであったか
(イ)特許法第17条の2第5項の規定
逐条解説第21版には、特許法17条の2第5項に関し、「補正を、先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限」するものであると述べているくらいで、その制度趣旨についてはここからは判然としない。しかし、この規定の制度趣旨が、迅速な審査を行うために補正に制限をかけたという点にあることに争いはないだろう。「迅速な審査を行うこと」が目的であり、補正の制限はあくまでそのための手段である。
ここで、「迅速な審査」とは誰のための利益かということを考えたい。補正の当事者たる出願人のための利益といえるだろうか?補正をしたい出願人にとっては、迅速に審査をする代わりに補正が制限されるというのは大きなお世話である。つまり、ここでいう「迅速な審査」とは、一個人の利益というよりも、総体的・社会的な利益と捉えるべきと思う。もう少し平易な言い方をすれば、出願人が「私が行った補正は私の事案において審査の迅速性を損なわない」といったところで、上記の制度趣旨が個人ではなく社会に重きを置くのであれば、視点として不十分ではないだろうか。
全体として迅速な審査が遂行されるためには、目的要件の適否を判断するのに、事案ごとの性質を見極めて、個々の事情を考慮するという作業自体の発生をなるべく抑えなければならない。結局、目的要件を充足するか否かの判断を行うのに、新たな審査と同等の時間を要するのであれば、それも制度趣旨に反してしまうからである。そうすると、ある程度形式的な面から基準を定める必要があるだろう。つまり、審査の迅速性を害さないか否かも、形式的に判断できる要素によって目的要件の該当性は判断されなければならないように思う。
ショット社の主張するように、事案の性質を考慮すれば、本件は迅速な審査を損なわせる補正ではないということもできたように思う。既に説明しているように、本件の追加従属項は、拒絶理由の発見されていない請求項1に従属しているため、進歩性についての審査を要しないことは明らかである。
また、追加従属項は、補正前の請求項10にあった構成の一部を削除したものである。補正前の請求項10は請求項8に従属し、請求項8は請求項1~7に従属していた。追加従属項は請求項8に従属せずに請求項1~7に従属するものであり、追加従属項が削除した構成は、補正前の請求項8と補正前の請求項10の一部ということになる。サポート要件の形式的要件(明細書に記載されていること)は当然に満たすであろうし、実体的要件(課題を解決することを当業者が理解できること)も請求項1が課題を解決しているのだから問題ないだろう。
通常の実務の感覚からすれば、補正前の請求項10に拒絶理由がないのであれば、追加従属項についての審査はさほどの時間を掛けることなくできるであろうし、拒絶理由もないと思う。
しかしながら、裁判所は、本件において迅速な審査が損なわれるかではなく、本件のような補正を認めることで、今後の審査にどのような影響が起こるかを考え、その視点で迅速な審査が担保されるかも検討するように思う。
ショット社の補正を認めると、①拒絶理由がない請求項に従属し、かつ、②いずれかの従属項に既に記載されている構成要件から任意に選択された1または複数の構成要件で構成される、という条件を満たせば、請求項を追加する補正が認められるということになる。
また、1項の増項を認めてしまうと、この条件を満たす請求項を2項増やすことを否定することは難しいだろう。追加する請求項が1項ならOKで2項ならNGになることを合理的に説明するのは難しいからである。つまり、1項の増項を認めれば、一体何項までなら追加が認められるかという線引きをするのは難しく、それをしようとすると、増項が及ぼす実態的な審査負荷を考えなければならない。それこそ、請求項が1項増えた場合に生じる新たな審査負荷は事案ごとに異なるであろうし、そうすると、審査負荷の考察に審査をする以上の負荷が掛かってしまいかねず、上述した制度趣旨に反することになる。
補正によって追加された請求項があった場合に、その請求項の内容が上記①及び②の条件を満たすかどうかを判断しなければならず、さらにその請求項の数にも制限がないとすれば、 迅速な審査の弊害となることは容易に想像できるだろう。
このように、総体的・社会的な視点でみれば、ショット社が行った増項補正を裁判所が認めるわけにいかないことも納得がいくように思う。
最初に言ったように、目的は「迅速な審査」であり、そのための手段として、先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限しているのである。先行技術文献調査の結果等を有効利用できさえすれば十分なのではなく、たとえ有効利用できるとしても迅速な審査を害してしまうのであれば、裁判所がそのような補正を法解釈によって制限しようとすることも当然のように思う。(平成17(行ケ)第10192号で裁判所が、特許法第17条の2第5項第2号括弧書きの要件に、補正前後の請求項に一対一の対応関係があることを要求したのも、総体的な視点で制度趣旨を見つめた上で導かれたように思う)
(ロ)どのように対応できたか
本件の増項補正を認めることによるその後の審査実務への影響を考えれば、本件で裁判所が増項補正を認めなかったのは納得がいく。一方で、本件だけでみれば、今回の増項補正によって迅速な審査を害すほどに審査の負荷が増すとは思えない。
審決で補正が却下されてしまえば、公益的・社会的な視点も踏まえ、取消訴訟では厳しい戦いを強いられることになるが、審査や審判段階であれば、審査官は、具体的な事案との関係で、先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限にあり、実質的に新たな審査を行う必要もないといえれば、裁量で増項補正を認めてくれる余地はあると思う。
審査基準には、第17条の2第5項に関して次のように記されている。(下線部は付記したもの)
「第17 条の2 第5 項の規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な不備をもたらすものではないから、無効理由とはされていない。したがって、同条第5 項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。」
このように、新規性や進歩性、サポート要件など、特許の実体的な判断に比べると、迅速な審査という目的で規定された特許法第17条の2第5項については、特許庁は審査官に趣旨を逸脱しない範囲での裁量を認めているように読める。
そして、審査官によって補正が認められ、特許査定がされた後は、これが異議申立ての取消理由や無効審判の無効理由となることはなく、特許法第17条の2第5項の違反を理由に争いが生じるリスクはおよそなくなる。(その審査に権限の逸脱濫用がある場合や、重大かつ明白な違法があれば、特許査定に対して、行政事件訴訟法上の取消訴訟や無効確認の訴えがされる可能性はあるかもしれないが(平26年(行コ)10004号など参照)、特許性という実体的な面に不備がない以上は、よほどのことがなければ取消しや無効とされることはないように思う。)
つまり、補正が第17条の2第5項各号の目的を満たすかどうかは、審査や審判の段階でケリをつけるのが妥当であり、審査官への連絡や面接を通じて、補正を認めてもらえるように事前交渉をするのが得策と考える。
拒絶査定を受けた段階で、チャレンジングな補正をしたいのであれば、拒絶査定不服審判を請求する前に、審査官と面接をすることを薦める。拒絶査定~不服審判を請求するまでの間も審査官との面接は可能であるし、補正をすれば前置審査で審査官が審査することになるのだから、事前に審査官と面接しておくことはメリットがある。上記の審査基準を挙げて、行おうとしている補正が、迅速な審査の妨げにはならないことを説明し、前置審査で特許査定をもらえるように試みるのがよい。審査官も、目的要件の判断の是非を審判や訴訟にあげられてまで争いたくはないという心情は働くだろうし、特許査定にしてしまえば審判に進むこともないのだから、審査官にとっても厳格な方向に判断することのメリットはない。本件のように少し見れば特許性が維持されているであろうことがわかる内容であれば、事前に審査官にお伺いを立てておくことで違う結果となっていたかもしれない。
なお、面接の機会は、拒絶査定~不服審判請求までの間に限られない。前置審査に際しても面接はできるし(審査前置移管通知が来た段階で審査官に面接を申し込めるし)、審判合議体との間でも面接はできる。
不服審判をする前の審査官との面接がうまくいかなかった場合には、そのような補正はせずに分割出願でケアするか、審判官と面接を行い、審判官と議論をするかの選択肢がある。しかし、審査官の面接がうまくいかなかった時点で、審判官との面接に賭けるのはリスクが高いように思う。個人的には、分割出願で権利取得を狙う方が無難だと思う。

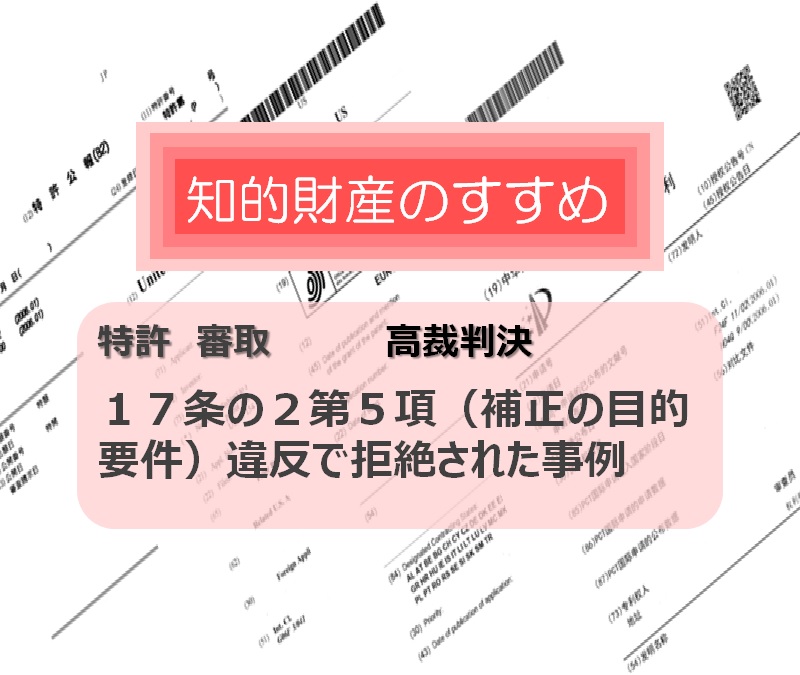


コメント