商標法第53条の2の「代理人」
令和4年9月12日(2022/9/12)判決言渡
#商標 #第53条の2
1.実務への活かし
・~出願まで #出願人の適格性(代理人になり得るか否か)
輸入販売業を行う者による商標登録出願を検討する場合(依頼を受ける場合)、その者及びその者の出願しようとする商標が、商標法第53条の2によって取消されないかのリスク判断をすべきである。
このとき、商53条の2の「代理人」に該当するか否かの判断は、「販売代理人契約」を締結している等外形的に代理人といえるか否かだけでは不十分であり、代理人契約が無くても実際の取引の実態から「代理人」と判断されることがある。
この点を注意してクライアントによる出願の適格性を判断すべきである。
2.概要
ダインス カンパニー リミテッド(以下、ダインス社と呼ぶ。)が、商標法第53条の2に基づき、株式会社ビーアンドオー研究所(以下、ビーアンドオー社と呼ぶ。)の有する商標第5911020号(以下、「本件商標」という。)の取消しを求め、特許庁がこれを認めたことに対し、商用権者であるビーアンドオー社が審決の取消しを求めた事例である。
ビーアンドオー社は、自らが、同法第53条の2の「代理人」に該当しないこと、及び、商標登録出願をすることについて「正当な理由」があることを主張した。
「代理人」に該当しないことについて、ビーアンドオー社は、特許庁が審決において、本件商標登録出願後の取引まで考慮して「代理人」に該当するか否かを判断したことが不当であり、ダインス社との取引数量、回数、及び金額といった取引の実態と、本件商標の出願前にダインス社(の総代理店)が有していた商標の使用に関する契約が妥結していなかったことから、未だダインス社との間に、「代理人」と言えるほどの信頼関係は築かれていないことを主張した。
「正当な理由」があることについて、ビーアンドオー社は、ダインス社自らの登録料未納付により商標出願が却下された後に本件商標の出願をしていることを主張した。
知財高裁は、ビーアンドオー社の主張に対し、期間内(商標登録出願から一年前まで)に「代理人」といえるだけの信頼関係が形成されていたかを判断するのに、継続的な取引が行われていたかを検討するため、期間後の取引も含めて総合的に判断することは許されるとし、「代理人」に該当するとの判断を維持した。
また、契約が、双方の要求が合わないこと(ビーアンドオー社は独占的使用権を求めたがダインス社は通常使用権なら許諾できると回答していた。)から結果的に妥結に至っていないという事実は、「代理人」であることを否定する事情にはならないと判断した。
さらに、知財高裁は、ダインス社が、商標出願が却下された後に改めて商標登録出願をする予定であることをビーアンドオー社は知っており、却下されてから本件商標が出願されるまでの期間が2か月にすぎないことからも、ダインス社が長期間にわたって商標登録出願がされていない状況のまま放置していたとはいえず、「正当な理由」があったとはいえないと判断した。
知財高裁の示した判断(判決から抜粋)
「商標法53条の2は、輸入者が権利者との間に存在する信頼関係に違背して、正当な理由がなく外国商標を勝手に出願して競争上有利に立とうとする弊害を除去し、商標の国際的保護を図る規定というべきであり、この観点からすると、ここにいう「代理人」に該当するか否かは、輸入者が「代理人」、「代理店」等の名称を有していたか否かという形式的な観点のみから判断するのではなく、商標法53条の2の適用の基礎となるべき取引上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討するのが相当である。
この点、原告は、被告商品を輸入して、日本国内でこれを販売するために被告との取引関係に入ったものというべきところ、前記1⑶のとおり、本件期間内の被告商品の納入は合計5回、1261万円に上り、決して少ないものとはいえず、さらに、本件期間後の平成29年3月14日まで継続している。そうすると、原告と被告の関係は、単発の商品購入にとどまるものではなく、継続的な取引関係の構築を前提とするものであり、このことは、原告がわが国におけるエスタッチ社商標の使用権を取得しようとしたこと、さらには、本件商標の登録出願をしたこと自体からも裏付けられるものである。以上の事情を総合考慮すると、原告と被告の間には、本件期間内に既に、代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が形成されたものと認めるのが相当であり、代理店契約の存否等にかかわらず、原告は、同条の2にいう「代理人」に該当するというべきである。」
3.判決内容の考察
3-1.判決についての感想
全体的な結果について:納得度90%
本件の結果については特に異論はない。以下では、商標法第53条の2の「代理人」の判断の歴史について、特許庁を含め、判例(裁判例+審判例)がどのようなアプローチを採っているのかを考察していきたい。
3-2.商標法第53条の2の「代理人」の判断についての考察
商標法53条の2
まず、商標法第53条の2をおさらいする。商標法53条の2は、次のような規定である。
商標法第53条の2
登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
このように、商標法53条の2は、代理人/代表者あるいは1年以内に代理人/代表者であった者による商標登録出願に係る商標登録を取り消す審判の規定であるが、53条の2に関する裁判例はあまり多くない。(探せばもっとあるかもしれないが、)ここでは、見つかった4つの裁判例を紹介する。
1つ目は昭和56年(行ケ)第60号、2つ目は平成21年(行ケ)第10138号、3つ目は平成23年(行ケ)第10194号、そして4つ目は令和2年(行ケ)第10100号である。
裁判所の判例
参考1 昭和56年(行ケ)第60号
参考1は、審判において特許庁が請求を認容し、商標権を取り消す審決をしたのに対し、東京高等裁判所が、これを覆した事例である。
元々の商標権者であるマクドナルド社から商標権を譲り受けたAに対し、Bは「マクドナルド社は53条の2の「代理人」にあたる」と主張して取消しを求めた。
裁判所は、次のように述べて、マクドナルド社は53条の2における「代理人若しくは代表者であった者」とは認められないと判断した。(下線及び色字は付記)
「マクドナルド社とゼオン社又は被告との間で、マクドナルド社がゼオン社又は被告の代理人としてケーサイト製品を販売する旨の契約は勿論、継続的取引契約すら締結されたことを具体的に得心せしめて右記載部分を裏付けるに足りる証拠は、ほかに全く存しないから…マクドナルド社が被告のケーサイト製品の一手売捌代理人としての契約上慣行上の地位を有していたものとは到底認めることができない。
さらに…マクドナルド社との取引量は少なく、本来一〇パーセントのデイスカウントを受ける資格がないこと、アメリカ以外の世界中に約一五〇〇のデイストリビユーターをもつており、マクドナルド社のオーダーを特別扱することはできない旨の記載があり、前記認定事実に照らし、これをもつてマクドナルド社が被告の一手売捌代理人として行為していたことを証するものとは到底できがたいところである。…
以上の事実によれば、マクドナルド社は、昭和三九年八月一日本件商標の登録出願当時、…単なる輸入販売業者であつたというにとどまり、それ以上に、マクドナルド社とゼオン社又は被告との間に、マクドナルド社が被告の代理人としてケーサイト製品を販売する法律上の関係ないしは特約店、輸入総代理店等日本においてケーサイト製品を販売するについての特別の契約上慣行上の関係が存したものと到底認めることはできず、その間に格別の信頼関係が形成されていたものともいえない。
商標法第五三条の二は、商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者がその権利者との間に存する信頼関係に違背して正当な理由がないのに同一又は類似の商標登録をした場合にその取消について審判を請求できる旨の規定であつて、以上認定の事実及び法律関係のもとにおいては、マクドナルド社は本件商標の登録出願当時又はその登録出願の日前一年以内に商標法第五三条の二に規定する「被告の代理人若しくは代表者であつた者」と認めることはできない。
参考1では、53条の2の規定が、「代理人若しくは代表者が権利者との間に存する信頼関係に違背していること」を根拠に、その代理人若しくは代表者を保護する規定であることを述べている。
また、この判例では、「代理人」といえるか否かの判断材料として、「代理人としての契約上慣行上の地位を有していたといえるか」「代理人として行為していたといえるか」「単なる輸入販売業者にとどまるといえるか」「格別の信頼関係が形成されていたといえるか」などを考慮している。
参考2 平成21年(行ケ)第10138号
参考2は、審判において特許庁が請求を認容し、商標権を取り消す審決をしたのに対し、知財高裁が、これを覆した事例である。
参考2では、商標登録出願の一年前から出願日までの間に「代理人」であったか否かの判断において、知財高裁は次のように判断し、「代理人」に該当しないとした。
「原告は本件商標登録出願後3か月余を経過した平成17年9月1日付けで被告との間で独占的販売契約( Exclusive Distributorship Agreement)を締結して,原告が何らかの意味で被告の代理人となったことは認められるが,それ以前は,被告から顧客として商品サンプルを購入して上記契約を締結するかどうかを検討する期間であったと認めることができる(原告が被告から商品を業として大量に購入するようになったのは,前記のとおり上記契約締結後である)。
…そうすると,本件商標登録出願がなされた平成17年5月12日より1年前以内に原告は被告の「代理人」であったとした審決は誤りであるということになる。」
参考2では、独占的販売契約を締結した時点(出願から3か月余後)では「代理人」であるとみとめられるが、サンプル品を購入している段階では「代理人」であるとはいえないと判断している。
参考3 平成23年(行ケ)第10194号
参考3は、「代理人」に該当するか否かの判断については簡潔に判断しているが、ここでは知財高裁は次のように述べている。
「原告ないし原告代表者が,本件商標の登録出願の日前1年以内に,被告ないし被告との間で日本における輸入代理店契約を締結している者から,日本における独占販売権を付与されていたわけでいないものの,原告及び原告代表者と被告との間には,継続的な取引により慣行が形成され,原告及び原告代表者は,日本国内における被告の商品の販売体系に組み込まれるような関係にあった者とみることができるから,商標法53条の2所定の「当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者」に該当する。」
参考3では、契約上の「代理人」の地位がないとしても、「継続的な取引により慣行が形成され、販売体系に組み込まれるような関係にある」といえる場合には「代理人」に該当すると判断している。つまり、①継続的な取引があること、②両社の間に取引上の慣行が形成されていること、③(外国の商標権者等の)販売体系に組み込まれる関係にあることを、代理人契約を締結していない者を「代理人」と認めるための要件としている。
参考4 令和2年(行ケ)第10100号
参考4は、知財高裁は「代理人若しくは代表者」の解釈について、次のように述べている。
「商標法53条の2の「代理人若しくは代表者」とは,商標に関する権利を有する者から代理権を与えられた者,又は商標に関する権利を有する法人の代表者に限られず,商標に関する権利を有する者との間で,契約に基づき継続的な法的関係があるか,あるいは少なくとも,継続的な取引から慣行的な信頼関係が形成され,商標に関する権利を有する者の事業遂行の体系に組み込まれている者であれば足りると解すべきである。」
参考4では、参考3と同じようなことをより規範的に表現しており、「代理人」の解釈が、契約上の代理人としての法律関係があるような直接的な代理人だけでなく、①継続的な取引があること、②取引から慣行的な信頼関係が形成されていること、③事業遂行の体系に組み込まれていること、を満たす者も、実体的な代理人に該当すると解している。 なお、ここでの「直接的な代理人」と「実体的な代理人」は、便宜上、このような呼び方によって言い分けているだけで、一般的にこのような使い分けがされているわけではない。以後も、この呼び方を用いる。
このように、4つの判例と本件を含めた5つの事例を見てみると、53条の2の「代理人」が、代理人契約を締結しているといった直接的に代理人といえるような者に限らず、取引上の関係から実体的に代理人といえるような者も含む、という考えは共通しており、これは既に確立された解釈といってもよいように見える。
一方で、「代理人」に当たるか否かの結論に至るまでの判断アプローチには違いがみられる。
裁判所の判断手法
(ア)立法趣旨アプローチ
参考1の事例は、立法趣旨から「代理人」に該当するかを判断するアプローチを取っている。このアプローチは、商標法53条の2の趣旨から「商標に関する権利を有する者とその代理人若しくは代表者との間に存する信頼関係に違背して」いることを取消請求の認容に要するとした上で、後は認定事実を総合考量し、「代理人」に該当するかを判断している。
このアプローチは、どのような行為が「代理人」に該当するかという具体的な規範を挙げることなく、両当事者が、「権利者」と「代理人」の関係にあるといえるかを、権利者と代理人という立場であったとしたら存するであろう信頼関係を有していたか評価することで判断している。
判断手法としてはやや大味で、総合考量というアプローチ上、裁判所の判断に広い裁量が生じることになる。参考2も、これと同様のアプローチと言える。
(ロ)規範定立アプローチ
参考3及び4の事例はそれぞれにやや表現の異なる部分はあるが、直接的な代理人であるといえない場合に「実体的な代理人」に該当するかの規範を定立した上で、当てはめを行っている。(事例3は、規範の定立と当てはめをまとめて行っている。)
このアプローチでは、①継続的な取引があること、②取引から慣行的な信頼関係が形成されていること、③事業遂行の体系に組み込まれていること、がいえるかどうかを、認定事実から判断している。
このアプローチの方が、第三者にとってはわかりやすく、裁判所の判断のブレも抑えることができる。
本件の判断アプローチ
それでは、本件がどちらのアプローチを採ったかというと、本件では、立法趣旨アプローチを採っていると解することができる。
知財高裁は、
「商標法53条の2は、輸入者が権利者との間に存在する信頼関係に違背して、正当な理由がなく外国商標を勝手に出願して競争上有利に立とうとする弊害を除去し、商標の国際的保護を図る規定というべきであり、この観点からすると、ここにいう「代理人」に該当するか否かは、輸入者が「代理人」、「代理店」等の名称を有していたか否かという形式的な観点のみから判断するのではなく、商標法53条の2の適用の基礎となるべき取引上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討するのが相当である。」 と述べ、立法趣旨から「取引上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討すべき」とし、このような観点も含めた上で総合考量から「代理人」に該当するか否かを判断しているといえる。
しかしながら、本件では、総合考慮される事情の中で、取引期間、回数、数量及び金額などの事実から「原告と被告の関係は、単発の商品購入にとどまるものではなく、継続的な取引関係の構築を前提とするもの」であると評価しており、実質的には、規範定立アプローチの①及び②に相当する事実認定が、判断の決め手となっている。
なぜ、規範定立アプローチを採らなかったか
本件では、総合考慮される事情の中に、規範定立アプローチの①及び②が含まれている以上、どちらのアプローチを採っても結論は変わらなかったように思う。
また、4つの参考判例からすると、立法趣旨アプローチを採用したといえる参考1及び2からは「代理人」に該当しないという結論が導かれており、規範定立アプローチを採用したといえる参考3及び4からは「代理人」に該当するという結論が導かれている。
規範定立アプローチの①から③の要件は、どちらかといえば権利者に有利な規範のように感じられる。例えば、参考1の事例において、規範定立アプローチに基づき①から③の要件の該当性を判断すれば、「代理人」に該当するという結論を導くこともできるように思える。
個人的に、規範定立アプローチが権利者有利と感じるのは、③の要件の緩さにある。③の要件は「事業遂行の体系に組み込まれていること」であるが、輸入販売行為が輸入販売元の事業遂行の体系に組み込まれていないことなど、通常あり得るのだろうか。相手が単なる輸入販売者であったとしても、販売元はその輸入販売者が自社の商品を販売し、認知度を広げてくれることを期待するのが当たり前で、そうすると誰であっても販売元の事業遂行の体系に組み込まれているということはできてしまう。
本件は、「代理人」に該当するという結論を導いているのだから、規範定立アプローチの方が結論を導きやすいようにも思えるが、知財高裁は立法趣旨アプローチを採用した。それは、本件の知財高裁も、規範定立アプローチの③の要件を判断要素から外したかったからではないだろうか。
特許庁の判例
それでは、特許庁は、商標法53条の2の取消請求においてどのようなアプローチで判断を導いているのだろうか。下の表は、53条の2の取消請求事件について、審決の結果と判断手法をまとめたものであるが、この表から非常に興味深いことがわかる。

黄色のマーカーは、請求棄却となった事件で、「代理人」に該当しないとされた事件であり、水色マーカーは、規範定立アプローチを採った事件である。表に示す通り、特許庁は、「代理人」であると判断した事件においては規範定立アプローチを採用している一方で、「代理人」に該当しないと判断した事件においては規範定立アプローチを採用していない。
このことは、規範定立アプローチの要件が権利者有利であることの証左といってもよいかもしれない。そしてこの事実は、商標法53条の2の「代理人」を判断するための要件を定める規範が未だ定立されていないことの表れともいえる。
要件①~③が請求を棄却する場合に使われないということは、この要件①~③は、「代理人」であると判断したい場合の規範といえ、ある意味で結論から導かれる規範でしかないともいえるからである。
規範定立アプローチにおける要件の変遷
特許庁では、上の表にも示されるように、規範定立アプローチで示される要件として「①と②」で構成されるケースと「①~③」で構成されるケースとがある。また、以前は①と②で構成することが主流であったが、最近になって①~③で構成されるケースが出てきたようにも見て取れる。
既に述べたが、私は、①~③で構成される方が、①と②で構成されるよりも、判断基準が緩やかになっている(「代理人」であると認めやすくなっている)と思っている。①~③は以下の通りであるが、
①継続的な取引があること
②取引から慣行的な信頼関係が形成されていること
③事業遂行の体系に組み込まれていること
①と②だけで構成される場合、結局のところ、継続的な取引とはどの程度の取引なのか、形成される信頼関係はどの程度のものなのか、という点がクリアになっていないので、厳しく判断することもできれば、緩く判断することもできるのである。
一方で、これに③が入ると、③の要件が、①及び②の要件におけるハードルを示すことになる。つまり、③の要件はそれ自体が①及び②から独立した要件であるのではなく、事業遂行の体系に組み込まれていると言える程度に①取引の継続性及び②信頼関係の形成がなされていればよいという、いわば①及び②の要件判断を補足する役割を担っているように思える。
そのため、「①と②」で構成されるよりも「①~③」で構成される方が、「代理人」であると認めやすいように感じるのである。
つまりは、特許庁は、以前よりも低いハードルで、「代理人」であると認める方向に変化しているということだろうか。
この点は、時代の変化も影響しているように思う。2000年当時と比べると、大企業だけでなく、中小企業も含めた多くの企業において、知的財産に関する教養レベルが向上しているように思える。またさらに、2010年当時と比べると、特許中心であった知的財産にも変化が見られ、意匠権や商標権についての注目が大きくなっているように感じる。いわゆる製造業だけでなく、サービス業、輸入販売業、また個人経営のお菓子屋さんなどでも商標権を取得し、これをアピールすることが増えてきている。
これには、ドラマなどの影響もあるだろうが、やはり、GAFAや中国の影響が大きいだろう。特に中国の模倣品ビジネスは、日本の事業者の意識を変え、ただ良い物を作れば売れるという考えを払しょくさせた。自社の「良い物」を粗悪な模倣品から守るため、自己のブランド価値を高めて他の商品との識別を図る必要があり、これを怠ると継続的な利益の確保が難しくなる時代になった。
このようにして、日本全体で、事業を行う者の知財リテラシーが底上げされると、商標法第53条の2における「代理人」の判断基準にも影響が出てくるのは致し方ないかもしれない。この規定は、「代理人または代表者」になる前の者には適用されないのであり、言い換えれば、「代理人または代表者」になる前に商標出願してしまえば、簡単にリスク回避ができるのである。
商標法第53条の2が、「パリ条約6条の7の規定を実施するため、すなわち、他の同盟国等で商標に関する権利を有する者の保護を強化し、公正な国際的取引を確保するために設けられた規定」であるとの解釈は妥当であり、これが変わることは考え難いことからすると、この規定はあくまで「他の同盟国等で商標に関する権利を有する者(以下、権利者と呼ぶ。)」を保護する規定であり、「代理人または代表者になる前の商標出願人」を保護する規定ではない。
そうすると、代理人または代表者になり得る者(権利者との間で取引をしようとする者)が知恵をつけ、これを悪用して、早期に商標登録出願をしてしまえとなってしまうと、同じハードルで判断していては権利者を適切に保護できなくなる。最近の判例が①~③を要件とするようになったのも、このような時代の変化に影響されているのかもしれない。
なお、そうはいっても「代理人」の判断基準のハードルを下げるのには限界があるだろう。例えば、事例2の事件のように、サンプル提供段階で、まだ購入すらしていない者(購入検討段階にある者)を、商標法第53条の2の「代理人」に含めていいかというと、それはさすがに難しいように思う。
そうなると、外国のある商品に目を付けてこれを国内展開したいと考える者が、日本に商標登録されていないことを確認し、権利者との交渉初期あるいは交渉前に商標登録出願だけ済ませてしまうと、商標法第53条の2によって取り消すことは難しい(但、53条の2がダメでも、4条1項7号や19号による無効の可能性は残されている。)。しかし、これは致し方ないだろう。
このグローバル経済の中にあっては、権利者の側にも、将来的な事業展開を見据えて商標登録出願を進めておくことについて、義務があるとまでは言わないが、多少なりとも考慮すべき立場にあるとはいえる。つまり、権利者は、全くの善意の立場にあるのではなく、商標登録出願できる立場にあってしていなかったことについて一応の帰責性は認められるため、権利者と取引者の間の利益衡量で判断するしかない。いや、利益衡量というよりも、権利者の過失の程度と、取引者の行為内容から、権利者を保護してよいかを判断するのだろう。
本判決の価値
本件は、「代理人」であると判断しつつ。この判断を規範定立アプローチではなく、立法趣旨アプローチで展開したことにその価値があると思う。つまり、規範定立アプローチでは、「代理人でない」という結論を導きにくいのに対し、立法趣旨アプローチからなら、「代理人である」との結論も導くことができることを示した一つの事例といえるだろう。立法趣旨アプローチでは、あくまで結論を導くために検討すべき考慮要素を挙げ、結局は総合考量で判断するしかないということになるかもしれないが、しばらくはこの判断手法の方が適切なのかもしれない。
時代が進み、誰もが商標法第53条の2の概要を認知しているようなレベルにまで達すれば、そこで初めて、公平に用いることのできる規範が定立できるようになるのかもしれない。
3-3.現時点で採るべき論法
これまで見てきたように、権利者側(取り消しを望む側)は当然、規範定立アプローチを軸に主張を展開していくべきであろう。但し、立法趣旨アプローチで総合考量により判断されてもいいように、要件①~③に関する事実だけでなく、相手が信頼関係に違背したといえるような事情も述べておくべきである。
一方で、商標登録出願人(取り消されたくない側)は、権利者側の規範定立アプローチには付き合わず、立法趣旨アプローチでの主張を展開する方がベターだと思う。権利者側が規範定立アプローチの①~③の要件を主張してきたら、まずは、この判断手法を否定しておくべきであろう。その上で、立法趣旨アプローチに持ち込み、自己に有利な事実を述べていくのがよいように思う。

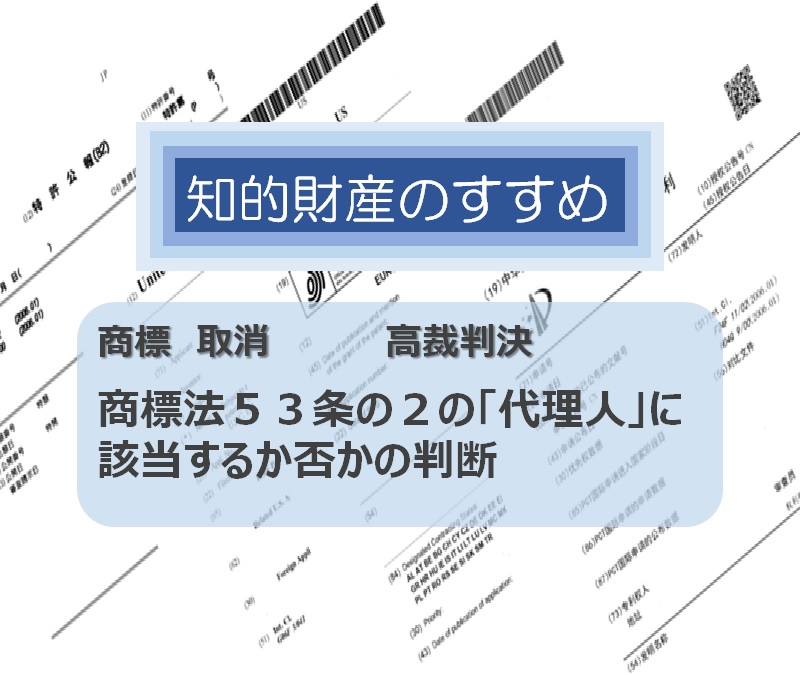
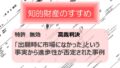
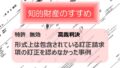
コメント