進歩性:出願時に市場になかったことが組合せの動機を否定する要因となった事例
令和4年8月31日(2022/8/31)判決言渡 判決文リンク
#特許 #第29条 #論理付け(動機付け)
1.実務への活かし
・~権利化まで #進歩性 #意見書
進歩性の主張をするときに、主引用発明に組み合わせる対象となる技術(物)が「出願日当時に市場に出回っていない」といえる場合には、この事実が組み合わせの動機付けを阻害することを主張できないか検討すべきである。
∵本件では、特許庁において無効と判断された請求項について、主引用発明に組み合わせられる技術が出願日当時市場に流通していなかったという事実を主張して判断が覆った。
2.概要
特許第6138324号(発明の名称「半田付け装置」他。以下、「本件特許」という。)の特許権者である株式会社パラット(以下、「パラット社」という。)と、本件特許の全部無効を請求する株式会社アンド(以下、「アンド社」という。)の双方が、無効審判で一部無効とされた審決を不服として争った審決取消訴訟である。
パラット社は、無効とされた一部の請求項(請求項1、2及び5ないし7)に対する審決の取り消しを求め、アンド社は、無効とされなかった一部の請求項(請求項4)に対する審決の取り消しを求めたが(2つの事件は併合)、知財高裁は、パラット社の主張を容れ、アンド社の主張を容れなかった。
つまり、無効審判事件(無効2019-800094号)において、令和3年10月8日にした特許庁の審決のうち、無効とした部分(請求項1、2及び5ないし7。以下、「対象請求項」という。)だけが取り消された。判決内容は、特許権者であるパラット社の全面勝訴といえる。
本件での主な争点は、進歩性である。
無効審判において、特許庁は、対象請求項に係る発明と甲1文献(特開2009-195938)に係る甲1発明との相違点に関し、①甲1発明に「フラックス含有量が1wt%(重量/質量% ※本件では、重量%と質量%の厳密な違いは問題にならない。)であるはんだ」を使用した場合に、当該相違点を満たすことになると判断し、また、②甲15(千住金属工業株式会社の製品安全データシート)において「半田にロジン(フラックス)を1~4wt%含有させること」が記載され、甲10の日本工業規格において、「やに入りはんだのをフラックス含有量が1wt%のはんだ規格としてフラックス含有量が1.0質量%、許容範囲が0.5質量%以上1.5質量%未満のものが記号F1と定められていること」が記載されていることを考慮すれば、フラックス含有量が1wt%の半田を用いることも当業者が容易になし得たことと認め、よって対象請求項は無効であると判断した。
これに対し、本訴においてパラット社は「甲1発明には、相違点に係る技術的思想がなく、また、甲1発明にフラックス含有量が1wt%の半田を用いることには技術的阻害要因があること」、また、「本件出願日当時には、フラックス含有量が1wt%の半田は存在していなかったこと」を主張した。
知財高裁は、パラット社の主張及び証拠から「フラックスの含有量を1wt%とする半田は、本件出願日当時、やに入り半田の市場において普通に流通していなかったものと認めるのが相当である」とし、甲1に接した当業者にとって、フラックスの含有量が1wt%Zの半田をわざわざ採用しようとする動機付けはない」として、進歩性を欠くということはできないと判断した。
知財高裁の判断(判決から抜粋。下線は付記)
「千住金属工業発行の商品カタログには、フラックスの含有量を2ないし4wt%とする半田のみが掲載され、フラックスの含有量を2wt%未満とする半田は掲載されていないこと…、ウェブサイトへの投稿記事においても、フラックスの含有量は2ないし4%とされていること、株式会社ニホンゲンマは、過去においてもフラックス含有量を1%とする半田を製造したことはなく、そのような半田を製造すると、フラックスが入っていない不具合が発生することが危惧される旨回答していること、本件出願日の後に作成された電子メールにおいてではあるが、千住金属工業の従業員も、フラックスの含有量を1%とする半田は提供できない旨回答していることに照らすと、フラックスの含有量を1wt%とする半田は、本件出願日当時、やに入り半田の市場において普通に流通していなかったものと認めるのが相当である。
…本件発明1は、溶融前の半田片をノズルの内壁及び端子の先端に必ず当接させるとともに、溶融した半田片を必ず真球にならないまま端子の上に載った状態で下方に移動しないように停止させ、ノズルからの熱伝導等により半田片及び端子を十分に加熱し、これにより適正温度での半田付けを実現する結果、半田付け不良の防止という効果を奏するものである。これに対し、甲1には、ランドに接地した糸半田が貫通孔の周壁から輻射熱、伝導熱及び対流熱により加熱され、遜色なく溶解され、より的確な半田付けが可能になった旨の記載はみられるものの(段落【0023】及び【0042】)、溶融した半田が必ず真球にならないまま停止すること、すなわち、溶融後も半田がノズルの内壁に当接し続けることにより半田片及び端子が十分に加熱されることについての記載及び示唆はないから、甲1に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決しようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構成を得るためにフラックスの含有量が1wt%の半田をわざわざ採用しようとする動機付けはないものといわざるを得ない。」
3.本件のより詳細な説明、及び、判決内容の考察
3-1.本件特許について
本件特許は半田付け装置、及び、半田付け装置を用いて半田付けをする方法や、半田付けされた製品の製造方法などを発明の対象としている。
半田付けは、一般に何かと何かを接続して固定するときに利用される(義務教育の中で実際にやったことがある人も多いのではないでしょうか。注意しないと火傷しちゃうやつですね。)。半田付け装置を利用してある部品を特定の対象に接続したい場合、半田付けをしたい対象をセットし、ノズルから供給される半田を対象の所望の位置に付けて、部品をこの半田に付けた状態で、半田を溶融している状態から固める。これにより、半田を介して、部品が対象に固定される。
本件特許では、この半田付けにおける「部品」として端子Tが挙げられており、端子Tが接続される対象(接続対象)として、プリント基板PのランドRや端子Tに巻き付けられたコイルなどが挙げられている。ざっくりと理解するなら、半田付けによって端子Tを何かに接続させることを想定した発明である。(それくらいの理解でも、この判例の理解には困らないと思う)
本件特許の課題は、大量に行われる半田付け作業において、作業のバラツキによる半田付け不良の発生を防止することである。(本件特許の段落5及び7参照)
本件特許における発明の特徴は、半田付け装置におけるノズル24の構造にある(下図の引用図1の赤枠のあたり)。なお、ここからは図を参照しながら説明するため、分かり易さの観点から符号を付けて説明する。
前置きとして、ノズル24は、部品(端子T)及び接続対象Rに半田を付ける処理を行う部分である。また、この半田付け装置では、長く巻かれている糸半田2(引用図1の赤下線)を適当な長さにカットして、半田片2aにした状態でノズル24に投入する(引用図5参照)。そして、ノズルに24投入された半田片2aをヒータ36で加熱し、溶融状態にして、端子Tと接続対象Rに付着させ、接続する。
本件特許におけるノズルの特徴は、ノズル24内に部品である端子Tの先端が侵入した状態で、半田片2aの動きを制限させる構造になっている点にある。この構造は、半田片2aの動きを制限し、半田片2aが端子Tの先端には接触するが接続対象Rには接触しないようにしている。
加えて、ノズル24の構造に関するもう一つの特徴が(引用図6(B)参照)、ノズル内に投入された半田片2aが溶融状態において、表面張力により丸まって略球状になろうとするが、これを真球にさせないようになっている点である。
この2つの特徴を順に、特徴1、特徴2、と呼ぶことにする。特徴1に係る具体的な構造については、例えば本件特許の明細書段落56に、また、特徴2に係る具体的な構造については、例えば、本件特許の明細書段落59に記載がある。

本件特許の明細書 段落56を抜粋
「さらに、ノズル24の挿入部24aは、端子Tの側面Twと当該側面Twに対向するノズル24の内壁25の先端側25a(端子近傍領域)との間隔S1が溶融前の半田片2a最小幅である外径D1より短く形成されている。このため、溶融前の半田片2aは、溶融前の半田片2aの端子T側の端部が端子Tの先端Tsに当接して留まっている当接位置A Pからこれ以上ランドR側へ移動しないように規制されている。すなわち、先端側25aの内壁25は、ノズル24内に供給された溶融前の半田片2aの端子T側の端部2bを前記端子Tの先端Tsに当接させる当接位置規制手段として機能する。」
本件特許の明細書 段落59を一部抜粋
「溶融部24bのノズル24の内壁25は、この内壁25に囲まれた空間の中心軸に垂直な断面の最小幅である内径S2が、当接位置APで溶融し質量変化せずに真球状に変形したと仮定した場合の当該真球状の半田片2aの大円の直径(糸半田溶融球形の直径)より小さい大きさに形成されている。」
また、特徴1を具体的に実現するノズル24の構造についてはいくつかの実施例が記載されているが、本件特許の請求項に関するものは、図5及び図7と推察される(下図参照)。

このような特徴1及び2を備えることで、上記の課題を解決するわけだが、この点については、本件特許の明細書段落63~78の<半田付けの動作>にて説明されている。全てを抜粋すると長くなるので、ここでは、私の解釈が入ってしまうが、簡潔にまとめることにする。(明細書の記載をなるべく使っているが、それでも実際の出願人の見解と相違する点があるかもしれないので、そこはご了承いただきたい。)
<課題解決原理>
糸半田2をカットして得られた半田片2aがノズル24内に供給されると、上方から落下するように供給された半田片2aは、案内部24cを通過中に予熱され、端部2bが端子Tの先端Tsに当接して当接位置APで停止し、位置が規制される。
溶融前の半田片2aが当接位置APからこれ以上ランドR側へ移動できないことで、溶融前の半田片2aによってランドRと端子Tへの不均一な伝熱が生じることを防止でき、その後の溶融で綺麗なフィレット形状が形成されずに不完全な半田付けになることを防止できる。(特徴1の効果)
当接位置APに案内された溶融前の半田片2aは、端子Tと反対側の端部が、ヒータ3 6の近くに位置する溶融部24bの内壁25に当接し、熱伝導により溶融される。このとき、半田片2aは、表面張力により丸まって略球状になろうとするが、ノズル24の内壁25と端子Tの先端に規制されるため真球になれず(図6(B)参照)、端子Tの先端Tsに接触した状態で太く短い形状に変形する。(短い円柱の両端が球面になった形状)
この形状によって、半田片2aを介して、端子Tにノズル24からの直接の熱伝導による伝熱を加えることができ、端子Tを急速に加熱することができる。これにより、半田のぬれ性が向上し、バックフィレット形状BFが再現性よく綺麗に形成できる。(特徴2の効果)
加熱によって、端子Tが適正温度に達すると、溶融した半田片2aは、ぬれ始め、端子Tの先端Tsから側面Tw、裏面側のランドRb、さらに毛細管現象により、側面TwとランドRh、表面側のランドRfへと広がっていく。
その後、ノズル24の先端面24dをプリント基板Pの裏面側のランドRbの表面から離隔し、急速な冷却により、溶融した半田片2aが固化して半田付け動作は終了する。このような動きにより、端子TはランドRに確実に半田付けされ、その仕上がり外観は美しく、バックフィレット形状BFも綺麗に形成される。よって、精度の良い半田付けを実現でき、半田付け不良を防止することができる。
このような特徴1及び2を備える半田付け装置を具体的に表した請求項1が以下の通りである(分かり易さのため、括弧書きで符号を付記)。なお、特徴1に係る記載を赤字で、特徴2に係る記載を青字で記す。
なお、請求項2は、請求項1とほぼ同様の内容であり、請求項5~7は、請求項1または2の装置を用いた半田付け方法や、半田付け製品の製造方法の請求項であるため、ここでは記載を省略する。
【請求項1】
端子(T)と当該端子に電気的に接続される接続対象(R)とを半田付けする半田付け装置であって、
前記端子の少なくとも先端を挿入または近接する筒状のノズル(24)と、
前記ノズルの内側へ半田片(2a)を供給する半田片供給手段(53)と、
前記半田片を加熱溶融する加熱手段(36)と、
前記端子と前記ノズルとの近接離間方向の相対距離を変化させる相対距離変化手段(6)と、 前記ノズル内に供給された溶融前の前記半田片の前記端子側の端部を前記端子の先端に必ず当接させ、当該溶融前の半田片を前記接続対象に接触させずに前記ノズル内に留めるように規制する当接位置規制手段(25)を備え、
前記当接位置規制手段は、
前記端子の側面との間隔(S1)が溶融前の前記半田片の最小幅(D1)より短く形成された前記ノズルの内壁(25)、
または、
溶融前の前記半田片を前記溶融前の前記半田片の前記端子側の端部が前記端子の先端に当接する位置に所定の姿勢で案内し且つ案内方向に垂直な方向への前記半田片の移動範囲を規制する前記ノズルのノズル先端部(24a)よりも狭い前記ノズルの内壁、 により構成され、
前記加熱手段は、前記端子の先端に当接した前記半田片に前記ノズルを介して熱伝達させる位置に設けられ、溶融前の前記半田片が前記端子の先端に当接した状態で当該熱伝達を受けて溶融し、溶融した前記半田片が丸まって略球状になろうとするが前記ノズルの内壁と前記端子の先端に規制されるため必ず真球になれないまま前記端子の上に載った状態で前記半田片が供給された方向へ移動せずに停止し、この停止した状態で前記ノズルから前記溶融した半田片に伝わる熱を当該溶融した半田片から前記端子に伝えて前記端子を加熱し、この加熱によって前記端子が加熱された後に前記溶融した半田片が流れ出す構成である半田付け装置。
3-2.判決についての感想
全体的な結果について:納得度40%
本件では、進歩性の判断に仕方が適切であったかに疑問がある。個人的には、知財高裁の判断の結果、本来保護されるべき第三者の実施行為を不当に制限してしまっているように思える。この点について、以下で考察する。
知財高裁の判断について
無効審判における特許庁の判断ロジック
知財高裁の判断ロジックを振り返る前に、まず、無効審判における判断ロジックについて振り返る。実質的にアンド社の主張する進歩性欠如のロジックだと思うが、この判断ロジックは、個人的にはよく出来ていると思う。やや変化球ではあるが、こういった崩し方は、審査ではなく当事者系の無効審判ならではだと思う。
具体的には、主引例である甲1には、上述の本件特許の特徴1及び2については開示がなかった。特許庁は、請求項1に係る発明(以下、本件発明1と呼ぶ。)と甲1発明との相違点を、次のように認定している。
相違点1(特徴1に係る相違点)
当接位置規制手段が、本件発明1は「前記ノズル内に供給された溶融前の前記半田片の前記端子側の端部を前記端子の先端に必ず当接させ、当該溶融前の半田片を前記接続対象に接触させずに前記ノズル内に留めるように規制する」ものであるのに対し、甲1発明はその旨特定されていない点
相違点2(特徴2に係る相違点)
本件発明1は「前記加熱手段は、前記端子の先端に当接した前記半田片に前記ノズルを介して熱伝達させる位置に設けられ、溶融前の前記半田片が前記端子の先端に当接した状態で当該熱伝達を受けて溶融し、溶融した前記半田片が丸まって略球状になろうとするが前記ノズルの内壁と前記端子の先端に規制されるため必ず真球になれないまま前記端子の上に載った状態で前記半田片が供給された方向へ移動せずに停止し、この停止した状態で前記ノズルから前記溶融した半田片に伝わる熱を当該溶融した半田片から前記端子に伝えて前記端子を加熱し、この加熱によって前記端子が加熱された後に前記溶融した半田片が流れ出す構成である」のに対して、甲1発明はその旨特定されていない点
一方で、甲1には、段落29や、段落40及び41の実施例において、ノズル部分の具体的な寸法の開示があった。以下に明細書の記載を抜粋する。(下図も参照)

甲1の明細書段落29、並びに、段落40及び41の一部を抜粋
【0029】
半田鏝1の貫通孔2の径(d)は、一回の半田付けに必要な半田の量に応じて適宜定めればよいが、供給半田片の径より大きく、半田付けするピンの径より大きいことが必須である。例えばピンの外径が0.6mmであるとき、糸半田Wの直径を0.8mm、貫通孔2の内径(d)を1.2mm、糸半田Wの切断片(半田片)の長さを1.2mmに設定することで、半田片が貫通孔2内でピンや貫通孔側壁に接触して起立した状態となり、半田片全体が速やかに加熱される。従って、糸半田Wが無鉛半田であった場合でも、半田鏝先端部の下端温度を350℃とすれば、良好に半田付けをすることができる。
【実施例】
【0040】
…図2で示した形状で、窒化アルミニウム焼結体から形成される半田鏝を使用した。半田鏝の先端部の径(d)が1.0mm、(L)が5mm、後端部の径(D)が2.5mmであるものを準備した。半田片は径が0.8mmであり、半田長さが1.2mmである無鉛半田を準備した。
【0041】
半田付けの対象部品として、ランド径1.5mmに電子部品の端子銅線径0.6mmのものを準備し、半田付けを行った。…
そこでまず、この寸法から相違点1が満たされることを導いた。具体的に、特許庁は「相違点1に係る構成は、ノズルの径、端子の径、半田片の径及び長さでなし得るところ、甲1発明の半田鏝の先端部の貫通孔は径1.0mm、電子部品の端子銅線(ピン)は径0.6mmであるから、前記先端部の貫通孔の内壁と前記ピンの側面との隙間の間隔は合計で0.4mm、すなわち、半田鏝とピンとが左右方向にどのように位置ずれしても最大で0.4mmである。また、ピンの先端が、径1.0mmの前記半田鏝の先端部の貫通孔内に位置するのは明らかである。そして、径0.8mm、長さ1.2mmの半田片は、最大でも0.4mmしかない隙間へ進入し得ないことは明らかであるから、半田鏝とピンとが左右方向にどのように位置ずれしても、半田片は前記半田鏝の先端部の貫通孔内で前記ピンの先端に当接して留まる。以上のことより…相違点1は実質的な相違点ではない。」と述べている。
次に、相違点2についてであるが、ここでは、半田片のフラックス含有量が考慮された。なぜなら、甲1が「フラックスの飛散を防止する」ことを課題の一つに挙げており、甲1発明における半田がフラックスを含有するものを前提とすることから、揮発成分であるフラックスを除いた値まで溶融した半田片の体積が減少し、球形となったときの直径の大きさにも影響し得るためである。
相違点2に係る「真球になれない構造」は、球形となった場合の直径よりも半田片が配置される位置におけるノズルの内径の方が小さい構造であればよいため、甲1の実施例におけるノズルの内径が固定値である以上は、半田片の直径が大きければ相違点2を満たしやすく、半田片の直径が小さければ相違点2を満たしにくいことになる。
そのため、フラックス含有量が多いほど、球形となったときの直径の減少効果は大きくなり、特許権者有利となる。逆に、フラックス含有量が少ないほど、球形となったときの直径の減少効果は小さいため、無効請求人有利となる。
そこで、特許庁は、甲10の「日本工業規格 JIS 3283:2006 やに入りはんだ」の以下の記載から、フラックス含有量が1wt%程度の半田を用い半田付けを行うことは当業者が容易になし得たことと認め、この場合に、相違点2を満たすかどうかを検討した。
甲10「日本工業規格 やに入りはんだ」に関する内容(判決より抜粋)
やに入り半田のフラックス含有量は、…表3による。
表3―フラックス含有量 単位 %(質量分率)
記号 フラックス含有量 許容範囲
F1 1.0 0.5以上1.5未満
F2 2.0 1.5以上2.5未満
F3 3.0 2.5以上3.5未満
F4 4.0 3.5以上4.5未満
F5 5.0 4.5以上5.5未満
F6 6.0 5.5以上6.5未満
相違点2に関する特許庁の判断(判決より抜粋 下線は付記)
「令和2年11月16日に提出された原告の回答書と同様の計算をすると、半田の比重は7.4、フラックスの比重は1.06であるから、100gの半田片における半田の体積は13.378cm3(99÷7.4)、フラックスの体積は0.943cm3(1÷1.06)で、半田片全体の体積は14.321cm3(13.378+0.943)となり、フラックス含有量1wt%の半田片におけるフラックスの体積の割合は6.58%(0.943÷14.321×100)、半田の体積の割合は93.42%(100-6.58)である。そうすると、甲1発明において半田片は径0.8mm、長さ1.2mmの円柱であるから、π×(0.8÷2)2×1.2より求めた円柱の体積の93.42%と同じ体積の球の直径を4÷3×π×(直径÷2)3により求めると、前記半田片が溶融し球となった場合の半田の直径は、約1.025mmである。ここで、甲1発明の半田片が溶融する半田鏝の先端部の貫通孔内壁の径は1.0mmであるから、半田片が溶融し球となった場合の半田の直径は半田鏝の先端部の貫通孔内壁の径より大きい。
なお、記号F1として定められた規格の上限であるフラックス含有量1.5質量%の半田片を用いた場合においても、球となった半田の直径は、約1.014mmであり、半田鏝の先端部の貫通孔内壁の径より大きい。
よって、甲1発明に、規格でF1と定められた半田を使用することにより、半田片が当接位置で加熱溶融され溶融した場合に半田鏝の先端部の貫通孔の内壁とピンの先端に規制されるために真球になれない。」
本件における知財高裁の判断ロジック
知財高裁は、本件において、以下の判断ロジックで結論を導いた。
まず、1wt%のフラックス含有量のはんだを用いた場合に、相違点2が導かれることについては、両当事者及び知財高裁において、特に異論はないように思われる。そのことは、判決で「甲1発明においてフラックス含有量が1.0wt%の半田片を用いた場合、半田片が溶融し球となった場合の半田の直径は半田ごての先端部の貫通孔内壁の径より大きくなるから、溶融した半田は真球になれない旨判断したところ、原告も、甲1の実施例1に関しては、この判断を強く争うものではない」と述べられていることからも窺われる。
その上で、知財高裁は、本件出願日当時の当業者が甲1発明においてフラックス含有量が1.0wt%の半田片を用いることを容易になし得なかったと判断した。
まず、知財高裁は、半田メーカーの商品カタログにおけるフラックス含有量の表示(甲16)、サイトの投稿記事の内容(甲37)、メーカーに問い合わせてフラックス含有量1wt%の半田の用意がない旨の回答を得たこと(甲41)、参考書の記載(甲42)、及び、メーカーにおいてフラックス含有量1wt%の半田を製造しない理由(甲45)などから、「フラックスの含有量を1wt%とする半田は、本件出願日当時、やに入り半田の市場において普通に流通していなかったものと認めるのが相当である。」と判断した。
さらに、知財高裁は、本件発明1が「半田付け不良の防止」という効果を奏するものであるのに対し、甲1には、溶融した半田が必ず真球にならないまま停止し、溶融後も半田がノズルの内壁に当接し続けることで半田片及び端子が十分に加熱されることについての記載及び示唆はないため、甲1に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決しようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構成を得るためにフラックスの含有量が1wt%の半田をわざわざ採用しようとする動機付けはないものといわざるを得ない、と判断した。また、知財高裁はさらに「なお、証拠(甲39)及び弁論の全趣旨によると、フラックスの含有量が小さい半田を用いると、半田付け不良の原因になるものと認められる。」とも述べている。
本件の判断ロジックに関連する進歩性判断の論点
上述したように、知財高裁は、甲1には、半田が真球にならないことから得られる作用効果についての記載も示唆もないのであるから、わざわざ(市場に出回っていない)フラックス含有量1wt%の半田を採用するような動機付けはないと判断したものと解することができる。なお、動機付けの結論において、市場に出回っていないことは直接的には触れられていないが、「わざわざ」という言葉を付けているのは、この事実が影響しているからと推察される。
そこで、このような進歩性判断の是非についてを論じる前に、まず、2つの論点についての考えを述べたい。一つ目は「①進歩性の論理付けの判断において、引用発明は、本件発明に至った思考プロセス(発明に想到するまでの因果経路)と同様の思考プロセスを辿る必要があるか」という論点であり、二つ目は「②本件発明に想到するための技術や物が出願日当時に市場に出回っていないことから直ちに進歩性を肯定する根拠となるか」という論点である。なお、この二つの議題は、知財高裁がこのように判断したと思っているわけではなく、この後の考察をしやすくするための思考整理と思っていただきたい。
本件発明に想到するのに、本件発明と同様の思考プロセスを辿る必要があるか
まず、進歩性という基準が何のために設けられているかを考えるべきである。考え方としては、発明者が発明をした行為を尊重するという発明者保護の考え方と、発明者の創作した発明を評価するという発明保護の考え方を挙げることができる。
前者の発明者保護を重視する立場からは、進歩性は発明者が発明をするに至るまでの行為に一定以上の技術的進歩があるかを判断し、その観点で発明を保護することを重要視するだろう。そうすると、重要なのは、発明者がその発明の創出に至るまでの技術的な思考プロセスであり、進歩性の判断においても、この思考プロセスが十分に検討されることになる。
例えば、異なる思考プロセスで同じ発明に到達した場合に、いずれの思考プロセスにも 一定以上の技術的進歩があり、産業の発達に資するといえる場合には、両方の発明が尊重され、保護されるということになるだろう。このとき、ダブルパテントの問題が出てくるが、権利範囲(技術的範囲)の解釈において、これらの思考プロセスの違いから境界を引くことで、一応はこの問題を解消することができる。
次に、後者の発明保護を重視する立場からは、客観的な視点で発明の技術的進歩を評価することが重要視されるだろう。そのため、進歩性は、当業者である第三者を基準とし、発明者による発明が、その当時に当業者が考え付く一定範囲内の技術的進歩を超えているかを判断し。、その観点で発明を保護することを重要視するだろう。そうすると、重要なのは、当業者が、その当時の技術知識に基づき一定範囲内の技術的進歩で、発明者の発明と同様の発明に想到できたか否かであり、必ずしも発明者と同じ思考プロセスを辿る必要はない。
例えば、当業者が技術常識から得られる他の思考プロセスで本件発明と同じ発明に想到した場合には、本件発明は保護の対象から外れることになるだろう。
我が国の特許法が進歩性においてどちらの考えを重視しているか。その答えは逐条解説にはっきりと現れているように思われる。
逐条解説(第21版)より抜粋 特許法第29条第2項について
二項は新しく設けられた規定で、いわゆる発明の進歩性(inventive step)に関するものである。規定の趣旨は、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利(特許権)を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。
このように、逐条解説によれば、29条2項の進歩性の規定は「通常の人が容易に思いつくような発明」に権利が与えないようにする趣旨で設けられており、これは、後者の発明保護を重要視する考えに沿っていると言える。
従って、進歩性判断において、引用発明に基づき本件発明に容易に想到することの論理付けを考える際には、必ずしも本件特許の明細書から理解される本件発明に至るまでの思考プロセスを辿る必要はないはずであるというのが、私の考えである。
出願日当時に市場に出回っていないことが直ちに進歩性を肯定する根拠となるか
ここでは、発明の本質は、技術にあるか、あるいは、技術思想にあるか、という点に触れたい。
上述したように、進歩性の判断においては、発明者個人の思考プロセスといった主観面からではなく、当業者の視点という客観面から発明を評価し、特許として保護するだけの価値があるか否かを判断するのが、法の趣旨に適っているように思われる。この点で、思想よりも客観的にその発明が備えている技術が、発明の本質にあるようにも思える。
しかしこれは、よくよく考えると、発明の本質をどう捉えるかとは別の話である。
特許法2条1項は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義している。このような発明そのものの定義を鑑みれば、発明の本質は、「技術思想」であり、必ずしも具体的な技術である必要はなく、技術思想の創作としての具体性が備わっていればよいと考えるべきではないか。
そして、このように考えると、発明は、必ずしも具体的に存在する「技術」だけで構成されなくてもよく、技術的な「思想」に基づいて創作しても成立し得るということになる。
では、上述の進歩性の判断において、思想よりもその結果物が重要視されることとの不整合が生じるか。
思うに、発明の本質とは、平たく言えば発明をどのように捉えるべきかという話なのだから、これは、進歩性判断における「発明の認定」(本願発明の認定および引用発明の認定)で重要視される事柄のはずである。そして、このようにして本件発明及び引用発明が認定された後の「論理付け」の判断においては、これらの発明を客観的に比較して、そこに特許として保護するだけの技術的進歩があるかを判断すればよく、このようにして考えれば、特許法2条1項の発明の定義と特許法29条2項の進歩性の趣旨との間に不整合も生じないといえそうである。
従って、引用発明の認定において、出願日当時に市場に流通していなかった技術をその対象から外す必要はなく、あくまで、技術思想の創作として成立するならば対象に含めるべきである。そして、出願日当時に市場に流通していなかったという事実は、論理付けを行う際に、進歩性を肯定する方向に働く事情として考慮すればよいはずである。
本件における知財高裁の判断について
今一度、知財高裁の判断を振り返ってみる。
知財高裁は、「甲1に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決しようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構成を得るためにフラックスの含有量が1wt%の半田をわざわざ採用しようとする動機付けはないものといわざるを得ない。」と判断している。
つまり、知財高裁は甲1発明に相違点2を組み合わせることに想到するには(少なくとも当業者がその動機付けを得るには)、本願発明に記載される課題や作用効果を知っている必要がある、と判断していることになる。
このような知財高裁の判断は何を根拠としているのか。
判決には、この判断の前に「甲1には、…旨の記載はみられるものの(段落【0023】及び【0042】)、溶融した半田が必ず真球にならないまま停止すること、すなわち、溶融後も半田がノズルの内壁に当接し続けることにより半田片及び端子が十分に加熱されることについての記載及び示唆はないから」と記載されている。
この文章の流れからすると、知財高裁は、「甲1に課題や作用効果の記載や示唆がない」という事実から、甲1に相違点2を採用するには、本件発明に記載される課題や作用効果を知っている必要がある」と判断したと考えることができる。
しかし、これは明らかに論理が飛躍していないだろうか。
本件発明に記載される課題や効果が引例に記載も示唆もないなら、進歩性を否定するには本件発明に記載される課題や効果を知る必要がある、というのは結局、引用文献に本件発明と同様の思考プロセスの記載や示唆があることを必須の要件としていることに等しい。
しかしながら、このような考え方は、上述したように、逐条解説に記載されている進歩性の趣旨とは反対方向を向いている。私は、今回の判決に見られる知財高裁の判断ロジックは適切なものとはいえず、進歩性についての法令の解釈に関する重要な事項を含むものとして、上告受理の申立理由になり得るのではないかと思う。
フラックス含有量1wt%のはんだを採用する動機
本件発明に想到するには本件特許に記載されている課題や作用効果を知らなければならないと判断するのに、本件特許をその根拠となる証拠に用いてはならないだろう。なぜなら、出願前に公然に知られていない本件特許の記載を根拠とすることは、まさに後知恵といえるからである。
一方で、本件特許の審査において、本件特許ではない証拠から事実を認定し、その事実を踏まえれば、本件発明に想到するのに本件特許と同様の思考プロセスが必要であると判断することは差し支えないだろう。なぜならそれは、認定された事実を評価しているに過ぎず、本件発明と認定された事実との関係から、本件発明に想到するための要件を判断しているといえるためである。(但し、裏を返せば、認定される事実には、本件発明に想到するのに本件特許と同様の思考プロセスが必要であるといえるだけの、説得力のある事実でなければならないはずである。)
ここで、一つの可能性について考察する。
知財高裁は、上述したように「甲1には課題や作用効果の記載及び示唆がない」ということだけを根拠としているのではなく、さらに「出願日当時、相違点2に係るフラックス含有量1wt%の半田は市場に流通していなかった」という事実も、判断の根拠に取り入れているという可能性である。
なお、なぜこれが「可能性」であるかというと、本件の判決には、知財高裁がこの事実を認定したというところまでは記載されているが、実際に、この事実が進歩性判断にどのように影響したかは直接的な記載がないからである。(事実認定だけしつつ、動機付けの判断においてこの事実を考慮しているかどうかが不明であり、この判決文はやや消化不良である。)
それでは、「出願日当時、相違点2に係るフラックス含有量1wt%の半田は市場に流通していなかった」という事実から、「甲1に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決しようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らずに」本件発明に想到する、つまり、甲1発明にフラックス含有量1wt%の半田を採用する動機付けはない、といえるか。
個人的には、この論理付けも不十分なように感じる。
そもそもフラックス含有量1wt%の半田は日本工業規格に示されている。規格が、その分野において全く不要な規定を設けるだろうか。規格というのは、通常、無関係の人間が決めるのではなく、それに関わる当業者の知見を踏まえて制定されるものである。それならば、規格に示されているということは、少なくとも、その技術分野において可能性としてはあり得る技術であるとの推定が働くのではないだろうか。
つまり、当業者において、フラックス含有量1wt%の半田を用いるという技術は、出願日当時に現実に存在してはいなくても、技術思想としては存在していたといえ、発明が技術思想の創作であるならば、技術的な阻害要因がない限りは、当業者において、ある先行発明に、フラックス含有量1wt%の半田を用いるという技術を採用する動機付けはあるように思える。
では、「出願日当時、相違点2に係るフラックス含有量1wt%の半田は市場に流通していなかった」という事実がこの動機付けを阻害するかというと、この事実だけで動機付けが阻害されるというのは、発明が技術思想の創作であるという前提に矛盾するのである。
加えて、「日本工業規格には規定されているが、出願日当時、市場に流通していなかった」という事実と、その市場に流通していなかった技術(フラックス含有量1wt%の半田)を採用するために「溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決しようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知っている必要がある」という判断には、特に因果性が見つからない。
例えば、フラックス含有量1wt%の半田には、大きな技術課題があり、当業者においてこれが利用されることは通常想定されないといえるのであれば、出願日当時にフラックス含有量1wt%の半田が市場に流通していなかったという事実は、この主張の補強証拠になるだろう。しかしながら、そのような主張は特になされていない。
資本主義社会において、市場に物が流通するのは一定以上の需要があるからで、ある時点においてその物が市場に存在していないといっても、技術的に作れないからとは限らない。市場に流通しない理由が技術的に困難だからなのか、技術的には可能だが需要がないから作らないだけなのかという違いは、当業者においてその技術の採用が容易であったか否かにも影響を与える事柄であり、その意味でも、単に市場に流通していなかったという事実認定だけでは結論を導くには不十分であり、より深い議論が必要ではなかったのかと思う。
それでは、甲1文献において、フラックス含有量1wt%の半田の採用を阻害するような事情が認められるか。
甲1は、フラックスの飛散を防止するとともに、詰まりの生じにくい半田鏝を提供することを課題とする発明を開示している。また、これらの課題のうち、フラックス飛散の防止に関しては、例えば、明細書段落6に以下の記載がある。
甲1明細書の段落6を抜粋 (下線は付記)
「この半田鏝によれば、鏝の軸方向に貫通孔があり、半田鏝の両端が開口しているので、この鏝をランドの上に立てて、一回の半田付けに必要な長さに切断した糸半田を鏝の後端から投入すれば、先端まで落下してランドやピンに接する。そして、鏝の先端部で半田を溶融させることにより、ピンやワイヤなどの相手側端子が一定量の半田で接合される。半田付け部が半田鏝の貫通孔で囲まれているので、溶融半田やフラックスが周囲に飛散することはなく、しかも溶融半田が均等に回り込むことができる。また、半田鏝の先端部が半田に対して濡れにくい材料( セラミック、ステンレス、チタン又はクロム) で形成されているので、貫通孔の内面に半田が付着することがほとんどなく、貫通孔の半田詰まりを抑制できる。その結果、供給半田の定量性が維持されるとともに、接合後のピンの外観がきれいに仕上がる。」
このように、甲1発明において、フラックス飛散の防止は、半田鏝の貫通孔内で、半田の溶融が行われ、半田付けがされることで達成され、半田詰まりは材料の選定によって達成されるものと理解できる。
そして、貫通孔内で半田が溶融されることがフラックス飛散の防止になるのであれば、フラックス含有量がいくらであるかは影響しないはずである。言い換えれば、使用する半田においてフラックス含有量がいくつであろうとも、フラックス飛散の防止の効果が得られることは容易に理解できることだと思う。
知財高裁は、「フラックスの含有量が小さい半田を用いると、半田付け不良の原因になるものと認められる。」と述べているが、甲1発明は、半田付け不良(半田詰まり)を材料の選定によって解決しようとするものであるから、フラックスの含有量が甲1発明を阻害するとは思えない。フラックスの含有量が1wt%の半田を用いると甲1発明の効果が生じないというならともかく、フラックスの含有量が1wt%の半田であっても発明の効果が得られるのであればフラックスの含有量が1wt%の半田だけが阻害される理由にはならず、むしろ半田付け不良を起こしやすいフラックスの含有量が1wt%の半田にこそ積極的に甲1発明の効果が表れるかもしれない。
本判決が抱える問題
本件発明は一旦忘れて、甲1発明及び日本工業規格が公知となっている状態で、甲1発明に、一般に使用されるフラックス含有量2%~4%の半田ではなく、フラックス含有量1%の半田を使用することを特定した発明(以下、甲1+α発明と呼ぶ。)が出願された場合を考えてみる。
果たしてこの出願に特許を認めてもよいだろうか。
例えば、この出願の出願人が、「出願日当時、フラックス含有量1wt%の半田は市場に流通していなかったから、たとえ日本工業規格に当該半田が示されていたとしても、甲1+α発明には進歩性がある」と主張したとして、この主張が容れられるだろうか。
個人的には認められないと思う。なぜならば、これを認めてしまうと、既に周知となっている発明を、市場に流通していない材料や含有量などの成分比によって限定することで特許性を満たすことになり、そのような出願が横行すれば、純粋かつ健全な発明行為が阻害され、産業の発達を妨げると思うからである。
本件発明と、甲1+α発明が、そこに至るまでの思考プロセスを異にするものであったとしても、少なくとも、進歩性の基準が、第三者が容易に思いつくような発明まで特許権によって実施が制限されることを防ぐ趣旨であるならば、私は、第三者における甲1+α発明の自由な実施が保護されない結末(本件の知財高裁の判断)は、避けるべきだったと思う。
別の着地点
理想的には、本件発明1から、甲1+α発明との重複部分を除く形で、本件発明が限定しておくべきだったのではないかと思う。但し、本件発明1においてそれが可能かどうかは疑問である。
もっとも簡単な対処は、本件発明1における半田が、フラックス含有量2%以上の半田であることに限定することであるが、このような限定は、新規事項の追加になる危険がある。
しかし、パラット社の主張する「通常は、フラックス含有量が2%以上の半田しか使わない」という事実が真であるなら、このような記載は当業者において当たり前であるがゆえにわざわざ明細書に記載されなくても理解される事項であり、ソルダーレジスト事件の法理からしても、新規事項の追加とならない可能性は十分にあると思う。
疑問点
最後に一つだけ、わからない点がある。
本件発明1は、無効審判において「溶融した前記半田片が丸まって略球状になろうとするが前記ノズルの内壁と前記端子の先端に規制されるため必ず真球になれないまま前記端子の上に載った状態で前記半田片が供給された方向へ移動せずに停止し、」として、それまでなかった「必ず」を追記する訂正がされた。
この訂正の適否に関し、特許庁は、「本件特許明細書の段落【0059】に「溶融部24bのノズル24の内壁25は、この内壁25に囲まれた空間の中心軸に垂直な断面の最小幅である内径S2が、当接位置APで溶融し質量変化せずに真球状に変形したと仮定した場合の当該真球状の半田片2aの大円の直径(糸半田溶融球形の直径)より小さい大きさに形成されている。」と記載され、また、段落【0069】に「半田片2aは、溶融すると表面張力により丸まって略球状になろうとするが、溶融部24bのノズル24の内壁25と端子Tの先端に規制されるため真球になれず、図6(B)の端面図に示すように、端子Tの先端Tsに接触している状態で太く短い形状に変形する。」と、溶融した半田片は規制され真球になれないことが記載されており、本件特許明細書には、溶融した半田片が必ず真球になれないことが記載されている。よって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。」として、訂正を認めた。
これによれば、「必ず真球になれないまま」とするための具体的な構造を示す根拠が「ノズル24の内径S2が、質量変化せずに真球状に変形したと仮定した場合の当該真球状の半田片2aの大円の直径(糸半田溶融球形の直径)より小さい大きさに形成されている」ことにあると言える。
そうすると、本件発明1における半田が「溶融状態になっても質量変化をしない」半田であることは必須なのではないかと思ったが、この点は争われていない。(なお、本件明細書には、どこにも「必ず真球になれない」とは記載されておらず、単に「真球になれない」と記載されるのみである。)
また、この点は措くとしても、本件発明1が、「質量変化せずに真球状に変形したと仮定した場合の当該真球状の半田片2aの大円の直径」を基準として、ノズル24の内径S2の大きさを決定すればよい発明なのであるなら、甲1発明に適用される半田を考えるときにもフラックス含有量を考慮する必要はあったのだろうかという疑問がある。
本件発明1においては、フラックスを含有する半田片であっても、質量変化しないと仮定したときの直径より小さければいいのだから、なぜ甲1発明の方だけ条件が厳しくなっているのかがわからなかった。(フラックスを含有することで質量変化した場合の直径より小さくなくてもよく、その場合は真球になり得るのではという疑問もある) フラックスが半田溶融時に揮発するのであれば、溶融前と溶融後で、半田片の質量は変化するのではと思っているが、この考え自体がおかしいのだろうか。ここでいう質量変化とは何かがわからないことがやや歯がゆい。

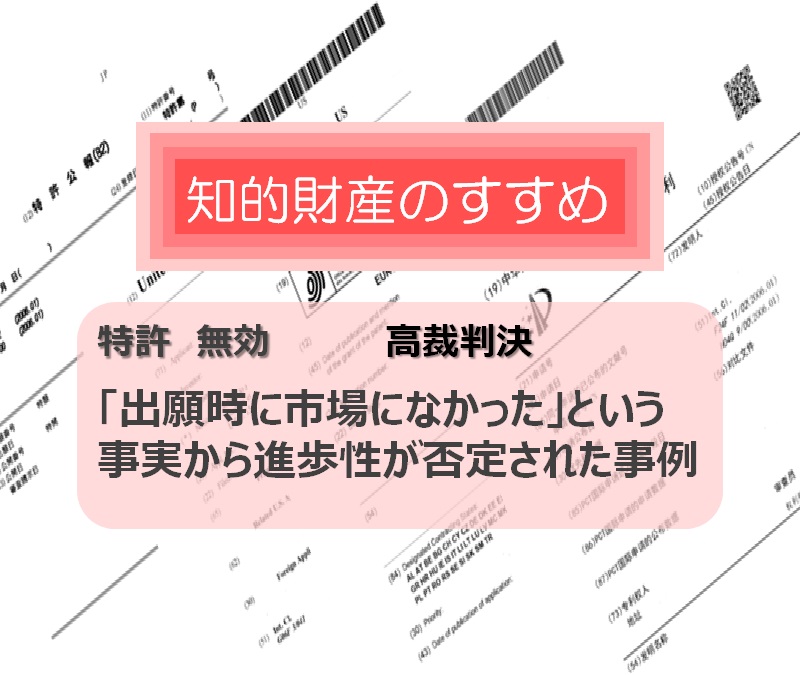


コメント