「誤記の訂正」の判断基準を示した事例
2025/1/15判決言渡 判決文リンク
#特許 #補正/訂正 #誤記の訂正
1.実務への活かし
・権利化/無効化 #補正/訂正 #誤記の訂正
誤記の訂正が適法といえるか否かの判断は、第一に「不整合が生じている記載が存在することが明らかといえるか」を検討し、次に「当業者がその不整合記載は誤記であると認識するか」を検討し、誤記であると認識するといえる場合に、「当業者において、訂正内容を一意に導くことができるか」を検討するとよい。
(「第一要件:不整合記載の存在確実性」→「第二要件:不整合記載が誤記であるとの認識」→「第三要件:誤記と認識できる場合には、訂正内容の一意性」の順に判断する)
2.概要
本件は、特許第第4960929号(以下、「本件特許」という。)の特許権者であるXが、ヤマハ発動機株式会社(以下、「ヤマハ」という。)に対し、不法行為又は不当利得に基づき一部請求として1億円の支払を請求した事案であり、原審の地裁判決において、特許無効の抗弁(サポート要件違反)が容れられたことにより請求が棄却された事件の控訴審である。
本件でXは、「誤記の訂正」を目的として、本件特許の明細書(以下、「本件明細書」という。)に記載された「Ψ」を角加速度を表す記号「Ψ’」へと訂正することを請求した。Xの主張する誤記訂正の根拠は、本件明細書に記載された式A「Ghosei=Gken-(Ψ・Rhsen)」が物理学上意味をなさない式となっていることにあった。
原審は、本件特許の課題が「車両の走行状態での正確な横Gを検出すること」にあるところ、本件明細書において、式Aの他に、センサーによる測定値を基に「正確な横G」を算出する方法についての記載はなく、この式Aが物理学上明らかに意味を持たない式であることを主な要因として、サポート要件違反と判断していた。
本件知財高裁も、原審と同様に、Xの請求する「誤記の訂正」を認めなかったが、本件で知財高裁は、「誤記の訂正」について、以下のように述べた。
「(ア) 特許がされた特許請求の範囲、明細書又は図面における訂正について、特許法126条1項ただし書2号は、「誤記又は誤訳の訂正」を目的とする場合には、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが、ここで「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載全体から客観的に明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解され、特許法134条の2第1項ただし書2号の「誤記又は誤訳の訂正」も同様に解される。
したがって、明細書等の記載について、物理学上意味をなさないことが客観的に明らかであることが認識できたとしても、物理学上意味をなさないことの一事をもって、ただちに同号の「誤記」と認められるわけではなく、当該物理学上意味をなさない記載について訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければ、同号の「誤記」とは認められないと解するのが相当である。」
その上で知財高裁は、本件明細書において誤記の訂正が認められないことについて、以下のように判断した。
知財高裁の判断(判決より抜粋)
「本件特許権に係る特許請求の範囲及び本件明細書の記載は、傾斜角加速度は傾斜角速度の時間微分で得られるという認識の下、両者を明確に区別した上で、「加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法」について、加速度の次元の物理量である実際の走行傾斜時に検出される検出横G(Gken)から、速度の次元の物理量である傾斜角速度(Ψ)にセンサー取付け高さRhsenを乗じた値を減算することで終始一貫していると認められる。
そうすると、本件明細書等に記載された「加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法」について、当業者は本件明細書に物理学上意味をなさない導出方法が記載されていることを理解するにとどまり、角速度Ψを角加速度Ψ’の趣旨に理解するのが当然であるとまでは認められない。」
3.雑感及び考察
全体的な結果について:納得度100%
本件は、事案そのものは複雑なものではなく、裁判所のした判断も妥当なものといえるだろう。本件の特許権者であるXは、サポート要件解消のために、請求項の記載を直すのではなく、明細書の記載を直そうとした。
本判決の意義は、知財高裁が、「誤記の訂正」が認められるための要件についての解釈を述べた点にある。
なお、本件では、特許法126条1項ただし書2号及び134条の2第1項ただし書2号の「誤記または誤訳の訂正」について述べられている。これらの規定は、訂正の対象として、明細書、特許請求の範囲又は図面を挙げており、本件では、明細書の訂正が判断された。
一方で、特許法17条の2第5項第3号にも「誤記の訂正」は挙げられているが、同項の規定が対象としているのは、特許請求の範囲のみであり、明細書の誤記訂正を行った本件の射程が気になるところではあるが、知財高裁の判断は、特許請求の範囲にも当てはまる内容であることからすると、17条の2第5項第3号の「誤記の訂正」にも当てはまるものと考えてもよいように思える。
知財高裁は、「「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載全体から客観的に明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解され」ると述べた。
実のところ、この記載だけでは、内容がやや観念的であり、具体的に実務に活かせるレベルにまで具体化することは難しいように思う。訂正前が間違いで訂正語が正しいことが明らかでなければならないというのは、ある意味で当たり前のことを述べているに過ぎず、この結論を導くためにどのように判断するかについては定かではない。
本件において、真に価値のある記載は、その先の内容である。
「明細書等の記載について、物理学上意味をなさないことが客観的に明らかであることが認識できたとしても、物理学上意味をなさないことの一事をもって、ただちに同号の「誤記」と認められるわけではなく、当該物理学上意味をなさない記載について訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければ、同号の「誤記」とは認められないと解するのが相当である」
これを分析してみると、「物理学上意味をなさないことが客観的に明らかであることが認識できたとしても」との記載は、そこに不整合が存在することが明らかに認識できること、つまりは「不整合記載の存在確実性」が認められることと置き換えることができる。
また、「当該物理学上意味をなさない記載について訂正後の趣旨に理解するのが当然である」というのは、いわば、訂正内容が一意に導かれること(「訂正内容の一意性」)ということができる。
つまり、「誤記の訂正」が認められるには、明らかに不整合を生じさせる記載が存在しているだけでは足りず、当業者が合理的に導くことのできる訂正内容が複数存在せず、およそ一つに定まる必要がある(不整合記載の存在確実性と訂正内容の一意性の両立)、というのが裁判所の考えと推察できるだろう。我々実務家も、「誤記の訂正」の適否を争う場合には、この二つの要件を意識して主張を展開するとよいということになる(が、これが考察の結論ではないので、誤解のないよう最後まで読んでいただきたい)。
なお、不整合記載の存在確実性と訂正内容の一意性を要件とする考え方は、欧州の誤記訂正の考え方に非常によく似ている。ただし、訂正内容の一意性をどこまで厳しく判断するかによって考え方には差が生じる。欧州における「訂正内容の一意性」はそれなりに厳格に判断されている。
例えば、明細書に「構成Aの重量は2kgである」という記載と「構成Aの重量は5kgである」という記載があったとする。これらは両立しないため、少なくとも不整合を生じさせる記載が存在していることは明らかである。
それでは、「構成Aの重量は3kgである」という訂正ができるかといえばこれは認められない。また、明細書の記載全体からして、構成Aは2kgでもあり得るし、5kgでもあり得るという場合も、どちらか一方に導けるわけではないため、どちらか一方に揃える誤記訂正も認められないということになる。
当業者が「2kgは誤記であり5kgが正しい」と疑いなく理解できる場合に、「構成Aの重量は2kgである」との記載を「構成Aの重量は5kgである」という記載に訂正することが認められる。
また、こういった数値の誤記もあるが、同様に多くみられるのが、単位系の違いである。明細書において、一方では「mm」で記載し、他方では「m」で記載するといった場合にも、誤記訂正が争点となり得る。
さて、本件について踏み込んでみよう。
本件では、補正された横Gの導出方法として明細書に説明されている式A「Ghosei=Gken-(Ψ・Rhsen)」が物理学上意味を成さないこと、つまり、明細書の記載内容において、当業者の理解において不整合が生じていることについては認めている。(Ghoseiが加速度の次元の物理量であり、Ψが角速度の次元の物理量であるためである。(Rhsenはセンサー取り付け高さ))
一方で、知財高裁は「補正後の横G(Ghosei)の導出方法」について、加速度の次元の物理量である実際の走行傾斜時に検出される検出横G(Gken)から、速度の次元の物理量である傾斜角速度(Ψ)にセンサー取付け高さRhsenを乗じた値を減算することで終始一貫していると認められるため、角速度Ψを角加速度Ψ’の趣旨に理解するのが当然であるとまでは認められない」と判断している。
この知財高裁の判断は、実は、前審の地裁判決(令和5年(ワ)第70114号 東京地裁民事46部)と大きく異なっている。
地裁判決では「式Aについて、原告が主張するとおりの誤記であると理解すれば、減算される物理量の次元が異なるという問題については解消される。しかし、次元を整える目的のみであれば、その訂正の方法は式A´とすることに限られるものではないのであり、他に解消方法を考え得る…。そうすると、式Aの記載のみから、どのような誤記であるかのかが一義的に定まるものであるとはいえない。…原告が主張する訂正をすると同記載部分の趣旨が理解できなくなってしまう。…そのような本件明細書について、当該式を訂正すると別の部分と矛盾が生じる内容になっている。これらからすると、当業者は、本件明細書に記載の誤りがあることを理解するとしても、本件明細書において、本来どのようなことが記載されようとしていたのかや、どの部分がどのような誤記であるかを理解することができるとは認められない。」と述べた上で、次のように結論した。
「以上のとおり、当業者は、式Aに…何らかの誤りがあることは理解できるものの、…問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、…式A´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。…さらに、訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。本件明細書の記載から、式Aが式A´の誤記であると理解できるとはいえない。」
このように、前審の地裁判決では、むしろ、本件知財高裁が示した「訂正内容の一意性」の要件の字義に忠実に判断をしている。訂正方法はXの主張する方法一つではなく、また、その方法は別の不整合を生じさせる。よって、当業者が、Xの主張する訂正以外の訂正方法はないと理解できるとは認められない、と根拠を積み上げている。
これと比べると、本件知財高裁の判断(考え方)の違いは顕著になるのではないか。
本件で知財高裁は、他の訂正方法が考えられるといった事実を判断の根拠に挙げていない。本件知財高裁が向き合ったのは「果たしてこの不整合記載は誤記なのか」という点ではなかったかと思う。
明細書に不整合が見られたときに、そこから直ちにその記載が「誤記」であると認定するべきではない。なぜならば、「発明者自身による間違い(思い違い)」という可能性もあるからである。
つまり、客観的(当業者)には間違っていると認識できるのだが、発明者がその間違いを正しいと思い込んで発明を記載している場合、後にその間違いが判明したとして、当業者が正しい内容を認識できるからといって「誤記の訂正」を認めてよいか、という問題がある。
当業者の視点から客観的に正解を導けたとしても、そもそも発明の適切な開示義務は発明者側にあるのであって、発明者が「間違った発明」を開示しておきながら、これが(発明者よりも優秀な)当業者の助けによって権利化されるとなれば、理論的には、出願時に発明者が開示していなかった発明に特許権を与える、という結果になるのである。このような帰結は、先願主義や公開代償といった基本的な特許法の原則にも抵触しかねず、認めるべきではない。
本件知財高裁は「本件明細書の記載における式Aは、物理学上意味をなさないものであるが、各パラメータについてその意味を誤解することなく、その上で、「物理学上間違った説明」が終始一貫してなされている」という理由から、原審のように他の訂正方法があるといった事情は持ち出さず、当業者の理解は「物理学上意味をなさない導出方法が記載されている」という程度にとどまる、と判断しているのである。
この知財高裁の意図は、当業者において「この発明者は間違って発明を認識しており、この説明は間違っている」と認識するというべきであり、「この発明者は正しい発明を認識しており、その上で間違えた説明を記載してしまっている」とは認識しない、ということではないかと推察できる。
そうすると、本件知財高裁は、その判断基準において「不整合記載の存在確実性」と「訂正内容の一意性」という二つの要件を挙げつつも、実質的には、第三の要件「不整合記載が誤記であるとの認識」によって、本件を処理した(結論を導いた)と分析することができよう。
そして、知財高裁が「訂正内容の一意性」に踏み込まずに結論を出したことからすると、本件知財高裁は「不整合記載が誤記であるとの認識」の要件は「訂正内容の一意性」の要件に優先して判断されるべき事項と考えているものと捉えられる。
私は、この知財高裁の判断は、前審の地裁判決よりも適切なものと感じている。上述したように、たとえ当業者が正解を導くことができるからといって、「この発明者は間違った発明を完成させている」と認められる場合にまで、当業者の助けを認めるべきではない。そうすると必然的に、その不整合記載が誤記ではなくただの間違った認識と認められる場合には、当業者において正しい内容を一意に導けるかという判断に進むべきではないという結論になるだろう。
以上から、実務的には、「第一要件:不整合記載の存在確実性」→「第二要件:不整合記載が誤記であるとの認識」→「第三要件:誤記と認識できる場合には、訂正内容の一意性」の順に議論を進めていくのがよいと考察される。
「誤記の訂正」適否のための議論のステップ
「第一要件:不整合記載の存在確実性」→「第二要件:不整合記載が誤記であるとの認識」→「第三要件:誤記と認識できる場合には、訂正内容の一意性」
また、「不整合記載の存在確実性」は、その明細書等の記載から客観的に導くことのできる要件であり、そこまで争点になるものではないだろう(ここをごねてもあまり意味はないだろう)。
より重要なのは、「不整合記載が誤記であるとの認識」と「訂正内容の一意性」の判断であり、ここの主張を合理的にかつ強固に進められる方が、係争を有利に進められるものと考えられる。
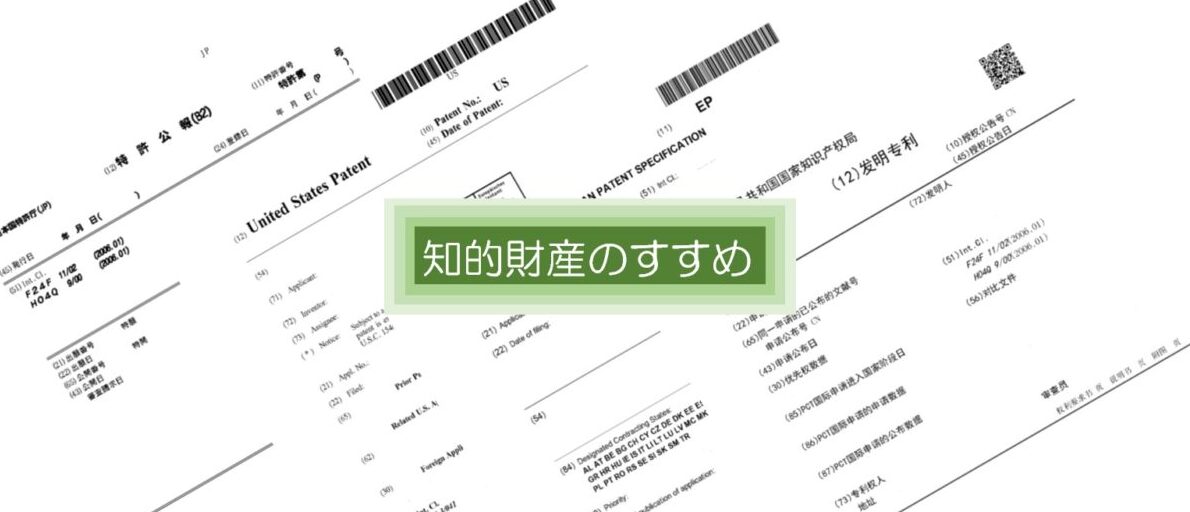
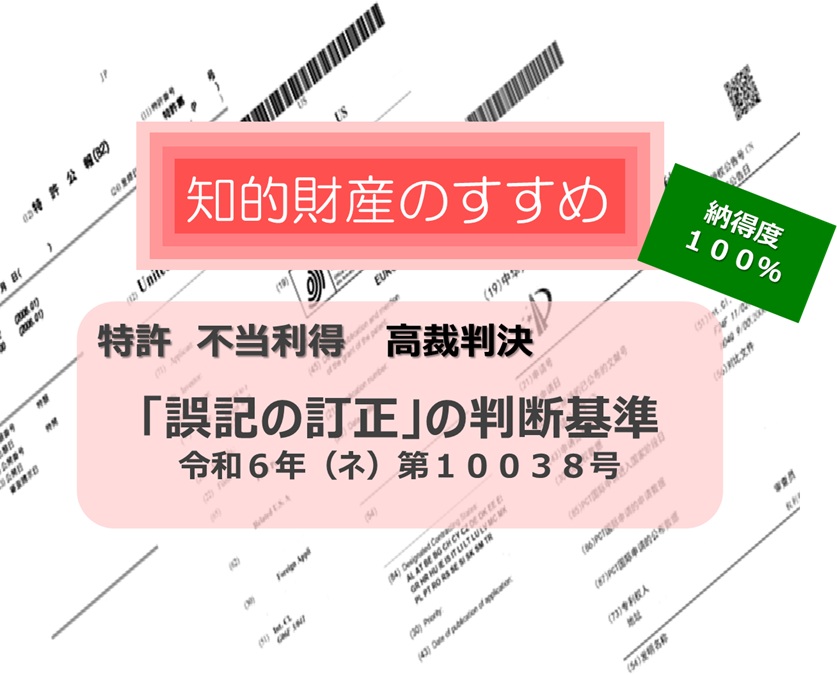

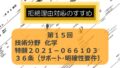
コメント