本講座の案内はこちらから
題材:本願請求項および発明が解決しようとする課題
題材1
【請求項】補正前
第1物質、第2物質、及び第3物質のうち、前記第1物質を含む2以上の物質を含有する、パラメータXの値が300以上となる組成物Y。
【発明が解決しようとする課題】
時間の経過によって組成物の状態が変化せず、良好な安定性を維持する組成物Yを得る。
第3回題材の趣旨
第3回は、「除くクレーム」を利用してサポート要件を解消する事例を挙げる。
ここではサポート要件の拒絶理由を挙げるが、実施可能要件や明確性要件などにおいても共通した考え方をすることができるはずであり、36条の拒絶理由解消に「除くクレーム」を活用することができるだろう。
通常の想定された「除くクレーム」の使い方は。新規性(29条1項)、拡大先願(29条の2)、同一発明(39条)の拒絶理由の解消を図るものである。
特許庁も「「除くクレーム」とする補正について」の中で、新規性・進歩性の拒絶理由を想定した話をしており。サポート要件や明確性要件などの36条拒絶理由については触れていない。それどころか、不用意に「除くクレーム」を用いることで、かえって明確性要件違反になるリスクがあると述べている。(「特許権者が想定しているとおりの技術的範囲とはならない可能性もあります。」や「「除く」部分の内容によっては、明確性要件違反(特許法第36条第6項第2号)や新規事項の追加(特許法第17条の2第3項)の拒絶理由が通知される可能性がある点にも注意してください。」などと述べている。)
確かに、「除くクレーム」によって“明確に意図した発明”を除かないと、意図しない部分が除かれたり、意図する範囲を超えた部分が除かれたりすることで、出願人は不利益を被る。その点で、特許庁の指摘は正しいし、私も他人のしたこのような「失敗した除くクレーム」を何度も目にしている。
しかしながら、「除くクレーム」が36条の拒絶理由を誘発するリスクがあることの逆転で、「除くクレーム」によって36条の拒絶理由を解消することも起こり得る。
第3回は、このような「除くクレーム」の事例を紹介する。(引用発明が登場しない以上、「引用発明と技術的思想として顕著に異なる」という場合といえるか否かも影響しない。)
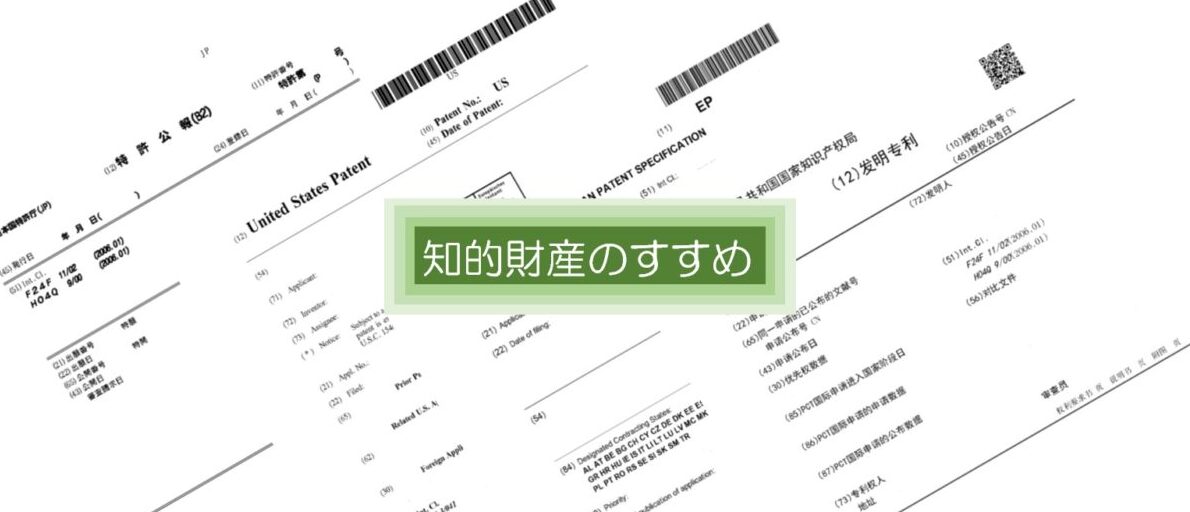
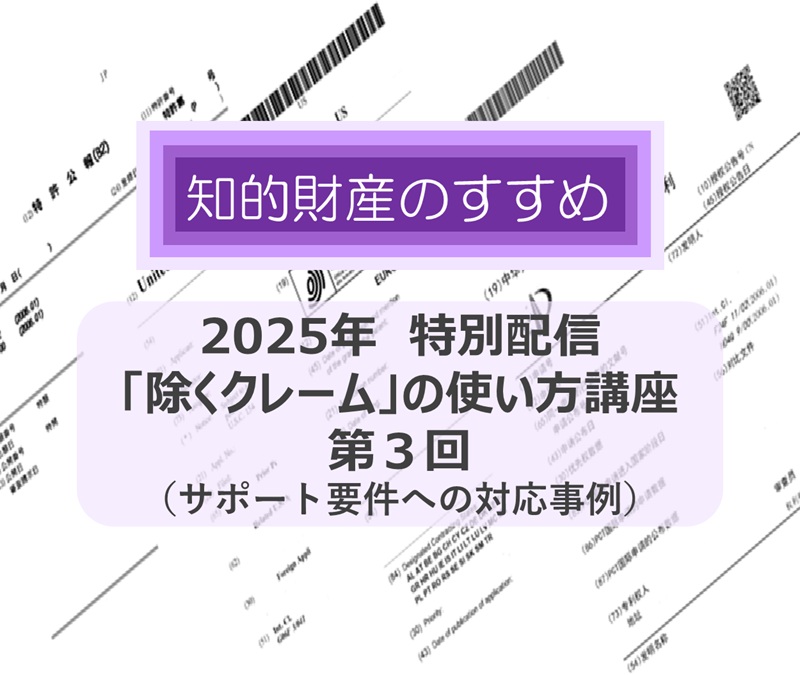

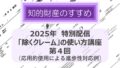
コメント