さて、今回のコラムでは、先日サイトにアップしたばかりの判例記事「令和5年(行ケ)第10069号」を書いていたときに気になった点があったため、これについての一考をお話しさせていただく。タイトル通り、進歩性判断に関し、「判決の拘束力」はどこまで及ぶのか、という点である。
実は、この点については、判例記事の中ですでに布石を打ってあった。
私は、判例記事の中で以下のように述べた。
「本件知財高裁の考えに従えば、「予測できない顕著な効果」はさておき、少なくとも進歩性判断においては「本願発明の認定」「引用発明の認定」「一致点及び相違点」及び「論理付け」の各ステップを必ず経ることになるため、これらのステップにおいて十分に争われていなかった論点があったとしても、これらの各ステップにおける判断の全てが「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」である以上、判決の拘束力により争えないということになろう。」
進歩性の判断において、「予測できない顕著な効果」は主張される場合とそうでない場合がある。これは、現行の実務において、「予測できない顕著な効果」は、「本願発明の構成に容易に想到することができる」として論理付けが認められた場合に、なお進歩性を認める要素があるかの判断として検討されていることによる。
進歩性の判断において、「本願発明の認定」「引用発明の認定」「一致点及び相違点」及び「論理付け」は、欠かすことのない判断事項であるが、「論理付け」の段階で、本願発明の構成に容易に想到することができないと判断されれば、「予測できない顕著な効果」は考慮されないため、これが主張されないことは往々にしてある。そこで以下の点について考えてみたい。
「前訴判決において、進歩性判断において「予測できない顕著な効果」が当事者間で争われなかった場合に、後訴において「予測できない顕著な効果」を主張することは「判決の拘束力」によって制限されるか」
この点について、それなりに判例に目を通す方であれば、一つの有名な事件が思い浮かぶであろう。「予測できない顕著な効果」について判断がなされた最高裁判例「平成30年(行ヒ)第69号」及び関連判例である。
この事案ではまさに、第一次判決(平成25年(行ケ)第10058号)において「予測できない顕著な効果」の主張がされることなく進歩性がないと判断されて判決が確定し、その後の審理において「予測できない顕著な効果」が主張された事案である。
第二次判決(平成29年(行ケ)第10003号)では、審決が「予測できない顕著な効果」により進歩性を認めたのに対し、当該効果は認められないと判断された。しかし、最高裁(平成30年(行ヒ)第69号)は、第二次判決における「予測できない顕著な効果」の判断には、法令の解釈適用の誤りがあるとして、原判決を破棄し、差し戻した。
差し戻し審である第三次判決(令和元年(行ケ)第10118号)では、「予測できない顕著な効果」が認められるとされ、判決は確定した。
この訴訟の流れを見ると、上述の点について考える必要はあるのか、と思う人もいるだろう。この一連の事件では、実際に、前訴で争われていなかった「予測できない顕著な効果」が後訴において主張され、当該主張が認められて進歩性が肯定されたのであるから、主張は認められるという結論が出ていると思われるかもしれない。
しかしながら、この事件は、非常に歪な訴訟の流れとなっており、次の2つの特徴を有している。
第一の特徴として、「判決の拘束力」について、第二次判決である平成29年(行ケ)第10003号と、第三次判決である令和元年(行ケ)第10118号とで、全く逆の判断を行っているという点である。
そして第二の特徴として、第二次判決において、当事者間では「判決の拘束力」が争われておらず、よって、最高裁(平成30年(行ヒ)第69号)も「判決の拘束力」については触れていないという点である。
さて、2つの特徴について詳細に説明する。
第一の特徴に関し、それぞれの裁判で知財高裁は以下のように述べている。
平成29年(行ケ)第10003号における裁判所の判断
「発明の容易想到性については,主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか,当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり,当事者は,第2次審判及びその審決取消訴訟において,特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も,これを否定する事実の主張立証も,行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後,再び開始された本件審判手続に至って,当事者に,前訴と同一の引用例である引用例1及び引用例2から,前訴と同一で訂正されていない本件発明1を,当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは,特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず,訴訟経済に反するもので,行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし,問題があったといわざるを得ない。」
令和元年(行ケ)第10118号における裁判所の判断
「前訴判決は,本件各発明について,その発明の構成に至る動機付けがあると判断しているところ,発明の構成に至る動機付けがある場合であっても,優先日当時,当該発明の効果が,当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである場合には,当該発明は,当業者が容易に発明をすることができたとは認められないから,前訴判決は,このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したものではなく,この点には,前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)は及ばないものと解される。」
このように、両裁判における「判決の拘束力」についての考えは真っ向対立している。皆さんは、これらの判断を見比べた場合、どちらの判断により説得力(合理性)を感じるだろうか。できることならば、自身が独立要件説の立場にあるか二次的考慮説の立場にあるかといった偏見は抜きにして眺めてもらいたい。
私としては、平成29年(行ケ)第10003号の判断により説得力を感じる(なお、当時のこちらの裁判の裁判長は髙部眞規子先生である。)。
なぜ説得的かというと、こちらの判断は、(上記には挙げなかったが)最高裁昭和63年(行ツ)第10号の判旨を挙げた上で、その法の趣旨からアプローチしているからである。判断の根拠の一つに「当事者は、前訴において「予測できない顕著な効果」を主張することが当然にできた」という考えがある。これは「発明の容易想到性については,主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか,当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであ」るとの記載に現れている。
なお、この記載を「独立要件説」を否定するものと解する必要はないだろう。当裁判所は、あくまで、進歩性判断の考量要素の一つとして「予測し難い顕著な効果」があり、これが独立した要件であるともないとも言っていない。それどころか、「~の有無の“ほか”」と記載し、論理付けまでの判断と区分けしているような書きぶりは、寧ろ独立要件説に寄った記載と解釈することも可能である。
少し話は逸れたが、判断の根拠のもう一つに「特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず,訴訟経済に反するもので」あるとの点が挙げられる。これはまさに、私が「令和5年(行ケ)第10069号」でも述べた、主張の後出しによる紛争の蒸し返しと考えを共にするものといえるだろう。
一方で、令和元年(行ケ)第10118号は、その判断(解釈)を導くための根拠を何ら記載していない。単に、前訴で「予測できない顕著な効果」が主張されなかったのならば、前訴の裁判所は判断していない以上、判決の拘束力は及ばないと述べているだけである。
しかし、前訴で裁判所が判断していない事項であれば判決の拘束力は及ばないとすれば、令和5年(行ケ)第10069号の事件においても、前訴で裁判所が審理しなかった事項を主張しているのであるから判決の拘束力は及ばないはずである。また、昭和63年(行ツ)第10号の最高裁の事件(旋回式バレル事件)においても、後に提出された証拠に基づく判断を裁判所はしていない以上、判決の拘束力は及ばないということになる。(最高裁判例に抵触することになる)
新たな証拠の提出はダメで、審理されていなかった事項の追加はダメで、「予測できない顕著な効果」であれば認められる、というこの境界について、何らの説得的な説明はなされていないのである。
次に、第二の特徴についてであるが、第一次判決では、進歩性判断において「技術常識の認定の誤り」「甲1の記載事項の評価の誤り」「甲4の記載事項の評価の誤り」「容易想到性の判断の誤り」が争われた。
その後、特許庁における無効審判の再審理において、進歩性判断に関し「予測できない顕著な効果」が主張され、進歩性を認める審決がされたため、第二次判決では、「予測できない顕著な効果」が争われた。
第二次判決の判決文における当事者の主張を読んでも、「本件明細書に記載された本件発明1の効果の解釈の誤り」「本件発明1の効果の顕著性の判断の誤り」について主張されているだけで、そこには、「顕著な効果を主張することは判決の拘束力により許されない」との主張はされていない。
そのため、第二次判決の裁判所も、「予測できない顕著な効果」があるとは認められないことを根拠に、判決主文を導いている。そして、上記の「判決の拘束力」に関する裁判所の判断は、判決文における「結論」の後ろに、付言する形で記載されたに過ぎないのである。
ご存じの通り、最高裁は事実審ではなく法律審であるが、そうかといって、当事者間で争いになっていない事項についての法律判断を下すところではない。当事者がサポート要件を争っていたにも関わらず、最高裁でいきなり明確性要件の法律判断がなされることはないだろう。
判決の拘束力とは、進歩性に限った話ではないため、進歩性判断についての争いではない。前訴でサポート要件の判断が確定したならば、サポート要件の判断に対して、判決主文を導くのに必要な事実及び法律判断に判決の拘束力が及ぶことになる。
このような事情があったため、平成30年(行ヒ)第69号の最高裁は、「判決の拘束力」について触れることはなく、また、触れることはできず、この点についてを考慮することなく、進歩性判断における法令の適用解釈に誤りがないかを判断したとみるのが適切であろう。
つまり、最高裁は、「前訴で主張されていなかった「予測できない顕著な効果」を後訴において主張することが判決の拘束力によって制限されるか」という点を考慮することなく、純粋に「予測できない顕著な効果」をどのようにして判断すべきかを述べたに過ぎない。仮に、本件が判決の拘束力によって制限されるべきものであったとしても、それはこの事件において最高裁が判断すべき審理事項ではないのである。(最高裁昭和63年(行ツ)第10号に抵触するのであれば再審をすべきである)
しかしながら、第二次判決が、結論の後に「付言」する形で判決の拘束力の話を持ち出してしまったが故に、第三次判決は「判決の拘束力」を無視して審理判断を進めることがしづらくなってしまった。(ここに、第二次判決が「付言」してしまったことによるこの事案の歪さが生じてしまっている。)
その一方で、最高裁が「本件各発明についての予測できない顕著な効果の有無等につき更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。」と述べた以上、審理を尽くさなければならない。言い換えれば、「判決の拘束力」によって審理を封じることもまた、しづらくなってしまたのである(そもそも当事者間で争われていなかったのであるから)。
判決の拘束力に触れなければならず、また、予測できない顕著な効果についても審理を尽くさなければならなくなった第三次判決の裁判所において、もはや選択肢は一つしかない。判決の拘束力は及ばないとし、予測できない顕著な効果を審理判断する他ないのである。
私には、第一の特徴で述べた、令和元年(行ケ)第10118号における判断の説得力のなさは、他にやりようがないのだから仕方ないといった姿勢のようにも見える。この事件の裁判所は、不本意ながらもこのように書くしか他に方法がなかったのかもしれない。
いずれにしても、第二次判決と第三次判決は、「判決の拘束力」についての判断が逆になっており、また、これらの判決の間にあった最高裁判決では「判決の拘束力」については審理されていない以上、第二次判決の判断が誤っていたということもできず、第三次判決の判断の方が正しいということもできないだろう。
私としては、どちらの判断に転んでもよいと思っているが、その際にはしっかりとした法律的説明がなされて欲しいと思うところである。
たとえ「予測できない顕著な効果」が独立した要件であるという立場(独立要件説の立場)にたったとしても、なぜ独立した要件であるから判決の拘束力が及ばないことになるのか、最高裁昭和63年(行ツ)第10号の判旨からそのことが直接読み取れない以上、更に一歩進めた判断が必要になることは間違いないであろう。(これができなかったために令和元年(行ケ)第10118号の判決文は説得力に欠けたあのような書きぶりになったのだと推察される)

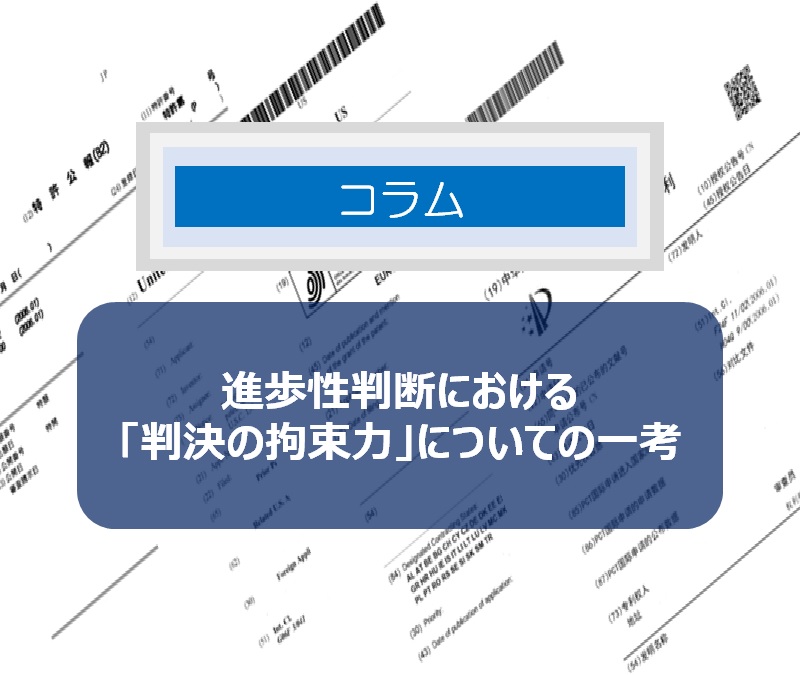


コメント